生活保護と障害年金は、どちらも生活に困窮する方々を支援する重要な社会保障制度です。しかし、これらの制度について「同時に受給できるのか」「併給した場合の金額はどうなるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。
実際のところ、生活保護と障害年金は同時受給が可能ですが、単純に両方の満額を受け取れるわけではありません。障害年金が「収入」とみなされ、生活保護費から差し引かれる仕組みになっているためです。ただし、障害者加算などの特別な支給もあり、結果として受給総額が増える場合もあります。
2025年7月現在の最新情報に基づき、併給時の金額計算方法、障害者加算の詳細、遡及支給時の注意点、そして申請時のポイントまで、実際の数字を交えながら詳しく解説していきます。これらの制度を正しく理解することで、より安定した生活基盤を築く参考にしていただければと思います。

生活保護と障害年金は同時にもらえるの?併給の基本的な仕組みとは
生活保護と障害年金は同時に受給することが可能です。 ただし、これらは全く異なる性質を持つ制度であることを理解しておく必要があります。
生活保護は世帯単位で適用される制度で、日本国憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを目的としています。一方、障害年金は個人単位で支給される公的年金制度で、病気や事故による障害で日常生活や就労に支障がある方への経済的支援を目的としています。
併給の基本的な仕組みは、「生活保護費から障害年金額を差し引いた金額が支給される」 というものです。これは生活保護制度の「他法他施策の優先利用」という原則に基づいています。つまり、障害年金などの他の公的制度を優先的に活用し、それでも不足する部分を生活保護で補うという考え方です。
具体的な計算式は以下の通りです:
支給される生活保護費 = 最低生活費 – 障害年金額
例えば、ある世帯の最低生活費が月額13万円と認定され、障害年金を月額6.5万円受給している場合、生活保護費として実際に支給されるのは6.5万円となります。結果として、手元に入る総額は13万円で、これは生活保護のみを受給した場合と同じ金額になります。
ただし、ここで重要なのは障害年金の性質の違いです。障害年金には原則として所得制限がなく、資産や収入があっても減額されません。また、受給した年金の使い道は完全に自由で、貯金することも可能です。これに対し、生活保護には資産の保有制限や支出に関する指導があります。
さらに、障害年金の支給額が最低生活費を上回る場合は、生活保護は打ち切りとなります。この場合、障害年金のみで生活することになりますが、年金額が十分であれば、より自由度の高い生活が可能になります。
生活保護と障害年金を併給した場合の実際の受給金額はいくらになる?
併給時の受給金額を理解するためには、まず各制度の支給額を把握する必要があります。2025年度の障害年金額は以下の通りです:
障害基礎年金:
- 1級:月額約81,427円(年額977,125円)
- 2級:月額約65,142円(年額781,700円)
- 子の加算:第1子・第2子各月額約18,742円、第3子以降各月額約6,250円
障害厚生年金は、これに加えて報酬比例部分が上乗せされ、配偶者がいる場合は月額約18,742円の加給年金も支給されます。
一方、生活保護の最低生活費は地域や世帯構成によって大きく異なります。例えば、東京都区部(1級地-1)の単身者の場合:
- 生活扶助:約8万円
- 住宅扶助:最大53,700円
- 合計:約13万3,700円
この場合で障害基礎年金2級(月額約65,142円)を受給していると:
実際の生活保護費 = 133,700円 – 65,142円 = 68,558円
しかし、ここで重要なのが障害者加算の存在です。障害年金1級または2級を受給している場合、生活保護に障害者加算が適用されます。
2025年7月からの障害者加算額(東京都区部・在宅者):
- 障害等級1級または2級相当:26,810円
- 障害等級3級相当:17,870円
つまり、上記の例では:
総受給額 = 生活保護費68,558円 + 障害年金65,142円 + 障害者加算26,810円 = 160,510円
これにより、生活保護のみの場合(133,700円)と比較して、月額約26,810円の増額となります。
地方都市の場合も見てみましょう。3級地の単身者で最低生活費が約11万円、障害基礎年金2級を受給している場合:
- 生活保護費:110,000円 – 65,142円 = 44,858円
- 障害者加算(3級地):23,060円
- 総受給額:132,060円(生活保護のみより約23,060円増)
夫婦世帯の場合はさらに複雑です。夫が障害厚生年金1級(基礎年金1級+厚生年金+配偶者加給年金)で合計月額約12万円を受給し、最低生活費が月額18万円の世帯では:
- 生活保護費:180,000円 – 120,000円 = 60,000円
- 障害者加算:26,810円
- 総受給額:206,810円
このように、障害者加算により実質的な収入増が期待できることが、併給の大きなメリットとなります。
障害者加算って何?生活保護と障害年金併給時の追加支給について
障害者加算は、障害のある方が健常者よりも高い生活コストを抱えることを考慮した、生活保護の特別加算です。この加算は併給時の最大のメリットといえるでしょう。
対象となる条件は以下の通りです:
- ア:障害等級表の1級もしくは2級、または国民年金法施行令別表に定める1級
- イ:障害等級表の3級、または国民年金法施行令別表に定める2級
重要な注意点として、精神障害者保健福祉手帳の3級は支給対象になりません。また、障害年金3級のみの受給者も障害者加算の対象外となります。
2025年7月からの障害者加算月額:
在宅者の場合:
- 1級地(東京23区など):
- ア(1級・2級相当):26,810円
- イ(3級相当):17,870円
- 2級地(政令指定都市など):
- ア:24,940円
- イ:16,620円
- 3級地(その他の地域):
- ア:23,060円
- イ:15,380円
入院患者・施設入所者の場合:
- ア(1級・2級相当):22,310円
- イ(3級相当):14,870円
特別な加算もあります:
- 常時介護が必要な重度障害者:16,100円
- 同一世帯の家族が介護する場合:13,490円
これらの加算は、障害年金の等級と必ずしも一致しない点に注意が必要です。例えば、身体障害者手帳3級でも障害年金では2級に該当し、障害者加算「ア」の対象となるケースがあります。
申請手続きについては、自動的には支給されません。障害が明らかに分かる場合でも、必ず申請が必要です。申請は担当のケースワーカーに対して行い、申請した月の翌月から支給開始となります。
実際の家計への影響を考えてみましょう。東京都区部の単身者で障害基礎年金2級を受給している場合:
- 通常の生活保護のみ:133,700円
- 併給+障害者加算:160,510円
- 月額26,810円、年額約32万円の増額
この増額分は使い道が自由で、以下のような用途に活用できます:
- 通院交通費や医療費の自己負担分
- 障害に配慮した食品や用具の購入
- リハビリテーション関連費用
- 将来への貯蓄
- 趣味や娯楽による生活の質向上
等級判定で迷った場合の戦略として、より高い等級で申請し、認められなかった場合に低い等級で再申請する方法が有効です。これにより、適正な加算額を確実に受給できます。
障害年金の遡及支給があった場合、生活保護費を返還する必要があるの?
障害年金の遡及支給時の生活保護費返還は、併給における最も重要な注意点です。この仕組みを理解せずに手続きを進めると、思わぬ経済的負担を負うことになります。
遡及支給とは、障害認定日から最長5年間に遡って障害年金を支給する制度です。例えば、2020年に障害認定日があったものの、2025年に初めて障害年金を申請して認定された場合、2020年から2025年までの5年分がまとめて支給されます。
問題となるのは、この遡及期間中に生活保護を受給していた場合です。生活保護制度では、他の収入があった場合に受け取った保護費は「過払い」として返還義務が生じます。
具体的な計算例:
- 遡及期間:2020年4月〜2025年3月(5年間)
- 障害基礎年金2級:月額約65,000円 × 60ヶ月 = 390万円
- 同期間の生活保護受給額:月額8万円 × 60ヶ月 = 480万円
この場合、390万円の障害年金が収入として認定され、その分の生活保護費返還が求められる可能性があります。つまり、390万円の年金を受け取っても、そのほぼ全額を返還することになります。
返還額の計算方法:
遡及支給された障害年金額と、同期間に受給した生活保護費を月単位で比較し、障害年金額が生活保護費を下回る月については、その差額のみが手元に残ります。
月単位の計算例:
- 最低生活費:13万円
- 障害年金:6.5万円
- 実際の保護費支給額:6.5万円
- 返還額:6.5万円(受給した保護費全額)
返還を避ける方法や軽減策:
- 事前の相談:障害年金申請前に、必ずケースワーカーに相談し、遡及支給の可能性と返還リスクを確認する
- 申請タイミングの調整:生活保護受給開始前に障害年金を申請できれば、返還リスクを回避できます
- 事後重症での申請:障害認定日ではなく、申請日から支給開始となる「事後重症」での申請を検討する
- 分割返還の相談:返還額が高額な場合、分割での返還が認められることがあります
実際の事例:
- Aさん:遡及支給300万円、返還額280万円、手元に残った額20万円
- Bさん:事前相談により事後重症で申請、返還なしで月額6.5万円の年金受給開始
専門家のサポートの重要性:
遡及支給のリスクは非常に複雑で、個人での判断は困難です。社会保険労務士などの専門家に相談し、最適な申請戦略を立てることが重要です。場合によっては、生活保護のケースワーカーと社労士が連携して、最も有利な方法を検討することもあります。
注意すべきタイミング:
- 生活保護申請時点で障害年金の可能性がある場合
- 既に生活保護受給中で、障害年金申請を検討している場合
- 過去に障害年金申請を却下され、再申請を考えている場合
これらの状況では、必ず事前に専門家に相談することをお勧めします。
生活保護と障害年金の併給申請で注意すべきポイントと専門家活用法
併給を成功させるためには、両制度の特性を理解し、適切な順序で手続きを進めることが重要です。ここでは、実践的なポイントと専門家の活用方法について詳しく解説します。
申請順序の戦略:
パターン1:障害年金申請が先の場合
- メリット:遡及支給による返還リスクがない
- 注意点:障害年金の審査期間(3〜6ヶ月)中の生活費確保
- 対策:審査期間中に生活が困窮した場合は、生活保護申請を検討
パターン2:生活保護申請が先の場合
- メリット:即座に生活の安定が図れる
- 注意点:後の障害年金遡及支給時の返還リスク
- 対策:ケースワーカーと連携し、障害年金申請のタイミングを慎重に決定
申請時の必要書類と準備:
生活保護申請時:
- 収入・資産に関する申告書
- 扶養義務者の状況
- 医療機関への通院状況
- 障害年金受給の可能性についても正直に申告
障害年金申請時:
- 初診日を証明する書類
- 診断書(指定様式)
- 病歴・就労状況等申立書
- 生活保護受給中であることの申告
収入申告の重要性:
生活保護受給中は、障害年金を含む全ての収入を申告する義務があります。申告を怠ると不正受給とみなされ、以下のリスクがあります:
- 保護費の返還請求
- 保護の停止・廃止
- 刑事告発の可能性(悪質な場合)
専門家活用のメリットと方法:
社会保険労務士(社労士)の活用:
- 障害年金申請の成功率向上:複雑な診断書作成支援、申立書の適切な記載
- 生活保護との調整:併給時の最適な戦略立案
- 費用について:成功報酬制が一般的で、自治体によっては社労士費用が生活保護の必要経費として認められる場合があります
ケースワーカーとの連携:
- 月1回以上の面談で状況を報告
- 障害年金申請の進捗状況を共有
- 障害者加算の申請手続き
- 将来の自立に向けた相談
無料相談窓口の活用:
- NPO法人による障害年金相談
- 自治体の福祉相談窓口
- 法テラスでの法律相談
- 社会保険労務士会の無料相談日
申請時期の最適化:
最適なタイミング:
- 障害の状態が安定している時期
- 医療記録が十分に蓄積された時期
- 生活状況に余裕がある時期
避けるべきタイミング:
- 障害の状態が不安定な時期
- 転居や転院直後
- 他の重要な手続きと重複する時期
成功事例に学ぶポイント:
事例1:計画的併給成功例
- 生活保護受給前に障害年金申請
- 社労士と連携し、適切な診断書を作成
- 結果:返還リスクなしで併給開始、障害者加算も適用
事例2:事前相談による最適化例
- 生活保護受給中に障害年金の可能性を発見
- ケースワーカーと社労士が連携
- 事後重症での申請により返還リスクを回避
最終チェックリスト:
□ 両制度の要件を満たしているか確認
□ 申請順序と時期を専門家と検討
□ 必要書類を漏れなく準備
□ 遡及支給のリスクを理解し対策を立案
□ 定期的な収入申告の準備
□ 障害者加算申請の準備
□ 専門家のサポート体制を確保
重要な心構え:
併給は複雑な制度ですが、適切な知識と専門家のサポートがあれば、より安定した生活基盤を築くことが可能です。一人で悩まず、積極的に相談し、利用できる制度は最大限に活用することが大切です。

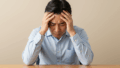

コメント