2025年、世界中の注目が再び大阪に集まります。半年間にわたる科学、文化、そして未来の祭典、大阪・関西万博が、いよいよそのフィナーレを迎えます。多くの人々に感動とインスピレーションを与えたこの万博の最後を飾るのが、2025年10月13日に開催される閉幕式(閉会式)です。このセレモニーは、単なる祭りの終わりを告げるものではなく、万博が掲げた「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマの集大成であり、次なる時代への希望を世界へと発信する重要な役割を担っています。本記事では、現時点で判明している閉幕式の内容、そしてファンの期待が寄せられる出演者の情報をまとめ、この歴史的なイベントの全貌に迫ります。

感動のフィナーレへ!大阪・関西万博 閉幕式の基本情報
2025年大阪・関西万博の閉幕式は、万博の最終日である2025年10月13日(月曜日・祝日)に開催されます。時間は14時00分から15時10分頃までを予定しており、会場は開会式と同じくEXPOホール「シャインハット」です。この式典の主な目的は、半年間にわたり万博を支え、訪れたすべての人々への感謝を伝えることです。さらに、国際博覧会(BIE)の旗を次回開催国へと引き継ぐ「引き継ぎの儀式」も行われ、万博の精神が未来へと継承される象徴的な場となります。閉幕式のテーマは「For the Futures」と発表されており、万博で生まれた経験や知見、そして人々の繋がりを、文字通り未来のために繋いでいくという強い意志が込められています。
万博の伝統を未来へ:BIE旗返還式の重要性
閉幕式の中でも、特に国際的で象徴的な意味を持つのが「BIE旗返還式」です。BIEとは、1928年に署名された「国際博覧会条約」に基づきフランス・パリに設立された博覧会国際事務局(Bureau International des Expositions)の略称です。この機関が承認した博覧会だけが、公式に「万博」を名乗ることができます。BIE旗は、まさにその公式な万博の象徴です。
返還式では、まず開催国の代表がBIEの代表へ旗を返還します。そして、そのBIE代表から、次回開催国の代表へと旗が手渡されます。例えば、2022年のドバイ万博閉会式では、UAEからBIEへ、そしてBIEから2025年大阪・関西万博の代表へと旗が引き継がれました。この一連の儀式は、万博の主催権が正式に移譲され、その理念と伝統が途切れることなく継承されていくことを世界に示す、極めて重要な意味を持っているのです。
閉幕式はどうすれば観覧できる?視聴方法の全貌
閉幕式のメイン会場であるEXPOホール「シャインハット」への入場は、残念ながら国内外の要人や関係者などの招待客に限定されています。しかし、一般の来場者や会場に足を運べない方々のために、複数の視聴方法が用意されています。万博会場内では、EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」とEXPOアリーナ「Matsuri」の2か所で、大規模なパブリックビューイングが実施されます。これにより、閉幕日当日に会場を訪れている多くの人々が、大スクリーンを通じてリアルタイムでセレモニーの感動を分かち合うことができます。また、ご家庭で楽しみたい方のために、NHK総合テレビでの全国生放送が決定しています。放送時間は13時55分から15時10分までとなっており、日本全国どこからでも歴史的瞬間を見届けることが可能です。さらに、大阪・関西万博の公式YouTubeチャンネルでは、日本語と英語の2か国語でライブ配信が行われ、世界中の人々が視聴できます。加えて、バーチャル万博アプリ内でも配信が予定されており、仮想空間からも閉幕式に参加できるという、まさに未来的な体験が提供されます。
注目の出演者は誰?現時点での情報と期待
2025年10月6日現在、閉幕式の具体的な出演者やパフォーマーのラインナップは、まだ公式に発表されていません。しかし、開会式の豪華な顔ぶれを振り返ることで、閉幕式への期待は大きく膨らみます。開会式では、万博アンバサダーのコブクロ、世界的指揮者の佐渡裕氏、そして関西を代表する5つのオーケストラが壮大な演奏を披露しました。さらに、尾上菊之助をはじめとする歌舞伎俳優や、バーチャルヒューマン「imma」が司会を務めるなど、伝統と革新が融合した演出が大きな話題を呼びました。閉幕式も、これらの演出を手掛けた催事企画プロデューサー、小橋賢児氏が引き続き重要な役割を担う可能性が高いと見られています。小橋氏は東京2020パラリンピック閉会式を成功に導いた実績もあり、その手腕には絶大な信頼が寄せられています。万博の集大成となる閉幕式では、開会式に勝るとも劣らない、サプライズに満ちた感動的な演出と、世界的なアーティストや日本の文化を象徴する人物の登場が期待されています。
閉幕日を彩る特別な一日「ありがとうと旅立ちの祭典」
閉幕式が行われる10月13日は、会場全体が感謝とフィナーレの雰囲気に包まれる特別な一日となります。特にEXPOアリーナ「Matsuri」では、公式イベントとして「JR西日本グループpresents ありがとうと旅立ちの祭典~Thank you for all…~」と題した大規模なステージが、13時から19時までの6時間にわたって開催されます。このステージイベントの観覧は事前予約制(抽選)となっているため、注意が必要です。
イベントは豪華3部構成で、多彩なゲストが登場します。第1部「美しい日本の文化・伝統によるおもてなし」では、元サッカー日本代表の中田英寿氏がプロデュースする日本酒の振る舞い酒企画に加え、モデルのアンミカ氏、タレントのゆうちゃみ&ゆいちゃみといったゲストも登場し、華やかなトークを繰り広げます。
第2部は「EXPO Thanks LIVE」と題した音楽ライブです。出演アーティストは、アバンギャルディ、CANDY TUNE、コブクロ、西川貴教、平原綾香という豪華なラインナップ。この顔ぶれには、単なる人気だけではない、万博のフィナーレにふさわしい深い意味が込められています。
万博の「始まりと終わり」を象徴するのが、公式アンバサダーのコブクロと、ダンスグループ「アバンギャルディ」です。コブクロは2020年の早期からアンバサダーとして万博に関わり、オフィシャルテーマソング「この地球の続きを」を制作。開会式でも特別バージョンを披露するなど、まさに万博の顔として活動してきました。一方、謎めいた制服姿とユニークなダンスで世界を席巻するアバンギャルディも、開会式で印象的なパフォーマンスを披露しています。この両者が再び閉幕日のステージに立つことは、万博という壮大な物語の始まりと終わりを繋ぎ、美しいフィナーレを飾るという重要な役割を担っています。
また、西川貴教氏の出演は、「地域との連携」という万博のもう一つの側面を象徴します。彼は「滋賀ふるさと観光大使」として関西パビリオンのPRを牽引するだけでなく、2009年から故郷で大規模な野外音楽フェス「イナズマロック フェス」を主催し続けるなど、長年にわたり地域貢献に尽力してきました。彼にとってこのステージは、関西全体を盛り上げたいという強い情熱の集大成となるでしょう。これら万博と縁の深いアーティストたちが、感謝のメッセージを込めて圧巻のパフォーマンスを披露し、会場のボルテージは最高潮に達するはずです。
そして第3部の「旅立ちのステージ」は、万博の過去と未来が交差する、最も象徴的な時間となるでしょう。ここで登場するのが、1970年の大阪万博のために河合楽器製作所が特別に製造した3台のうちの1台、通称「万博ピアノ」です。今回演奏されるのは、万博のイメージカラーであった鮮やかなエメラルドグリーンに塗装されたフルコンサートグランドピアノ。万博終了後、奈良県立宇陀高等学校に寄贈され、50年以上の時を経て大切に受け継がれてきた「生きた遺産」です。この歴史の証人とも言えるピアノを、人気ピアニストのハラミちゃんが演奏します。半世紀の時を超えて蘇る音色と、未来を担う大阪府立夕陽丘高等学校音楽科の生徒による合唱が重なり合うとき、会場は深い感動に包まれ、万博が紡いできた時間の物語が美しく完結するのです。
パレードや花火も!閉幕日のその他イベント
10月13日は、アリーナでのステージイベント以外にも見逃せない催しが目白押しです。16時からは、万博に参加した158の国・地域、7つの国際機関の旗が会場を練り歩く「フラッグパレード」が開催されます。予約なしで観覧できるこのパレードは、万博の国際性と多様性を象徴する壮大な光景となるでしょう。さらに、閉幕が近づく夜空を彩る「EXPO Thanks 花火大会」も予定されており、万博の最後を華々しく飾ります。その他にも、万博の184日間を写真で振り返る展示「未来への旅路」など、最後まで万博の魅力を満喫できる企画が用意されています。
過去と未来をつなぐ閉幕式の歴史的意義
2025年の大阪・関西万博は、1970年に開催された前回の大阪万博から実に55年ぶりの開催となります。この半世紀以上の時の流れは、閉幕式を単なるセレモニーではなく、時代の変化を映し出す歴史的な鏡像として特別な意味を持たせています。
1970年9月13日、6400万人以上が訪れた巨大な祭典の終わりを告げた閉会式は、多くの人々の記憶に刻まれました。会場の電子掲示板に「さようならEXPO’70」の文字が映し出され、別れの曲として『蛍の光』が流れる中、万博の象徴であった岡本太郎作「太陽の塔」の目が閉じるように灯りが消えました。この感傷的な演出は、高度経済成長の頂点で未来への希望に満ちていた一つの時代の終わりを象徴する光景でした。
そして、その跡地は万博記念公園として整備され、「太陽の塔」は当初の予定であった撤去を覆し、市民の熱い要望によって永久保存されることになりました。これは、万博の「レガシー」が単なる建造物ではなく、人々の心の中に生き続ける記憶や愛着であることを示す最高の事例です。1970年万博が「動く歩道」などの未来技術の断片を示したように、2025年万博も「空飛ぶクルマ」やAI、最先端医療といった現代の夢を提示しました。閉幕式は、これらの技術や理念が、一過性の祭りで終わるのではなく、いかにして我々の未来の日常へと繋がっていくのか、そのビジョンを力強く示す場となるのです。
2025年万博のシンボルである大屋根(リング)の一部が閉幕後も保存・再利用が計画されていることは、まさに1970年の「太陽の塔」の物語から学んだ教訓と言えるでしょう。1970年の「万博ピアノ」が2025年のフィナーレで演奏されるように、閉幕式は過去からのバトンを受け取り、それを未来へと手渡すという、壮大な時間軸の物語を完結させる重要な役割を担っているのです。
演出家・小橋賢児氏が描く「地球共感覚」という未来
大阪・関西万博の催事全体をプロデュースする小橋賢児氏は、単なるイベントの成功以上の、壮大なビジョンを掲げています。その核心となるのが「地球共感覚」というコンセプトです。これは、かつて人類が自然と深く結びついていた時代の「魂の記憶」を呼び覚まし、文化や言語の違いを超えて、すべてのいのちが意識の世界で繋がる体験を目指すものです。小橋氏は、万博を「未来社会の実験場」と位置づけ、来場者一人ひとりのポジティブな願いや他者を思いやる心が集まることで、現実世界をより良い方向へ変える力になると信じています。
この思想は、具体的な演出プランにも反映されています。例えば、特定の時間に会場全体の音響システムをジャックし、すべての来場者が同じ音楽を聴きながらドローンショーを見上げる、といった一体感創出のアイデアです。これは、空間全体をメディアとして捉え、偶然そこに居合わせた人々が感動を共有し、「人生の交差点」としての万博で新たな「セレンディピティ(幸運な偶然の出会い)」を生み出すことを狙いとしています。閉幕式のテーマ「For the Futures」も、この「地球共感覚」の思想と深く結びついており、万博での体験が個人の未来、そして地球全体の未来へと繋がっていくというメッセージが込められているのです。
万博が残すもの(レガシー)と閉幕式後の未来図
閉幕式は終わりであると同時に、万博が社会に残す「レガシー」を未来へと解き放つ新たな始まりの合図でもあります。そのレガシーは、物理的な施設や技術に留まらず、人々の意識や社会の仕組みにまで及ぶ、多層的なものとして計画されています。
未来都市へと進化する夢洲
万博会場となった夢洲は、閉幕後、未来技術の社会実装をリードする実証フィールドへと生まれ変わります。会場の象徴であった大屋根(リング)や「静けさの森」といった施設は理念を伝える遺産として保存され、その周辺では自動運転バスや次世代モビリティ、そして「空飛ぶクルマ」が日常的に行き交う未来都市の構築が進められます。エンターテイメント、ビジネス、医療研究といった多様な機能を持つ複合都市として開発されるこの地は、まさに万博が描いた未来社会のプロトタイプとなるのです。
社会実装される未来のテクノロジー
万博は、未来の生活を具体的に体験できる技術のショーケースでもありました。その中でも特に注目されるのが、個人の医療・健康情報と日常の活動データを連携させる「パーソナル・ライフ・レコード(PLR)」という概念です。個々のQOL(生活の質)向上を目指すこの仕組みは、万博終了後、うめきた2期地区などで規模を拡大し、本格的な社会実装が検討されています。その他にも、CO2を原料とするコンクリート「CUCO-SUICOM」のようなグリーン技術や、AI自動翻訳、川崎重工業の4脚ロボット「CORLEO」といったデジタル技術も、今後の日本のまちづくりや産業に大きな影響を与える重要なレガシーとなるでしょう。
人々の心と社会に根付く「ソフト・レガシー」
最も重要なレガシーは、人々の心や社会の仕組みといった「ソフト・レガシー」かもしれません。1970年万博が「ジョイントベンチャー」という新しいビジネス手法を生んだように、今回も新たな連携の形が生まれることが期待されます。また、万博を機に「いのち」について議論するために生まれた市民参加のコミュニティ「いのち会議」のように、閉幕後も活動を継続し、社会課題の解決に取り組む動きも始まっています。万博での感動的な体験が、来場者一人ひとりのSDGsや未来社会への意識を高め、行動を変えるきっかけとなること。それこそが、測定不可能な最大のレガシーと言えるのかもしれません。閉幕式は、これらの有形無形のレガシーが、確かに未来へと引き継がれたことを確認する、約束の場でもあるのです。

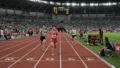
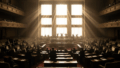
コメント