固定電話が使えなくなるという噂を耳にして、不安を感じている方は少なくないでしょう。2024年から2025年にかけて、NTT東日本とNTT西日本が提供する固定電話サービスは大きな転換期を迎えました。インターネットやSNSでは「固定電話サービス終了」というキーワードが話題になり、多くの利用者が今後の対応について悩んでいます。しかし、実際には固定電話そのものが完全に廃止されるわけではなく、通信技術の基盤が変わるという内容です。長年親しまれてきたアナログ回線やISDN回線といったメタル回線から、インターネット技術を活用したIP網への移行が進められており、この変化が「サービス終了」という誤解を生んでいるのです。本記事では、固定電話のサービス終了時期に関する正確な情報と、2025年以降の動向について、一般家庭や企業が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していきます。

固定電話サービスは本当に終了するのか
固定電話サービス自体は終了しません。これは最初に強調しておきたい重要な事実です。多くの方が誤解されているのは、固定電話が完全に使えなくなるという点ですが、実際には通信インフラの技術が変わるだけで、電話番号や電話機はそのまま使い続けることができます。
従来の固定電話は、銅線を使ったメタル回線で音声を伝送していました。このメタル回線には、一般家庭で広く使われているアナログ回線と、企業やビジネス用途で利用されているISDN回線の2種類があります。これらの回線を支える通信設備が老朽化し、維持管理が困難になってきたことが、今回の技術移行の主な理由です。
NTT東日本とNTT西日本は、これまでのPSTNと呼ばれる公衆交換電話網から、IP網と呼ばれるインターネット技術を基盤とした通信方式へと段階的に移行を進めています。この移行により、通信の仕組みは大きく変わりますが、利用者が電話を使う際の操作方法や使い勝手はほとんど変わりません。電話番号もそのまま継続して使用でき、基本料金も大きく変動することはありません。
2024年から2025年にかけての主要な変更点
固定電話のサービス終了時期について理解するためには、2024年から2025年にかけて実施された主要な変更点を把握しておく必要があります。
2024年1月1日をもって、NTT東日本とNTT西日本は固定電話のインフラをPSTNからIP網へ移行しました。この移行作業は2024年11月までに完了しており、現在ではすべての固定電話通信がIP網を経由して行われています。この技術移行は、通信設備の老朽化に対応するための措置でした。具体的には、中継交換機や信号交換機といった通信を支える重要な設備が2025年頃に保守限界を迎えることが判明していたため、新しい技術基盤への移行が必要だったのです。
IP網への移行により、利用者にとって大きく変わったことは多くありません。電話番号は変わらず、基本料金もほぼ据え置かれています。普段の電話のかけ方や受け方も従来通りで、多くの家庭や企業では移行前後で違いを感じることなく電話を使い続けています。
ただし、一部のサービスについては終了や変更がありました。例えば、177番の天気予報サービスは2025年3月31日をもって終了しました。また、104番の電話番号案内サービスは2026年3月31日に終了予定となっています。これらのサービスは利用率が大幅に低下していたことや、インターネットで同様の情報を簡単に入手できるようになったことが終了の理由です。
さらに2025年1月からは、双方向番号ポータビリティという新しいサービスが開始されました。これは、固定電話とIP電話の間で電話番号を相互に移行できる制度です。従来は固定電話からIP電話への番号移行は可能でしたが、逆方向の移行ができませんでした。この新制度により、IP電話から従来型の固定電話サービスへ戻る際にも同じ電話番号を維持できるようになり、利用者の選択肢が広がりました。
2035年頃に予定されているメタル回線の完全終了
固定電話のサービス終了時期として最も重要な節目となるのが、2035年頃に予定されているメタル回線の完全終了です。NTT東日本とNTT西日本は2025年9月29日に、メタル回線を使った固定電話サービスを2035年頃に終了すると正式に発表しました。
この発表の背景には、メタル回線設備の老朽化と利用者数の減少があります。かつて全国で約6000万回線あった固定電話の契約数は、現在では1000万回線を下回る水準まで減少しています。携帯電話やスマートフォンの普及により、固定電話の必要性が低下していることが主な要因です。
メタル回線設備を維持するためには、銅線の保守や交換設備の管理など、多大なコストと人的資源が必要です。しかし、利用者が減少する中でこれらの設備を維持し続けることは、技術的にも経済的にも限界に近づいています。部品の供給が停止されたり、設備を管理できる技術者の確保が困難になったりするなど、さまざまな課題が表面化しているのです。
ただし、2035年にメタル回線が終了しても、固定電話サービス自体は継続されます。これは何度強調しても足りないほど重要なポイントです。2035年以降も、IP網を使った固定電話サービスは提供され続けます。電話機や電話番号はそのまま使い続けることができ、通話品質にも大きな影響はないと考えられています。
IP網移行による技術的な変化とメリット
従来のメタル回線とIP網では、通信の仕組みが根本的に異なります。メタル回線では銅線を使って音声信号をアナログで伝送していましたが、IP網では音声をデジタルデータに変換し、インターネットと同じパケット通信方式で伝送します。この技術はVoIPと呼ばれ、すでに多くのIP電話サービスで採用されています。
IP網への移行により、さまざまなメリットが期待されています。通信インフラの維持管理がより効率的になることは、大きな利点の一つです。IP網は既存のインターネットインフラを活用できるため、専用の電話網設備を維持する必要が減り、コスト削減につながります。このコスト削減効果は、長期的には利用者の料金負担軽減にも寄与する可能性があります。
新しいサービスの提供がしやすくなることも重要なメリットです。IP技術を使うことで、音声通話だけでなく、ビデオ通話や多様な付加サービスの提供が容易になります。企業向けには、通話録音機能や自動音声応答システム、着信ルーティングといった高度な機能を比較的低コストで導入できるようになります。
災害時の復旧が迅速化される可能性も期待されています。IP網は柔軟なネットワーク構成が可能なため、障害が発生した場合の代替ルートの確保や復旧作業がスムーズに行えます。従来のメタル回線では物理的な銅線が断線すると復旧に時間がかかりましたが、IP網では論理的な経路の変更で対応できる場合が多くなります。
通話料金の変化と企業へのメリット
IP網への移行により、通話料金の体系も大きく変わりました。この変更は特に企業にとって大きなメリットとなっています。
従来のPSTN網では、固定電話から固定電話への通話料金は距離に応じて異なっていました。市内通話、県内市外通話、県外通話といった区分があり、遠距離になるほど通話料金が高くなる仕組みでした。例えば、東京から大阪への通話は3分間で数十円という高額な料金がかかっていました。全国に支店や取引先を持つ企業では、この長距離通話料金が経営の大きな負担となっていたのです。
しかし、IP網への移行により、固定電話から固定電話への通話料金が全国一律で3分あたり9.35円になりました。これは従来の市内通話料金とほぼ同等の水準です。この料金体系の変更により、長距離通話が多かった企業では通話料金の大幅な削減が実現しています。例えば、東京の本社から北海道や九州の支店への通話が頻繁にある企業などでは、年間の通信費を数十万円から数百万円削減できるケースも珍しくありません。
この通話料金の一律化は、地方に拠点を持つ企業や全国展開している企業にとって特に大きなメリットとなっています。従来は通話料金を気にして電話でのコミュニケーションを控えていた場合でも、料金を気にせず気軽に連絡を取れるようになり、業務効率の向上にもつながっています。
企業が注意すべきISDN回線の終了
企業にとって特に重要な変更点が、ISDN回線のデジタル通信モードの終了です。2024年にINSネットのデジタル通信モードが終了したことで、この回線を使用していた企業には大きな影響が出ています。
ISDN回線は、その安定性と信頼性の高さから、長年にわたって企業で重用されてきました。特にEDIと呼ばれる電子データ交換システムの通信回線として、卸売業や製造業などで広く採用されていました。取引先とのデータのやり取り、受発注システム、在庫管理システムなどで、ISDN回線の安定した通信が活用されていたのです。
小売店舗のPOSレジシステムでもISDN回線が広く使われていました。店舗で集計された売上データを本部に送信する際に、ISDN回線の安定性が重視されていました。しかし、IP網移行に伴いINSネットのデジタル通信モードが廃止されたことで、これらのシステムが正常に動作しなくなるリスクが生じています。データが適切に本部に反映されなければ、売上管理や在庫管理に支障をきたし、経営判断にも影響が出てしまいます。
企業がISDN回線を使用しているかどうかを確認するには、NTTからの請求書をチェックする方法があります。請求書にINS通信料という項目が記載されている場合、INSネットのデジタル通信モードを利用している可能性が高いため、早急に対応策を検討する必要があります。
NTT東日本とNTT西日本では、IP網移行に伴う代替サービスへの切り替えを基本的に無料で対応しています。ただし、古い機器の交換が必要な場合は機器代金が発生する可能性があります。企業としては、使用している電話設備やPBX、周辺機器の対応状況を早めに確認し、必要に応じて更新計画を立てることが重要です。
クラウドPBXという新しい選択肢
IP網移行を機に、多くの企業が検討しているのがクラウドPBXの導入です。PBXとは構内交換機のことで、企業内の電話を管理制御するシステムを指します。
従来のPBXは、専用の機器を企業内に設置する必要があり、初期費用が数十万円から数百万円、大規模なシステムでは数千万円に達することもありました。また、機器の保守費用や更新費用も継続的に発生するため、特に中小企業にとっては大きな負担となっていました。
一方、クラウドPBXは、このPBX機能をクラウド上で提供するサービスです。専用機器の購入や設置工事が不要なため、初期費用を大幅に削減できます。月額利用料を支払うサブスクリプション型のサービスが多く、従業員数や必要な機能に応じて柔軟にプランを選択できます。
クラウドPBXの大きなメリットは、リモートワークへの対応のしやすさです。インターネット接続があれば、どこからでも会社の電話番号で発着信ができます。自宅やコワーキングスペース、カフェなど、場所を選ばずに会社の電話対応ができるため、働き方改革やハイブリッドワークの推進にも寄与します。
スマートフォンとの連携も容易です。専用アプリをインストールすれば、個人のスマートフォンを会社の内線として使用できます。外出先でも内線通話が可能になり、通信費の削減にもつながります。また、社員の携帯電話番号を顧客に教える必要がなくなるため、プライバシー保護の観点からもメリットがあります。
通話録音、自動音声応答、着信ルーティング、稼働状況の可視化など、多様な付加機能を利用できることも魅力です。これらの機能は従来のPBXでは高額なオプションとして提供されていましたが、クラウドPBXでは標準機能として含まれている場合が多く、業務効率化につながります。
光電話という選択肢とそのメリット
一般家庭や小規模事業所では、光電話が固定電話の代替手段として注目されています。光電話とは、光ファイバーを使ったインターネット回線を利用して通話を行うサービスのことです。
光電話の最大のメリットは料金の安さです。従来のアナログ固定電話の月額基本料金は住宅用で1870円程度でしたが、光電話の月額基本料金は500円前後と大幅に安くなっています。年間で計算すると、16000円以上の節約になる計算です。
通話料金も割安です。光電話から固定電話への通話は全国一律で3分8円程度となっており、従来のアナログ固定電話の県外通話料金と比べると大幅に安くなっています。遠方の親戚や友人と頻繁に電話をする方にとっては、通話料金の削減効果は非常に大きいでしょう。
アナログ固定電話を新規に契約する際に必要だった電話加入権も不要です。この電話加入権は正式には施設設置負担金と呼ばれ、39600円という高額なものでした。光電話ではこの負担がないため、初期費用を大幅に抑えることができます。
通話品質も優れています。デジタル信号で音声を伝送するため、ノイズが入りにくく聞き取りやすい通話が可能です。一般的にアナログ固定電話よりも音がクリアで、特に高齢者の方からは「相手の声がはっきり聞こえるようになった」という評価を受けています。
既存の電話番号や電話機もそのまま使えることが多いのも大きなメリットです。NTT東日本やNTT西日本の加入電話から光電話へ切り替える場合、基本的に現在使っている電話番号を継続して利用できます。番号ポータビリティにより、長年使い慣れた電話番号を変更する必要がありません。また、電話機本体も従来のアナログ電話機をそのまま使用できるため、新たに電話機を購入する必要もありません。
光電話のデメリットと注意点
光電話には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点もあります。これらを理解した上で導入を検討することが重要です。
最も大きなデメリットは、停電時に使えないことです。光電話はインターネット接続が必須であり、光回線終端装置やルーターなどの機器が電気で動作しているため、停電になると使用できなくなります。従来のアナログ固定電話は電話回線から電力供給を受けていたため停電時でも通話が可能でしたが、光電話ではこの利点が失われます。
特に災害時には、停電が長期化する可能性があります。そのような状況では、光電話が使えず連絡手段が断たれてしまうリスクがあります。災害時の備えとして、携帯電話を充電しておくことや、モバイルバッテリーを常備しておくことが重要です。また、光回線終端装置に接続できるバッテリーバックアップ装置を導入する方法もあります。
光電話を利用するには光回線の契約が必須となります。電話だけを使いたいという場合でも、光回線とセットで契約する必要があり、光回線の月額料金も負担することになります。光回線の月額料金は事業者やプランによって異なりますが、一般的に4000円から6000円程度です。ただし、インターネットも利用する場合は通信費を一本化できるため、むしろお得になる場合が多いでしょう。
光回線を新たに導入する場合は、開通工事が必要になります。工事には立ち会いが必要な場合が多く、工事日程の調整が必要です。また、工事費用も発生しますが、多くの光回線事業者では新規契約者向けのキャンペーンで工事費を実質無料にするなどの施策を行っています。
一部の電話サービスが利用できないという点にも注意が必要です。例えば、106番のコレクトコールや114番のお話し中調べなど、一部の特番サービスは光電話では利用できません。0120や0800のフリーダイヤルへの発信は可能ですが、一部のナビダイヤルや特殊な番号には発信できない場合があります。仕事で特定の番号をよく利用する方は、事前に利用可能かどうか確認しておくことをお勧めします。
固定電話が依然として重要な理由
スマートフォンが普及した現代でも、固定電話が依然として重要な役割を果たしている場面は多くあります。
災害時の通信手段として、固定電話は重要です。大規模災害時には携帯電話がつながりにくくなることがあります。東日本大震災や熊本地震などの大規模災害では、携帯電話の基地局が損傷したり、通信回線が混雑したりして、携帯電話が使えない状況が発生しました。一方、固定電話は比較的安定した通信手段として機能する傾向があります。複数の通信手段を確保しておくことが、災害時の安心につながります。
高齢者世帯にとっては、使い慣れた固定電話の方が安心できるという声も多く聞かれます。スマートフォンは多機能で便利ですが、操作が複雑で高齢者には使いにくいという側面があります。固定電話は操作が簡単で、大きなボタンの電話機も多く販売されています。また、受話器を持って話すという従来のスタイルは、高齢者にとって慣れ親しんだ安心感のある方法です。
企業の代表番号としても、固定電話番号は信頼性の象徴として重要視されています。特に03番号や06番号などの地域番号は、その地域に実際の拠点があることを示す重要な情報となります。携帯電話番号やIP電話の050番号だけを掲載している企業と比べて、地域の固定電話番号を持っている企業の方が信頼性が高いと評価される傾向があります。顧客や取引先に対して、確固たる事業基盤があることをアピールする効果もあります。
金融機関やクレジットカード会社への登録では、固定電話番号が必要とされる場合があります。本人確認や信用情報の観点から、固定電話番号の有無が審査に影響することもあります。住宅ローンやカードローンの審査では、固定電話番号があることがプラスの評価につながることが多いです。これは、固定電話があることで居住地が明確であり、連絡が取りやすいと判断されるためです。
2025年5月の全国一律提供義務廃止とその影響
固定電話サービスに関する重要な政策変更として、2025年5月にNTT東日本とNTT西日本の固定電話全国一律提供義務を廃止する法律が可決されました。この変更は、固定電話サービスの将来に大きな影響を与える可能性があります。
これまでNTT東日本とNTT西日本は、電気通信事業法により、日本全国どこでも同一条件で固定電話サービスを提供する義務を負っていました。この義務はユニバーサルサービス義務と呼ばれ、通信インフラが社会の基盤として重要であるという考えから、採算性に関わらず全国均一でサービスを提供することが求められていたのです。
しかし、固定電話の契約者数が大幅に減少し、携帯電話が広く普及した現在、この義務を維持することの必要性が見直されることになりました。年代別の固定電話利用率を見ると、その変化は顕著です。80歳以上の高齢者では94.7パーセントが固定電話を利用している一方、30代では21.4パーセント、20代ではわずか8.1パーセントという調査結果が出ています。若い世代ほど固定電話を持たずに携帯電話のみで生活するスタイルが一般的になっているのです。
義務の廃止により、NTT東日本とNTT西日本は、利用者が極めて少ない地域などではサービス提供を見直す可能性もあります。特に人口減少が進む過疎地域では、固定電話サービスの維持コストが収益を大きく上回っている場合があり、そうした地域でのサービス継続が課題となる可能性があります。
ただし、これは直ちに固定電話サービスが廃止されることを意味するわけではありません。需要がある地域では引き続きサービスが提供されますし、他の通信事業者がサービスを提供する選択肢もあります。政策的には、固定電話から携帯電話やインターネット通信へと、通信インフラの中心がシフトしていることを反映した変更と言えます。
IP網移行に便乗した詐欺への注意
IP網移行に伴い、残念ながらこの変化に便乗した詐欺や悪質な勧誘が増加しています。固定電話のサービス終了時期に関する誤った情報を利用して、利用者の不安を煽る手口が報告されているため、十分な注意が必要です。
典型的な詐欺の手口として、電話やメール、訪問販売などで「固定電話が使えなくなる」「今すぐ工事をしないと電話が止まる」「工事料が無料になるのは今日だけ」といった不正確な情報で不安を煽り、不要な契約を迫るケースがあります。実際には、前述の通り固定電話サービス自体は継続されますし、IP網への移行はすでにNTT側で対応済みです。一般の利用者が追加で工事や契約をする必要は基本的にありません。
不審な勧誘を受けた場合は、まず勧誘してきた業者の名称や連絡先を確認することが重要です。正規の業者であれば、会社名や担当者名、連絡先を明確に伝えるはずです。名刺やパンフレットを受け取り、後で確認できるようにしておきましょう。
次に、NTT東日本やNTT西日本に直接問い合わせて、その業者が正規の代理店かどうか、工事や契約が本当に必要かどうかを確認することをお勧めします。公式の問い合わせ窓口の電話番号は、請求書や公式ウェブサイトで確認できます。電話で問い合わせる際には、勧誘業者から聞いた内容を詳しく伝え、事実確認をしてもらいましょう。
契約を急がせる業者には特に注意が必要です。「今日中に契約しないと間に合わない」「このチャンスを逃すと損をする」などと言って契約を迫る場合は、詐欺の可能性が高いと考えられます。正規の業者であれば、利用者が十分に検討する時間を提供するはずです。
高額な機器の購入や工事費を要求された場合も警戒が必要です。IP網移行自体は基本的に無料で対応されているため、高額な費用を請求されること自体が不自然です。数万円から数十万円の機器購入を求められた場合は、一度立ち止まって家族や信頼できる人に相談することが重要です。
不審な勧誘や詐欺被害に遭った場合は、最寄りの消費生活センターに相談することをお勧めします。消費者ホットライン188番に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。また、明らかな詐欺行為があった場合は、警察への相談も検討してください。
利用者が今取るべき対応
固定電話のサービス終了時期や今後の変化について理解した上で、利用者が今取るべき対応をまとめます。
まず、現在使用している固定電話サービスの種類を確認しましょう。加入電話なのか、INSネットなのか、あるいはすでに光電話などのIP電話サービスを利用しているのかを把握することが第一歩です。NTTからの請求書を確認すれば、契約しているサービスの種類が記載されています。不明な場合は、NTTのカスタマーセンターに問い合わせることで確認できます。
次に、使用している電話機や周辺機器がIP網に対応しているかを確認します。ほとんどの一般的な電話機は問題なく使用できますが、古いFAX機や特殊な通信機器を使用している場合は、対応状況を確認する必要があります。メーカーのウェブサイトや取扱説明書で確認できますし、不明な場合はメーカーやNTTに問い合わせることもできます。
法人企業の場合は、電話システム全体の見直しを検討する良い機会です。クラウド型のPBXサービスや、リモートワークに対応した電話システムなど、業務効率化につながる選択肢を検討してみましょう。特にテレワークを導入している企業や、複数の拠点を持つ企業では、クラウドPBXの導入により大幅なコスト削減と業務効率化が実現できる可能性があります。
固定電話の必要性そのものを見直すことも重要です。本当に固定電話が必要なのか、代替手段で十分なのかを判断し、必要に応じてサービスの見直しを行いましょう。一人暮らしで携帯電話があれば十分という場合は、固定電話を解約して通信費を削減することも選択肢の一つです。一方、高齢者と同居している家庭や、企業の代表番号として固定電話が必要な場合は、より経済的なサービスへの切り替えを検討すると良いでしょう。
停電時の対策も考えておく必要があります。IP電話や光電話は停電時に使用できなくなるため、携帯電話を常に充電しておく、モバイルバッテリーを常備する、バッテリーバックアップ装置を導入するなどの対策を講じることが重要です。
今後の展望と通信サービスの変化
2025年以降も固定電話サービスは継続されますが、その形態は徐々に変化していくでしょう。IP技術の進化により、音声通話だけでなく、映像や多様なデータを組み合わせた新しいコミュニケーションサービスが登場する可能性があります。
5G通信やIoT技術との連携により、固定電話の概念そのものが変わっていくかもしれません。家庭内のスマートデバイスと連携した通信サービスや、AI技術を活用した自動応答システム、音声認識による自動文字起こし機能など、さまざまな可能性が考えられます。固定電話が単なる音声通話の手段から、スマートホームの一部として進化していく可能性もあります。
企業においては、クラウドPBXなどのIP技術を活用した電話システムへの移行が加速すると予想されます。リモートワークやハイブリッドワークが定着する中で、場所を問わず会社の電話番号で発着信できるシステムの需要は高まっています。また、AI技術を活用した自動応答システムや、顧客管理システムとの連携など、電話システムの高度化も進んでいくでしょう。
メタル回線の終了が2035年頃に予定されているため、それまでの約10年間で段階的な移行が進められることになります。NTT東日本とNTT西日本は、利用者が混乱しないよう丁寧な案内と対応を行うことが期待されています。総務省も固定電話網の移行を監督し、利用者保護の観点から適切な移行が行われるよう指導しています。
特に高齢者世帯や、固定電話を重要な連絡手段としている企業に対しては、十分な移行期間と支援が必要です。デジタルデバイドを解消し、誰もが安心して通信サービスを利用できる環境を整えることが、今後の重要な課題となっています。高齢者向けの簡単な操作説明会や、企業向けの移行支援サービスなど、きめ細かいサポートが求められます。
固定電話サービスは長い歴史の中で、私たちの生活や社会インフラとして重要な役割を果たしてきました。技術は変わっても、人と人をつなぐというコミュニケーションの本質は変わりません。2025年以降も、形を変えながら固定電話サービスは私たちの生活を支え続けていくでしょう。
今回の固定電話サービス終了時期に関する変化は、単なる技術移行にとどまらず、私たちの通信環境全体を見直す良い機会となっています。自分や家族、企業にとって最適な通信手段は何かを考え、必要に応じて新しいサービスへの切り替えを検討することで、より快適で経済的な通信環境を実現できるでしょう。

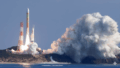

コメント