2025年の秋は、インフルエンザの動向が例年とは大きく異なる様相を見せています。通常であれば晩秋から冬にかけて流行が本格化するところ、今年は9月の時点ですでに全国各地の学校で学級閉鎖が相次ぎ、異例の早期流行が報告されました。この現象は単なる季節のずれではなく、記録的な猛暑による免疫力の低下、国際的な人の往来の活発化によるウイルスの早期流入、そして新型コロナウイルスのパンデミック後の社会環境の変化など、複数の要因が複雑に絡み合った結果と考えられています。11月を目前に控えた今、私たちはこれまでの常識が通用しない新しいインフルエンザシーズンに備える必要があります。本記事では、2025年11月以降の流行予測について最新のデータに基づいて詳しく解説するとともに、今シーズンから大きく変更されたワクチンの情報、そして日常生活で実践できる効果的な予防策まで、総合的にお伝えします。

2025年11月からのインフルエンザ流行予測
早期流行が示す異変の兆候
2025年のインフルエンザシーズンは、これまでの経験則では予測できない特異な展開を見せています。9月の時点で全国各地の小中学校において学級閉鎖が報告され、通常よりも明らかに早い時期から感染が広がり始めました。この異例の早期流行には、明確な理由があります。
まず第一に挙げられるのが、2025年に日本を襲った記録的な猛暑の影響です。インフルエンザウイルスは低温・乾燥した環境を好むため、従来は夏場の流行は考えにくいとされてきました。しかし、猛暑がもたらした間接的な影響が、ウイルスの拡散に好都合な環境を作り出してしまったのです。連日の熱帯夜による睡眠不足、夏バテによる栄養バランスの乱れは、私たちの免疫力を著しく低下させました。さらに、酷暑を避けるために冷房の効いた室内で過ごす時間が増えたことも重要な要因です。冷房が効いた部屋は窓が閉め切られ、空気が循環せず乾燥しやすくなります。この密閉された乾燥空間では、ウイルスの活性が高まるだけでなく、私たちの喉や鼻の粘膜の防御機能も弱まってしまいます。
第二の要因として、グローバルな人の移動が挙げられます。インフルエンザウイルスは季節を追いかけるように地球上を移動しながら流行を繰り返します。日本の冬の流行を予測する上で重要な指標となるのが、南半球の流行状況です。特にオーストラリアでは6月から8月にかけて冬を迎えるため、その時期の流行データは日本の流行予測に直結します。近年、国際的な人の往来が活発化したことで、オーストラリアで流行していたウイルスが旅行者などを介して日本に持ち込まれる機会が大幅に増加しました。実際に、京都府京都市などの一部地域では、9月上旬の時点で流行開始の目安となる数値を超え、全国に先駆けて流行期入りが宣言されています。
11月以降の流行タイムラインと予測される規模
南半球での流行パターンと国内の初期動向を分析すると、2025年11月以降のインフルエンザ流行について具体的な見通しが立てられます。
本格的な感染者数の増加は11月半ば頃から始まると予想されています。その後、流行のピークは12月下旬に訪れる可能性が高いと考えられます。ただし、医療現場の実感としては、2025年12月第1週から2026年1月第2週にかけて、最も患者数が多い期間が続くと見込まれています。
今シーズンの流行で特に警戒すべきなのが、ピーク期間の長期化です。先行指標となる2025年のオーストラリアの流行では、感染者数がピークに達した後、なかなか減少せず高止まりする傾向が観察されました。このパターンが日本でも再現されるとすれば、2026年1月中旬から下旬まで感染拡大が続く可能性があります。年末年始の休暇で一度落ち着いたように見えても、年明けに再び感染の波が訪れる可能性を念頭に置き、長期間にわたる警戒が必要です。
流行の規模については、過去のパンデミックのような爆発的な大流行と比較すると、ピーク時の感染者数はやや低めになる可能性がありますが、例年のシーズンと比較すれば十分に大きな流行規模に達すると予測されており、決して油断はできません。
A型とB型の同時流行リスク
今シーズンのもう一つの特徴として、異なる種類のインフルエンザウイルスが同時期に、あるいは時期をずらして流行する二峰性のパターンを示す可能性が指摘されています。
過去の2024-2025年シーズンを振り返ると、11月から1月にかけてA型が猛威を振るい、その後2月から3月にかけてB型が流行するという傾向が見られました。その結果、シーズン中にA型とB型の両方に感染し、インフルエンザに2度かかるというケースも珍しくありませんでした。
2025-2026年シーズンも、このA型・B型の両方が流行すると考えられています。オーストラリアの2025年の流行データでは、特に5歳から19歳の若年層において、インフルエンザB型の占める割合が顕著に高いという特徴が見られました。この事実は、日本国内の学校や家庭において、シーズン早期からB型インフルエンザの集団感染が発生するリスクが高いことを示しています。
すでに日本の臨床現場では、2025年9月の時点で成人を中心にインフルエンザA型の陽性者が散見されており、A型ウイルスが水面下で広がり始めていることが確認されています。これに加えてB型が、特に子どもたちの間で広がるとなれば、社会全体としてA型とB型の両方に対処する必要が生じ、医療機関への負担増大も懸念されます。
2025-2026年シーズンのワクチン情報
4価から3価ワクチンへの歴史的転換
2025-2026年シーズンにおける最も重要な変更点は、これまで2015年度から使用されてきた4価ワクチンから3価ワクチンへの切り替えです。
従来の4価ワクチンは、A型の2種類(H1N1亜型、H3N2亜型)とB型の2つの系統(ビクトリア系統、山形系統)の合計4種類のウイルス株に対応していました。一方、今シーズンから供給される3価ワクチンは、A型の2種類はそのままに、B型はビクトリア系統の1種類のみを含む構成となります。
この変更は、ワクチンの品質低下やコスト削減が目的ではありません。これは最新のウイルス学的知見に基づいた、極めて合理的かつ科学的な判断によるものです。その背景には、一つのウイルス系統が地球上から姿を消したという驚くべき事実が存在します。
B型山形系統株の消滅という歴史的出来事
3価ワクチンへの移行の直接的な原因は、インフルエンザB型山形系統株が2020年3月以降、世界中のどこからも確実には検出されなくなったという事実にあります。
この現象の引き金となったのは、新型コロナウイルスのパンデミックです。世界中で実施されたマスク着用、手指衛生の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、ロックダウンといった大規模な感染対策は、新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザを含む他の呼吸器系ウイルスの伝播も劇的に抑制しました。その後、社会活動が徐々に再開されるにつれて、インフルエンザA型やB型ビクトリア系統は再び流行し始めましたが、B型山形系統だけは復活しませんでした。
もともと他のインフルエンザウイルスに比べて感染伝播力がやや弱い特性があったB型山形系統は、世界的な感染の連鎖が断ち切られたことで、自然界から消滅した可能性が極めて高いと考えられています。
この状況を受けて、世界保健機関(WHO)は、もはや流行していないB型山形系統株をワクチンに含める必要はないと結論付けました。それだけでなく、むしろワクチンから除外すべきであると強く推奨するに至りました。その理由は、一部の国で使用されている経鼻弱毒生ワクチンに関係しています。この生ワクチンは弱毒化されているとはいえ生きたウイルスを使用するため、接種者がワクチン由来のウイルスを排出し、それが免疫のない人々の間で広がる「ワクチン由来株の再導入」というリスクが懸念されるからです。実際に、2020年以降に報告された数少ないB型山形系統の検出例の多くが、この生ワクチンに由来するものであったことが指摘されています。
したがって、B型山形系統株をワクチンから除くという決定は、存在しないウイルスへの備えを止めるだけでなく、ワクチンが原因でウイルスを再流行させてしまうという潜在的なリスクを未然に防ぐための、重要な公衆衛生上の措置なのです。
今シーズンのワクチン製造株と供給体制
厚生労働省によって決定された、2025-2026年シーズンに日本国内で製造・供給される3価インフルエンザHAワクチンの具体的な製造株は次の通りです。
A型株として、A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)とA/パース/722/2024(IVR-262)(H3N2)の2種類が含まれます。このうちA/H3N2株は昨シーズンから更新されており、現在流行しているウイルスによりよく適合するよう選定されています。B型株としては、B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)が含まれます。
ワクチンの供給量については、今シーズン全体で約5,293万回分が見込まれています。これは近年の平均的な使用量である約4,860万回分を上回る量であり、適切に使用されればワクチンが不足することはないとされています。
供給スケジュールも、早期流行に対応できるよう前倒しで計画されました。ワクチンの出荷は9月下旬から始まり、10月初旬の時点ですでに総供給量の6割を超える約3,578万回分が出荷されました。これにより、流行が本格化する11月よりも前に、多くの方が接種を受けられる体制が整えられています。
高齢者向け高用量ワクチンという新たな選択肢
今シーズンは、従来のワクチンに加え、特定の年齢層を対象とした新しい選択肢が登場しています。
特に注目すべきは、60歳以上の高齢者を対象とした高用量ワクチン「エフルエルダ®」が承認され、提供が開始されることです。高齢者は加齢に伴い免疫機能が低下する傾向があり、通常のワクチンでは十分な免疫応答が得られない場合があります。高用量ワクチンは、標準的なワクチンよりも多くの抗原量を含むことで、より強力な免疫応答を誘導し、高齢者の発症予防および重症化予防効果を高めることが期待されています。
また、2歳から18歳までの子どもや若者には、注射ではなく鼻から噴霧するタイプの経鼻弱毒生ワクチン「フルミスト®」も選択肢の一つとなります。
ワクチンの効果と安全性の正しい理解
インフルエンザワクチンの効果を正しく理解することは非常に重要です。ワクチンの発症予防効果は、その年の流行株とワクチン株の一致度などにもよりますが、一般的に40%から60%程度とされています。つまり、ワクチンを接種してもインフルエンザにかかる可能性はゼロではありません。
しかし、ワクチンの最も重要な役割は、感染そのものを100%防ぐことではなく、重症化を防ぐことにあります。ワクチン接種は、入院や集中治療室での治療が必要になるような重篤な状態に陥るリスク、そして最悪の場合には死亡するリスクを大幅に低下させることが数多くの研究で証明されています。
安全性に関しても、インフルエンザワクチンは長年の使用実績があり、安全性の高いワクチンです。また、新型コロナウイルスワクチンとの同時接種も可能であり、同日に両方のワクチンを接種することができます。
インフルエンザの基本知識と見分け方
普通の風邪との決定的な違い
インフルエンザと普通感冒(いわゆる風邪)は、どちらもウイルスによる呼吸器感染症ですが、原因となるウイルスも症状の重さも全く異なります。
インフルエンザは、インフルエンザウイルス(季節性流行の主因はA型とB型)によって引き起こされます。一方、風邪はライノウイルス、アデノウイルス、RSウイルスなど、200種類以上もの多種多様なウイルスが原因となり得ます。この原因ウイルスの違いが、症状の現れ方に決定的な差を生み出します。
インフルエンザの最も顕著な特徴は、症状が突然かつ全身に現れることです。潜伏期間は1日から3日と短く、発症すると38℃以上の高熱が急激に出現します。それに伴い、強い悪寒、激しい頭痛、そして節々が痛むと表現されるような顕著な関節痛や筋肉痛、強い全身倦怠感が襲います。咳や喉の痛み、鼻水といった呼吸器症状は、これらの全身症状にやや遅れて現れることが多いです。特に2025年の流行では、40℃以上の高熱や強い全身倦怠感を訴えるケースが多いと報告されています。
対照的に、風邪の症状は比較的緩やかに始まり、主に局所的です。喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳といった上気道症状が中心で、発熱しても37℃台の微熱で済むことが多く、38℃を超える高熱が出ることは稀です。インフルエンザのような強い関節痛や筋肉痛、全身倦怠感が見られることはほとんどありません。
このように、急な高熱と強い全身症状(特に体の痛み)の有無が、インフルエンザと風邪を見分けるための重要なポイントとなります。
感染経路と感染拡大を防ぐ社会的責任
インフルエンザの感染力は非常に強く、その拡大メカニズムを理解することは予防策を講じる上で不可欠です。
主な感染経路は、咳やくしゃみによって放出されるウイルスを含んだ飛沫を吸い込むことによる飛沫感染です。感染者から約2メートル以内の距離にいると、感染リスクが非常に高まります。また、ウイルスが付着したドアノブや手すりなどに触れた手で目や鼻、口を触ることによる接触感染も起こり得ます。
ウイルスに感染してから症状が現れるまでの潜伏期間は、1日から3日間と非常に短いのが特徴です。この短さが、学校や職場などで爆発的な集団感染を引き起こす一因となっています。
感染を広げないためには、発症後の行動が極めて重要です。学校保健安全法では、インフルエンザは第二種の感染症に指定されており、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで出席停止とされています。これは、症状が軽快しても体内からウイルスが排出され続けているためです。社会人においても、多くの職場でこの基準に準じた自宅療養が推奨されます。自身の回復だけでなく、周囲への感染拡大を防ぐという社会的責任を果たすためにも、この期間は外出を控え、安静に努めることが求められます。
重症化リスクが高い方々と警戒すべき合併症
インフルエンザは多くの方にとっては一週間程度で回復する疾患ですが、一部の方々にとっては命に関わる重篤な病態を引き起こす可能性があります。
特に重症化リスクが高いとされるのは、高齢者、乳幼児、妊婦、そして喘息などの慢性呼吸器疾患、心疾患、糖尿病、免疫機能が低下しているといった基礎疾患を持つ方々です。これらの方々は、ウイルスそのものによる症状が重くなるだけでなく、危険な合併症を引き起こしやすいため、特に注意が必要です。
インフルエンザにおける最も警戒すべき合併症は、二次性細菌性肺炎です。インフルエンザウイルスに感染すると、気道の上皮細胞が破壊され、体の防御機能が一時的に低下します。この無防備になった気道に、肺炎球菌や黄色ブドウ球菌といった細菌が侵入し、肺炎を引き起こすのです。過去のパンデミックにおいても、死亡例の多くがこの細菌性肺炎の合併によるものでした。インフルエンザの症状が一度改善しかけた後に、再び高熱や激しい咳、膿性の痰、呼吸困難などが出現した場合は、細菌性肺炎を強く疑い、直ちに医療機関を受診する必要があります。
その他にも、子どもでは中耳炎や熱性けいれん、稀ではありますが脳の炎症であるインフルエンザ脳症といった重篤な合併症が起こることがあります。インフルエンザを軽視せず、症状の経過を注意深く観察し、異常を感じたら速やかに専門家の診断を仰ぐことが、最悪の事態を避けるために不可欠です。
効果的な予防と対策
ワクチン接種と組み合わせる日々の予防策
ワクチンが重症化を防ぐための鎧だとすれば、これから紹介する予防策は、ウイルスとの接触機会そのものを減らすための盾の役割を果たします。これらを組み合わせることで、防御はより強固になります。
手指衛生の徹底が最も基本的かつ効果的な予防策です。流水と石鹸による手洗いは、手指に付着したウイルスを物理的に洗い流すための最良の方法です。外出からの帰宅時、食事の前、トイレの後、咳やくしゃみを手で押さえた後など、こまめに行うことが重要です。石鹸をよく泡立て、手のひら、手の甲、指の間、爪の先まで、最低20秒以上かけて丁寧に洗いましょう。流水が使えない状況では、アルコールベースの手指消毒剤も有効ですが、手に目に見える汚れがある場合は効果が低下するため、まずは洗い流すことが優先されます。
マスク着用と咳エチケットも重要です。新型コロナウイルスのパンデミックを経て、マスクの有効性は広く認識されるようになりました。特に人混みや換気の悪い屋内、公共交通機関などでは、マスクを適切に着用することが、飛沫の吸い込みと拡散の両方を防ぐのに役立ちます。また、咳エチケットの実践も社会全体の感染対策として重要です。咳やくしゃみが出る際は、マスクをするか、マスクがなければティッシュやハンカチ、あるいは肘の内側で口と鼻をしっかりと覆い、他人から顔をそむけましょう。
環境の整備として、換気と加湿も大切です。定期的に窓を開けて室内の空気を入れ替える換気は、空気中のウイルス濃度を下げるのに非常に効果的です。対角線上にある2か所の窓を開けると、空気の流れができて効率的に換気できます。また、インフルエンザウイルスは乾燥した環境で活性化します。加湿器などを使用して、室内の湿度を50%から60%に保つことで、ウイルスの生存率を低下させると同時に、喉や鼻の粘膜の防御機能を維持することができます。
感染してしまった場合の治療法
適切な予防策を講じても、感染を完全に避けることが難しい場合もあります。インフルエンザと診断された場合、症状を和らげ、回復を早めるために抗インフルエンザウイルス薬が用いられます。これらの薬は、発症から48時間以内に服用を開始すると最も効果が高いとされています。
現在、主に使用されている抗インフルエンザ薬は、作用機序によって大きく二つのグループに分けられます。
ノイラミニダーゼ阻害薬は、細胞内で増殖したウイルスが細胞の外に放出されるのを防ぐことで、体内でのウイルス拡散を抑制します。代表的な薬には、5日間服用する経口薬のタミフル®(一般名:オセルタミビル)、5日間吸入する吸入薬のリレンザ®(ザナミビル)、そして1回の吸入で治療が完了する長時間作用型の吸入薬イナビル®(ラニナミビル)があります。吸入薬は気道に直接作用しますが、喘息などの呼吸器疾患がある場合は使用に注意が必要です。
エンドヌクレアーゼ阻害薬は、比較的新しい作用機序を持つ薬で、ウイルスの遺伝子複製そのものを阻害します。代表薬はゾフルーザ®(バロキサビル マルボキシル)です。この薬の最大の特徴は、経口薬でありながら、たった1回の服用で治療が完了するという利便性の高さにあります。
どの薬を選択するかは、患者の年齢、症状、基礎疾患の有無、そして服薬のしやすさなどを考慮して、医師が総合的に判断します。例えば、タミフルにはジェネリック医薬品があり、ゾフルーザに比べて安価であるという側面もあります。
自宅療養での回復を早めるポイント
抗ウイルス薬を服用すると同時に、体の免疫力がウイルスと戦うのを助けるための自己管理が回復への近道です。
安静と睡眠が何よりも重要です。体力を消耗せず、免疫システムがウイルス排除に集中できる環境を整えましょう。
水分補給も欠かせません。高熱が出ると、汗や呼吸によって大量の水分が失われ、脱水状態に陥りやすくなります。お茶やスープ、経口補水液、スポーツドリンクなどで、こまめに水分と電解質を補給してください。ただし、利尿作用のあるコーヒーや緑茶などのカフェイン飲料は、水分補給には適していません。
栄養摂取も大切です。食欲がない場合が多いですが、消化が良く、エネルギーになりやすい食事を心がけましょう。おかゆやうどん、スープ、ゼリーなど、口当たりの良いものが適しています。
家庭内での感染対策も忘れてはいけません。家族など同居者に感染を広げないための配慮も必要です。可能であれば療養は個室で行い、看病する人は限定しましょう。ドアノブやテーブルなど共有部分を定期的に消毒し、タオルは別々のものを使用します。療養している部屋も定期的に換気することが推奨されます。
まとめ
2025年11月以降のインフルエンザシーズンは、記録的猛暑や活発な国際交流といった現代社会を象徴する要因に後押しされ、例年よりも早く、そして長く続く可能性を秘めた、注意すべきシーズンとなることが予測されています。
しかし、私たちはこの脅威に対して、かつてないほど多くの科学的知見と効果的なツールを手にしています。早期かつ長期の流行に備える意識を持ち、11月からの本格的な流行開始と年明けまで続く可能性のある長期戦を念頭に置き、早期からの予防策の徹底が求められます。
今シーズンの3価ワクチンへの移行は、B型山形系統株の世界的消滅という科学的事実に基づいた、合理的かつ先進的な対応です。ワクチンは依然としてインフルエンザによる重症化を防ぐための最も強力な武器であることに変わりはありません。特に高齢者の方は、新たに利用可能となった高用量ワクチンも有力な選択肢となります。
そして、ワクチン接種と日々の予防策を組み合わせる多層的な防御が不可欠です。ワクチン接種を基本としつつ、日々の手洗い、咳エチケット、適切な環境管理といった地道な努力を重ねることが、感染リスクを最小限に抑えるための鍵となります。
正確な知識を持ち、科学的根拠に基づいたワクチン接種と予防行動を一人ひとりが着実に実践することで、私たちはこの流行シーズンを乗り越えることができます。自分自身の健康、そして社会全体の健康を守るために、賢明な選択と行動を心がけましょう。

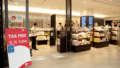

コメント