2025年は日本の税制において重要な転換点となります。多くの家庭に影響を与える扶養控除の所得要件が大幅に見直され、従来の103万円の壁が123万円の壁へと変更されることになりました。この変更は2025年12月1日から施行され、同月に実施される年末調整から適用が始まります。働く学生やパート・アルバイトで収入を得ている扶養家族にとって、収入の上限が20万円引き上げられることは家計に大きなプラスとなります。また、19歳から22歳の大学生世代を対象とした特定親族特別控除という新しい制度も創設され、150万円まで親が満額の控除を受けられるようになりました。施行時期が2025年12月と年末に設定されているため、企業の給与担当者は年末調整の準備を急ぐ必要があります。本記事では、扶養控除の所得要件変更がいつから施行されるのか、具体的な変更内容、実務対応について詳しく解説していきます。

施行時期の詳細といつから適用されるのか
2025年の扶養控除に関する税制改正の施行時期は、実務において非常に重要なポイントとなります。施行日は2025年12月1日と定められており、この日から新しい制度が適用されます。具体的には、2025年1月1日から12月31日までの所得に対して、12月に実施される年末調整から新制度が適用される仕組みです。
2025年11月までの給与や公的年金等の源泉徴収事務については、従来のルールがそのまま継続されます。つまり、2025年の大半の期間は旧制度で源泉徴収が行われ、年末調整のタイミングで一気に新制度へと切り替わることになります。この年末での一括適用という方式は、給与担当者にとって年末調整の業務負担が増加することを意味しており、事前の準備と従業員への周知が極めて重要となります。
一方、源泉徴収税額表の変更については、さらに後の2026年1月1日以降に支払う給与から適用されることになっています。このため、2025年12月は年末調整では新制度が適用される一方で、毎月の源泉徴収は旧制度のままという複雑な状況が発生します。この二段階の施行方式は、実務担当者が正確に理解しておくべき重要なポイントです。
2025年分の所得税を計算する年末調整や確定申告では新制度が適用されますが、毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額の計算には、2026年1月までは旧制度が使われます。このタイミングのずれにより、2025年12月の年末調整では還付額が例年より大きくなる可能性が高く、企業は資金繰りへの影響も考慮する必要があります。
施行時期が年末に設定されたことで、2025年の大半の期間は従来通りの運用が可能である反面、12月に集中的な対応が求められることになります。給与システムの更新、申告書様式の変更、従業員への説明など、準備すべき事項は多岐にわたります。特に中小企業では、システム対応が間に合わない可能性もあるため、国税庁が提供する年調ソフトの活用も検討する価値があります。
扶養控除の所得要件変更の具体的な内容
扶養控除の所得要件変更の中心となるのは、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下へと10万円引き上げられたことです。この合計所得金額を給与収入に換算すると、従来の103万円から123万円へと20万円の拡大となります。
この20万円の拡大は、基礎控除と給与所得控除の両方が10万円ずつ引き上げられたことによって実現されました。まず、合計所得金額2,350万円以下の納税者が受けられる基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました。基礎控除は誰もが受けられる基本的な控除であり、この増額は多くの納税者に恩恵をもたらします。
さらに、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられました。給与所得控除は給与所得者が必要経費として認められる控除であり、この増額により給与所得者全体の税負担が軽減されます。基礎控除の10万円増額と給与所得控除の10万円増額が組み合わさることで、合計20万円の所得金額の引き上げとなり、結果として103万円の壁が123万円の壁へと移行したのです。
この変更により、扶養親族となる子どもや親が年間123万円まで収入を得ても、扶養控除の対象として親や配偶者が控除を受けられるようになりました。従来は年収が103万円を超えると扶養から外れてしまい、親の税負担が急増するため、多くの学生やパート労働者が収入を抑える働き方を選択していました。新制度では20万円分多く働けるようになり、年間の手取り収入が大幅に増加する可能性があります。
また、扶養控除だけでなく配偶者控除についても同様の変更が行われました。配偶者の年収が123万円以下であれば、納税者は最大38万円の配偶者控除を受けることができるようになります。さらに、配偶者特別控除の満額適用範囲も150万円から160万円へと引き上げられており、配偶者が160万円まで収入を得ても、納税者は最大38万円の控除を受けられます。
扶養控除の金額自体は変更されておらず、一般の扶養親族については38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)については63万円、老人扶養親族については48万円から58万円の控除額が維持されています。変わったのは、この控除を受けられる扶養親族の所得要件であり、より多くの収入を得ても扶養控除の対象となれるようになった点が重要です。
特定親族特別控除の新設と段階的控除の仕組み
2025年度の税制改正で最も注目すべき新制度が特定親族特別控除です。この制度は、19歳から22歳の大学生世代の子どもがいる家庭を対象とした画期的な控除制度であり、働く学生とその家族の税負担を大幅に軽減することを目的としています。
特定親族特別控除の最大の特徴は、子どもの年収が123万円を超えて扶養控除の対象外となっても、150万円以下であれば親は扶養控除と同額の63万円の控除を受けられるという点です。従来の制度では、扶養控除の要件から外れると一気に控除額がゼロになり、親の税負担が急激に増加していました。この新制度により、123万円を超えても段階的に控除額が減少する仕組みとなり、働く学生の収入増加意欲を阻害しない設計となっています。
具体的な控除額の計算方法を見てみましょう。子どもの年収が150万円までは、扶養控除と同額の63万円の控除が満額適用されます。150万円を超えた場合は、収入額に応じて段階的に控除額が減少していきます。子どもの年収が160万円の場合、控除額は51万円となります。年収が170万円の場合、控除額は31万円に減少します。さらに年収が180万円の場合は11万円となり、188万円を超えると控除額はゼロになります。
このように、一気に控除がなくなるのではなく、段階的に減少していく設計となっているため、働く学生にとっては収入を増やしやすく、親にとっては税負担が急増しない仕組みとなっています。特に、大学の学費や生活費の負担が大きい19歳から22歳の期間において、学生がアルバイトで収入を得やすくなることは、家計全体にとって大きなメリットとなります。
特定親族特別控除の適用時期については、計算の目的によって異なる点に注意が必要です。1年分の所得税を計算する年末調整や確定申告では2025年分から適用されます。一方、毎月の給与や賞与、年金から源泉徴収する所得税を計算する場合は2026年1月1日以降の支給分から適用されます。このタイミングのずれは、実務上混乱を招く可能性があるため、給与担当者は特に注意が必要です。
従来の制度では、大学生の子どもが年間103万円を超えて働くと、親は特定扶養控除63万円を失い、親の所得税と住民税が合わせて年間10万円以上増加するケースもありました。このため、多くの学生が103万円以内に収入を抑える働き方を選択せざるを得ませんでした。新制度では150万円まで満額の控除が受けられるため、年間47万円も多く働くことができ、学生の経済的自立を支援する効果が期待されています。
年末調整での実務対応と申告書の変更
2025年の年末調整では、申告書の様式が大きく変更されます。従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変更されます。
この統合により、従業員が記入する書類の枚数自体は増えませんが、1枚の申告書に記入すべき内容が増加し、複雑化することになります。基礎控除、配偶者控除等、所得金額調整控除に加えて、特定親族特別控除の申告欄が追加されるため、記入方法について従業員への丁寧な説明とサポートが必要になります。
改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいる場合には、扶養控除等異動申告書の追記提出を受ける必要があります。具体的には、子どもの収入が従来は103万円を超えていたため扶養対象外だったが、123万円以下であるため新たに扶養対象となる場合が該当します。また、19歳から22歳の子どもの収入が123万円を超えるが150万円以下であり、特定親族特別控除の対象となる場合も、申告書の提出が必要となります。
給与担当者は、従業員に対して改正内容を十分に周知し、該当者から必要な申告書を確実に提出してもらう必要があります。周知方法としては、社内メールでの一斉案内、社内掲示板への掲示、説明会の開催などが考えられます。特に、19歳から22歳の子どもがいる従業員や、親を扶養している従業員には、個別に案内することが望ましいでしょう。
特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員からは、給与所得者の特定親族特別控除申告書の提出を受ける必要があります。この申告書には、対象となる親族の氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、収入額などを記載する必要があり、正確な情報の把握が重要です。記入方法については、国税庁のホームページに詳細な記入例が掲載されており、従業員への案内の際にはこれらの資料を活用することが推奨されます。
年末調整の実務においては、計算ミスのリスクが高まる点にも注意が必要です。2025年の改正では、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設など、控除額の条件や判断基準に複数の見直しが行われています。そのため、例年と同じように処理をすると、控除額の誤適用や判定ミスが起きやすくなります。
特にミスが発生しやすいポイントとしては、扶養親族の所得要件の判定における103万円と123万円の混同、特定親族特別控除の対象者の判定における年齢要件(19歳から22歳)と収入要件(150万円以下)の確認漏れ、段階的控除額の計算ミス(150万円超188万円以下の場合の控除額計算)などが挙げられます。
これらのミスを防ぐためには、チェックリストの作成と活用、二重チェック体制の構築、システムによる自動計算の活用、従業員への丁寧な説明と正確な申告の依頼といった対策が有効です。特に、給与計算システムが2025年の改正に正しく対応しているかを事前に確認し、必要に応じてシステムの更新やテストを実施することが重要です。
企業の給与計算システム対応と更新の必要性
2025年の税制改正に対応するため、企業の給与計算システムには大幅な更新が必要となります。主な更新項目としては、扶養控除の所得要件を48万円以下から58万円以下に変更すること、給与収入ベースでは103万円から123万円に変更すること、特定親族特別控除の計算ロジックを新たに追加することなどが挙げられます。
特定親族特別控除の計算ロジックは複雑であり、年齢19歳から22歳の親族について、収入が123万円超150万円以下の場合は満額63万円、150万円超188万円以下の場合は段階的に減少する控除額を正確に計算する必要があります。また、基礎控除額を48万円から58万円に変更し、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に変更する必要もあります。
これらの変更は複雑であり、手作業での対応はミスのリスクが高まります。特に、特定親族特別控除の段階的控除額の計算は、収入額に応じて控除額が変動するため、正確な計算式をシステムに組み込む必要があります。システムベンダーに依頼してシステムを更新する場合は、2025年12月の年末調整に間に合うよう、早めの対応が必要です。
国税庁が提供する年調ソフトは、2025年の制度改正に完全対応しており、無料で利用できます。CSVファイルでのデータ入出力も可能なため、既存の給与システムからデータを移行して計算し、結果を戻すことができます。中小企業で専用の給与システムを導入していない場合や、システム更新のコストが負担となる場合は、この年調ソフトの活用が有効な選択肢となります。
2025年の大幅な税制改正を機に、クラウド型給与システムへの移行を検討する企業が増えています。クラウド型システムの最大の利点は、税制改正への自動対応です。法改正があってもシステム提供者側でアップデートが行われるため、企業側は特別な作業なしに新制度に対応できます。これにより、毎年の税制改正への対応コストと手間を大幅に削減できます。
クラウド型システムは初期投資が少なく、月額料金制で利用できるため、中小企業でも導入しやすいという利点があります。また、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、テレワークにも対応しやすいという特徴もあります。2025年の改正をきっかけに、給与計算業務のデジタル化を進めることも検討する価値があるでしょう。
源泉徴収税額表の変更と2026年1月以降の対応
2026年1月1日以降に支払う給与に適用される源泉徴収税額表が改正されます。扶養控除等申告書には、従来の控除対象扶養親族に加え、特定の特定親族を含んだ源泉控除対象親族を記載することとなります。
この変更により、毎月の給与計算における源泉徴収税額の計算方法が変わります。具体的には、扶養親族の数のカウント方法が変更され、特定親族特別控除の対象となる親族も一定の条件下で源泉控除対象親族として計上されることになります。源泉徴収税額表自体も改正され、控除額の引き上げを反映した新しい税額表が適用されます。
2025年12月の年末調整では新制度が適用されますが、毎月の源泉徴収については2026年1月から新制度が適用されるという二段階の実施となります。このため、2025年12月の給与計算では、年末調整は新制度で行うものの、源泉徴除は旧制度で行うという複雑な状況が発生します。
給与担当者は、この移行期の処理を正確に理解し、適切に対応する必要があります。特に、年末調整での還付額が例年より大きくなる可能性があるため、資金繰りへの影響も考慮が必要です。2025年の大半は旧制度で源泉徴収されているため、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設による控除増加分が、12月の年末調整で一気に還付されることになります。
2026年1月以降は、毎月の源泉徴収額が新制度に基づいて計算されるため、天引きされる税額が減少し、手取り額が増加することになります。従業員にとっては手取り収入が増えるメリットがありますが、企業側は源泉徴収税額表の変更に対応したシステム更新を2026年1月までに完了させる必要があります。
源泉徴収税額表の改正に対応するためには、給与システムの税額計算ロジックを更新する必要があります。特に、扶養親族の数のカウント方法が変更されるため、扶養控除等申告書の情報を正しくシステムに入力し、源泉徴収税額を正確に計算することが重要です。システムベンダーと早めに連携し、2026年1月の給与計算に間に合うよう準備を進めることが推奨されます。
配偶者控除と配偶者特別控除の変更内容
扶養控除だけでなく、配偶者控除と配偶者特別控除についても2025年の税制改正で重要な変更が行われました。従来、配偶者の年収が103万円以下の場合に配偶者控除が適用されていましたが、2025年からは配偶者の年収が123万円以下であれば、納税者は最大38万円の配偶者控除を受けることができるようになります。
この変更は、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ10万円ずつ増額されたことに対応したものです。基礎控除は48万円から58万円に、給与所得控除は最低控除額が55万円から65万円に引き上げられたため、基礎控除と給与所得控除を合計して、年間123万円までは扶養から外れることなく働けるようになりました。
配偶者控除だけでなく、配偶者特別控除についても重要な変更が行われました。2025年の税制改正で、配偶者特別控除を満額受けるための配偶者の年収上限が、150万円から160万円に引き上げられました。配偶者の年収が160万円までであれば、納税者は最大38万円の配偶者特別控除(配偶者控除と同額)を受けられます。
配偶者の年収が123万円を超えて160万円までの場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用されますが、控除額は同額の38万円が維持されます。160万円を超えると、段階的に控除額が減少していく仕組みです。この段階的減少により、配偶者がより多くの収入を得ても、納税者本人の税負担が急増しない配慮がなされています。
この改正により、パートタイムで働く配偶者がより多くの収入を得られるようになり、手取り収入の増加が期待されています。従来は103万円の壁を意識して働く時間を調整していた配偶者も、123万円まで働くことができるようになり、年間20万円の収入増加が可能になります。さらに、160万円までは配偶者特別控除により、納税者本人の税負担も増加しないため、家計全体としてのメリットは大きいと言えます。
配偶者控除と配偶者特別控除の申告についても、年末調整での申告書様式が変更されます。配偶者の収入が変動する可能性がある場合は、年末の時点で正確な収入額を確認し、適切な控除を申告することが重要です。配偶者の収入が当初の見込みと異なった場合は、確定申告により税額を修正することもできます。
税額計算の具体例とシミュレーション
扶養控除が適用されると、課税所得額から一定の金額が所得控除として差し引かれます。扶養親族の年齢や状況によって控除額が異なり、一般の扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)は38万円の控除、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円の控除、老人扶養親族(70歳以上)は48万円から58万円の控除(同居老親等の場合は58万円)となります。
具体的な例として、年収500万円の給与所得者が、大学生の子ども(19歳、年収120万円)を扶養している場合を考えてみましょう。
2024年(改正前)の場合
子どもの年収が103万円を超えているため、扶養控除は適用されません。基礎控除48万円と給与所得控除146万円のみが適用され、課税所得は約306万円となります。所得税は約20万円、住民税は約30万円、合計約50万円の税負担となります。
2025年(改正後)の場合
子どもの年収が123万円以下であるため、特定扶養控除63万円が適用されます。基礎控除58万円と給与所得控除146万円も適用され、課税所得は約233万円となります。所得税は約11万円、住民税は約23万円、合計約34万円の税負担となります。
この例では、年間約16万円の税負担軽減効果があることがわかります。基礎控除の引き上げと特定扶養控除の適用により、大幅な税負担の軽減が実現されます。家計にとって年間16万円の軽減は非常に大きく、この金額を教育費や生活費に回すことができます。
さらに、特定親族特別控除の段階的控除の計算例を見てみましょう。子どもの年収が150万円の場合、従来の制度では扶養控除が一切適用されませんでしたが、2025年からは特定親族特別控除により、段階的に控除が適用されます。
子どもの年収150万円の場合は控除額63万円が満額適用され、年収160万円の場合は控除額51万円、年収170万円の場合は控除額31万円、年収180万円の場合は控除額11万円、年収188万円超の場合は控除額0円となります。この段階的な控除の仕組みにより、子どもの収入が増えても親の税負担が急激に増加することがなく、働く意欲を削がない設計となっています。
基礎控除と給与所得控除の引き上げは、扶養親族がいない単身者にとってもメリットがあります。年収が同じでも、控除額が増えることで課税所得が減少し、結果として所得税と住民税が減少します。特に、年収が500万円から800万円程度の中間層にとって、この軽減効果は実感しやすいものとなります。
確定申告での対応方法と注意点
2025年分の所得に対する確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までの期間に行います。扶養控除や特定親族特別控除の変更は、この確定申告から適用されます。還付申告については、翌年の1月1日から5年間有効であり、2025年分の還付申告なら、2026年1月1日から2030年12月31日までできます。
年末調整で控除を受けていない場合や、控除額に誤りがあった場合は、確定申告により正しい税額を申告することができます。インターネットから申告するe-Taxの受付期間は、1月4日(木)から3月17日(月)までとなっています。e-Taxは確定申告の期間中、土日祝日も含めて24時間受け付けており、e-Taxの提出期限は確定申告期限日の24時までです。
窓口での申告と異なり、深夜でも申告が可能なため、仕事が忙しい方にも便利です。申告ソフトを持っていなければ、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、パソコンとマイナンバーカードを使ってe-Taxで電子申告するのが最も簡単です。画面の指示に従って入力していくだけで、税額が自動計算され、申告書が作成されます。
確定申告で扶養控除を申告する場合、確定申告書の扶養控除の欄に、扶養親族の氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、所得金額などを記入する必要があります。特定親族特別控除を申告する場合は、19歳から22歳の親族について、その収入額と控除額を正確に記入する必要があります。国税庁のホームページには詳細な記入例が掲載されているため、これを参考にすることをお勧めします。
年末調整で扶養控除や特定親族特別控除の適用を受けていても、扶養親族の収入が当初の見込みと異なった場合は、確定申告により税額を修正する必要があります。例えば、年末調整の時点では子どもの年収を120万円と見込んでいたが、実際には125万円だった場合、扶養控除から特定親族特別控除に変更する必要があります。このような場合、確定申告で正しい控除額を申告し直すことになります。
逆に、年末調整で控除を受けていなかったが、後から扶養親族の収入が確定して控除が受けられることがわかった場合も、確定申告により還付を受けることができます。会計ソフトなどを使って仕訳をしていれば正規の簿記の原則により記帳していることになりますし、確定申告期限までにe-Taxで電子申告すれば、青色申告特別控除も受けることができます。
社会保険の扶養要件との違いに注意
税法上の扶養控除の要件が123万円に拡大されましたが、社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養要件は別の基準で判定されます。扶養の範囲には、所得税制上の扶養の範囲と社会保険制度上の扶養の範囲があり、これらは別々に判定されることを理解しておく必要があります。
有配偶パート女性が社会保険適用拡大の対象となる企業(2024年10月より従業員数51人以上)に勤務している場合、雇用契約上の週労働時間が20時間以上かつ月収8.8万円(年106万円)以上の場合、勤務先の社会保険に加入し、配偶者の社会保険の被扶養者から外れます。これがいわゆる106万円の壁です。
2025年6月に年金改正法が成立し、2025年6月20日から3年以内には、社会保険の月収8.8万円以上という加入要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されることになっており、働き方や雇用管理にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
社会保険適用拡大の対象とならない企業に勤務している場合は、年収が130万円を超えると配偶者の社会保険の被扶養要件を外れ、自らで社会保険(国民健康保険、国民年金)に加入する必要があります。これが130万円の壁です。この130万円の基準は、2025年の税制改正では変更されていません。
したがって、税法上は123万円まで扶養控除を受けられても、社会保険では130万円を超えると扶養から外れてしまう点に注意が必要です。具体的な例で考えてみましょう。配偶者の年収が125万円の場合、税法上の扶養では年収123万円以下の要件を超えているため、配偶者控除は適用されませんが、160万円以下であるため、配偶者特別控除38万円が満額適用されます。一方、社会保険上の扶養では年収130万円未満であるため、社会保険の被扶養者として認められ、配偶者自身が社会保険料を支払う必要はありません。
このように、税法と社会保険では基準が異なるため、収入を考える際には両方の要件を確認する必要があります。特に、配偶者を扶養している場合は、この違いを理解しておく必要があります。130万円を超えると、社会保険料の負担が発生するため、手取り収入が大幅に減少する可能性があります。
住民税の控除額と注意点
本記事で主に解説してきた控除額は所得税のものですが、住民税についても控除があります。ただし、住民税の控除額は所得税とは異なる点に注意が必要です。
例えば、特定親族特別控除の場合、所得税では63万円の控除ですが、住民税では45万円の控除となります。また、基礎控除についても、所得税では58万円に引き上げられましたが、住民税では43万円となっており、金額が異なります。
一般の扶養控除についても、所得税では38万円ですが、住民税では33万円となります。特定扶養親族については、所得税では63万円ですが、住民税では45万円です。老人扶養親族については、所得税では48万円(同居老親等は58万円)ですが、住民税では38万円(同居老親等は45万円)となります。
このように、所得税と住民税では控除額が異なるため、税額計算をする際には両方を考慮する必要があります。ただし、年末調整や確定申告で正しく申告していれば、住民税についても自動的に計算され、適切な控除が適用されます。住民税は、前年の所得に基づいて翌年に課税されるため、2025年分の所得に対する住民税は2026年6月から徴収が始まります。
従業員への周知と対応方法
2025年の扶養控除改正は、多くの従業員に影響を与える重要な変更です。企業は従業員に対して、扶養控除の所得要件が123万円に拡大されたこと、特定親族特別控除という新しい制度が創設されたこと、申告書の様式が変更され記入内容が増えること、申告内容に変更がある場合は必ず届け出ることなどを丁寧に周知する必要があります。
周知方法としては、社内メール、掲示板、説明会の開催などが考えられます。特に、19歳から22歳の子どもがいる従業員や、親を扶養している従業員には個別に案内することが望ましいでしょう。従業員から想定される質問に対する回答を事前に準備しておくことも重要です。
よくある質問としては、子どもの収入が123万円を超えそうだがどうすればいいか、特定親族特別控除を受けるためにはどのような手続きが必要か、今まで扶養控除を受けていなかったが今年から受けられるか、申告書の記入方法がわからないといったものが考えられます。これらの質問に対して、正確かつわかりやすく回答できるよう、人事労務担当者は制度の詳細を理解しておく必要があります。
近年、スポットワークや短期間のアルバイトにより、扶養している子どもの年収が変動するケースが増えています。収入が変動した場合、控除額が変わったり扶養の要件から外れたりする可能性があります。これにより、年末調整後に再度、扶養控除の計算を見直す必要が生じ、従業員に追加の手続きを依頼しなければならないケースが想定されます。従業員には、扶養親族の収入が当初の見込みから大きく変わった場合は、速やかに届け出るよう周知することが重要です。
家計への影響と収入増加の可能性
扶養控除の所得要件が123万円に拡大されたことで、扶養親族となる家族が従来より多く働いても扶養控除を維持できるようになります。例えば、パートタイムで働く配偶者や、アルバイトをする学生の子どもが、年間103万円までに抑えていた収入を123万円まで増やすことができます。年間20万円の収入増加は、家計にとって大きなプラスとなります。
特定親族特別控除の創設により、19歳から22歳の大学生世代は最も大きな恩恵を受けます。従来は103万円を超えると親の扶養から外れてしまい、親の税負担が急増するため、収入を抑える必要がありました。しかし新制度では、150万円まで親の控除額63万円が維持され、さらに188万円まで段階的に控除が受けられます。
これにより、学費や生活費の負担が大きい大学生世代が、アルバイトで収入を得やすくなり、親の負担軽減にもつながります。大学生が年間150万円まで働けるようになることで、学費の一部を自分で賄ったり、生活費を稼いだりすることが容易になります。親にとっても、子どもが経済的に自立する過程を支援しながら、税負担の急増を避けられるというメリットがあります。
基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、広範囲の納税者が税負担の軽減を受けられます。年収が同じでも、控除額が増えることで課税所得が減少し、結果として所得税と住民税が減少します。特に、年収が500万円から800万円程度の中間層にとって、この軽減効果は実感しやすいものとなります。年間数万円から十数万円の税負担軽減は、家計の可処分所得を増やし、消費や貯蓄に回すことができます。
今後の税制改正の方向性と展望
2025年の改正は、いわゆる年収の壁問題への対応という側面があります。今後も、働き方の多様化や社会保険との整合性を踏まえた税制改正が継続的に行われる可能性があります。
特に、社会保険の扶養要件との統一化、配偶者控除と配偶者特別控除のさらなる見直し、子育て世帯への支援強化、働き方改革との連動といった論点について、今後さらなる改正が検討される可能性があります。企業の給与担当者は、毎年の税制改正大綱に注目し、早めの情報収集と対応準備を行うことが重要です。
2025年の扶養控除の所得要件変更と特定親族特別控除の創設は、多くの家庭と企業に影響を与える大きな改正です。特に、働く学生とその家族にとっては、収入を増やしやすくなり、税負担も段階的に変化する仕組みとなったことで、大きなメリットがあります。
一方で、企業の給与担当者にとっては、システム対応、申告書の変更、従業員への周知など、対応すべき事項が多く、丁寧な準備が必要です。この改正を機に、税制についての理解を深め、適切に制度を活用することで、個人の家計改善と企業の円滑な給与事務運営の両立を目指していきましょう。
企業が今すぐ取るべき具体的対応
企業の給与担当者が今すぐ取るべき対応としては、まず給与計算システムの更新確認が挙げられます。システムベンダーに2025年改正対応状況を確認し、必要なアップデートのスケジュールを把握することが重要です。システム更新には時間がかかる場合もあるため、早めの対応が求められます。
次に、従業員への周知を徹底する必要があります。社内メールや説明会で制度変更を案内し、特に影響を受ける従業員には個別に連絡することが望ましいでしょう。申告書様式の準備も重要であり、新しい様式の申告書を準備し、記入方法を分かりやすく説明する資料を作成することが推奨されます。
質問対応体制の構築も欠かせません。よくある質問への回答を事前に準備し、相談窓口を明確化することで、従業員からの問い合わせにスムーズに対応できます。また、社内マニュアルの更新も必要です。年末調整マニュアルを2025年版に更新し、給与担当者が参照できるようにしておくことで、業務の正確性と効率性が向上します。
特に、2025年12月の年末調整は制度変更初年度となるため、例年以上に丁寧な準備と対応が求められます。10月から11月にかけて、従業員への説明会を開催し、申告書の記入方法を詳しく解説することも有効です。また、システムのテスト運用を行い、計算ロジックが正しく動作するかを事前に確認しておくことも重要です。
2025年の税制改正は、働く世代と学生世代の収入増加を支援し、税負担を軽減することを目的としています。企業は、この改正を正しく理解し、従業員が適切に制度を活用できるようサポートすることで、従業員満足度の向上にもつながります。2025年12月の年末調整に向けて、今から計画的に準備を進めることを強くお勧めします。

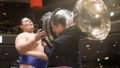

コメント