70歳以上の医療費が3割負担となるのは、住民税課税所得が145万円以上、かつ単身世帯で年収383万円以上、複数世帯で合計年収520万円以上の「現役並み所得者」に該当する方です。この制度は2006年10月から実施されており、現在も継続しています。本記事では、70歳以上の医療費3割負担の判定基準、年収条件の詳細、制度の歴史的経緯から将来の改正動向まで、知っておくべき情報を網羅的に解説します。高額療養費制度による自己負担上限額や、負担を軽減するための申請手続きについても詳しくお伝えしますので、ご自身やご家族の医療費負担を正確に把握するための参考にしてください。

70歳以上の医療費3割負担とは何か
70歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担は、原則として1割または2割ですが、一定以上の所得がある方は現役世代と同じ3割を負担する仕組みになっています。この「現役並み所得者」に対する3割負担制度は、年齢ではなく経済的な支払い能力に応じて負担を求める「応能負担」の考え方に基づいています。
日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入しており、国民皆保険制度を維持しながら増大する医療費をどのように分担するかは、国家の重要課題となっています。かつて1970年代には「老人医療費無料化」という政策が実施されていましたが、人口構造の変化と経済成長の鈍化により、その方針は大きく転換されました。現在では、「高齢者だから一律に負担を軽くする」のではなく、「経済力のある高齢者には相応の負担を求める」という全世代型社会保障の考え方が基本となっています。
70歳以上の医療費3割負担はいつから始まったのか
70歳以上の現役並み所得者に対する3割負担は、2006年(平成18年)10月から実施されました。この制度変更は、改正高齢者医療確保法の施行に伴うもので、それまで1割または2割だった高齢者の窓口負担に、新たに3割という区分が設けられた画期的な転換点でした。
この改革の背景には、2002年の健康保険法改正があります。この改正により2003年4月から現役世代(サラリーマン本人)の窓口負担が2割から3割へ引き上げられ、「現役世代=3割負担」という基準が確立されました。すると当然、「現役世代が3割負担しているのに、同程度の所得がある高齢者が1割や2割で済むのは不公平ではないか」という世代間公平性の議論が活発化し、2006年の制度改正につながったのです。
導入当初は急激な負担増を緩和するための経過措置も設けられましたが、原則としての3割負担はこの時点で確立され、現在まで継続しています。
高齢者医療費負担の歴史的変遷を振り返る
現在の3割負担制度を正しく理解するためには、過去50年にわたる制度変更の歴史を知ることが重要です。日本の社会保障政策は「福祉」から「保険」へ、そして「年齢による一律区分」から「所得による選別」へと大きく舵を切ってきました。
1973年「福祉元年」と老人医療費無料化
1973年(昭和48年)、当時の田中角栄内閣は「福祉元年」を掲げ、老人福祉法の改正によって70歳以上の高齢者の医療費自己負担を無料化しました。高度経済成長期の成果を高齢者に還元するという趣旨で、多くの自治体ですでに先行実施されていた無料化措置を国策として追認したものでした。この政策により高齢者は経済的な不安なく医療を受けられるようになり、受診率は劇的に向上しました。しかし同時に、治療の必要性が低い長期入院が常態化する「社会的入院」という問題を招き、医療費の爆発的な増大につながりました。
1983年「老人保健法」で定額負担を導入
無料化政策は約10年で見直しを迫られることになりました。石油ショック後の低成長時代に入り、増え続ける老人医療費が現役世代や国保財政を圧迫し始めたためです。1983年(昭和58年)2月に「老人保健法」が施行され、70歳以上の高齢者に対して「一部負担」という概念が再導入されました。当初の負担額は外来で月額400円、入院で日額300円という極めて少額な「定額負担」でしたが、その後も医療費の伸びは止まらず、1986年、1991年、1997年と相次ぐ法改正によって定額負担額は段階的に引き上げられていきました。
2002年健康保険法改正で「3割負担」の基準が確立
2000年代に入ると少子高齢化はさらに加速し、現役世代の負担増が限界に近づいていました。2002年(平成14年)の健康保険法改正は、日本の医療保険制度における大きな転換点となりました。2003年4月から現役世代の窓口負担が2割から3割へ引き上げられ、この「現役世代=3割負担」という新たな基準が、後の高齢者医療制度設計に決定的な影響を与えることになります。
2014年に70歳〜74歳の「原則2割」化が実現
3割負担の導入と並行して、一般所得者層の負担割合引き上げも議論されていました。法律上は2008年4月から70歳〜74歳の負担割合を原則1割から2割へ引き上げることが決まっていましたが、政治的な判断により「凍結」が続きました。この凍結が解除されて実際に2割負担がスタートしたのは2014年(平成26年)4月のことです。ただし、移行措置として「2014年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人」から順次2割負担とされたため、2014年4月1日以前にすでに70歳に達していた人(1944年4月1日以前生まれ)は、現在も特例的に1割負担が継続されています。
2022年に後期高齢者医療制度で2割負担層を新設
制度変更の最新の動きは2022年(令和4年)10月でした。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度において、それまで「原則1割(現役並みは3割)」だった区分に、新たに「2割負担(一定以上所得者)」という中間層が設けられました。団塊の世代が75歳以上になり始める「2025年問題」を目前に控え、現役世代からの支援金の負担上昇を抑制するための措置でした。これにより、高齢者の負担区分は「1割」「2割」「3割」の三層構造となり、よりきめ細かい負担体系が完成しました。
70歳以上の医療費3割負担の対象となる年収と判定基準
70歳以上の方が最も気になるのは、「自分は3割負担の対象になるのか」という点でしょう。この判定基準は複雑で、住民税の課税状況、年収、世帯構成などが組み合わさって決まります。
判定の第一関門は住民税課税所得145万円
3割負担かどうかを判定する最初のステップは「住民税課税所得」の確認です。これは年収そのものではなく、年収から公的年金等控除、給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの各種所得控除を差し引いた後の金額を指します。
同一世帯に属する70歳以上の被保険者のうち、一人でもこの住民税課税所得が145万円以上の人がいれば、その世帯の70歳以上の被保険者は全員、原則として3割負担の候補となります。
社会保険(協会けんぽや健保組合)加入者の場合は、住民税情報の代わりに「標準報酬月額」が用いられ、標準報酬月額が28万円以上である場合に課税所得145万円以上と同等とみなされます。
「145万円」という基準は、厚生年金受給者の平均的な収入モデルにおいて、当時の現役世代の平均的な収入下限と同程度になるラインとして設定されました。
年収要件による救済措置「基準収入額適用申請」
課税所得が145万円以上であっても、実際の収入が現役世代ほど多くないケースは多々あります。例えば控除が少ないために課税所得が高く出てしまう場合などです。そこで設けられているのが、年収ベースでの救済措置である「基準収入額適用申請」です。
このステップでは「所得」ではなく「収入」を見ます。ここでの収入とは、必要経費や控除を引く前の額面金額の合計です。公的年金、給与、不動産家賃収入、株式配当(申告したもの)、個人年金などが含まれますが、退職金や非課税の遺族年金・障害年金は含まれません。
単身世帯は年収383万円が3割負担の境界線
70歳以上の被保険者が世帯に一人の場合、その人の年収が383万円未満であれば、申請により3割負担が解除され、1割または2割(一般所得区分)に戻ります。逆に言えば、課税所得が145万円以上あり、かつ年収も383万円以上ある単身者は、現役並み所得者として3割負担が確定します。
複数世帯は合計年収520万円が3割負担の境界線
同一世帯に70歳以上の被保険者が二人以上いる場合、例えば夫婦ともに70歳以上で国保に加入しているケースでは、その全員の年収合計が520万円未満であれば、申請により一般区分に戻ることができます。たとえば夫の収入が高くて課税所得145万円以上に該当しても、妻の収入が少なく、二人の合計年収が500万円であれば、夫婦ともに3割負担を回避できるのです。
混合世帯には特例計算がある
さらに複雑なのが、夫婦の一方が75歳を迎えて後期高齢者医療制度に移行し、もう一方が70歳〜74歳で国民健康保険に残るケースです。制度上は別々の保険加入者となりますが、実態としての家計は一つです。そのため特例として、70歳以上の国保被保険者の収入と、後期高齢者医療制度に移行した元国保被保険者の収入を合算して判定することが認められています。この合算額が520万円未満であれば、国保に残った70歳代前半の方の負担割合は一般区分(2割)となります。
3割負担の判定ロジックまとめ
結局のところ、3割負担となるのは以下の条件をすべて満たした人のみです。まず住民税課税所得が145万円以上(または標準報酬月額28万円以上)であること、そして単身であれば年収383万円以上、複数であれば世帯年収520万円以上であること。逆に言えば、どちらか一つでも基準を下回れば、1割または2割負担にとどまることができます。
3割負担者の高額療養費制度による自己負担上限
「3割負担」という言葉の響きは重いものがありますが、実際の支払いには上限があります。日本の医療保険制度が誇る「高額療養費制度」により、1ヶ月の自己負担額には所得に応じた限度額が設定されています。ただし、3割負担者(現役並み所得者)の上限額は、一般の高齢者に比べてかなり高く設定されており、ここでも応能負担の原則が貫かれています。
2018年(平成30年)8月の改正により、現役並み所得者の上限額は所得に応じて3段階に細分化されました。
現役並みⅢ(年収約1,160万円以上)の上限額
最も所得が高い層で、標準報酬月額が83万円以上、または課税所得が690万円以上の人が該当します。この層の1ヶ月の自己負担限度額は「25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1%」となります。例えば100万円の医療費がかかった場合、窓口負担(3割)は30万円ですが、高額療養費制度により実際の支払いは約25万4,180円で抑えられます。さらに過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合(多数回該当)、4回目からは一律14万100円に下がります。
現役並みⅡ(年収約770万円〜1,160万円)の上限額
標準報酬月額が53万円〜79万円、または課税所得が380万円〜690万円未満の人が該当します。限度額は「16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1%」です。100万円の医療費の場合、自己負担は約17万1,820円となります。多数回該当の上限は9万3,000円です。
現役並みⅠ(年収約370万円〜770万円)の上限額
3割負担者の中では最も所得が低い層、いわゆるボーダーライン層です。標準報酬月額28万円〜50万円、または課税所得145万円〜380万円未満の人が該当します。限度額は「8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1%」です。100万円の医療費の場合、自己負担は約8万7,430円となります。多数回該当の上限は4万4,400円です。
一般区分との負担額の差は大きい
比較のために、3割負担に該当しない一般所得者(2割負担)の上限額を見ると、外来のみで月額1万8,000円(年間上限14万4,000円)、入院を含めた世帯上限でも5万7,600円(多数回該当4万4,400円)です。同じ手術を受けても「現役並みⅢ」の人は約25万円を支払うのに対し、一般の人は約5万7千円で済むことになります。この約20万円の差こそが、現役並み所得判定が家計に与える実質的な影響の大きさを示しています。
制度運用の実務と知っておくべき注意点
制度は精緻に設計されていますが、現実の運用では手続き上の注意点や、知らないと損をするポイントが存在します。
判定のタイミングと高齢受給者証
70歳から74歳の人には、保険証とは別に「高齢受給者証」が交付され、そこに負担割合(2割または3割)が明記されています。この負担割合は毎年8月1日に更新されます。判定の基準となるのは前年(1月〜12月)の所得です。毎年6月頃に住民税の決定通知が出ると、そのデータが保険者に連携され、新しい負担割合が決定されて7月末までに新しい受給者証が郵送されます。
したがって、前年に不動産を売却して一時的に所得が跳ね上がった場合などは、その翌年の8月から1年間だけ3割負担になり、その翌々年の8月からはまた2割に戻るといった変動が起こり得ます。
基準収入額適用申請の手続きに注意
前述した「基準収入額適用申請」が自動適用されるか、申請が必要かは、加入している健康保険によって対応が異なります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、自治体が住民税データと所得情報を把握しているため、多くの場合は年収要件を満たしていれば自動的に一般区分に判定されます。
しかし、大企業の健康保険組合や協会けんぽの場合、保険者は給与情報は持っていますが、退職後の年金収入やその他の所得の詳細までは把握していないことが一般的です。そのため、標準報酬月額が28万円以上ある被保険者に対してはとりあえず3割判定の通知を出し、「年収が基準以下なら証明書類を添えて申請してください」というスタンスを取ることがあります。
この通知を見落としたり、「役所が勝手にやってくれるだろう」と思い込んで放置すると、本来2割で済むはずが3割負担のまま医療費を払い続けることになります。払い過ぎた分は後から申請すれば差額が返還される場合が多いですが、時効(2年)の壁もあるため注意が必要です。毎年8月の更新時期に届く書類は隅々まで目を通すことが重要です。
世帯分離という選択肢
介護保険料や医療費負担を軽減するために、同居している親子があえて住民票上の世帯を分ける「世帯分離」という方法が知られています。70歳以上の医療費負担判定においても、これは一定の効果を持つ場合があります。3割負担の判定は「同一世帯の70歳以上の被保険者」の所得で行われるため、高所得の息子(70歳未満)と同居していても、息子の所得は親の3割負担判定には直接影響しません。
ただし、夫婦間の世帯分離については実態としての生計同一性が問われるため、必ずしも負担区分が下がるとは限りません。また、世帯分離によって国民健康保険料の合算上限が使えなくなり、かえって保険料総額が上がるリスクもあるため、慎重なシミュレーションが必要です。
負担増による受診控えと医療現場の懸念
制度改革によって自己負担が増えることは、高齢者の受診行動そのものを変化させる可能性があります。
受診をためらう高齢者の増加
2022年10月に後期高齢者の2割負担が導入された際に行われたアンケート調査によると、窓口負担が2割になった人のうち、約1割から2割の人が「受診をためらうようになった」「受診回数や薬を減らした」と回答しました。特に歯科や整形外科など、生命に直結しないと患者自身が判断しやすい診療科での受診抑制が顕著でした。また「食費を削って受診する」「預金を切り崩す」といった回答も見られ、医療費の支払いが生活の質を直接圧迫している実態が明らかになりました。
重症化リスクへの懸念
医療従事者が最も懸念するのは、経済的な理由による受診控えが疾患の発見遅れや重症化を招くことです。高血圧や糖尿病などの慢性疾患の通院を自己中断してしまい、数年後に脳卒中や透析が必要な状態で救急搬送されるケースが危惧されています。短期的な医療費削減が長期的には重篤な患者の増加を招き、結果として医療財政をさらに悪化させるのではないかという指摘は、日本医師会や患者団体から繰り返しなされています。
医療現場の声は賛否両論
医師へのアンケートでは、窓口負担の引き上げに対して賛否が分かれています。勤務医や若手医師の間では「現役世代の負担軽減のためにはやむを得ない」「世代間公平の観点から賛成」という意見が多数を占める一方、開業医や地域医療の現場からは「患者が治療を中断してしまう」「窓口でお金の相談を受けることが増え、診療に支障が出る」といった反対意見も根強く存在します。
2025年以降の制度改正の展望
政府は「全世代型社会保障」の構築を掲げており、負担能力の評価基準をさらに精緻化する議論が進んでいます。
金融所得を判定に反映する動き
現在、最大の論点となっているのが「金融所得」の扱いです。現行制度では、株式の配当や譲渡益などの金融所得は、確定申告をしない限り(源泉分離課税を選択している限り)、医療保険の所得判定に含まれません。これにより、数億円の金融資産を持ち多額の配当収入を得ている高齢者であっても、公的年金が少なければ「住民税非課税世帯」として1割負担で済み、保険料も軽減されるという現象が起きています。
政府はマイナンバー制度を活用して金融所得情報を把握し、これを医療費の窓口負担割合や保険料算定に反映させる検討を進めています。この改革はシステム改修などの課題もあり、2028年度頃までの実現を目指して議論が行われています。方向性としては「資産を持つ者には負担を求める」という流れは進んでいくと考えられます。
現役並み所得の判定基準引き下げの議論
もう一つの論点は、3割負担のボーダーラインである「課税所得145万円」という基準そのものの見直しです。この基準は2006年の導入以来、約20年間据え置かれています。現役世代の手取り収入が伸び悩む中で、この基準は高すぎるのではないか、もっと広く薄く負担を求めるべきではないかという議論が提起されています。
具体的には、現在2割負担の対象となっている層の一部を3割負担に組み入れる案や、判定基準に資産の要素を組み合わせる案などが検討されています。高齢者団体からの反発が予想されるテーマですが、社会保障費の膨張が続く限り、避けて通れない議論となるでしょう。
まとめ:70歳以上の医療費3割負担制度を正しく理解する
70歳以上の医療費3割負担制度は、日本の社会保障が直面する「理想と現実の相克」を映し出す鏡といえます。現役世代の負担を減らすためには高齢者の負担増が避けられない一方で、高齢者の生活を守るためには過度な負担は課せないというジレンマの中で、制度は複雑化してきました。
重要なポイントを改めて整理すると、70歳以上の3割負担は2006年10月から実施されており、対象となるのは住民税課税所得145万円以上かつ、単身で年収383万円以上または世帯で520万円以上の方です。ただし年収が基準未満であれば「基準収入額適用申請」により負担を軽減できる場合があります。また、3割負担者にも高額療養費制度による上限があり、所得に応じて3段階の限度額が設定されています。
ご自身やご家族の所得状況と負担区分を正確に把握し、利用できる救済措置を最大限に活用することが、医療費負担を適切に管理するための第一歩です。制度は常に変化していますので、毎年8月の更新時期に届く書類を確認し、最新の情報を把握しておくことをお勧めします。
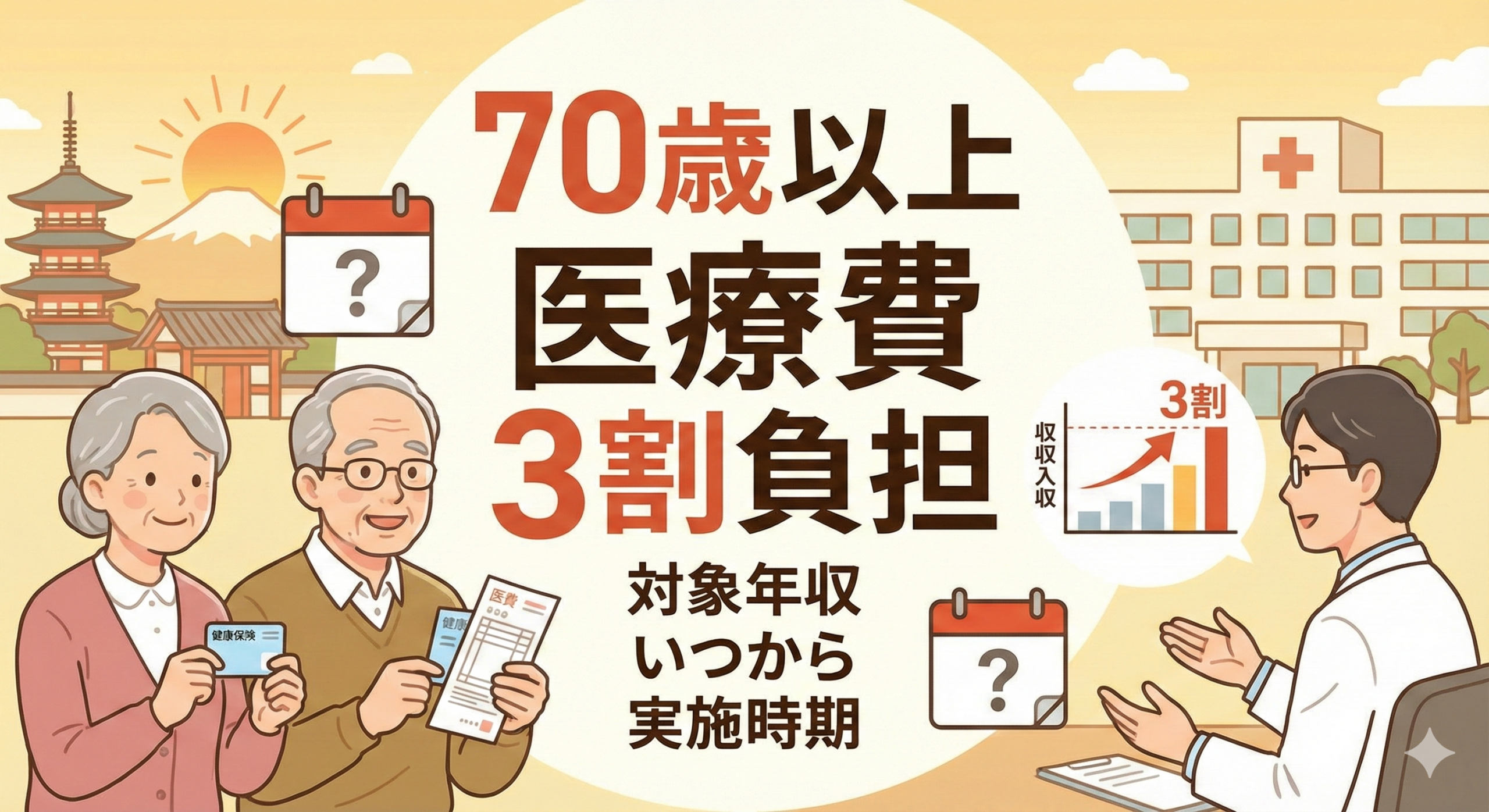


コメント