2024年12月2日から健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する新制度がスタートしました。この大きな変革により、多くの方が「いつまで従来の保険証が使えるのか」「併用期間はどのくらいあるのか」といった疑問を抱えていることでしょう。
現在は移行期間として、従来の健康保険証とマイナ保険証の併用が認められており、2025年12月1日まで最長1年間の猶予期間が設けられています。この期間中は、患者の皆様がどちらの方法でも医療機関を受診することが可能です。
しかし、移行期間といっても全ての方が同じ期限というわけではありません。保険証の有効期限や保険者の変更などにより、個別に使用期限が異なる場合があります。特に後期高齢者医療保険の被保険者については、2025年7月31日という早い期限が設定されており、注意が必要です。
また、マイナンバーカードを持たない方や利用に不安のある方に対しては「資格確認書」の自動交付制度が整備されており、誰もが安心して医療を受けられる環境が維持されています。この制度変更は単なるカードの置き換えではなく、日本の医療制度全体のデジタル化を推進する重要な施策として位置づけられています。

マイナンバーカードと従来の健康保険証はいつまで併用できるの?
マイナンバーカードと従来の健康保険証の併用期間は、2024年12月2日から2025年12月1日までの最長1年間となっています。この期間中は、どちらの方法でも医療機関での保険診療を受けることが可能です。
ただし、すべての方が2025年12月1日まで使えるわけではないことに注意が必要です。併用期間の終了時期は、以下の条件によって個別に決まります:
保険証の有効期限による制限
従来の健康保険証に記載されている有効期限が2025年12月1日より前に設定されている場合は、その有効期限をもって使用できなくなります。多くの保険証は年単位で更新されるため、2025年春頃から順次期限を迎える保険証が出てくる予定です。
保険者の変更による制限
転職や転居により保険者が変更となった場合、その時点で従来の保険証は使用できなくなります。新しい保険者からは原則としてマイナ保険証の利用が前提となり、必要に応じて資格確認書が交付されます。
特別な期限設定
後期高齢者医療保険の被保険者については、健康保険証の有効期限が2025年7月31日に統一して設定されています。これは高齢者への配慮として別途対応措置が講じられているためで、一般の保険証よりも早く期限が到来することになります。
併用期間中の利用状況を見ると、2025年2月時点でのマイナ保険証利用率は26.62%となっており、まだ多くの方が従来の保険証を使用している状況です。政府はこの移行期間を活用して、マイナ保険証の利便性を実感していただき、円滑な移行を進めることを目指しています。
医療機関側でも、併用期間中は両方の確認方法に対応する必要があり、システムの整備と職員研修が継続されています。患者の皆様には、ご自身の保険証の有効期限を確認し、計画的にマイナ保険証への移行準備を進めることをおすすめします。
移行期間中に従来の健康保険証が使えなくなるのはどんな場合?
移行期間中であっても、従来の健康保険証が使用できなくなるケースがいくつかあります。主な理由と対処法について詳しく説明します。
保険証の有効期限切れ
最も一般的なケースが、保険証に記載された有効期限の到来です。従来は期限前に新しい保険証が郵送されていましたが、2024年12月2日以降は新規発行が停止されているため、期限が来ても新しい紙の保険証は届きません。
この場合の対処法として、マイナ保険証への切り替えか、保険者からの資格確認書の交付を受ける必要があります。特に2025年春頃から多くの保険証の有効期限が到来するため、早めの準備が重要です。
転職・転居による保険者変更
転職により健康保険組合や協会けんぽから別の保険者に移る場合、転居により国民健康保険の保険者(市町村)が変わる場合などは、その時点で従来の保険証は無効となります。
新しい保険者では、マイナンバーカードでの健康保険証利用登録を推奨しており、登録が完了していない場合は資格確認書が交付されます。手続きの空白期間が生じないよう、事前の登録手続きが重要です。
家族構成の変更
結婚、離婚、子どもの就職などにより被扶養者の状況が変わった場合も、保険証の変更が必要となります。特に被扶養者から外れる場合は、すぐに新しい保険への加入手続きが必要で、従来の保険証は使用できなくなります。
後期高齢者医療制度への移行
75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行する場合、従来の保険証は誕生日の前日で無効となります。後期高齢者医療制度では、2025年7月31日まで保険証が有効ですが、その後はマイナ保険証または資格確認書を使用することになります。
保険料滞納による資格喪失
国民健康保険料や健康保険料の長期滞納により、保険資格を喪失した場合は当然ながら保険証も使用できなくなります。この場合は保険料の支払いと資格の回復手続きが先決となります。
これらのケースで保険証が使えなくなった場合でも、適切な手続きを行えば10割負担を避けることができます。医療機関では「被保険者資格申立書」制度により、患者が窓口で資格を申し立てることで標準的な自己負担割合での診療を受けることが可能です。万が一全額負担を求められた場合でも、後日療養費として保険者からの払い戻しを受けることができる仕組みが整備されています。
マイナンバーカードを持っていない人はどうすればいい?
マイナンバーカードを持っていない方や、持っているが健康保険証として利用登録していない方のために、「資格確認書」の自動交付制度が整備されています。この制度により、申請不要で従来通りの医療サービスを受けることができます。
資格確認書が自動交付される対象者
以下に該当する方には、保険者から自動的に資格確認書が発行されます:
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
- マイナンバーカードを返納した方
特に75歳以上の方については、2026年7月末まで暫定的にマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付される措置が講じられており、高齢者への十分な配慮が行われています。
各保険者の対応状況
協会けんぽでは2025年7月下旬から順次、資格確認書を被保険者の自宅へ送付しています。新規加入者については、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れることで交付される仕組みになっています。
健康保険組合や市町村の国民健康保険なども、それぞれの被保険者の状況に応じて資格確認書を交付しており、誰もが継続して医療を受けられる環境が維持されています。
資格確認書の特徴と注意点
資格確認書の有効期限は各保険者が5年以内で設定し、定期的な更新が必要となります。従来の保険証と同様に医療機関の窓口で提示することで、通常の自己負担割合での診療を受けることができます。
ただし、資格確認書ではマイナ保険証特有のメリット(限度額適用認定証の申請不要、医療費控除手続きの簡素化、対応医療機関での診療費減額など)は受けられません。これらの利便性を享受するためには、マイナンバーカードの取得と健康保険証利用登録が必要となります。
デジタル支援の取り組み
政府は「デジタル活用支援推進事業」を通じて、スマートフォンを利用したオンライン行政手続きについて講習会形式での支援を行っています。各自治体でも独自の取り組みを実施しており、群馬県長野原町ではスマートフォンの貸与とドコモスマホ教室の開催、東京都渋谷区では高齢者への無償スマートフォン貸し出しなどの実証事業が行われています。
マイナンバーカードの取得を希望される方には、これらの支援制度を活用して段階的にデジタル機器に慣れ親しんでいただくことをおすすめします。一方で、デジタル機器の利用に不安のある方には、資格確認書により安心して医療を受けられる環境が確保されています。
医療機関でマイナ保険証が使えないトラブルが起きたらどうなる?
マイナ保険証の利用時にシステムトラブルが発生することがありますが、患者が10割負担を強いられることなく適切な保険診療を受けられる仕組みが整備されています。
よくあるトラブル事例
全国保険医団体連合会の調査によると、70%の医療機関が何らかのトラブルを経験しており、主な問題として以下が報告されています:
電子証明書の期限切れ(31%の医療機関で発生) – マイナンバーカードの電子証明書は5年ごとに更新が必要で、期限切れになると健康保険証として利用できなくなります。2025年は約1580万件の電子証明書が更新期限を迎えるため、特に注意が必要です。
システムエラーによる資格確認の失敗 – オンライン資格確認システムの不具合により、正常なカードでも読み取りができない場合があります。
氏名・住所の表示異常 – システム上で患者の氏名や住所が「●」で表示され、正しい情報が確認できない問題が発生することがあります。
医療機関での対処方法
これらの問題が発生した場合、78%の医療機関が紙の健康保険証を代替手段として使用していることが明らかになっています。医療機関では以下の代替手段を用意しています:
- 従来の健康保険証による確認
- 資格確認書による確認
- 保険者への電話確認
- 被保険者資格申立書制度の活用
患者の負担軽減措置
厚生労働省は2025年3月までの暫定措置として、期限の切れた紙の健康保険証を持参した患者に対しても、保険資格が確認できる限り10割負担を求めないよう医療機関に通知しています。
また、「被保険者資格申立書」制度により、患者が窓口で資格を申し立てることで標準的な3割負担での診療を受けることが可能です。万が一全額負担を求められた場合でも、後日療養費として保険者からの払い戻しを受けることができます。
緊急時の対応
大規模災害やシステム障害などの緊急事態に備えて、厚生労働省では医療機関が保険診療を継続できるようガイドラインの整備と周知を行っています。停電時や通信障害時でも、患者が医療を受けられなくなる事態を防ぐ対策が講じられています。
今後の改善策
2025年からのスマートフォン対応開始により、マイナンバーカード以外の選択肢も増える予定です。また、医療機関への技術支援強化や、システムの安定性向上に向けた取り組みが継続されています。患者の皆様には、万が一のトラブルに備えて資格確認書の準備や、電子証明書の期限確認を定期的に行うことをおすすめします。
2025年12月以降はどのような制度になる予定?
2025年12月2日以降は、従来の健康保険証との併用期間が終了し、マイナンバーカードによる保険証機能が基本となります。ただし、多様な国民のニーズに対応するため、複数の選択肢が用意されています。
基本的な制度構造
2025年12月以降の医療保険制度では、以下の3つの方法で保険診療を受けることができます:
マイナンバーカード(マイナ保険証) – カード型の従来通りの利用方法で、医療機関の顔認証付きカードリーダーで本人確認を行います。
スマートフォン対応 – 2025年夏頃から本格開始される予定で、iPhoneとAndroidの両方でマイナ保険証機能が利用可能となります。専用アプリを通じて医療機関での受付が可能になります。
資格確認書 – マイナンバーカードを持たない方や利用に不安のある方に対して継続的に交付され、従来の保険証と同様の機能を提供します。
スマートフォン対応の詳細
スマートフォンでの利用は、まずマイナポータルアプリでマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行い、次にスマートフォンマイナンバーカード機能の利用申請・登録を行います。医療機関では、専用のカードリーダーにスマートフォンをかざして本人確認を行い、画面の「同意する」ボタンを押すことで手続きが完了します。
ただし、医療機関側では従来の顔認証付きカードリーダーとは別に、スマートフォン対応の汎用カードリーダーを設置する必要があり、対応は医療機関の任意となっています。
医療DXの進展
2025年以降は、マイナ保険証を基盤とした医療DXがさらに発展します。処方箋の完全電子化、医療情報の施設間連携強化、予防医療との統合など、デジタル技術を活用した次世代医療サービスの提供が本格化します。
電子処方箋システムでは、複数の医療機関や薬局での薬剤情報の共有が可能となり、患者の同意のもとで最近5年間の服薬情報に基づく相互作用のチェックが実現されます。
高齢者への特別措置
75歳以上の方については、2026年7月末まで暫定的にマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付される措置が継続されます。これにより、高齢者の方々には十分な時間的余裕を持って新制度に適応していただくことができます。
国際的な展望
日本のマイナンバーカード健康保険証システムは、韓国の住民登録証や台湾の健保ICカードなどと比較して先進的な取り組みとして国際的に注目されています。デジタル技術を活用した次世代医療サービスモデルとして、今後の発展が期待されています。
2025年12月以降の新制度は、デジタル化の恩恵を享受できる方にはより便利で効率的なサービスを提供し、同時にデジタル機器の利用が困難な方にも安心して医療を受けられる環境を維持する、包括的で柔軟な医療保険制度として設計されています。国民の皆様には、ご自身に最適な方法を選択し、新しい制度のメリットを活用していただければと思います。


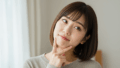
コメント