2025年10月20日、世界最大のクラウドサービスプロバイダーであるアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)で大規模な障害が発生し、世界中の企業やユーザーに深刻な影響を与えました。この障害は日本時間の午後4時11分頃から始まり、約15時間から16時間にわたって継続しました。任天堂Switch Onlineが全面的に利用できなくなったほか、フォートナイトやApex Legendsなどの人気オンラインゲーム、さらにはZoomやSlackといったビジネスツール、Disney+やApple Musicなどのエンターテインメントサービスまで、数百ものサービスが影響を受けました。AWS障害の原因は、US-EAST-1リージョンにおけるDynamoDB APIエンドポイントのDNS解決問題であり、この技術的な問題が連鎖的に35以上のAWSサービスに波及したことが明らかになっています。現代社会がいかに特定のクラウドインフラに依存しているか、そして単一障害点がもたらすリスクの大きさを、この出来事は改めて浮き彫りにしました。本記事では、この大規模障害の詳細な原因、復旧までの時系列、影響範囲、そして今後の対策について徹底的に解説していきます。

- 障害の発生日時と継続期間の詳細
- AWS障害の根本原因を技術的に解説
- DynamoDBとDNS障害のメカニズム
- 連鎖的な障害の拡大プロセス
- 復旧プロセスの詳細な時系列
- 影響を受けたAWSサービスの全容
- グローバル企業への影響と被害状況
- 日本国内での影響と被害の詳細
- エンドユーザーが直面した具体的な問題
- ビジネスへの多面的な影響
- US-EAST-1リージョンの重要性とリスク
- クラウド依存がもたらすシステミックリスク
- 企業が学ぶべき教訓と実践的な対策
- AWSの対応と透明性のある情報開示
- 過去のAWS障害との比較と傾向分析
- SLA(サービスレベルアグリーメント)と補償制度の実態
- 企業が実施すべき具体的な対策(レベル別)
- マルチクラウド戦略の詳細な解説
- 主要クラウドプロバイダーの特徴比較
- クラウド障害情報の効果的な確認方法
- 今回の障害が示す未来への重要な示唆
- クラウド時代のリスクマネジメントの本質
障害の発生日時と継続期間の詳細
2025年10月20日に発生したAWS障害は、米国太平洋夏時間の10月19日午後11時49分、日本時間では10月20日午後4時11分頃に最初の異変が観測されました。AWSの高度なモニタリングシステムが異常を検知したのは米国太平洋夏時間の深夜0時11分で、US-EAST-1リージョン(米国バージニア州北部)において複数のサービスのエラー率が急上昇していることが確認されたのです。このリージョンはAWSにとって最も歴史が長く、多くのグローバル企業がプライマリリージョンとして採用している重要な拠点であるため、障害の影響は瞬く間に世界中に広がりました。
障害は想定以上に長期化し、約15時間から16時間という長時間にわたって継続しました。完全復旧が公式に発表されたのは、ニューヨーク時間の10月20日午後6時、つまり日本時間では10月21日午前7時頃でした。この間、世界中のビジネスが停止や遅延を余儀なくされ、ユーザーは通常利用しているサービスにアクセスできない状況が続きました。特に深夜から早朝にかけての時間帯であったため、米国の企業活動にとっては業務時間中の障害となり、日本では夕方から夜にかけての時間帯であったため、ゲームやエンターテインメントサービスの利用が多い時間帯と重なり、多くのユーザーからの不満の声がソーシャルメディア上で見られました。
AWS障害の根本原因を技術的に解説
AWSの技術チームが実施した詳細な調査の結果、今回の障害の根本原因は単一の問題ではなく、複数の技術的問題が重なり合ったことによるものであることが判明しました。この複雑な原因の解明には、高度な技術力と膨大なログデータの分析が必要とされました。
障害の最初のトリガーとなったのは、US-EAST-1リージョンにおけるDynamoDB APIサービスエンドポイントのDNS解決問題でした。DNS(ドメインネームシステム)は、インターネットの基盤となる重要な仕組みで、人間が読みやすいドメイン名である「dynamodb.us-east-1.amazonaws.com」のようなアドレスを、コンピュータが理解できるIPアドレスに変換する役割を担っています。このDNS解決プロセスが失敗してしまうと、たとえサービスエンドポイント自体は正常に稼働していたとしても、クライアントアプリケーションはサービスに到達することができなくなってしまうのです。
AWSは午前0時26分という早い段階でこの問題の本質を特定し、技術者チームがDynamoDB APIエンドポイントのDNS解決に関連する問題であることを突き止めました。公式ステータスメッセージだけでなく、独立したDNSプローブツールによる調査も同様の結果を示しており、DynamoDBエンドポイントの解決が確実に失敗していることが複数の観点から確認されました。
さらに、EC2インスタンス起動障害については、ネットワークロードバランサーの健全性監視を担う内部サブシステムに根本原因があったことが説明されています。具体的には、主要なデータベースサービスを管理するデジタルディレクトリシステムに不具合が生じたことで、広く利用されているデータベースに依存するソフトウェアコンポーネントが必要な情報を取得できなくなり、連鎖的な障害を引き起こしました。
DynamoDBとDNS障害のメカニズム
今回の障害を深く理解するためには、DynamoDBとDNSという二つの重要な技術要素について知る必要があります。DynamoDBはAWSが提供する完全管理型NoSQLデータベースサービスで、高速でスケーラブルなデータアクセスを実現する重要なコンポーネントです。多くのアプリケーションは、メタデータ、セッション状態、認証トークン、リーダー選出状態など、規模は小さいものの極めて重要なデータをDynamoDBに保存しています。
DynamoDBの特徴として、ミリ秒単位の低レイテンシでデータにアクセスできる点、自動的にスケーリングして負荷に対応できる点、そしてインフラ管理が不要な完全マネージド型である点が挙げられます。これらの特性により、ユーザー認証、フィード組み立て、分散システムの調整といった、アプリケーションの根幹を成す機能がDynamoDBに依存する構造が広く普及していました。
DNS障害のメカニズムについて説明すると、DNSサーバーが正しいIPアドレスを返せない状態、あるいはDNSクエリに応答しない状態が発生すると、クライアントアプリケーションはサービスの所在を特定できなくなります。公式ステータスメッセージと独立したDNSプローブの両方がDynamoDBエンドポイントの解決失敗を示していたことから、DNS解決プロセスそのものに深刻な問題が発生していたことが確認されています。この状況では、DynamoDB自体のサーバーやデータは正常であっても、アクセスする手段が失われてしまうため、実質的にサービスが利用できない状態となりました。
連鎖的な障害の拡大プロセス
今回の障害で特に注目すべき点は、わずか20分程度という短時間で、影響が35以上ものAWSサービスに広がったという連鎖的な障害の発生でした。この急速な拡大は、現代のクラウドサービスアーキテクチャにおける相互依存性の高さを如実に示しています。
DynamoDBが「中断」状態となったことで、それに依存する数多くのサービスが次々とドミノ倒しのようにダウンしていきました。具体的には、CloudWatch(システム監視ツール)、Lambda(サーバーレスプログラム実行環境)、IAM(アイデンティティとアクセス管理)などの基盤サービスがエラーを起こし始めました。これらのサービスは、AWS上で動作するほぼすべてのアプリケーションにとって不可欠な要素であり、いわばAWSエコシステムの土台を支える柱のような存在です。
午前2時24分にDynamoDB DNS問題が解決された後も、問題は完全には収束しませんでした。DynamoDBへの依存関係により、EC2インスタンスを起動するための内部サブシステムに後続の障害が発生したのです。さらにNetwork Load Balancerのヘルスチェック機能も障害状態となり、Lambda、DynamoDB、CloudWatchなどの複数サービスでネットワーク接続に関する問題が継続しました。このように、一つの問題が解決されても、それが引き金となって発生した別の問題が新たな障害を生み出すという、複雑な連鎖反応が観測されました。
復旧プロセスの詳細な時系列
障害からの復旧は、AWSの技術チームによる懸命な努力により段階的に進められました。以下、重要なマイルストーンを時系列で詳しく見ていきます。
米国太平洋夏時間の午前0時11分、AWSの高度なモニタリングシステムが最初の異常を検知しました。この時点で、エラー率の急上昇とレイテンシの増加が複数のサービスで観測され、システムアラートが発動されました。技術チームは即座に対応を開始し、問題の特定作業に取り掛かりました。
わずか15分後の午前0時26分には、DynamoDB APIエンドポイントのDNS解決問題が根本原因であることを特定することに成功しました。この迅速な問題特定は、AWSが構築している包括的な監視システムと、熟練した技術者チームの能力によるものです。問題が特定されると、DNS解決問題に対する修正作業が開始されました。
午前2時24分、約2時間の作業の末、DynamoDB DNS問題の解決に成功し、サービスの回復が始まりました。しかし、この時点ではまだ完全復旧には至っておらず、DynamoDBへの依存により発生していた二次的な障害への対処が必要でした。
午前3時35分には、DNSの問題が完全に緩和され、AWSのサービスオペレーションのほとんどが正常に成功するようになりました。ただし、一部のサービスではまだ完全な復旧に至っていない状態が続いていました。
最終的に、ニューヨーク時間の午後6時、日本時間では10月21日午前7時頃、すべてのサービスが「通常の運用状態に戻った」との公式発表が行われました。ただし、日本時間の21日午前6時時点では完全復旧に至っていないという一部報道もあり、サービスや地域によって復旧のタイミングに若干のばらつきがあったことが示唆されています。
影響を受けたAWSサービスの全容
今回の障害では、データベースサービスのAmazon DynamoDBが停止したほか、20以上のAWSサービスでエラー率やレイテンシの増加が観測されました。影響を受けた主なサービスを詳しく見ていきましょう。
Amazon CloudWatchは、AWSリソースとアプリケーションをリアルタイムで監視するサービスで、システムの健全性を把握するための目となる重要なツールです。このサービスが影響を受けたことで、多くの企業は自社システムの状態を把握することが困難になりました。
AWS Lambdaは、サーバーを管理することなくコードを実行できるサーバーレス実行環境で、イベント駆動型のアプリケーション構築に広く利用されています。Lambdaの障害により、多くの自動化処理やバックエンド機能が停止しました。
Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)は、AWSの中核をなす仮想サーバーサービスで、新規インスタンスの起動に問題が発生しました。これにより、スケーリング操作や新規デプロイメントが実施できない状況となりました。
IAM(Identity and Access Management)は、AWSリソースへのアクセスを安全に制御するためのサービスで、認証と認可の根幹を担っています。IAMの障害により、ユーザー認証やアクセス権限の確認に問題が発生し、正規のユーザーでもリソースにアクセスできない事態が生じました。
Network Load Balancerは、トラフィックを複数のターゲットに分散させる負荷分散サービスで、高可用性を実現するための重要なコンポーネントです。このサービスのヘルスチェック機能が障害となったことで、トラフィックの適切な分散ができなくなりました。
その他にも、Amazon RDS(リレーショナルデータベースサービス)、Amazon S3(ストレージサービス)、Amazon ECS(コンテナオーケストレーション)、Amazon EKS(Kubernetesサービス)、AWS支援ツールなど、AWSエコシステムの中核を成す多数のサービスが影響を受けました。これらのサービスは企業のビジネスインフラの基盤となっているため、障害の影響は極めて広範囲に及びました。
グローバル企業への影響と被害状況
この障害により、世界中の数百のサイトやサービスが影響を受け、多くの企業とユーザーに混乱が生じました。主な被害を受けた企業とサービスを分野別に詳しく見ていきます。
コミュニケーションとビジネスツールの分野では、Zoomのビデオ会議サービスが影響を受け、企業のリモート会議やオンライン授業に支障が出ました。Slackのビジネスチャットツールも障害の影響を受け、多くの企業で社内コミュニケーションが困難になりました。Snapchatのメッセージングアプリも接続問題が報告され、若年層を中心としたユーザーとのコミュニケーションが途絶えました。
金融サービスの分野では深刻な影響が見られました。Robinhood Marketsの株式取引アプリが利用できなくなったことで、投資家は取引機会を逃す可能性がありました。Coinbaseの暗号資産取引所も影響を受け、仮想通貨の売買が一時的に停止しました。Venmoの個人間送金アプリも利用できなくなり、日常的な金銭のやり取りに支障が出ました。
エンターテインメントとメディアの分野では、Disney+の動画配信サービスが視聴できなくなり、多くのユーザーが楽しみにしていたコンテンツを見ることができませんでした。Apple MusicやApple TV+といったAppleの音楽・映像サービスも影響を受け、エンターテインメント体験が中断されました。Robloxのオンラインゲームプラットフォームも接続問題が発生し、多くの若いゲーマーがプレイできない状況となりました。
AI・検索サービスの分野では、PerplexityというAI検索サービスが影響を受けました。これらの企業は、AWSのUS-EAST-1リージョンに依存していたため、DNSの問題により直接的かつ深刻な影響を受けることになりました。
日本国内での影響と被害の詳細
日本国内でも多くの企業やサービスが影響を受け、特にゲーム関連サービスへの被害が顕著でした。日本時間の夕方から夜にかけての障害発生であったため、多くのユーザーがサービスを利用しようとしていた時間帯と重なり、影響が拡大しました。
ゲーム関連では、任天堂Switch Onlineが全面的な障害に見舞われ、オンラインプレイが完全に不可能になりました。多くのSwitchユーザーが、スプラトゥーンやマリオカートなどのオンライン対戦を楽しもうとしていた時間帯に接続できず、ソーシャルメディア上で不満の声が相次ぎました。
フォートナイトでは、ログイン機能が停止し、新規にゲームを始めることができない状態となりました。既にログインしていたプレイヤーも、セッションが切れるとログインし直すことができず、実質的にプレイ不可能な状況が続きました。
パルワールドというゲームでは、接続が不安定になり、プレイ中に突然切断される事象が多発しました。オンライン要素が重要なこのゲームにとって、接続の不安定性は致命的な問題でした。
Apex Legendsでも接続問題が報告され、ランクマッチやカジュアルマッチへの参加が困難になりました。競技性の高いこのゲームでは、接続問題によるペナルティを受けるプレイヤーも出てきました。
その他のサービスでは、Skebというクリエイター向けプラットフォームがネットワーク障害を経験し、クリエイターとクライアントのやり取りに支障が出ました。ecforceというECプラットフォームも影響を受け、オンラインショップの運営に問題が生じました。
AWS上に構築された各種業務システム、ECサイト、アプリケーションにおいて、アクセス遅延やログイン不能の報告がソーシャルメディア上に相次ぎました。特に夕方から夜にかけての時間帯は、ECサイトにとって重要な売上時間であるため、経済的損失も大きかったと考えられます。
エンドユーザーが直面した具体的な問題
この障害により、世界中のエンドユーザーは様々な問題に直面し、日常生活やビジネス活動に支障をきたしました。具体的にどのような問題が発生したのか、詳しく見ていきます。
最も一般的だったのは、ウェブサイトやアプリケーションへのアクセスが完全に不能になるという問題でした。ブラウザやアプリを開いてもエラーメッセージが表示されるだけで、目的のコンテンツやサービスに到達できない状況が広範囲で発生しました。
ログイン機能の停止も深刻な問題でした。DynamoDBに認証情報やセッション状態を保存していたアプリケーションでは、ログイン機能が完全に停止し、既存のログインセッションも維持できなくなるという事態が発生しました。ユーザーは自分のアカウントにアクセスできず、パーソナライズされたサービスを受けることができませんでした。
データの読み込みエラーも頻繁に報告されました。ページを開いても画像が表示されない、コンテンツが途中までしか読み込まれない、エラーメッセージが繰り返し表示されるといった症状が見られました。
サービスの応答遅延も大きな問題となりました。完全にダウンしているわけではないものの、通常であれば数秒で完了する操作に数分かかる、あるいはタイムアウトしてしまうといった状況が発生し、ユーザーの生産性を著しく低下させました。
オンラインゲームへの接続が不能になったことで、多くのゲーマーが娯楽の時間を失いました。特に競技性の高いゲームでは、ランクマッチなどに参加できないことで、プレイヤーの進行に影響が出ました。
ビジネスツールの利用不可により、企業の業務が停止または大幅に遅延しました。ZoomやSlackが使えないことで、リモートワークを中心とする企業では業務の継続が困難になりました。
決済サービスの停止は、ECサイトや店舗での購入に影響を与えました。購入手続きの途中でエラーが発生し、決済が完了しない、あるいは決済が完了したかどうか確認できないといった混乱が生じました。
動画配信サービスの視聴不能により、多くのユーザーがエンターテインメント体験を奪われました。休日の夜に家族で映画を見ようとしていた家庭や、配信を楽しみにしていた視聴者にとって、大きな失望となりました。
ビジネスへの多面的な影響
企業側にとっても、この障害は経済的、評判的、業務的に大きな損失をもたらしました。それぞれの側面について詳しく見ていきます。
経済的損失の面では、サービス停止による売上機会の損失が最も直接的な影響でした。ECサイトでは商品を販売できず、サブスクリプションサービスではユーザーがサービスを利用できないことによる顧客満足度の低下が懸念されました。約15時間という長時間の障害であったため、その損失額は企業によっては数百万円から数億円規模に達した可能性があります。
顧客からの問い合わせ対応コストも大幅に増加しました。サービスが利用できないことに対するユーザーからの問い合わせが殺到し、カスタマーサポート部門は通常業務を停止して障害対応に追われることになりました。深夜から早朝にかけての時間帯であっても、緊急対応のためにスタッフを招集する必要があった企業も多かったでしょう。
復旧作業のための人的リソース投入も無視できないコストです。技術者チームは障害の原因究明、代替手段の検討、復旧後の動作確認など、通常業務とは別の作業に多くの時間を費やすことになりました。
SLA(サービスレベルアグリーメント)違反による補償の可能性も考えられます。企業が顧客に対して一定のサービスレベルを約束している場合、障害によってそれを満たせなかったことに対する補償を求められる可能性があります。
評判への影響も深刻でした。顧客からの信頼が低下し、「あのサービスは障害が多い」という印象を持たれてしまうと、長期的な顧客離れにつながる可能性があります。特に競合サービスが正常に動作していた場合、ユーザーがそちらに移行してしまうリスクがあります。
ソーシャルメディアでのネガティブな反応も企業イメージに打撃を与えました。TwitterやFacebookで不満の声が拡散されることで、障害を直接経験していないユーザーにも否定的な印象が広まってしまいます。
ブランドイメージの毀損は、短期的な売上損失以上に長期的な影響をもたらす可能性があります。特に信頼性を売りにしているサービスにとって、大規模障害は致命的なダメージとなりえます。
業務への影響としては、内部業務システムの停止により、従業員が通常の業務を遂行できなくなりました。社内の顧客管理システム、在庫管理システム、勤怠管理システムなどがAWS上で動作していた場合、これらすべてが停止してしまいます。
従業員の生産性低下も避けられません。システムが使えないために待機せざるを得ない、手作業で代替処理を行う必要がある、といった状況により、通常の数分の一の生産性しか発揮できない状況が続きました。
代替手段の確保に伴う混乱も発生しました。急遽オンプレミスのシステムに切り替える、別のクラウドサービスを使用する、紙ベースの処理に戻すなど、準備されていない代替手段を即座に実施することは多くの混乱を招きました。
US-EAST-1リージョンの重要性とリスク
今回障害が発生したUS-EAST-1リージョン(米国バージニア州北部)は、AWSにとって最も重要かつ歴史的なリージョンの一つであり、その特殊な地位が障害の影響を拡大させた要因となりました。
US-EAST-1は、AWSが最初に開設したリージョンであり、多くのレガシーサービスがホストされているという特徴があります。AWSの歴史とともに成長してきたこのリージョンには、長年にわたって構築されてきたシステムやデータが集積しており、技術的負債も蓄積している可能性があります。
多くのグローバル企業がこのリージョンをプライマリとして利用しています。特に米国東海岸に拠点を置く企業や、グローバル展開している企業の多くが、US-EAST-1を主要なリージョンとして選択しています。これは、地理的な近さによるレイテンシの低さ、豊富なサービスの availability、そして歴史的な経緯などが理由です。
一部のAWSサービスは、US-EAST-1でのみ利用可能、または最初に展開されるという特性があります。新しいサービスや機能は、多くの場合まずUS-EAST-1でリリースされ、その後他のリージョンに展開されるため、最新の機能を使いたい企業はこのリージョンを選択せざるを得ない状況があります。
多くのサードパーティサービスがこのリージョンに依存しているという点も重要です。AWSのマーケットプレイスで提供されているサービスや、AWS上で動作するSaaSサービスの多くが、US-EAST-1を標準のリージョンとして設定しています。
このリージョンの重要性ゆえに、今回の障害の影響が特に大きくなったと考えられます。過去にもUS-EAST-1での障害は複数回発生しており、2017年のS3障害、2020年のKinesis障害、2021年のネットワーク障害など、このリージョンへの集中がリスク要因となっていることが繰り返し指摘されています。
クラウド依存がもたらすシステミックリスク
今回の障害は、現代のインターネットインフラストラクチャがいかに少数の企業のサービスに依存しているかを改めて浮き彫りにし、集中化がもたらすシステミックリスクの大きさを示しました。
単一障害点(Single Point of Failure)のリスクは、今回の障害で最も明確に示された問題です。多くの企業が同じクラウドプロバイダー、さらには同じリージョンに依存していることで、一箇所の障害が世界中に波及する構造になっています。これは、効率性と利便性を追求した結果として生まれた、現代のインターネットインフラの構造的な脆弱性といえます。
相互依存性の問題も深刻です。DynamoDBのような基盤サービスに多くのサービスが依存していることで、一つのサービスの障害が連鎖的に他のサービスへ波及するリスクがあります。今回の障害では、わずか20分で35以上のサービスに影響が広がったことが、この相互依存性の危険性を如実に示しています。
DNS障害の影響範囲の広さも重要な教訓です。DNSという基盤的なインフラストラクチャの問題が、実際のデータやサービスが正常であっても、アクセス不能という状態を引き起こす可能性があることが明らかになりました。DNSは「インターネットの電話帳」と呼ばれ、その重要性は理解されていましたが、今回の障害によってその重要性が実証されました。
集中化のメリットとデメリットのバランスを考える必要があります。少数の大手クラウドプロバイダー(AWS、Microsoft Azure、Google Cloud)に世界中のサービスが集中していることは、規模の経済によるコスト削減、高度な技術の活用、グローバルなインフラの利用といったメリットをもたらします。しかし同時に、一つのプロバイダーの障害が広範な影響を及ぼすという大きなリスクも生み出しています。
地理的集中もリスクを高める要因です。US-EAST-1のような特定のリージョンに多くのサービスが集中していることで、そのリージョンでの障害、自然災害、電力供給問題などが、世界中のサービスに影響を与える可能性があります。
企業が学ぶべき教訓と実践的な対策
この障害から学ぶべき教訓は多岐にわたりますが、最も重要なのは「クラウド障害は必ず発生する」という前提に立ったシステム設計と運用体制の構築です。
マルチリージョン構成の重要性は、今回の障害で最も強く認識された対策です。単一リージョンへの依存を避け、複数のリージョンにシステムを分散配置することで、一つのリージョンの障害時にも継続してサービスを提供できる体制を構築する必要があります。例えば、US-EAST-1とUS-WEST-2、さらにAP-NORTHEAST-1(東京リージョン)といった地理的に離れた複数のリージョンにシステムを展開することで、リスクを分散できます。
マルチクラウド戦略の検討も重要な選択肢です。AWS以外のクラウドプロバイダー(Microsoft Azure、Google Cloud Platform等)も併用することで、特定のプロバイダーへの依存を減らすことができます。ただし、マルチクラウドは管理の複雑性の増加、異なるプラットフォーム間でのデータ転送コスト、複数のプラットフォームに精通した人材の必要性など、デメリットも伴うため、慎重な検討が必要です。
障害時の対応計画の策定は必須です。クラウドサービスの障害を想定した事業継続計画(BCP)や災害復旧計画(DR)を策定し、定期的に訓練を実施することが重要です。計画書を作成するだけでなく、実際に障害を想定した訓練(ファイアドリル)を行い、チームメンバーが迅速に対応できるようにしておく必要があります。
監視とアラートの強化により、障害の早期検知と迅速な対応が可能になります。AWSのステータスページや監視ツールを活用し、異常が発生した際に即座に通知を受け取れる体制を整えることが求められます。CloudWatch、Datadog、New Relicなどの監視ツールを適切に設定し、異常なエラー率やレイテンシの増加を検知できるようにしておきましょう。
依存関係の可視化は、リスク評価の基礎となります。自社のシステムがどのAWSサービスに依存しているかを明確に把握し、各サービスの障害が及ぼす影響を事前に評価しておくことが重要です。依存関係マップを作成し、どのサービスが停止すると業務にどのような影響があるかを可視化しておくと、優先的に対策すべき箇所が明確になります。
DNS冗長性の確保は、今回の障害を受けて特に重要性が増した対策です。DNSの冗長性を確保し、単一のDNSプロバイダーへの依存を避けることで、DNS障害のリスクを軽減できます。Route 53だけでなく、Cloudflare DNSやGoogle Cloud DNSなど、複数のDNSサービスを組み合わせることも検討に値します。
SLAの確認と理解も欠かせません。AWSが提供するサービスレベルアグリーメント(SLA)を正しく理解し、障害時の補償範囲や手続きを把握しておくことが必要です。重要なのは、SLAで保証されている稼働率と、実際のビジネス要件が一致しているかを確認することです。
AWSの対応と透明性のある情報開示
AWSは障害発生後、ステータスページを通じて定期的に状況を更新し、技術的な詳細についても比較的透明性の高い情報開示を行いました。この対応は、顧客が適切な判断と対応を行うために重要な役割を果たしました。
透明性のある情報開示として、AWSは障害の根本原因、影響を受けたサービス、復旧のタイムラインについて詳細な情報を提供しました。DNS解決問題という技術的な原因、DynamoDBへの影響、そして連鎖的に障害が広がったメカニズムについて、技術者が理解できる レベルの説明を行いました。これにより、顧客は状況を理解し、自社システムへの影響を評価し、適切な対応を取ることができました。
技術的な説明の提供により、同様の問題に備えるための知見が共有されました。DNS解決問題、DynamoDBへの依存による連鎖障害、Network Load Balancerのヘルスチェック障害など、具体的な技術要素について説明することで、他の企業も自社システムの脆弱性を評価できるようになりました。
今後の改善策については、AWSは今回の障害を詳細に分析し、同様の問題が再発しないよう、システムの改善を進めることが期待されます。過去の障害事例でも、AWSは事後分析(Post-Mortem)を公開し、再発防止策を示してきた実績があります。
ただし、一部では情報開示のタイミングや詳細度について批判的な声もありました。障害発生から数時間後でも具体的な復旧見込み時刻が示されなかったことや、一部のサービスの状態が不明確だったことなど、改善の余地も指摘されています。
過去のAWS障害との比較と傾向分析
US-EAST-1リージョンでは過去にも複数回の大規模障害が発生しており、今回の障害と比較することで、AWSのインフラの課題と傾向が見えてきます。
2017年2月に発生したS3の障害は、人為的なミスがトリガーとなりました。エンジニアがデバッグ作業中に、意図した以上のサーバーを停止させてしまったことが原因で、多くのウェブサイトやサービスが影響を受けました。この障害では、S3に依存している多くのサービスが連鎖的にダウンし、インターネットの一部が「壊れた」ような状態になりました。
2020年11月には、Kinesis Data Streamsの障害が発生しました。この障害では、データストリーミングサービスの問題により、リアルタイムデータ処理に依存する多くのアプリケーションが影響を受けました。特にIoTデバイスやログ収集システムなど、継続的なデータ送信が必要なシステムで深刻な影響が出ました。
2021年12月には、ネットワーク機器の障害によりEC2やRDSが影響を受ける事象が発生しました。ネットワーク層での問題は、多くの上位サービスに影響を与え、復旧にも時間を要しました。
2022年にも複数の障害が発生しており、US-EAST-1の信頼性に対する懸念が高まっていました。
今回の2025年10月の障害は、DNS解決問題という比較的珍しい原因によるものでしたが、連鎖的な障害の発生パターンは過去の事例と類似しています。基盤となるサービスやインフラの問題が、依存している多数のサービスに波及するという構造的な課題は、依然として解決されていないことが明らかです。
障害の傾向として、US-EAST-1での障害頻度が他のリージョンと比較して高いこと、基盤サービスの障害が連鎖的に影響を拡大させること、復旧に長時間を要するケースが増えていることなどが指摘できます。
SLA(サービスレベルアグリーメント)と補償制度の実態
AWSには、サービス稼働率や返金などについて規定しているSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意)がありますが、その内容と実際の補償には大きなギャップがあることを理解する必要があります。
サービスレベル保証の具体例として、マルチAZ構成のAmazon EC2では、月間稼働率99.99%を保証しています。これは、月間のダウンタイムが約4.32分以内に収まることを意味します。一方、個別のEC2インスタンス(Single EC2 Instance)については、月間稼働率99.5%のSLAがあり、これは月間のダウンタイムが約3.6時間まで許容されることを示しています。
さらに重要な点として、シングルAZ構成の場合、SLAとして設定されている稼働率は90%にすぎません。これは、月間のダウンタイムが約72時間、つまり3日間まで許容されることを意味し、高可用性を重視する場合はマルチAZ構成が必須であることがわかります。
補償の仕組みについて理解しておくべき重要なポイントがあります。SLAを満たさなかった場合、顧客はサービス料金の一部をサービスクレジットとして受け取ることができますが、これは現金で返金されるのではなく、将来の同サービスの利用料から割引される形で提供されます。つまり、障害により数千万円の損失を被ったとしても、受け取れるのは次月の利用料から数万円が割引されるといった程度の補償にとどまる可能性があります。
さらに、サービスクレジットを受領するには、顧客自身がAWSサポートセンターにケースを申請する必要があります。自動的に補償されるわけではなく、申請の際には件名欄に「SLAクレジットの請求」の表記と、請求の対象となる各使用不能の日時などの詳細情報を提供することが求められます。
SLAの最大の限界は、返金義務のないSLAと無保証・責任限定条項により、どんなに長時間サービスの稼働がストップしても、Amazon社が負うビジネスリスクは限定されるようになっていることです。つまり、今回のような15時間以上の障害が発生しても、AWSが顧客に支払う補償は、実際のビジネス損失に比べて極めて限定的なものとなる可能性が高いのです。
このため、企業は「AWSのSLAに頼るだけでは不十分」という認識を持ち、自社でも冗長性の確保、事業継続計画の整備、保険の検討など、独自のリスク管理策を講じる必要があります。
企業が実施すべき具体的な対策(レベル別)
今回の障害を受けて、企業が実施すべき具体的な対策について、組織のレベル別に整理します。
経営層が取るべき対策としては、まず現在のAWS依存度を正確に評価し、包括的なリスク分析を実施することが挙げられます。自社のビジネスのどの部分がクラウドサービスに依存しているか、障害時にどの程度の経済的損失が発生するかを定量的に把握する必要があります。
マルチクラウド戦略の検討会議を具体的なスケジュールを設定して開催することも重要です。AWS以外のクラウドプロバイダーの活用、ハイブリッドクラウド構成、オンプレミスとの組み合わせなど、リスク分散の選択肢を検討する必要があります。
事業継続計画(BCP)の見直しと更新を指示し、クラウド障害を想定したシナリオを追加することが求められます。従来のBCPは自然災害や火災などを想定したものが多いですが、クラウド障害という新たなリスクシナリオを組み込む必要があります。
クラウド障害時の経済的影響をシミュレーションし、最悪のケースでどの程度の損失が発生するかを把握しておくことも重要です。これにより、対策への投資の優先順位を適切に判断できます。
IT部門への投資予算を見直し、冗長性確保のための予算を確保することも経営判断として必要です。短期的にはコスト増加に見えても、障害時の損失を考えれば、適切な投資といえます。
IT部門・エンジニアが取るべき対策としては、障害時の連絡フローを文書化し、チーム全員がアクセスできる場所に配置することが基本です。誰が誰に連絡するか、どの順番で対応するか、エスカレーションの基準は何かなど、具体的な手順を明確にしておく必要があります。
AWSの各サービスへの依存関係を可視化したマップを作成することも重要です。どのアプリケーションがどのAWSサービスに依存しているか、そのサービスが停止するとどのような影響があるかを図示することで、リスクの全体像を把握できます。
マルチリージョン構成への移行計画を段階的に策定し、実行に移すことが求められます。すべてのシステムを一度に移行するのは現実的ではないため、重要度の高いシステムから順次移行するロードマップを作成します。
障害検知のための監視ツールとアラート設定を強化することも必須です。CloudWatch、Datadog、New Relic、Prometheusなどの監視ツールを適切に設定し、異常を早期に検知できる体制を整えます。
定期的な障害対応訓練(ファイアドリル)を実施することで、実際の障害時にスムーズに対応できるようになります。少なくとも年に2回程度は、障害を想定した訓練を行うことが推奨されます。
AWSステータスページを定期的に確認する習慣をつけることも重要です。障害発生後に確認するだけでなく、計画メンテナンスの予定なども事前に把握しておくことで、影響を最小限に抑えられます。
具体的なアーキテクチャ対策としては、US-EAST-1への過度な依存を見直し、他のリージョン(US-WEST-2、AP-NORTHEAST-1など)への分散を検討する必要があります。地理的に離れた複数のリージョンにシステムを配置することで、リージョン単位の障害に対する耐性が向上します。
DynamoDBのグローバルテーブル機能を活用し、複数リージョンでのデータ同期を実現することも有効な対策です。これにより、一つのリージョンでDynamoDBが停止しても、他のリージョンのデータにアクセスできます。
Route 53のヘルスチェックとフェイルオーバー機能を適切に設定し、自動的なリージョン切り替えを可能にすることで、障害時の手動対応を減らし、復旧時間を短縮できます。
重要なアプリケーションについては、複数のクラウドプロバイダーでのホスティングを検討することも選択肢です。AWS とAzure、あるいはAWSとGCPなど、異なるプロバイダーに同じアプリケーションを展開することで、一方の障害時にも継続してサービスを提供できます。
認証システムやセッション管理など、アプリケーションの根幹を成す重要な機能の冗長性を特に重視して確保する必要があります。これらの機能が停止すると、アプリケーション全体が使用不能になるため、優先的に対策すべきです。
マルチクラウド戦略の詳細な解説
今回の障害は、単一のクラウドプロバイダーへの依存がもたらすリスクを明確に示しました。マルチクラウド戦略について、より実践的な観点から詳しく解説します。
マルチクラウド戦略とは、AWS、Azure、GCPなどの複数のクラウドプロバイダーを組み合わせて使用するアプローチです。例えば、基本的なインフラとデータベースはAWSを利用し、AIや機械学習の機能はGCPのサービスを使い、Microsoft製品との統合が必要な部分はAzureを活用するといった使い方が可能です。
マルチクラウドの主なメリットとして、ベンダーロックインの回避が挙げられます。特定のプロバイダーに縛られず、サービスや価格の変更に柔軟に対応できます。一つのプロバイダーが価格を大幅に引き上げたり、サービスを終了したりしても、他のプロバイダーに移行する選択肢があります。
障害時のリスク分散も大きなメリットです。今回のように一つのプロバイダーで大規模障害が発生しても、他のプロバイダーでサービスを継続できる体制を構築できます。完全な冗長性を実現するには投資が必要ですが、ビジネスの継続性を重視する企業にとっては価値のある投資といえます。
最適なサービスの選択が可能になる点も魅力です。各クラウドプロバイダーには得意分野があり、AWSはサービスの豊富さ、GCPはAIとデータ分析、AzureはMicrosoft製品との統合といった強みがあります。用途に応じて最適なサービスを選択することで、パフォーマンスとコストの最適化が図れます。
価格交渉力の向上も見逃せないメリットです。複数のプロバイダーを利用していることを示すことで、価格交渉の際に有利な立場に立つことができます。
一方、マルチクラウドには明確なデメリットも存在します。管理の複雑性の増加は最大の課題です。複数のプラットフォームを管理する必要があり、それぞれ異なるコンソール、API、設定方法を習得しなければなりません。運用負荷が増加し、管理ツールの統合も難しくなります。
コストの増加も避けられません。複数のプロバイダーとの契約、データ転送費用(特にクラウド間のデータ転送は高額)、管理ツールのライセンス費用などで、単一クラウドよりもコストが高くなる可能性があります。
スキル要求の高まりも課題です。複数のクラウドプラットフォームに精通した人材が必要になり、教育コストや採用コストが増加します。一つのプラットフォームを深く理解するよりも、複数のプラットフォームを広く理解する必要があり、専門性の獲得が難しくなる面もあります。
統合の難しさも無視できません。異なるプラットフォーム間でのデータ連携、認証の統合、ネットワークの接続など、技術的に難しい課題が多く存在します。
マルチクラウド実装のポイントとして、ベンダーロックインを防ぐためには、マルチクラウド対応のツールやオープンスタンダードの技術を活用することが重要です。Kubernetesのようなコンテナオーケストレーションツールを使用することで、どのクラウドプロバイダーでも同じようにアプリケーションを動作させることができます。Terraform のようなインフラストラクチャ as Code ツールを使えば、複数のクラウドのインフラを統一的に管理できます。
主要クラウドプロバイダーの特徴比較
マルチクラウド戦略を検討する上で、各プロバイダーの特徴と強みを正確に理解することが重要です。
クラウドサービス市場におけるシェア状況を見ると、2022年第4四半期のデータでは、AWSのシェア率は32%で最大のシェアを誇ります。次いでAzureのシェア率は23%、GCPのシェア率は10%となっています。この数字からも、AWSが市場で圧倒的な地位を占めており、今回の障害の影響が広範囲に及んだ理由が理解できます。
AWS(Amazon Web Services)の最大の特徴は、サービスの種類が最も豊富で、200以上のサービスを提供している点です。拡張性に優れており、スタートアップから大企業まで幅広く利用されています。グローバルに展開する企業にとって、世界中に配置されたリージョンとエッジロケーションは大きな魅力です。
AWSは最も歴史が長く、成熟したサービスとエコシステムを持っています。ドキュメントの充実度、コミュニティサポートの活発さ、サードパーティツールの豊富さなど、エコシステムの成熟度では他のプロバイダーを大きくリードしています。
Azure(Microsoft Azure)の最大の強みは、エンタープライズ向け機能の充実とMicrosoft環境との統合です。Windows Server、Active Directory、Office 365、Microsoft 365などとのシームレスな統合は、既存のMicrosoft製品を使用している企業にとって大きなメリットです。
ハイブリッドクラウド構成に強みを持ち、オンプレミスとクラウドを統合的に管理できるAzure Stackなどのソリューションを提供しています。日本国内でのデータセンター展開も充実しており、データの国内保存が求められるケースに対応できます。
GCP(Google Cloud Platform)は、AIやデータ分析、機械学習に強みを持つプロバイダーです。BigQueryなどのデータ分析ツールは業界トップクラスの性能を誇り、大規模データの分析に優れています。
Kubernetesの開発元であり、コンテナ技術とマイクロサービスアーキテクチャに強いという特徴があります。技術先行型のプロジェクトやスタートアップに向いており、比較的シンプルで直感的なインターフェースは、初めてクラウドを使う開発者にも扱いやすいと評価されています。
クラウド障害情報の効果的な確認方法
クラウドサービスで障害が発生した際に、迅速かつ正確に情報を収集する方法について、実践的なアプローチを解説します。
公式ステータスページの活用は基本中の基本です。各クラウドプロバイダーは、サービスの稼働状況を公開するステータスページを提供しています。AWS Service Health Dashboard、Azure Status、Google Cloud Status Dashboardなどを定期的にチェックする習慣をつけることが重要です。
これらのページでは、リアルタイムでサービスの状態を確認でき、各リージョン、各サービスごとの状態が表示されます。過去の障害履歴も閲覧できるため、特定のサービスやリージョンの信頼性を評価する際の参考になります。
ただし、ステータスページには重要な限界があることを理解しておく必要があります。クラウドサービス側の問題であっても、一定以上のユーザーに影響が出ることが確認できないと、ダッシュボードには掲載されません。少なくともGCPはこの方針を明言しています。このため、自社のシステムで問題が発生していても、ステータスページには何も表示されていないというケースがあり得ます。
ソーシャルメディアでの情報収集は、公式情報を補完する重要な手段です。クラウドが原因となる障害が発生している場合、世界中の誰かが必ずソーシャルメディア上で報告しています。X(旧Twitter)で「AWS 障害」「AWS outage」「Azure down」「GCP issue」などのキーワードで検索することで、リアルタイムの情報を収集できます。
特に有用なのは、同じサービスを使用している他の技術者や企業の報告です。「DynamoDB が応答しない」「EC2のインスタンス起動に失敗する」といった具体的な症状の報告から、問題の範囲や原因を推測できることがあります。
監視ツールの活用により、公式発表を待たずに問題を検知できます。AWS CloudWatch、Azure Monitor、Google Cloud Monitoringなどのクラウドネイティブな監視ツールに加えて、Datadog、New Relic、Prometheus、Grafanaなどのサードパーティ製監視ツールを併用することで、より包括的な監視が可能になります。
重要なのは、クラウドプロバイダーの監視ツールだけに頼らないことです。クラウドプロバイダー自体に問題がある場合、そのプロバイダーの監視ツールも正常に動作しない可能性があります。外部の監視サービスを併用することで、この問題を回避できます。
障害情報を収集するための具体的なチェックリストとして、定期的に公式ステータスページを確認する、ソーシャルメディアでリアルタイム検索を行う、自社の監視ツールのアラートを確認する、AWSやAzureのサポートに問い合わせる、同業者のコミュニティで情報交換するといった行動を習慣化することが推奨されます。
今回の障害が示す未来への重要な示唆
2025年10月20日のAWS障害は、クラウドコンピューティングの未来と、デジタル社会のあり方に対して重要な示唆を与えています。
クラウド依存度の加速は今後も続くでしょう。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進むにつれ、クラウドサービスへの依存度はますます高まっています。オンプレミスからクラウドへの移行、クラウドネイティブなアプリケーション開発、AIやビッグデータ分析のクラウド活用など、あらゆる場面でクラウドの利用が拡大しています。
しかし、今回の障害は、この加速する依存度に対して警鐘を鳴らすものでもあります。クラウドを活用する際には、その利便性だけでなく、リスクも十分に認識し、適切な対策を講じることが不可欠です。「クラウドに移行すればすべて解決する」という楽観的な見方は危険であり、クラウドには クラウド特有のリスクが存在することを認識する必要があります。
レジリエンス(回復力)の重要性は、今後のシステム設計における最重要課題となるでしょう。「障害は必ず発生する」という前提に立ち、障害発生時にも迅速に回復できるレジリエントなアーキテクチャを構築することが求められます。
これには、自動フェイルオーバー機能の実装、データのリアルタイムレプリケーション、ステートレスなアプリケーション設計、サーキットブレーカーパターンの採用など、様々な技術的アプローチが含まれます。
カオスエンジニアリングの実践が広がることも予想されます。Netflixが開発したChaos Monkeyのような、意図的にシステムに障害を発生させて耐性をテストする手法が、より重要になるでしょう。定期的に障害シナリオをテストし、システムの弱点を事前に発見することで、実際の障害時の被害を最小限に抑えることができます。
規制と透明性の向上も今後の重要なテーマです。クラウドサービスが社会インフラとして重要性を増す中で、規制当局による監督や、プロバイダーに対する透明性の要求が高まる可能性があります。障害発生時の報告義務、最低限の冗長性基準、データ保護要件などが法制化される可能性もあります。
特に、金融、医療、重要インフラなどの分野では、クラウド利用に関する規制が強化される可能性が高いでしょう。企業は、コンプライアンス要件とクラウド活用のバランスを取る必要があります。
インターネットインフラの分散化が進む可能性もあります。今回の障害が示したように、少数の大手プロバイダーへの集中は大きなリスクを生み出します。今後、より分散化されたインフラ、エッジコンピューティングの活用、分散型クラウドの発展などが進む可能性があります。
クラウド時代のリスクマネジメントの本質
2025年10月20日のAWS障害は、約15時間にわたって世界中に影響を与えた大規模なインシデントでしたが、同時に現代のデジタル社会における重要な教訓を提供する出来事でもありました。
クラウドサービスは、その利便性、拡張性、コスト効率性から、現代のビジネスにとって不可欠なインフラとなっています。しかし、その依存度が高まるほど、障害時の影響も指数関数的に大きくなっていきます。今回の障害では、たった一つのリージョンの問題が、世界中の数百のサービスと数億のユーザーに影響を与えました。
企業に求められる姿勢として、クラウドサービスの利便性を享受しつつ、そのリスクも正しく認識することが挙げられます。クラウドは魔法の解決策ではなく、適切に管理されなければ大きなリスクとなりえることを理解する必要があります。
単一のプロバイダーやリージョンへの過度な依存を避けることも重要です。コストや管理の簡便さを理由に単一のプロバイダーに集中させることは、短期的には合理的に見えても、長期的には大きなリスクを抱えることになります。
マルチリージョン、マルチクラウド戦略を適切に検討し、自社のビジネス要件とリスク許容度に応じた最適なアーキテクチャを選択する必要があります。すべての企業がマルチクラウドを採用すべきというわけではありませんが、少なくともその選択肢を検討し、意識的な判断を下すことが重要です。
事業継続計画(BCP)を整備し、定期的に訓練することも欠かせません。計画書を作成するだけでは不十分で、実際に障害を想定した訓練を行い、チームが迅速に対応できる体制を構築する必要があります。
障害発生時の対応フローを明確化し、チーム全体で共有することで、混乱を最小限に抑えられます。誰が何をするか、どのタイミングでエスカレーションするか、顧客へのコミュニケーションはどうするかなど、具体的な手順を文書化しておくことが重要です。
技術的な対策だけでなく、組織的な備えも重要です。技術だけで完全にリスクを排除することはできません。組織全体でリスクを認識し、経営層から現場まで一貫した対応ができる体制を構築することが求められます。
今回の障害は、「クラウドは絶対に安全」という神話を打ち砕き、「障害は必ず発生する」という現実を改めて認識させました。この認識に基づき、適切なリスクマネジメントを実施することが、クラウド時代を生き抜く企業にとって不可欠な要素となります。
AWSをはじめとするクラウドプロバイダーも、今回の障害から学び、システムの改善と信頼性の向上に取り組むことが期待されます。より堅牢なDNSインフラ、サービス間の依存関係の見直し、障害の連鎖を防ぐアーキテクチャの改善など、様々な取り組みが必要でしょう。
同時に、顧客である企業側も、自社のシステムアーキテクチャとリスク対策を見直し、より resilient(回復力のある)なシステムを構築していく必要があります。クラウドプロバイダーに全てを任せるのではなく、自社でもできる限りの対策を講じることが重要です。
クラウドコンピューティングの時代において、技術的な知識だけでなく、リスクマネジメントの視点を持つことが、すべての企業とエンジニアに求められています。今回の障害を貴重な学びの機会として活用し、より強靭なシステムとビジネスを構築していくことが、デジタル社会を支える私たちの責任といえるでしょう。
2025年10月20日のAWS障害は、クラウド時代のリスクと対策について、世界中の企業と技術者に重要な教訓を残しました。この教訓を活かし、より安全で信頼性の高いデジタル社会を構築していくことが、今後の課題となります。

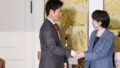
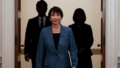
コメント