ふるさと納税を活用して地域を応援しながら税金控除を受けたいと考える方にとって、ワンストップ特例制度は非常に便利な仕組みです。この制度を利用すれば、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができるため、会社員やパートタイマーなど給与所得者の方々に広く利用されています。2025年(令和7年)1月1日から12月31日までに行ったふるさと納税について、ワンストップ特例制度を利用する場合の申請期限は2026年1月10日となっており、この日付までに申請書類が寄附先の自治体に届いている必要があります。特に重要なのは、この期限が「必着」であるという点です。消印有効ではないため、年末年始の郵便事情を考慮して余裕を持った手続きが求められます。本記事では、ふるさと納税のワンストップ特例制度について、申請期限である2026年1月10日を見据えながら、制度の仕組みから具体的な申請方法、注意すべきポイントまでを詳しく解説していきます。これからふるさと納税を検討している方も、すでに寄附を済ませて申請を控えている方も、ぜひ参考にしてください。
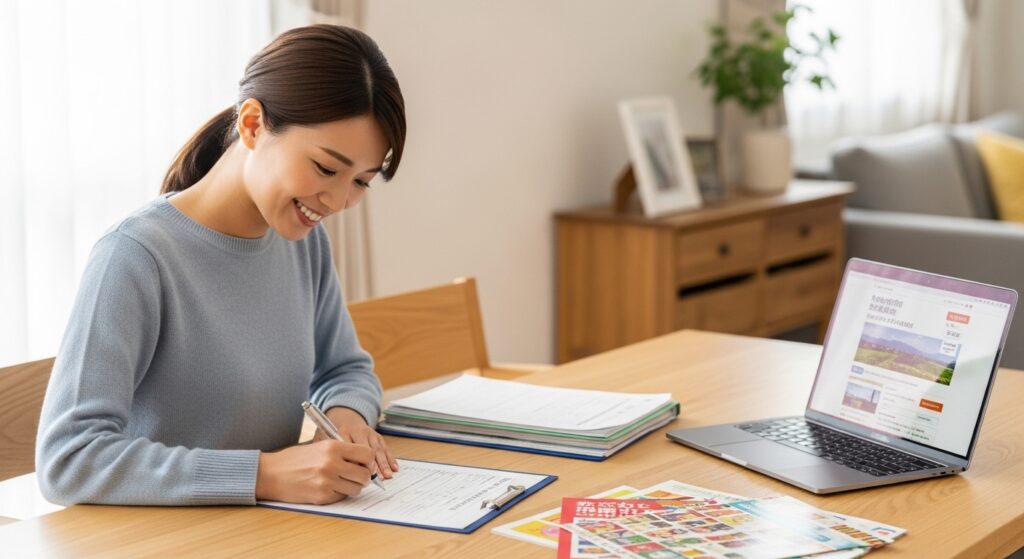
ワンストップ特例制度の基本的な仕組み
ワンストップ特例制度は2015年4月1日から導入された制度で、ふるさと納税を行った際に確定申告をせずとも税金控除を受けられる仕組みとして設計されました。この制度が生まれた背景には、ふるさと納税をより多くの方に利用してもらいたいという政策的な意図があります。従来、ふるさと納税で税金控除を受けるためには確定申告が必須でしたが、確定申告に慣れていない給与所得者にとっては大きなハードルとなっていました。ワンストップ特例制度の導入により、寄附先の自治体に申請書を提出するだけで控除手続きが完了するようになり、多くの方がふるさと納税を気軽に利用できるようになったのです。
この制度を利用した場合の税金控除の仕組みについて詳しく説明します。通常の確定申告でふるさと納税の控除を申請する場合、控除は所得税と住民税の両方から行われます。しかしワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、全額が住民税から控除されるという特徴があります。具体的には、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除額が差し引かれる形になります。
ここで重要なのは、控除方法が異なるだけで、最終的に受けられる税金控除の総額は確定申告を行った場合と全く同じであるという点です。例えば30,000円のふるさと納税を行った場合、自己負担額の2,000円を除いた28,000円が控除対象となりますが、確定申告では所得税と住民税から分けて控除されるのに対し、ワンストップ特例制度では28,000円全額が住民税から一括で控除されます。どちらの方法を選んでも経済的なメリットは変わらないため、自分の状況に合った申請方法を選択することができます。
ワンストップ特例制度を利用するための条件
ワンストップ特例制度は誰でも利用できるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件をすべてクリアしていなければ、確定申告でふるさと納税の控除を申請することになります。
まず第一の条件として、確定申告が不要な給与所得者であることが挙げられます。この制度はもともと確定申告を行わない方を対象として設計されているため、確定申告が必要な方は利用することができません。具体的には、会社員やパートタイマー、アルバイトなど勤務先で年末調整を受けている方が対象となります。一方で、個人事業主やフリーランスの方、年間の給与収入が2,000万円を超える方、医療費控除を受ける予定の方、初年度の住宅ローン控除を受ける方、2か所以上から給与を受けている方、副業収入が20万円を超える方、株式の譲渡益や配当金について申告する方などは、確定申告が必要となるためワンストップ特例制度を利用することができません。
第二の条件は、1年間の寄附先が5自治体以内であることです。ここで注意すべきは「5回以内」ではなく「5自治体以内」という点です。同じ自治体に複数回寄附を行った場合でも、1自治体としてカウントされます。例えばA市に3回、B市に2回、C市に1回の合計6回寄附を行ったとしても、自治体数は3つなのでワンストップ特例制度の条件を満たします。ただし申請書は寄附1回につき1通提出する必要があるため、この例では合計6通の申請書を提出することになります。
第三の条件として、医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受けないことが挙げられます。これらの控除を受けるためには確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度との併用はできません。ただし2年目以降の住宅ローン控除については年末調整で申請できるため、ワンストップ特例制度と併用することが可能です。
申請期限2026年1月10日の重要性
2025年1月1日から12月31日までに行ったふるさと納税について、ワンストップ特例制度を利用する場合の申請期限は2026年1月10日(必着)です。この「必着」という言葉の意味を正確に理解することが極めて重要です。必着とは、2026年1月10日までに申請書類が寄附先の自治体に届いている必要があるということであり、消印有効ではありません。つまり1月10日に郵便局で投函しても間に合わない可能性が高いのです。
年末年始は郵便の配達が通常よりも遅れることがあるため、余裕を持った投函が必要です。特に12月に駆け込みでふるさと納税を行った場合は、申請書の準備と郵送に時間がかかることを考慮して、遅くとも12月25日頃までには投函することをお勧めします。2025年12月後半から2026年1月初旬にかけては郵便局も年末年始の繁忙期となるため、通常よりも配達に時間がかかる可能性があることを念頭に置いておく必要があります。
もし2026年1月10日の期限に間に合わなかった場合や申請書類に不備があった場合は、ワンストップ特例制度の申請は受理されません。しかし税金控除自体を諦める必要はなく、確定申告を行うことで控除を受けることができます。2025年分の確定申告期間は2026年2月16日から3月15日までとなっています。ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合や期限に間に合わなかった場合でも、確定申告という選択肢が残されているため、慌てる必要はありません。ただし確定申告はワンストップ特例制度に比べて手続きが複雑なため、できる限り期限内に申請を済ませることが望ましいでしょう。
オンライン申請と郵送申請の選択
ワンストップ特例制度の申請方法にはオンライン申請と郵送申請の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分の状況や環境に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
オンライン申請は近年急速に普及している方法で、マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば自宅から簡単に手続きを完了させることができます。多くの自治体がオンライン申請に対応しており、書類の郵送が不要なため期限ギリギリでも対応できるという大きなメリットがあります。オンライン申請の場合、本人確認書類のコピーを準備する必要がなく、公的個人認証サービスを利用することで本人確認がオンラインで完結します。また郵送料金が不要であるため、複数の自治体に申請する場合はその分の費用を節約できます。さらに申請状況をリアルタイムで確認できるため、確実に申請が完了したことを把握することができます。
主要なオンライン申請サービスとしては自治体マイページとふるまど+IAMアプリの2つがあります。自治体マイページはマイナンバーカードとマイナポータルアプリを使用して申請を行うサービスで、対象の自治体であれば複数の自治体への申請を一括で行うことも可能です。ふるまどはIAMアプリをダウンロードして使用するサービスで、スマートフォンがあれば簡単にワンストップ特例申請を完結できます。
ただしオンライン申請にはいくつかの注意点もあります。すべての自治体がオンライン申請に対応しているわけではないため、寄附先の自治体が対応しているかどうか事前に確認が必要です。また自治体マイページとふるまどでは対応している自治体が異なるため、複数の自治体に寄附している場合はそれぞれの自治体がどのサービスに対応しているか確認する必要があります。さらにマイナンバーカードのパスワードを忘れた場合や連続で間違えてロックがかかった場合は、市区町村の窓口でリセット手続きが必要となるため、事前にパスワードを確認しておくことが大切です。
郵送申請の場合は、申請書と本人確認書類を寄附先の自治体に郵送します。オンライン環境がない方やマイナンバーカードを持っていない方でも利用できる方法ですが、期限が必着であるため余裕を持った投函が重要です。
申請書の記入方法と必要書類
ワンストップ特例制度の申請に必要な書類は、主に寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)と本人確認書類の2つです。申請書は寄附時に自治体から送付される場合が多く、ふるさと納税ポータルサイトや自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。多くのふるさと納税サイトでは、寄附手続き時に「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」というチェック項目があるため、これにチェックを入れておくと後から申請書を探す手間が省けます。
申請書には提出日、寄附先自治体の長の宛名、申請者の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日、電話番号、寄附年月日、寄附金額などを記入します。ここで特に注意が必要なのは住所の記載です。記入する住所は寄附した年の翌年1月1日時点で住民税が課税される住所でなければなりません。2025年の寄附分であれば2026年1月1日時点の住所を記入します。引っ越し予定がある場合は特に注意が必要で、申請後に住所が変更になった場合は「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
寄附金額についても注意点があります。申請書は寄附1回につき1通作成する必要があり、同じ自治体に複数回寄附した場合でも合計金額を記入するのではなく、それぞれの寄附ごとに申請書を作成して各回の寄附金額を記入します。これは見落としがちなポイントで、同じ自治体だからといって1通にまとめてしまうと一部の寄附が控除対象外になってしまう可能性があります。
申請書には2つの重要なチェック項目があります。1つは「地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である」、もう1つは「地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である」というものです。これらは確定申告をしないことと寄附先が5自治体以内であることを確認するもので、該当する場合はチェックを入れます。
本人確認書類については、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナンバーカードの表面と裏面のコピーを提出します。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー確認書類としてマイナンバー通知カードのコピーまたは個人番号が記載された住民票の写しと、本人確認書類として運転免許証やパスポートなどのコピーを組み合わせて提出します。
ここで重要な注意事項として、マイナンバー通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止されていることを覚えておく必要があります。通知カードに記載されている住所や氏名と現在の住民票の住所や氏名が異なる場合、通知カードは個人番号を証明する書類として使用できません。この場合は個人番号が記載された住民票の写しを取得する必要があります。
申請後の変更届について
ワンストップ特例申請書を提出した後、寄附した年の翌年1月1日までに氏名の変更(結婚や離婚など)、住所の変更(引っ越し)、その他申請書の記載事項の変更(電話番号を除く)があった場合は、「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。この変更届出書の提出期限も2026年1月10日(必着)となっています。
変更届を提出しないと、ワンストップ特例制度が正しく適用されない可能性があります。特に住所変更の場合、住民税は1月1日時点の住所地で課税されるため、申請書に記載した住所と実際の住所が異なると控除が正しく反映されない恐れがあります。引っ越しの予定がある方は特に注意が必要で、変更があった場合は必ず届出を行ってください。申請事項変更届出書は寄附先の自治体のホームページからダウンロードできるほか、多くのふるさと納税ポータルサイトでもテンプレートを提供しています。
ワンストップ特例制度の注意点とよくある失敗
ワンストップ特例制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておかないと、せっかく申請したのに控除を受けられなくなってしまう可能性があるため、しっかりと確認しておきましょう。
最も重要な注意点の1つは、確定申告を行うとワンストップ特例が無効になるということです。ワンストップ特例制度で申請した後に、医療費控除などの理由で確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請はすべて無効になります。この場合、確定申告でふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告する必要があります。ワンストップ特例制度で申請済みだからといって確定申告時にふるさと納税の申告を省略すると、控除を受けられなくなってしまうため、確定申告を行う場合は必ずふるさと納税分も含めて申告してください。
また6自治体以上に寄附した場合も注意が必要です。1年間の寄附先が6自治体以上になった場合、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。すでに5自治体以下でワンストップ特例申請をしていた場合でも、6自治体目への寄附を行った時点ですべてのワンストップ特例申請が無効になります。この場合は確定申告ですべての寄附について控除を申請する必要があります。
申請書の提出先についても誤解が多いポイントです。申請書は寄附を行った自治体に提出するもので、自分の住所地の自治体ではありません。5つの自治体に寄附した場合は5つの自治体それぞれに申請書を送付する必要があります。送付先住所は寄附時に届く書類や各自治体のホームページで確認できます。
控除上限額の計算と確認方法
ふるさと納税を行う前に必ず確認しておきたいのが控除上限額です。控除上限額を超えて寄附を行うと超過分は自己負担となってしまうため、自分の上限額を正確に把握することが重要です。控除上限額は年収や家族構成、お住いの地域などによって異なり、ふるさと納税を行う年の1月1日から12月31日までの所得金額で計算されます。
ふるさと納税の控除額は所得税からの控除、住民税からの控除(基本分)、住民税からの控除(特例分)の3つの要素で構成されています。所得税からの控除額は「(ふるさと納税を行った金額 - 2,000円)× 所得税の税率」で求められ、所得税率は課税所得金額によって5%から45%まで段階的に設定されています。住民税からの控除(基本分)は「(ふるさと納税を行った金額 - 2,000円)× 10%」で計算され、住民税からの控除(特例分)は「(ふるさと納税を行った金額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)」となります。ワンストップ特例制度を利用した場合は所得税からの控除は行われず、その分も含めて住民税からの控除として処理されます。
給与所得者(会社員)の場合の控除上限額の目安として、独身または共働き(配偶者控除なし)の場合、年収300万円で約28,000円、年収400万円で約42,000円、年収500万円で約61,000円、年収600万円で約77,000円、年収700万円で約108,000円、年収800万円で約129,000円、年収1,000万円で約176,000円となります。夫婦(配偶者控除あり)の場合は、年収300万円で約19,000円、年収400万円で約33,000円、年収500万円で約49,000円、年収600万円で約69,000円、年収700万円で約86,000円、年収800万円で約120,000円、年収1,000万円で約166,000円となります。
子供がいる場合の注意点として、中学生以下の子供は控除額に影響がないため計算に入れる必要はありませんが、高校生以上の子供がいる場合は扶養控除の対象となるため控除上限額に影響します。正確な控除上限額を知るには、各ふるさと納税ポータルサイトが提供しているシミュレーションツールを活用することをお勧めします。主要なふるさと納税サイトであるさとふる、ふるなび、楽天ふるさと納税などではすべて無料でシミュレーションツールを提供しています。
控除上限額を超えて寄附を行った場合、超過分は単なる寄附となり税金控除の対象外となります。例えば控除上限額が50,000円の方が70,000円の寄附を行った場合、50,000円までは控除対象(自己負担2,000円)ですが、残りの20,000円は控除対象外となり、実質的な自己負担額は22,000円となってしまいます。これを避けるために、寄附を行う前に必ず自分の控除上限額を確認し、余裕を持った金額で寄附を行うことをお勧めします。
2025年のふるさと納税制度変更について
2025年には、ふるさと納税制度にいくつかの重要な変更がありました。最も注目されたのは2025年10月からのポイント付与禁止です。2025年10月以降、ふるさと納税の仲介サイトにおいて寄附に伴うポイント付与が禁止されました。これまで多くのふるさと納税ポータルサイトでは寄附金額に応じてポイントが付与されるキャンペーンが実施されていましたが、この制度変更により終了しています。
ただしクレジットカードや電子決済サービスなど決済方法に付随するポイント還元は引き続き獲得可能です。例えばクレジットカードで寄附を支払った場合のカードポイントはこれまで通り付与されます。2025年9月までに寄附を済ませた方はポイントのメリットを享受できましたが、10月以降に寄附を行った方はポイント付与を受けられなくなっています。現在は2025年11月ですので、すでにこの制度変更は施行されています。
さらに2026年10月からは追加の制度変更が予定されています。自治体の経費基準が厳格化され、返礼品の調達費用を寄附額の30%以下に抑える基準がより厳しく適用される見込みです。これにより一部の返礼品の内容が変更される可能性があるため、今後のふるさと納税計画を立てる際には最新の情報を確認することが重要です。
確定申告との比較とメリット・デメリット
ワンストップ特例制度と確定申告、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、自分の状況に合った方法を選択することが大切です。
ワンストップ特例制度の最大のメリットは手続きが簡単であることです。確定申告の知識が不要で、税務署に行く必要もありません。オンライン申請に対応した自治体であれば自宅から完結させることができます。一方でデメリットとしては、寄附先が5自治体以内に限定されること、寄附ごとに申請書を提出する必要があること、確定申告が必要になると無効になること、申請期限が翌年1月10日と早いことが挙げられます。
確定申告のメリットは寄附先の自治体数に制限がないことです。6自治体以上に寄附したい方は確定申告を選択することになります。また医療費控除や住宅ローン控除など他の控除と一緒に申請できること、申請期限が3月15日と余裕があること、1回の手続きですべての寄附を申告できることも利点です。デメリットとしては手続きが複雑であること、確定申告の知識が必要であること、税務署に行くかe-Taxの利用が必要であること、寄附金受領証明書の保管が必要であることが挙げられます。
会社員で寄附先が5自治体以内、医療費控除などの必要がない方はワンストップ特例制度が便利です。一方で個人事業主の方や6自治体以上に寄附したい方、他の控除と合わせて申告したい方は確定申告を選択することになります。どちらの方法を選んでも控除される金額は同じであるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
申請スケジュールの立て方と実践的なアドバイス
2025年のふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合の、おすすめスケジュールをご紹介します。
2025年1月から9月の期間は計画的に寄附を行う時期です。年間の寄附計画を立て、計画的に寄附を行うことが大切です。2025年10月からポイント付与が禁止されたため、ポイントを重視する方は9月までの寄附がお得でした。寄附時には「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」にチェックを入れておくと、後から申請書を探す手間が省けます。
2025年10月から11月は年末に向けた準備期間です。控除上限額を再確認し残りの寄附枠を確認します。年末は混雑するため余裕を持った寄附がお勧めです。届いた申請書は紛失しないよう保管しておきましょう。現在は2025年11月ですので、まさにこの準備期間にあたります。
2025年12月は最終調整と申請書準備の時期です。12月中に寄附を完了させ、すべての申請書を準備します。本人確認書類のコピーも必要枚数分用意しておきます。年末年始の郵便事情を考慮し、12月25日頃までには投函することをお勧めします。
2026年1月1日から10日は最終確認の期間です。申請書の提出状況を確認します。オンライン申請の場合はこの時期でも間に合います。1月10日必着を忘れずに、すべての申請を完了させましょう。
まとめ
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告の手間を省いて税金控除を受けられる便利な制度です。2025年の寄附分については、2026年1月10日(必着)が申請期限となります。
制度を利用するための重要ポイントをおさらいすると、まず利用条件として確定申告が不要な給与所得者であること、年間の寄附先が5自治体以内であること、医療費控除や初年度住宅ローン控除を受けないことが挙げられます。申請に必要なものとしてはワンストップ特例申請書(寄附1回につき1通)と本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)があります。
注意事項として、申請期限は2026年1月10日必着(消印有効ではない)であること、確定申告を行うとワンストップ特例は無効になること、住所や氏名に変更があった場合は変更届が必要であること、6自治体以上に寄附するとワンストップ特例は利用不可であることを覚えておいてください。
ふるさと納税は自己負担2,000円で地域を応援しながら返礼品を受け取れる魅力的な制度です。ワンストップ特例制度を上手に活用して、手軽に税金控除のメリットを享受しましょう。申請期限を過ぎてしまった場合でも確定申告で対応できますので焦らず手続きを進めてください。ただし確定申告はワンストップ特例制度に比べて手続きが複雑なため、できる限り期限内の申請をお勧めします。2025年のふるさと納税で、地域貢献と節税のダブルメリットを実感してみてはいかがでしょうか。



コメント