2026年4月1日、日本の年金制度において画期的な変更が実施されます。在職老齢年金制度の支給停止基準額が、現行の月額51万円から月額62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。この改正は、2024年に成立した年金制度改正法に基づくもので、長年「働き損」と呼ばれてきた制度の壁を本格的に緩和する政策転換といえます。高齢者の就労意欲を削いできた年金カットの仕組みが大きく変わることで、働くシニア世代の手取り収入が増加し、企業の人材戦略にも大きな影響を与えることが予想されます。本記事では、在職老齢年金62万円改正の具体的な内容から、個人のキャリアプランや繰下げ受給への影響、そして企業が取るべき対策まで、2026年4月の制度変更について詳細に解説していきます。この改正がもたらす変化を正しく理解し、シニア世代の新しい働き方を考える上での参考としていただければ幸いです。

在職老齢年金制度の基本的な仕組みを理解する
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給する資格を持つ方が60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働く場合に、その収入に応じて年金の一部または全部が支給停止される仕組みのことです。この制度を正確に理解するためには、基本月額と総報酬月額相当額という二つの重要な概念を把握する必要があります。
基本月額とは、在職老齢年金の計算基礎となる年金額であり、具体的には本人が受け取る老齢厚生年金の月額、つまり報酬比例部分を指します。ここで注目すべき点は、老齢基礎年金(国民年金部分)と経過的加算額はこの計算に含まれないということです。これらの年金は在職老齢年金の支給停止対象外であり、どれだけ収入があっても必ず全額が支給されます。また、配偶者がいる場合に加算される加給年金額も基本月額からは除外されます。つまり、在職老齢年金でカットされる可能性があるのは、あくまでも老齢厚生年金の報酬比例部分のみということになります。
一方、総報酬月額相当額は単純にその月の給与だけを指すものではありません。この金額は、その月の標準報酬月額(月給)と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を足し合わせたものとして計算されます。この計算方法が在職老齢年金制度を複雑にしている大きな要因となっています。
賞与が総報酬月額相当額に含まれることは、シニア層の働き控えを意図せず助長してきた最大の原因の一つです。月給については労働時間を調整することである程度コントロールが可能ですが、賞与は業績連動や成果評価に基づいて支給額が変動するため、事前に調整することが困難です。過去1年間に受け取った賞与の合計額が、向こう1年間の毎月の総報酬月額相当額を押し上げ続けるため、例えば会社に貢献して6月に多額の賞与を受け取った場合、その賞与の12分の1の額が翌年5月までの12ヶ月間、毎月加算され続けることになります。この加算によって合計額が支給停止基準額を超えてしまうと、成果を上げたがために1年間にわたって年金がカットされ続けるという事態が発生するのです。この制度設計は、シニア層に対して「賞与をもらうと損をする」という強力な負のインセンティブを与え続けてきました。
現行制度51万円と新制度62万円の違いを具体例で検証する
2026年3月までの現行制度では、支給停止基準額は月額51万円(2025年度基準)に設定されています。現行ルールでは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が51万円を超えた場合、その超過した金額の半分が毎月の老齢厚生年金から支給停止されます。この仕組みを具体的な人物モデルを使って検証してみましょう。
まず、年金カットの影響を強く受けている方のケースを考えます。68歳のAさんは長年の勤務経験から老齢厚生年金の基本月額が月額15万円で、定年後の再雇用先で嘱託社員として働き、総報酬月額相当額が月額45万円です。Aさんの合計額は15万円と45万円を足した60万円となります。現行の51万円基準で計算すると、60万円から51万円を引いた9万円が超過額となり、この半分である4万5千円が支給停止されます。したがって、Aさんが実際に受け取る年金は本来の15万円から4万5千円が差し引かれた10万5千円となってしまいます。
2026年4月1日以降、新しい基準額の62万円が適用されると状況は一変します。Aさんの合計60万円は新基準の62万円を下回るため、支給停止額はゼロとなり、Aさんは本来の年金15万円を全額受け取ることができるようになります。Aさんは働き方や給与を一切変えていないにもかかわらず、制度改正によって毎月の年金手取り額が4万5千円増加し、年額にすると54万円もの増収となるのです。
次に、より高い収入を得ている方のケースも見てみましょう。70歳のBさんは豊富な経験を買われて役員として活躍しており、基本月額は20万円、総報酬月額相当額は60万円です。Bさんの合計額は80万円となります。現行の51万円基準では、80万円から51万円を引いた29万円の半分、つまり14万5千円が支給停止されます。その結果、Bさんが受け取る年金は本来の20万円から14万5千円が引かれた5万5千円にまで減ってしまいます。
2026年4月以降の新制度では、80万円から62万円を引いた18万円の半分である9万円が支給停止額となります。Bさんの手取り年金額は20万円から9万円を引いた11万円となり、改正前の5万5千円と比較するとほぼ倍増することになります。高所得であるため年金が全額支給されるわけではありませんが、支給停止額が月額14万5千円から9万円へと大幅に減少し、年間では66万円もの増収効果が生まれます。
51万円から62万円への引き上げが持つ歴史的意義
51万円から62万円への引き上げ幅は11万円、率にして約21.5%の増加となります。この数字は単なる微調整ではなく、政策の大転換を示すものです。これまでの支給停止調整額は名目賃金の変動に応じて毎年度改定される、いわば物価スライドや賃金スライドに似た技術的な調整でした。しかし、今回の62万円への引き上げは2024年に成立した年金制度改正法という法律改正に基づくものであり、政治的な意思決定による基準額そのものの再設定を意味します。
在職老齢年金制度の歴史を振り返ると、2022年4月に重要な改革が行われました。この時、60歳から64歳までの60代前半の支給停止基準額が従来の28万円から47万円へと大幅に引き上げられたのです。それ以前は60代前半が28万円、65歳以上が47万円という二重基準が敷かれており、非常に複雑な制度となっていました。高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用確保義務化が進む現実を踏まえ、60代前半の就労意欲を不当に削ぐべきではないという判断から、65歳以上の基準である47万円に統一されました。
2022年に47万円に統一された後、基準額は毎年度見直されることになりました。2022年度は47万円、2023年度は48万円、2024年度は50万円、2025年度は51万円と推移してきました。これらの変更は名目賃金の変動に応じた技術的なスライドでした。そのような経緯を踏まえると、2026年4月に51万円から62万円へと11万円も一気にジャンプすることの異例さが際立ちます。2022年改正が60代前半と65歳以上の不平等解消という第一の改革であったとすれば、2026年改正はシニア層全体の働き損の抜本的解消を目指す第二の構造改革と位置づけられます。
在職老齢年金62万円改正の背景にある社会的課題
この抜本的な改革の背景には、日本社会が直面する二つの重大な課題があります。表層的な理由としては、高齢者の就労意欲促進と働き控えの解消が挙げられます。現行制度は働き損の構造を内包しており、一定以上の収入を得ると年金がカットされるため、多くのシニア層が意図的に就労時間を調整する働き控えを選択してきました。調査によると、実に44.4%もの人が年金額が減らないように就業時間を調整していると回答しており、年金の壁が現実に存在していることが明らかになっています。62万円への基準額引き上げは、この壁を大幅に引き上げることで、より多くの人々が年金カットを気にせずに働けるようにする直接的な解決策となります。
深層的な理由としては、日本の構造的危機である人手不足が挙げられます。日本は全産業的に深刻な人手不足に直面しており、経験豊富で高いスキルを持つ高齢者は単なる引退予備軍ではなく、社会を支える貴重な労働力として位置づけられています。特に熟練の技術やノウハウを若手や中堅に継承する技能継承の観点からも、シニア層が年金カットを恐れて早期にリタイアしたり就業調整を行ったりすることは、個々の企業の競争力、ひいては日本経済全体にとって大きな損失となります。
2026年の改正は、日本の政策プライオリティにおける歴史的な転換点を示しています。旧来の論理では、在職老齢年金制度は高い給与所得があり生活基盤が安定している人には年金の支給を調整し、制度全体を支える側に回ってもらうという社会保障における所得再分配の考え方に基づいていました。しかし、この論理が現在の日本が直面する労働力不足の解消という最大の経済的課題の深刻な足かせとなっていました。2026年の62万円改正は、社会保障政策の論理が労働経済政策の必要性、つまり人手不足解消のためにシニア層に制約なく働いてもらうという要請の前に、優先順位を譲ったことを意味します。年金財政の観点から見れば支給停止を緩和することは年金の支出増につながりますが、それ以上にシニア層が働き控えすることによる経済全体の生産性低下や技能継承の停滞による損失の方がはるかに大きいと国が判断したのです。
繰下げ受給の判断に与える重大な影響
在職老齢年金62万円への改正は、手取り収入の増加だけでなく、年金の繰下げ受給のメリットとデメリットの計算を根本から覆すことになります。繰下げ受給とは、65歳で老齢年金を受け取らずに66歳から最大75歳まで受給開始を遅らせる仕組みです。1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額し、例えば70歳で受け取り始めれば42%、75歳なら84%、増額された年金が生涯にわたって続くという非常に強力な制度です。
改正前の51万円基準では、高所得シニアにとって繰下げ受給は非常に合理的な選択肢でした。先のAさんのような方の思考はこうなります。どうせ65歳から年金をもらい始めても在職老齢年金で毎月4万5千円もカットされ満額の15万円をもらえないのだから、65歳では目減りした年金をもらうのではなく、いっそ1円も受け取らずに繰下げを選択しようと考えます。そして70歳で退職すると同時に42%増額された、つまり15万円の1.42倍である21万3千円の年金をもらい始めた方が生涯の受給総額で得になる可能性が高いと判断するわけです。これまでは在職老齢年金によるカットが繰下げを選択する強い動機になっていたのです。
2026年4月以降、Aさんの年金はカットされなくなります。この新しい状況で繰下げを選ぶということは、今、目の前にある満額の年金である月15万円の受給を将来の増額のために我慢するという選択に変わります。以前はカットされて目減りした10万5千円を我慢するだけでしたが、改正後は満額の15万円を我慢しなければなりません。この心理的なハードルや経済的な機会損失は比較にならないほど高くなります。
結論として、2026年4月の改正は高所得シニア層にとって繰下げ受給の魅力を相対的に低下させます。なぜなら、働きながら同時に満額の年金を受け取るという、これまで存在しなかった最も魅力的な第三の選択肢が生まれるからです。これは個人のライフプランニングにおける重大な見直しを迫るものとなります。
企業が直面する実務的な課題と対応策
この変革は働く個人だけでなく、シニア層を雇用する企業側にも迅速かつ戦略的な対応を求めます。企業の人事労務担当者は、2026年4月の施行に向けて複数の実務的な準備が必要となります。
まず、定年再雇用制度や嘱託規定の見直しが不可欠です。多くの企業の現在の規定は、年金がカットされない範囲でという旧来の51万円基準を前提にシニア層の給与や労働時間が設計されています。その前提が崩れるため、規定の全面的な見直しが必須となります。
次に、報酬設計と人件費への影響検討が求められます。シニア層の就労意欲が高まり、フルタイム勤務やより高い報酬を求める従業員が増加することが予想されます。これに対応する報酬体系の再設計と、それに伴う人件費の増加シミュレーションが重要な課題となります。
また、雇用契約書の改訂と従業員への説明も欠かせません。報酬体系や就労時間の変更に伴い、個別の雇用契約書の改訂が必要になる場合があります。従業員が混乱しないよう、制度改正の概要をわかりやすく説明する資料の作成や個別相談の場の設置が不可欠です。
企業の経営戦略としてのシニア人材活用
本質的に重要なのは、この改正を単なる管理コストの増加や事務負担として捉えるのではなく、経営戦略上の絶好の機会と捉え直すことです。高齢人材の活用を再設計する絶好の機会であり、人手不足に悩む企業にとって経験豊富なシニア人材を再戦力化するまたとないチャンスといえます。
この制度改正は企業の採用力とリテンション、つまり人材定着の強力なツールとして活用できます。リテンション戦略としては、優秀なシニア社員が働き控えのために65歳で退職したり労働時間を短縮したりしようとしている場合、企業は積極的に引き留め交渉が可能になります。2026年4月からは給与を上げても62万円の範囲内であれば年金は一切減らないことを説明し、フルタイムでこれまでの経験を活かして若手の指導や技能継承にあたってほしいと具体的な条件を提示して引き留めることができます。
採用戦略としては、他社で働き控えをしている、あるいは旧来の制度設計の下で能力を発揮しきれていない優秀なシニア人材に対して、62万円の枠改正を見据えたシニア層向けの報酬制度を整備していることをアピールできます。これにより採用市場における競争力を高めることが可能となります。この改正への対応は企業の人材戦略を強化する投資と見なすべきなのです。
2026年4月以降のシニア世代の働き方の変化
在職老齢年金62万円改正により、シニア世代の働き方は大きく変化することが予想されます。最大のメリットは年金カットを恐れずに働けるようになることで、これまで51万円の壁を意識して意図的にパートタイム勤務や短時間労働に甘んじていた人が、フルタイム勤務やより責任と報酬の高い役職に就くことを選択しやすくなります。自身の健康や意欲に応じてより柔軟で高収入な働き方を選べるようになることは、キャリアプランの再設計を強力に後押しします。
62万円という基準額は、月給と賞与の月割額、そして年金の報酬比例部分を合計した金額の上限を示しています。例えば年金の基本月額が12万円の場合、総報酬月額相当額が50万円までであれば年金は全額支給されます。年金の基本月額が15万円であれば総報酬月額相当額は47万円まで、年金の基本月額が20万円であれば総報酬月額相当額は42万円まで全額支給の対象となります。この金額範囲が大幅に拡大されることで、より多くのシニア世代が年金を満額受給しながら働くことが可能となるのです。
これからの生涯現役社会に向けた展望
2026年4月の在職老齢年金62万円改正は、単なる年金制度の技術的な変更ではありません。日本の生涯現役社会のあり方を具体的に規定し直す、社会システムの大きな転換点といえます。
働く個人にとっては、年金の壁を前提として組み立ててきたキャリアプランやライフプランが2026年4月をもって過去のものとなります。働くシニア層およびその予備軍は、自身の健康や就労意欲、そして繰下げ受給とのバランスを改めて見直し、より自由で豊かな働き方を設計し直す時期に来ています。
企業にとっては、シニア層をコストや管理対象としてではなく、深刻な人手不足時代を乗り切るための戦略的資産として再定義することが求められます。その能力を最大限に引き出すための報酬制度や職務設計を今から準備する必要があります。
今後の展望として、62万円という基準もまた通過点に過ぎない可能性があります。多くの有識者からは、この在職支給停止の仕組みそのものを撤廃するか、基準をさらに十分に引き上げることが望ましいという指摘が相次いでいます。日本社会は意欲あるシニアがその能力を最大限発揮し、制約なく働き続けられる社会へと不可逆的な一歩を踏み出したのです。
この制度改正を契機に、シニア世代は自らの働き方を主体的に選択できる時代が到来します。年金制度の変更を正しく理解し、自分自身のライフプランに最適な選択をすることが、これからの豊かな人生を築く鍵となるでしょう。

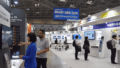

コメント