2025年、日本の通信環境に大きな転換期が訪れています。NTT東日本とNTT西日本が約30年ぶりとなる固定電話料金の値上げを発表したことは、単なる価格改定にとどまらず、日本の通信インフラ全体が新たな時代へと移行する象徴的な出来事となっています。携帯電話やスマートフォンの普及により、固定電話の利用者は年々減少を続けており、総務省の統計データでは2023年時点で固定電話を保有する世帯の割合は57.9パーセントまで低下しました。特に若年層では20代の保有率がわずか8.1パーセントという状況です。その一方で、80歳以上の高齢者世帯では94.7パーセントと依然として高い保有率を維持しており、世代間で大きな格差が生じています。こうした構造変化の中で実施される今回の固定電話料金値上げは、利用者減少と設備老朽化という二重の課題に直面するNTT東西にとって避けられない選択でした。メタル回線設備の維持には年間数百億円規模のコストがかかっており、2035年頃には現行のサービス提供が技術的にも経済的にも限界を迎えると予測されています。この記事では、固定電話料金値上げの詳細、背景にある通信業界の構造変化、光回線電話への移行計画、災害時の通信確保といった重要なポイントについて、最新の統計データとともに詳しく解説していきます。

固定電話料金値上げの詳細と実施時期
2025年9月、NTT東日本とNTT西日本は固定電話の基本料金を約30年ぶりに値上げすると正式に発表しました。この料金改定は2026年4月1日から実施される予定で、事業用では月額330円、住宅用では月額220円の値上げとなります。具体的には、事業用の月額基本料金が現行の1870円から2200円へ、住宅用が1870円から2090円へと引き上げられることになります。
この値上げが対象とするのは、NTT東西が提供する「加入電話」および「加入電話・ライトプラン」です。これらはメタル回線(銅線)を使用した従来型の固定電話サービスで、長年にわたって日本の通信インフラの基幹を担ってきました。約30年ぶりという長期間にわたって据え置かれてきた料金体系が、ここにきて大きく変わることになります。
値上げの実施時期である2026年4月という設定には、利用者への周知期間を十分に確保するという配慮が込められています。発表から実施までに約7ヶ月の期間を設けることで、利用者が代替サービスへの移行を検討したり、家計や事業の通信費予算を見直したりする時間的余裕を提供しています。
注目すべきは、この値上げと並行してNTT東西が実施する代替サービスの料金据え置き政策です。光回線を利用した「ひかり電話」や「光回線電話」、モバイルネットワークを活用した「ワイヤレス固定電話」などの代替サービスについては、現行料金を維持する方針が示されています。これにより、従来型のメタル回線ベースの固定電話と代替サービスとの間に明確な料金差が生まれ、利用者の移行を促進する構造が作られています。
値上げの背景にある通信業界の構造変化
固定電話料金の値上げには、日本の通信業界が直面している深刻な構造変化が背景にあります。最も大きな要因は、携帯電話やスマートフォンの普及による固定電話利用者の大幅な減少です。総務省が公表している統計データによると、固定電話の契約総数は2020年度末時点で5284万契約となり、前年度比で1.5パーセントの減少を記録しました。この減少傾向は2000年代初頭から続いており、ピーク時には6000万契約を超えていた固定電話契約は、現在では5000万契約台前半まで落ち込んでいます。
世帯保有率についても顕著な減少が見られます。2018年時点では固定電話を保有する世帯の割合は64.5パーセントでしたが、2023年には57.9パーセントまで低下しました。わずか5年間で約7ポイントの減少という数字は、固定電話が家庭から姿を消すペースが加速していることを明確に示しています。
特に深刻なのは世代間格差の拡大です。世帯保有率全体が68.2パーセントである中、80歳以上の高齢者世帯では94.7パーセントと極めて高い保有率を維持している一方、30代の世帯では21.4パーセント、20代の世帯ではわずか8.1パーセントにまで低下しています。この格差は、通信手段に対する世代間の考え方の違いを反映しており、若年層は生まれた時から携帯電話が存在し、個人が直接つながる通信手段としてスマートフォンを優先的に利用するため、固定電話の必要性をほとんど感じていません。
こうした利用者減少の中で、NTT東西はメタル回線設備の維持に年間数百億円規模の赤字を抱えているとされています。設備の老朽化も深刻な問題となっており、地下に埋設された銅線ケーブルの腐食、接続部の劣化、電柱設備の老朽化など、様々な箇所で修繕が必要な状態です。これらの修繕には多額の費用がかかる一方、利用者数の減少により収益は減り続けており、事業として持続可能性を保つことが年々難しくなっています。
NTTグループの試算によれば、2035年頃にはこれらの設備を維持したサービス提供が困難になると予測されています。この見通しが、今回の値上げと光回線・モバイル回線への移行計画を推進する大きな動機となっています。
メタル回線から光回線・モバイル回線への移行計画
NTT東日本とNTT西日本は2025年9月29日、メタル回線を利用した固定電話サービスから光回線・モバイル回線を活用したサービスへの具体的な移行計画を公表しました。この計画は2035年度までの完了を目指す大規模なインフラ転換プロジェクトで、日本の通信史において極めて重要な意味を持つものとなっています。
代替サービスの種類と特徴
NTT東西は、加入電話の代替サービスとして主に三つのサービスを提供します。それぞれのサービスには異なる特性があり、利用者の環境やニーズに応じて選択することができます。
第一に「光回線電話」があります。これは2025年10月1日より全国の光提供エリアで提供が開始されたサービスで、光ファイバー網を利用した固定電話サービスです。光回線電話は、既存の加入電話と同様の使い勝手を維持しながら、より高品質な通話を実現します。デジタル信号で音声を伝送するため、従来のアナログ方式に比べて音質が格段に向上し、背景ノイズが少なく、クリアな通話が可能になります。特に高齢者や聴覚に不安がある方にとって聞き取りやすい通話環境が実現するという利点があります。
第二に「ワイヤレス固定電話」があります。このサービスは、モバイルネットワーク(携帯電話の電波網)を利用して固定電話番号での通話を可能にするものです。物理的な回線工事が不要であるため、光ファイバーの敷設が困難な地域や、工事期間を待てない利用者にとって有効な選択肢となります。また、メタル回線の敷設が困難な山間部や離島などの地域でも、モバイルネットワークのカバーエリア内であれば固定電話サービスを提供できるため、過疎地域の通信環境改善にも寄与します。制度・準備が整い次第、全国に順次展開される予定です。
第三に「ひかり電話」があります。これは光ファイバーによるブロードバンドサービス(フレッツ光など)とセットで利用できる固定電話サービスで、すでに多くの家庭や企業で利用されています。インターネット接続と電話サービスを一体的に提供することで、トータルでのコスト削減が可能になります。実際、総務省の統計によると、2020年度には固定電話市場全体の67.5パーセントをIP電話が占めるようになっており、利用者は自然な流れでIP電話への移行を進めています。
移行時の料金体系と費用支援
NTT東西は、利用者の負担を軽減し円滑な移行を促進するため、2025年10月1日以降、加入電話の契約者が光回線電話やワイヤレス固定電話に移行する際の初期費用を無償化する措置を講じています。
通常、新しい電話サービスへの移行には、工事費、事務手数料、機器代金などを含めて合計2万2880円(税込)の初期費用がかかります。この金額は一般家庭にとって決して小さな負担ではありません。NTT東西はこの全額を無償化することで、経済的な理由で移行をためらう利用者が出ないよう配慮しています。
月額料金については、光回線電話とワイヤレス固定電話のいずれも、現行の加入電話と同じ1870円(税込)に設定されます。ただし、これは2026年4月の値上げ前の料金との比較であり、値上げ後の加入電話料金(事業用2200円、住宅用2090円)と比較すると、代替サービスの方が月額220円から330円安くなり、経済的な選択となります。
また、フレッツ光とひかり電話の初期費用についても無償化する方針が示されていますが、具体的な実施時期については追って案内されるとのことです。この措置により、インターネット接続と電話サービスを同時に光回線へ移行する利用者の負担も大幅に軽減されることになります。
段階的な移行スケジュール
移行プロセスは段階的に進められます。まず、設備の老朽化が特に進んでいる一部エリアや、過去の災害によってメタル設備の再敷設が必要となったエリアについては、2026年度から先行して代替の電話サービスへの移行が実施されます。
これらの先行移行エリアでは、NTT東西の担当者が個別に利用者を訪問し、サービス移行の説明と手続きの支援を行う予定です。特に高齢者世帯など、自力での手続きが困難な利用者に対しては、きめ細かなサポートが提供されます。
その後、全国各地で順次移行作業が展開され、2035年度までにすべての加入電話契約者が光回線またはモバイル回線を利用した電話サービスへ移行することを目指しています。この長期的なスケジュールは、利用者が十分な時間をかけて新しいサービスに慣れ、必要な準備を整えられるよう配慮したものです。
INSネットの料金改定と企業への影響
加入電話の基本料金値上げに加えて、NTT西日本はISDN回線を使用した「INSネット」の回線使用料についても、2025年4月1日から改定すると発表しています。INSネットは主に企業や店舗でファックスやクレジット決済端末などに使用されてきましたが、こちらも利用減少と設備維持の問題に直面しています。
INSネットは1988年にサービスを開始したデジタル通信サービスで、一つの回線で2チャンネル分の通話が同時に可能という特徴から、企業のビジネスフォンやファックス専用回線として広く普及しました。しかし、インターネットの普及に伴い、企業の通信環境がIP化したことで、INSネットの必要性は大幅に低下しています。
企業にとって、固定電話の値上げは通信コストの増加要因となります。特に複数の固定回線を保有している企業では、月額費用の増加が無視できない規模になる可能性があります。事業用の固定電話料金が月額330円上がることは、10回線を保有している企業であれば月額3300円、年間では3万9600円のコスト増となります。
そのため、これを機にひかり電話などのより経済的なサービスへの切り替えを検討する企業が増えることが見込まれます。ひかり電話は基本料金が据え置かれるだけでなく、通話料金も従来の固定電話より安価に設定されているケースが多いため、トータルでの通信コスト削減効果が期待できます。
災害時・停電時における固定電話の役割と課題
固定電話の重要な特徴の一つとして、災害時や停電時の通信手段としての役割があります。メタル回線からIP電話への移行を検討する上で、この災害時の通信確保という観点は非常に重要な要素となっています。
従来型固定電話の災害時メリット
従来のアナログ回線による固定電話には、災害時において重要な利点がありました。メタル回線(銅線)には、電話局から約48ボルトの直流電圧が常時供給されており、この電力によって電話機を動作させることができます。そのため、家庭やオフィスが停電になった場合でも、電話回線自体が無事であれば、商用電源を使用しない電話機を使うことで通話が可能でした。
これは大規模災害時に非常に重要な機能で、東日本大震災などの過去の災害では、停電した地域でもメタル回線の固定電話で安否確認や救援要請ができたケースが多数報告されています。また、従来型の固定電話は物理的な回線で接続されているため、携帯電話網が混雑して通話制限がかかっている状況でも、比較的つながりやすいという特性がありました。
ただし、東日本大震災の際には、固定電話についてもNTT東日本で90パーセント、KDDIで90パーセント、ソフトバンクテレコムで80パーセントという高い割合で通信が制御されました。これは、災害時に安否確認の電話が集中し、通信網全体がパンクすることを防ぐための措置です。緊急通信を優先するため、一般の通話には制限がかけられます。
IP電話・光回線電話の災害時デメリットと対策
一方、光回線を使用した電話、ADSL回線を使用した電話、CATV回線を使用した電話などのIP電話サービスは、基本的に停電時には利用できなくなります。これらのサービスは、家庭内に設置されたモデムやONU(光回線終端装置)などの機器を経由して通信を行うため、これらの機器に電力供給がないと動作しないからです。
総務省は公式サイトで、停電時の固定電話サービスの利用について注意喚起を行っています。停電の際には、固定電話サービスについて、商用電源を使用しない電話機などを利用してアナログ電話を利用している場合を除き、基本的に利用できなくなることが明記されています。
ただし、光回線電話やIP電話にも停電時の対策が全くないわけではありません。多くのサービスプロバイダーは、停電時のバックアップ電源を提供しています。たとえば、ひかり電話の接続機器には、オプションでバッテリーバックアップユニットを接続できる機種があります。このバッテリーを接続しておくことで、停電時でも一定時間(通常8時間程度)は通話が可能になります。
また、ワイヤレス固定電話の端末には、充電式バッテリーが内蔵されているため、こちらも停電時に一定時間は使用可能です。ただし、これらはあくまで短期間の停電に対する対策であり、長期にわたる停電や、バッテリーの充電が不十分だった場合には十分に機能しない可能性があります。
災害時の代替通信手段の重要性
固定電話だけに頼るのではなく、災害時には複数の通信手段を確保しておくことが重要です。携帯電話やスマートフォンは、停電時でもバッテリーが残っている限り使用可能であり、モバイルバッテリーを常備しておくことで通信手段を確保できます。
また、災害時には携帯電話各社が公衆Wi-Fiスポットを無料開放したり、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板サービスを提供したりしています。さらに、SNSやインターネットメッセージングアプリ(LINE、X(旧Twitter)など)も、安否確認や情報共有の有効な手段となります。これらは音声通話に比べてデータ量が少ないため、通信網が混雑している状況でも比較的つながりやすいという利点があります。
自治体や地域によっては、災害時の情報伝達手段として防災無線や防災アプリを提供しているところもあります。こうした地域の防災システムを事前に確認し、活用方法を理解しておくことも重要です。
固定電話料金値上げへの対応策と今後の展望
固定電話料金の値上げは、まだメタル回線ベースの固定電話を使用している家庭や企業に直接的な影響を与えます。特に高齢者世帯や、長年同じ電話番号を使用してきた家庭では、サービスの変更に戸惑いを感じる可能性があります。
利用者が検討すべき選択肢
現在、従来型の加入電話を使用している利用者には、主に三つの選択肢があります。
第一の選択肢は、値上げ後も従来の加入電話を継続利用することです。月額220円から330円の負担増となりますが、使い慣れたサービスを継続できるという安心感があります。ただし、NTT東西は2035年度までにメタル回線の廃止を目指しているため、いずれは代替サービスへの移行が必要になります。
第二の選択肢は、光回線電話やワイヤレス固定電話への移行です。NTT東西が提供する初期費用無償化の措置を利用すれば、2万2880円の費用負担なしで移行できます。月額料金も据え置きとなるため、長期的には経済的な選択となります。光回線電話は音質が向上し、ひかり電話と組み合わせればインターネット接続も快適になるという追加メリットもあります。
第三の選択肢は、固定電話サービスの解約です。特に若年層の世帯では、携帯電話のみで生活することも十分可能です。固定電話を解約すれば、月額料金だけでなく、電話機の購入費用やメンテナンスの手間も不要になります。ただし、長年使用してきた固定電話番号を失うことになるため、連絡先の変更を周知する手間が発生します。
高齢者世帯への配慮とサポート体制
日本の固定電話利用者の多くは高齢者であり、新しい技術やサービスへの理解と適応に時間がかかる可能性があります。この課題に対して、NTT東西は専用のサポート窓口を設置し、丁寧な説明と手続き支援を提供する体制を整えています。
また、地域の自治体や社会福祉協議会とも連携し、高齢者が孤立することなく移行を完了できるよう、地域ぐるみでのサポート体制の構築も進められています。移行手続きが複雑で自力では難しいと感じる高齢者は、遠慮なくこれらのサポート窓口に相談することが推奨されます。
便乗詐欺への警戒
固定電話の移行に関連して、NTTや関連企業を装った詐欺が発生する可能性が指摘されています。不審な電話や訪問があった場合は、即座に応じず、NTTの正規の連絡先に確認することが重要です。正規のNTT担当者は、電話で金銭を要求したり、キャッシュカードや通帳の提示を求めたりすることはありません。
特に高齢者は詐欺のターゲットになりやすいため、家族や周囲の人々が注意を呼びかけることも大切です。固定電話の移行に関する連絡があった際は、一人で判断せず、家族や信頼できる人に相談することが望ましいです。
今後の展望
NTT東西による固定電話料金の値上げと設備更新は、2026年4月からスタートし、2035年頃までの長期的なプロセスとなります。この間、利用者は徐々に新しいサービス体系に適応していくことになります。
値上げ実施後も、NTT東西は従来の固定電話サービスを継続して提供しますが、長期的には光回線やモバイルネットワークを利用したサービスへの完全移行を目指しています。このため、まだメタル回線ベースの固定電話を使用している利用者は、早めに代替サービスへの移行を検討することが推奨されます。
固定電話の料金値上げは、日本の通信インフラが新たな時代に入ることを示す重要な転換点です。利用者、事業者双方にとって、この変化にどう対応していくかが今後の課題となるでしょう。統計データが示すように、固定電話の契約数と世帯保有率は今後も減少を続け、2035年頃にはさらに大幅な減少が見込まれます。
一方で、完全にゼロになることは考えにくく、ビジネス用途や特定の用途での需要は残り続けると予想されます。企業の代表番号、店舗の問い合わせ先、公共機関の連絡先などでは、引き続き固定電話番号が使用される可能性が高いためです。NTT東西の移行計画は、このような将来予測を踏まえて策定されており、残存する利用者に対しても十分な対応時間を確保するという配慮が見られます。
光回線やモバイルネットワークへの移行により、設備の維持コストを大幅に削減できると同時に、より効率的な運用が可能になります。また、デジタル化された通信インフラは、将来的な技術革新や新サービスの展開にも柔軟に対応できるという利点があります。この移行は日本の通信業界全体にとっても重要な転換点となり、通信業界全体のデジタル化とIP化がさらに加速することが期待されています。


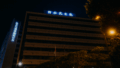
コメント