昨日2025年11月7日、日本の社会保障制度において歴史的な瞬間が訪れました。高市早苗首相が衆議院予算委員会で、2013年から2015年にかけて実施された生活保護基準引き下げについて、政府のトップとして初めて公式に謝罪したのです。この謝罪は、2025年6月27日に最高裁判所が生活保護基準引き下げを違法と判断してから4カ月以上が経過した後のことでした。生活保護制度は、日本国憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を実現するための最後のセーフティネットとして機能しています。今回の訴訟は「いのちのとりで裁判」と呼ばれ、全国29都道府県で1000人を超える原告が参加する大規模な集団訴訟となりました。最高裁が生活保護基準の引き下げを違法と判断したのは初めてのことであり、行政の裁量権にも限界があることを明確に示した歴史的な判決として、法律専門家からも高く評価されています。この問題は、単に生活保護受給者だけの問題ではなく、社会のセーフティネットをどう守り、すべての人が人間らしく生きられる社会をどう実現するかという、私たち全員に関わる重要な課題です。

高市首相による歴史的な謝罪の内容と背景
昨日の衆議院予算委員会において、高市早苗首相は立憲民主党の長妻昭議員の質問に答える形で、「厚生労働大臣の判断の過程・手続に誤り・欠落があったと指摘されました。深く反省し、おわびを申し上げます」と明確に述べました。この謝罪は、生活保護基準引き下げ問題について、政府トップが公式に謝罪した初めてのケースとなり、社会保障行政における大きな転換点として記録されることになります。
最高裁判決が出てから4カ月以上が経過してからの謝罪となった背景には、厚生労働省内での対応の遅れと、補償問題をめぐる複雑な事情がありました。6月の最高裁判決後も、厚生労働省からは謝罪の言葉がなく、省の職員は「判決を精査して適切に対応する」と繰り返すのみで、原告側は強い不満を表明していました。原告たちは繰り返し謝罪と全額補償を求めてきましたが、政府の反応は鈍く、原告や支援者たちは9月には専門委員会への追加の意見陳述機会を求める要請書を提出し、8月には専門委員会の強引な設置に抗議する声明を発表するなど、粘り強く声を上げ続けてきました。
高市首相の謝罪は、こうした原告たちの長年にわたる闘いと、最高裁による厳しい違法判断を受けての重要な一歩です。しかし、謝罪だけでは十分ではなく、違法な引き下げによって困窮を強いられた受給者への適切な補償と、二度と同じ過ちを繰り返さないための制度改革が求められています。
最高裁判決が示した画期的な判断枠組み
2025年6月27日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、生活保護基準引き下げを違法とする初の統一判断を示しました。この判決は裁判官5人中4人の多数意見で原告勝訴が確定し、日本の社会保障法制史において極めて重要な位置を占めることになりました。
最高裁が特に重視したのは、違法性の判断について「統計などの客観的な数値との合理的な関連性、専門的知見との整合性の有無を審査するべきだ」とする新たな判断枠組みでした。この枠組みは、従来の判例で認められていた行政の広範な裁量権に対して、一定の歯止めをかける重要な意味を持ちます。過去の朝日訴訟や堀木訴訟では、最高裁は健康で文化的な最低限度の生活の概念は抽象的で相対的であり、厚生大臣の裁量に委ねられているとの判断を示していましたが、今回の判決はその流れを受けつつも、行政の裁量権が無制限ではないことを明確にしました。
特に厳しく批判されたのが「デフレ調整」に関する判断です。判決文には「物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法というべき」という厳しい指摘が含まれています。最高裁は、物価について「飽くまで消費と関連付けられる諸要素の一つにすぎず、物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものとはいえない」として、物価下落を理由に生活保護費を機械的に引き下げることの問題性を明確に指摘しました。
さらに重要なのは、このデフレ調整が専門家の審議会に諮られることなく実施された点が違法と判断されたことです。最高裁は、デフレ調整が「専門的知見に裏付けられた合理性を欠く」として違法と断じ、専門的知見を軽視した行政判断の危険性を警告しました。この判断は、今後の行政訴訟全般に影響を与える可能性があり、行政が重要な政策決定を行う際には、客観的なデータと専門的知見に基づくことが一層求められることになります。
日本弁護士連合会も判決を受けて声明を発表し、最高裁が専門的知見の重要性を強調し、厚生労働大臣の判断を違法と断じたことは極めて重要であると評価しました。全国32件の同種訴訟のうち、半数以上にあたる18件の判決で生活保護基準の引き下げが違法と判断されており、司法が生存権保障に対して厳格な姿勢を示している傾向が明確になっています。
生活保護基準引き下げの実態と影響
2013年から2015年にかけて、厚生労働省は生活保護費のうち食費や光熱水費などの「生活扶助」の基準を平均6.5パーセント引き下げ、670億円を削減しました。この削減は、デフレ調整とゆがみ調整を併せて行ったもので、一部の世帯では最大10パーセントの削減となり、受給者の生活に深刻な影響を与えました。
この引き下げの直接的なきっかけは、2012年に野党だった自民党が選挙公約に生活保護基準の10パーセント引き下げを掲げ、実際に政権を獲得したことにあります。2012年春には、人気お笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことをめぐり、いわゆる生活保護バッシングが社会問題化し、このバッシングを主導したのは、当時自民党の生活保護プロジェクトチーム座長だった世耕弘成氏や片山さつき氏らでした。同年12月の衆議院総選挙で、野党だった自民党は生活保護費の10パーセント削減を公約に掲げて大勝し、政権に復帰すると、まるで選挙公約に合わせるかのように引き下げが決定されました。
一部の報道では、政治的な圧力が厚生労働省の判断に影響を与えた可能性も指摘されています。専門家の審議を経ずにデフレ調整が導入された背景には、自民党政権への忖度があったのではないかという指摘もあり、財政再建や社会保障費抑制の流れの中で、生活保護費は格好の削減対象とされました。今回の最高裁判決は、そうした政治的な思惑が専門的知見を軽視し、違法な行政判断につながったことを明確に示したものとして、政治的な圧力によって福祉政策が歪められることへの警鐘とも受け取ることができます。
東京の女性原告は訴訟の中で、引き下げによる生活困窮の実態を次のように訴えています。「今年は人生で一番つらかった。お米がない、電気代がとても高い。電気を止められて、春までとても寒くて、今も体調が悪い。厚生労働省にはこういうことをちゃんと考えてほしい」この証言は、生活保護基準の引き下げが単なる数字の問題ではなく、実際の人々の生命と尊厳に関わる深刻な問題であることを示しています。
引き下げによって、食費を切り詰めたり、必要な医療を受けることを躊躇したり、冷暖房の使用を我慢したりする受給者が続出しました。実際の調査によれば、生活保護を受給している人の中で67.2パーセントが経済的理由で食事をあきらめた経験があり、36.8パーセントが過度な光熱費削減により健康被害を受け、34.8パーセントが病院受診をあきらめているという深刻な実態があります。生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度であるにもかかわらず、引き下げによってその最低限度すら維持できなくなった受給者が多数存在したのです。
さらに悲しいことに、訴訟の長期化により、判決を聞くことなく亡くなった原告も少なくありません。2014年以降、全国で最大1027人の原告が訴訟を提起しましたが、裁判が10年以上にわたったため、232人以上、つまり原告の20パーセント以上が勝訴判決を聞くことなく既に亡くなっています。これらの原告たちは、生前、自らの尊厳と権利のために声を上げ続けました。その声が最高裁によって認められたことは、亡くなった原告たちの思いを受け継ぐ意味でも重要です。
厚生労働省の対応と補償問題の行方
昨日11月7日、厚生労働省は社会保障審議会生活保護基準部会の専門委員会を開催し、最高裁判決への対応を協議しました。この会議は第8回目の開催となり、違法と判断された引き下げ分についての補償方針が議論されました。
厚生労働省は、全額補償ではなく一部補償とする方針を示しています。省側は、当時の一般低所得世帯の消費実態を考慮すると、全額補償は困難だと判断しました。また、訴訟を起こしていない受給者も補償の対象とする方針も示されましたが、この一部補償案については、原告側から強い反発が出ています。
受給者側は、2013年以降の減額決定の影響で受領できなかった金額の規模は、2017年度までに最大3000億円に上るとみており、判決後に国に適正な支払いと検証を求めています。立命館大学の桜井啓太准教授の試算によれば、減額分の差額を遡及して支払う総額は4000億円を超えるとされています。これは原告だけでなく、すべての受給者、当時約200万人以上に支払う必要があるためです。この巨額の補償問題が、政府が全額補償を躊躇する一因となっている可能性があります。
厚生労働省が全額補償を見送る方針を固めたことが報道されると、原告や支援者、弁護団などで構成される「いのちのとりで裁判全国アクション」は、昨日、東京・霞が関の厚生労働省前で抗議活動を行いました。参加者たちは「生活保護利用者の声を聞け」「また引き下げか」などと声を上げ、厚生労働省の対応を批判しました。原告たちは、最高裁が10年以上にわたる違法行為を認定したにもかかわらず、適切な補償がなされないことに強い不満を表明しています。
一方で、物価高騰に対応するため、厚生労働省は2025年度から生活扶助の特例加算を月額500円引き上げ、1人あたり月額1500円とすることを決定しています。この特例加算は2023年度から2年間実施されていた月額1000円の加算を延長・増額するものですが、この増額は物価高騰への対応であり、違法と判断された2013年から2015年の引き下げの補償とは別の措置である点に注意が必要です。
生活保護削減の長い歴史と構造的問題
2013年から2015年の引き下げは、生活保護削減の歴史の中でも特に大規模なものでしたが、実は生活保護費の削減はそれ以前から繰り返し行われてきました。この削減の歴史を知ることは、今回の問題の深刻さを理解する上で重要です。
2004年からは老齢加算の段階的廃止が始まりました。老齢加算は、1960年に70歳以上の受給者の加齢に伴う特別な生活需要に応えるために創設されたものでしたが、2004年から段階的に廃止され、2006年に完全廃止されました。その結果、高齢者世帯の生活扶助は約20パーセント減額され、多くの高齢受給者が困窮に陥りました。
また、母子加算も2005年から段階的に廃止され、2009年には完全廃止されました。母子加算は、一般の母子世帯との公平性の観点から廃止されたとされましたが、子どもの貧困対策の必要性から、2009年12月に復活しました。廃止前の月額23260円(都市部)の母子加算が完全廃止された際には、約10万世帯の母子家庭、約18万人の子どもが影響を受けました。
このように、老齢加算の廃止が始まった2004年から、20年にわたって断続的に削減が行われてきました。2013年からの引き下げは、こうした削減の歴史の延長線上にあるものであり、生活保護制度が長期にわたって縮小傾向にあることを示しています。
さらに深刻なのは、生活保護制度が抱える構造的問題です。「水際作戦」と呼ばれる問題があります。これは、福祉事務所の窓口で、生活困窮者が生活保護を申請することを阻止しようとする違法な対応です。法律上、困窮している人は誰でも生活保護を申請する権利があるにもかかわらず、窓口で追い返される事例が後を絶ちません。2021年の統計では、生活保護の相談に訪れた人のうち、実際に申請に至るのは約31.4パーセントに過ぎず、約70パーセントの人が申請に至っていないという驚くべき実態があります。
この背景には、自治体が生活保護費の4分の1を負担することによる財政圧力や、ケースワーカーの人手不足があります。主要都市の約70パーセントが、標準とされる「ケースワーカー1人あたり80世帯」という基準を満たしておらず、実際には一人のケースワーカーが約120世帯を担当しており、過重な負担となっています。
北九州市では、2005年から2007年にかけて、3年連続で餓死事件が発生しました。市が月あたりの申請件数に上限を設けるなどの水際作戦を行った結果でした。また、群馬県桐生市でも、窓口で申請書を渡さないなどの不適切な対応が複数発覚しています。これらの事例は、水際作戦が単なる不適切な対応ではなく、人命に関わる深刻な問題であることを示しています。
もう一つの大きな問題が「扶養照会」です。これは、生活保護を申請した人の親族に対して、扶養の可能性を問い合わせる制度ですが、この制度が生活保護の申請を妨げる大きな障壁となっています。つくろい東京ファンドの調査によれば、生活保護を利用しない理由として「家族に知られたくない」を挙げた人が34.4パーセントに上り、受給者の54.2パーセントが扶養照会に抵抗感を持っています。
しかも、この扶養照会の実効性は極めて低いことが明らかになっています。足立区の2019年のデータでは、実際に扶養につながったケースはわずか0.3パーセント、荒川区の2018年から2019年のデータでは0パーセントでした。つまり、多くの人が申請を躊躇する原因となっているにもかかわらず、実際の効果はほとんどないのです。
この問題に対しては、廃止を求める運動が展開され、本人の同意のない扶養照会は行わないことを求めるオンライン署名が短期間で約5万8000筆集まりました。その結果、2021年3月30日、厚生労働省は画期的な事務連絡を発出し、本人が希望しない場合は扶養照会を止めることができるとの方針を示しました。しかし、支援団体は前近代的な制度の完全廃止を求めて活動を続けています。
日本の生活保護制度の国際的な課題
日本の生活保護制度の大きな問題として、極めて低い「捕捉率」があります。捕捉率とは、生活保護を受給する資格がある人のうち、実際に受給している人の割合を指します。日本の捕捉率は推計で約20から40パーセント、研究によっては10.8パーセントという低い数値も示されています。つまり、本来受給資格がある人の60から80パーセントが生活保護を受けていないということになります。
これに対して、諸外国の捕捉率は非常に高い水準にあります。スウェーデン、イギリス、フランスはいずれも約90パーセント、ドイツは100パーセント、アメリカは76.7パーセント、韓国は23.2パーセントとなっています。G7諸国の中で、日本は貧困率が2番目に高いにもかかわらず、生活保護の利用率と捕捉率は最も低いという極めて深刻な状況にあります。
この極めて低い捕捉率は、制度の機能不全を示しています。本来助けを必要としている人々が制度から取り残されているのです。捕捉率の推計では、受給資格のある世帯のうち実際に受給しているのはわずか15.3から18パーセントという試算もあり、これは制度が社会のセーフティネットとして機能していないことを示す重大な数字です。
韓国では2014年に福祉の死角地帯をなくす法律を制定し、受給資格のある人を見つけ出す大規模なキャンペーンを展開しました。地下鉄に申請を促す広告を掲載するなど、積極的な取り組みを行っています。また、韓国では単給制度を導入し、住宅扶助や医療扶助だけを単独で受給できるようにするなど、利用しやすい制度設計を進めています。日本もこうした諸外国の取り組みから学ぶべき点が多くあります。
さらに、生活保護に対する「スティグマ」(社会的烙印)の問題も深刻です。国連の社会権規約委員会は、日本に対して、スティグマが生活保護の申請を妨げていることを指摘し、申請手続きの簡素化と市民教育によるスティグマの撤廃を勧告しています。生活保護に対する多くの誤解や偏見があり、それがスティグマを生み、制度利用を妨げています。
生活保護を受けていることについて、友人や家族に伝えているのは41.5パーセントに過ぎず、26.5パーセントは誰にも言えずにいます。「他人の税金で食べさせてもらっている」という罪悪感を持ち、ひっそりと暮らそうとする受給者も少なくありません。メディア報道が生活保護受給者への偏見や差別を助長し、真に必要な人々の生存を脅かしているという指摘もあります。
福祉事務所の職員自身が、申請者を潜在的な不正受給者や犯罪者のように見なし、利用者に対して差別的な視線を向けることもあります。申請の障壁を乗り越えてようやくたどり着いた受給者に対して、職員から「税金で生活しているんだ」と繰り返し言われ、わずかな収入しかないのに生活保護をやめてしまうケースもあるのです。
不正受給に関する誤解と実態
生活保護に対する誤解として、不正受給が多いという認識が広まっていますが、実態は大きく異なります。2010年のデータでは、不正受給は2万5355件で全体の1.8パーセント、金額は128億7000万円で総費用の0.38パーセントでした。より最近のデータでは、不正受給は約164万世帯中約4万件(約2.4パーセント)、2022年の不正受給額は約106億円で、総額2兆7900億円の生活保護費の0.4パーセント未満に過ぎません。
しかも、「不正受給」とされるケースの多くは、悪質な詐欺ではありません。約61パーセントが稼働収入の無申告または過少申告であり、多くの人が高校生の子どものアルバイト収入などを申告する必要があることを理解していなかったというケースです。収入申告のルールを理解する能力に欠けている人も少なくなく、悪意のない誤りが「不正受給」としてカウントされている実態があります。
実際の不正受給のデータは、件数で約2パーセント、金額で0.4パーセント程度と限られた部分に留まっているにもかかわらず、メディアが不正受給を強調して報道し、SNSでの批判的なコメントが広がることで、本当に支援が必要な人までもが生活保護を利用することを躊躇する社会的雰囲気が作られています。
また、「不正受給」とされたケースの中には、申請時に行政が適切な資産調査を行わなかったことに起因するものもあります。つまり、行政側の不備が原因であるにもかかわらず、受給者が非難されるという不合理な状況も存在します。こうした誤解が、生活保護制度全体に対する不信感や受給者への偏見を助長し、本来制度を利用すべき人々が申請を躊躇する大きな要因となっています。
憲法第25条が保障する生存権の意義
生活保護制度は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するための最後のセーフティネットです。憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、同条第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務を明記しています。
この生存権の具体的な内容については、過去にも重要な判例があります。朝日訴訟(1967年最高裁判決)では、最高裁は憲法25条1項は国が国政を運営するにあたり配慮すべき責務を負うことを宣言したものであるが、個々の国民に対して具体的権利を直接付与したものではないとし、また健康で文化的な最低限度の生活の判断は、厚生大臣の裁量に委ねられているとの判断を示しました。
堀木訴訟(1982年最高裁判決)でも、最高裁は憲法25条における健康で文化的な最低限度の生活の概念は極めて抽象的・相対的であり、立法による実現を要するものとし、立法措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合に限り、司法審査が可能であるとの判断枠組みを示しました。
しかし、今回の最高裁判決は、これらの過去の判例の流れを受けつつも、行政の裁量権に一定の歯止めをかける重要な判断を示しました。統計などの客観的な数値との合理的な関連性、専門的知見との整合性を重視する新たな判断枠組みは、行政の裁量権が無制限ではないことを明確にしました。
また、近年の下級審判決でも注目すべき動きがあります。2023年11月30日の名古屋高等裁判所判決では、生活保護基準引き下げの取消だけでなく、国に対する損害賠償も命じられました。判決は、受給者が長期間にわたり生活扶助の引き下げにより一層逼迫した生活を強いられたと指摘しています。全国32件の同種訴訟のうち、半数以上にあたる18件の判決で生活保護基準の引き下げが違法と判断されており、司法が生存権保障に対して厳格な姿勢を示している傾向が見られます。
いのちのとりで裁判の歴史的意義
「いのちのとりで裁判」は、全国29都道府県で展開され、1000人を超える原告が参加する大規模な集団訴訟となりました。最高裁が生活保護基準の引き下げを違法と判断したのは初めてのことであり、歴史的な判決となりました。この判決は、行政の裁量権にも限界があることを明確に示したものとして、法律専門家からも高く評価されています。
原告の一人は「私たちは人間らしく生きたいだけです」と訴えています。最低限度の生活を保障することは、社会の基盤であり、そのための制度が適切に運用されることは極めて重要です。原告たちは「だまってへんで、これからも」と声を上げ続けており、最高裁判決を真摯に受け止め、生活保護制度が本来の役割を果たせるよう、政府の誠実な対応が求められています。
この訴訟の背景には、憲法第25条で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が侵害されたという原告たちの切実な思いがあります。引き下げによって、食費を切り詰め、必要な医療を受けることを躊躇し、冷暖房の使用を我慢する生活を強いられた受給者たちが、自らの尊厳と権利のために声を上げ続けた結果が、この歴史的な判決につながりました。
今後の課題と制度改革への道筋
最高裁判決から4カ月以上が経過した昨日になって、ようやく高市首相が謝罪したものの、具体的な補償の内容については依然として原告側と政府側の間に大きな隔たりがあります。原告側は全額補償を求めているのに対し、厚生労働省は一部補償の方針を示しています。この点について、今後どのような形で決着がつけられるのかが注目されています。
また、訴訟を起こしていない受給者への補償をどのように行うのか、その具体的な手続きや金額についても、今後詰めていく必要があります。当時の受給者は約200万人以上に上るため、すべての該当者に適切に補償を行うためには、複雑な手続きと大規模な作業が必要となります。
さらに重要なのは、生活保護基準の決定プロセスそのものを見直し、今回のような違法な引き下げが二度と起こらないようにするための制度改革です。専門家による審議を経ずに重要な決定が行われたことが違法と判断された以上、今後は専門的知見を十分に尊重した基準設定が必要となります。最高裁が示した「統計などの客観的な数値との合理的な関連性、専門的知見との整合性の有無を審査するべきだ」という判断枠組みを、実際の行政運営に反映させることが求められます。
水際作戦や扶養照会といった構造的問題の解決も不可欠です。生活保護制度が真に最後のセーフティネットとして機能するためには、制度の抜本的な見直しと、受給者の尊厳を守る運用が必要です。ケースワーカーの人員を増やし、一人あたりの担当世帯数を適正化することも急務です。
捕捉率の低さという問題に対しては、韓国のような積極的な広報活動や、申請手続きの簡素化、単給制度の導入などが考えられます。本来助けを必要としている人々が制度を利用できるよう、制度設計そのものを見直す必要があります。
スティグマの解消については、市民教育を通じて生活保護制度の正しい理解を広めることが重要です。生活保護は憲法で保障された権利であり、誰もが生活困窮に陥る可能性がある以上、制度の充実は社会全体の安心と安定につながるという認識を社会で共有することが必要です。
今回の最高裁判決と高市首相の謝罪は、日本の社会保障制度のあり方を問い直す重要な契機となりました。しかし、判決が出て政府が謝罪したからといって、問題がすべて解決したわけではありません。むしろ、これからが本当の意味での改革の始まりです。
社会全体で考えるべき生活保護制度の未来
この問題は、単に生活保護受給者だけの問題ではありません。社会のセーフティネットをどう守り、すべての人が人間らしく生きられる社会をどう実現するかという、私たち全員に関わる重要な課題です。誰もが生活困窮に陥る可能性がある以上、生活保護制度の充実は、社会全体の安心と安定につながります。
生活保護制度は、日本の社会保障制度全体の一部です。貧困や格差の問題に根本的に対処するためには、生活保護制度の改善だけでなく、雇用政策、住宅政策、教育政策、医療政策など、総合的な取り組みが必要です。最低賃金の引き上げや、非正規雇用の待遇改善、手ごろな価格の住宅供給、教育の機会均等、医療へのアクセス改善など、さまざまな施策を連携させることで、そもそも生活困窮に陥る人を減らすとともに、困窮した際に適切に支援を受けられる体制を整えることが重要です。
「いのちのとりで裁判」の原告たちが声を上げ続け、10年以上にわたって闘い続けた結果、ようやく最高裁が違法判断を示し、政府が謝罪するに至りました。この歴史的な成果を一過性のものとせず、真の制度改革につなげていくことが、今後の課題です。原告たちの勇気ある行動と粘り強い闘いは、社会保障制度の改善という形で、社会全体に貢献することになります。
すべての人が尊厳を持って生きられる社会、困ったときに必要な支援を受けられる社会を実現するために、私たち一人ひとりが生活保護制度について正しく理解し、偏見をなくし、制度の改善を求めていくことが重要です。生活保護を利用することは恥ずかしいことではなく、憲法で保障された正当な権利であるという認識を社会で共有することが、制度改善の第一歩となります。
今回の高市首相の謝罪は重要な一歩ですが、それはあくまでも始まりに過ぎません。具体的な補償の実現、制度改革の実行、そして社会全体の意識改革という、より大きな課題が私たちの前に横たわっています。この課題に真摯に向き合い、一歩ずつ前進していくことが、憲法が保障する生存権を実現し、誰もが安心して暮らせる社会を築くために不可欠なのです。
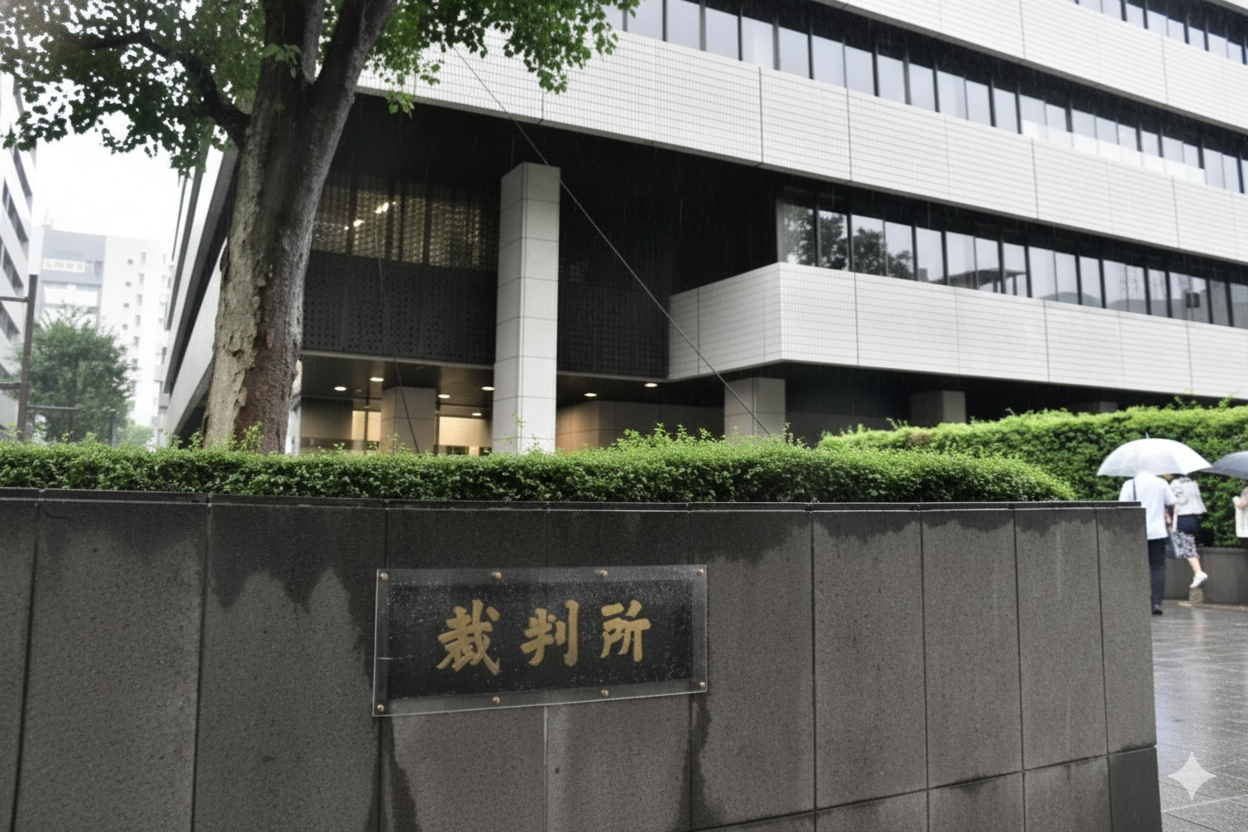


コメント