生活保護を受給している方、またはこれから申請を検討している方にとって、ケースワーカーとの相談内容がどのように記録され、どれくらいの期間保存されるのかは非常に重要な関心事です。面談時に話した内容が詳細に記録され、その記録が長期間にわたって保存されることで、将来の支援内容や生活保護費の支給額に影響を与える可能性があります。2025年現在、生活保護制度における記録管理はデジタル化が進み、より効率的な情報管理が実現される一方で、個人情報保護やプライバシーへの配慮も一層求められています。本記事では、ケースワーカーが作成する記録の具体的な内容、法的根拠に基づく保存期間、記録の開示請求方法、そして不正受給調査における記録の役割まで、生活保護における相談内容と記録の残存について包括的に解説します。これから生活保護を申請する方も、すでに受給中の方も、記録がどのように管理され活用されているかを正しく理解することで、より適切にケースワーカーと向き合うことができるでしょう。

ケースワーカーの役割と相談業務の実態
生活保護制度において、ケースワーカーは受給者と制度を繋ぐ重要な役割を担っています。彼らは福祉事務所に配置される専門職員であり、生活保護受給者の生活状況や健康状態、家族関係などを把握し、個々のケースに応じた支援を提供することが主な業務です。
厚生労働省の定める基準によれば、生活保護ケースワーカーは都市部では80世帯に1人、郡部では65世帯に1人という配置基準が設けられています。しかし実際には、この基準を超える世帯数を担当しているケースワーカーが多く、業務負荷の高さが深刻な課題となっています。
ケースワーカーの業務は多岐にわたります。生活保護費の1円単位での計算と支給処理、相談援助業務に関するケース記録の作成、国や都道府県からの調査報告への対応、受給者の戸籍や金融機関への照会、生活状況の確認など、複数の業務を同時並行で進めなければなりません。この中でも、受給者との面談内容を記録する業務は、適切な支援の継続と制度の適正運営のために欠かせない重要な作業となっています。
厚生労働省により、家庭訪問は少なくとも年2回以上実施することが義務付けられており、実際には年間2回から4回程度の訪問が行われています。訪問頻度は受給者の状況によって異なり、指導を聞いて真面目に自立を目指す受給者の場合は訪問回数が少なく、指導をあまり聞かない受給者に対しては訪問頻度が高く設定される傾向があります。これらの訪問時に行われる面談では、受給者の生活状況について詳細な聞き取りが実施され、その内容はすべて記録として残されます。
相談内容の記録対象と具体的な質問事項
ケースワーカーとの面談では、生活保護制度の適正な運用と受給者への適切な支援を目的として、詳細な質問が行われます。これらの質問内容と回答は、すべて記録として残され、長期間保存されることになります。
初回申請時の質問内容
生活保護の申請時には、家庭環境や生活保護を申請するに至った経緯を詳細に説明する必要があります。具体的には、現在の生活状況と困窮の理由、家族構成と世帯の状況、収入・資産の有無と詳細、働く能力の有無と就労の可能性、他の社会保障制度の利用状況などが質問されます。
これらの質問に対する回答は、生活保護の受給可否を判断する重要な材料となるため、申請書類とともに詳細に記録され、長期間保存されることになります。初回面談での記録は、その後の支援方針を決定する基礎資料となるため、特に重要な意味を持つ記録として扱われます。
定期訪問での質問内容
定期的な家庭訪問では、最近の生活状況に大きな変化はないかという基本的な確認から始まり、様々な側面について質問が行われます。
健康状態については、通院状況の確認、処方薬の服薬状況、体調の変化について詳しく聞かれます。医療機関への通院に必要な交通費や、診療科の追加など、医療関係の変更事項は特に詳細に記録されます。
生活状況については、住居の状態、部屋が汚れていて健康を害する可能性はないか、新たに購入した家具や家電がある場合はその購入方法などが確認されます。また、アパートの契約更新料など一時的な費用についての相談も記録対象となります。
収入・支出については、就労による収入、年金や各種手当などの収入について報告が求められ、これらの情報は生活保護費の支給額決定に直接影響するため、特に詳細に記録されます。働いて給与がある人や、年金・手当などの収入がある人には、生活保護費の支給決定に必要な収入申告が必須となります。
家族関係についても、親族との交流状況、扶養義務者との関係、家庭内の問題などが聞き取られ、記録として残されます。親族との関係性の変化は、将来的な扶養の可能性を判断する材料となるため、詳細に記録される傾向があります。
就労状況については、求職活動の進捗状況、就労の可能性、自立に向けた取り組みの進展などが質問され、自立支援プログラムの策定や見直しに活用されます。
ケース記録の作成と管理システム
ケースワーカーは、面談や相談の内容をケース記録として作成することが法律で義務付けられています。これらの記録は、生活保護法に基づく重要な行政文書として扱われ、受給者一人ひとりのケースファイルとして厳格に管理されています。
記録の作成にあたっては、相談内容だけでなく、ケースワーカー自身の判断や今後の支援方針、関係機関との連携状況なども含まれます。面談時には受給者の回答を詳細にメモに取り、後日それをケース記録として正式に文書化します。この記録には、質問内容だけでなく、受給者の表情や態度、住居の状況、周辺環境なども含まれることがあります。
生活保護に関する記録は、国や都道府県からの調査報告、戸籍や金融機関への照会結果、生活状況確認の結果なども含む包括的な内容となっており、受給者の生活全般にわたる詳細な情報が蓄積されています。これらの包括的な記録により、受給者の状況を多角的に把握し、より適切な支援を提供することが可能となっています。
デジタル化の進展と情報管理システム
2025年現在、生活保護業務においてもデジタル化が大きく進展しており、従来の紙ベースの記録管理から電子的な情報管理システムへの移行が進んでいます。
NTTデータ関西が2023年1月から提供を開始したケースワーカー支援システム「さぽとも」では、生活保護ケースワーカーが受給申請者へ訪問調査する際の業務をデジタル化し、業務負担の軽減とノウハウの共有を実現しています。このシステムでは、ケース記録ごとの査察指導員からの指導内容やノウハウをWEB上で記載し、訪問時に現地でタブレットに表示させることができます。また、多岐にわたる法制度など業務に必要なマニュアルなどのドキュメントをシステム内に集約でき、膨大なファイルの中身をキーワードで検索し、必要な情報を簡単に参照することができます。
総合福祉システム「あゆむくん」では、ケース記録や相談管理をシステム上で実施し、情報を一元管理しているため、相談内容や手帳情報、福祉サービス等のサービス利用状況をすぐに把握することができます。このようなシステム化により、ケースワーカー間の情報共有が効率化され、より一貫した支援の提供が可能になっています。
電子化により、過去の記録の参照が容易になり、より継続性のある支援が可能になっています。しかし、電子化に伴うセキュリティ対策や、システムの安定性確保、災害時のデータ保護なども重要な課題となっており、これらへの対応が継続的に求められています。
記録の法的根拠と保存期間
生活保護に関する記録の保存については、公文書管理法および生活保護法関係文書の保存期間に関する厚生労働省通知により詳細に規定されています。
昭和36年9月29日付け社発第726号により、生活保護法関係文書の保存期間が定められており、文書の重要度に応じて永久保存、10年、5年、3年、1年の区分で保存されています。ケース記録については、その重要性から比較的長期間の保存が義務付けられており、受給期間中はもちろん、受給終了後も一定期間は保存され続けます。
公文書管理法第5条では、行政職員が行政文書を作成または取得した際、行政機関の長が規則に従って分類、名称、保存期間、満了日を設定することが定められています。第7条では行政文書ファイル管理簿の作成が義務付けられ、文書の分類、名称、保存期間、満了日、移管・廃棄の区分、保存場所が記録され、一般の閲覧に供されオンラインで公表されています。
この法的枠組みにより、生活保護に関する記録は適切に管理され、必要な期間保存されることが保証されています。同時に、保存期間が満了した記録については、個人情報を含む機微な内容であることを考慮し、原則として焼却処分されることとされています。これは、記録に含まれる個人情報の漏洩防止と、プライバシー保護の観点から重要な措置となっています。
記録の利用目的と情報開示制度
生活保護に関する記録は、適切な保護の実施、不正受給の防止、受給者の自立支援などの目的で活用されています。また、これらの記録は情報公開請求の対象となる可能性があり、個人情報保護法の規定に従って、本人や正当な利害関係者による開示請求が認められる場合があります。
ケース記録の開示請求制度
平成17年4月1日から個人情報保護法が施行され、従来は「要保護者といえども閲覧請求の権利をもつものではない」とされていた状況が変更され、各地方公共団体の個人情報保護条例に基づく開示請求が可能になりました。
開示請求の対象となる文書には、ケース診断会議記録、面接記録票、保護台帳、保護決定調書、生活指導記録票、ケース記録票、受付簿、保護申請処理簿、保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書などがあります。これらの記録を開示請求することで、自分に関する記録の内容を確認することができます。
しかし、実施機関は以下の理由により部分開示や非開示の決定を行う場合があります。開示請求者以外の特定の個人を識別することができる部分、戸籍謄本及び附票並びに住民票、生活保護法第29条照会に係る金融機関からの回答書、関係機関との協議の内容、援助方針に係る部分などについて、個人情報保護条例の各号に該当することを理由として部分開示決定が行われることがあります。
審議会の判断では、実際に非開示部分を見分し、異議申立人を本人とする保有個人情報に該当しないもの、条例第19条第2号に該当し開示制限が適当なもの、逆に開示すべきものなどを個別に判断しています。このプロセスにより、個人情報保護と情報開示のバランスが図られています。
ただし、記録には他の受給者や関係者の個人情報、調査手法に関する情報なども含まれているため、開示にあたっては個人情報保護の観点から慎重な検討が行われます。
プライバシー保護と訪問調査の実態
生活保護受給者のプライバシー保護は、制度運営における重要な課題となっています。ケースワーカーによる調査や記録作成は、受給者の生活に深く関わる内容を含むため、必要最小限の範囲で行われることが求められています。
訪問調査における記録と課題
生活保護法第29条に基づく訪問調査は、受給者の生活実態を把握するために実施される重要な調査です。ケースワーカーは受給者の状況に応じて訪問頻度をランク付けしており、これらの判断基準や訪問時の対応についても詳細に記録が残されます。
訪問調査では、住居の状況、家族構成や同居人の有無、健康状態などが確認され、部屋が汚れていて健康を害する可能性はないか、服薬が正しく行われているかなどの詳細な生活状況がチェックされ記録されます。
プライバシー侵害の具体例としては、必要以上にプライベートなことを詮索される、生活保護に直接関係のない交友関係、恋愛、家族の個人的な事情について執拗に聞かれる、訪問時に他の住人に生活保護受給者であることを知られる、大きな声で「生活保護の件で来ました」と言われるなどのケースが報告されています。これらの問題についても、ケースワーカーは記録として残すことがあります。
しかし、適切な保護の実施と不正受給の防止のため、一定程度の調査と記録作成は避けられないのが現状です。このバランスを取ることは、生活保護制度運営上の重要な課題となっています。また、家主からの苦情や近隣トラブルに関する情報がケースワーカーに寄せられることも多く、これらの情報の取り扱いについても慎重な配慮が求められています。
訪問の拒否と受給者の権利
生活保護の家庭訪問は年2回以上の実施が義務付けられているため、原則として拒否することはできません。ケースワーカーには生活保護法第28条に基づく「立入調査権」があり、正当な理由なく訪問を拒否し続けていると、生活保護を廃止することも法律上は可能とされています。
ただし、法律上は「必要な調査」とあるだけで、「必ず家庭訪問でなければならない」とは明記されていないため、合理的な理由がある場合には、訪問以外の方法で生活状況を確認してもらう交渉の余地があります。
受給者の対処法として、「前回の訪問時に不適切な発言があったため、今回から録音させていただきます」と伝えることで、ケースワーカーの態度が変わることが多いとされています。このような対応についても、ケースワーカーは記録として残すことがあります。録音の申し出自体は違法ではなく、受給者の権利を守るための正当な手段として認められています。
不正受給調査における記録の重要性
生活保護制度の適正な運営のため、ケースワーカーによる不正受給の調査と記録作成は重要な業務の一つとなっています。2025年現在の調査体制と記録管理について見ていきます。
ケースワーカーによる不正受給の発見方法
ケースワーカーによる主な調査方法として、定期的な自宅訪問があります。定期訪問の目的は、自立した生活に向けた生活状況の調査や受給者とのコミュニケーションです。同時に、申告していない同居人がいないか、収入・資産がないかなどもチェックされ、これらの確認事項はすべて詳細に記録されます。
生活保護の申請後、実際にケースワーカーが自宅に伺い申請者の生活環境の調査を行います。主な目的としては申請者とのコミュニケーションを取ることと、家の中に現金や高価なものがないかの確認になります。この際の発見事項や疑問点も記録として残され、今後の調査の参考資料となります。
ケースワーカーの生活調査や定期訪問、課税調査によって発覚するケースが多く報告されています。ケースワーカーは原則自宅を訪問するため、生活保護受給者とは思えないほど裕福な生活をしている場合などは、不正受給を疑って調査を行い、その過程と結果を詳細に記録します。
働いているにも関わらず申告しなかった場合は、税金関連で発覚するケースが多く見られます。勤務先が適切に税務申告を行っている場合、収入等が判明するため、不正受給が発覚します。これらの発覚経緯についても、ケース記録として詳細に記載されます。
不正受給調査の統計と現状
厚生労働省の統計によると、不正受給は生活保護全体の0.4%未満となっています。その多くは悪質なものではなく、収入の申告漏れや手続き上のミスに過ぎませんが、これらすべてのケースについて詳細な調査記録が作成され保存されています。
2011年から2020年にかけて不正受給の件数は減っているものの、年間の不正受給件数は3万件以上となっています。中でも収入を申告しないことによる不正受給が全体の半数ほどを占めており、これらのケースについてはケースワーカーの記録が発覚の重要な要因となっています。
DXやAIの活用により、調査業務の効率化と精度向上が図られています。これにより、ケースワーカーは事務作業から解放され、本来注力すべき相談支援業務に多くの時間を割くことが可能になっています。同時に、AI技術を活用した記録の分析により、不正受給の早期発見も期待されています。
また、生活保護適正実施推進員として、警察官OBを職員として福祉事務所に配置する取り組みが進んでいます。元警察官としての専門的な見地から、不正受給事案に対する調査及び検討、並びに悪質な事案に対する告訴手続きに係る調整を行っており、これらの専門職員による記録も重要な調査資料となっています。
自治体間の情報共有と記録の連携
2024年4月1日に施行された生活保護実施要領等の改正により、福祉事務所間の情報共有体制がさらに強化されています。各自治体の個人情報保護条例に基づき、適切な情報管理を行いながら、必要な情報共有が行われています。
生活保護法第29条により、福祉事務所長は保護の決定・実施・執行のために必要な場合、銀行、信託会社、雇用主その他の関係者に対して、申請者・受給者の資産、収入、支出の状況について報告を求めることができるとされており、これが自治体間の情報共有の法的根拠となっています。
また、社会福祉事務所員から生活保護申請者の資産や収入状況等の個人情報の提供を要請された場合、「法令に基づく場合」として個人情報保護法上の問題はないとされており、適切な手続きに従った情報共有が可能となっています。
国による被保護者調査では、生活保護を受給している全ての世帯を対象とする統計調査が実施されており、月次調査では受給世帯数や受給者数など基本的な数値について毎月実施し、年次調査では受給している世帯の状況や世帯員の状況について毎年7月に詳細な調査が行われています。この全国的な調査により、自治体間でのデータ共有と制度運営の標準化が進められており、ケースワーカーの記録についても一定の統一性が保たれています。
相談・申請は市の福祉事務所、町村については都道府県の保健所(保健福祉センター)で受け付けており、これらの機関間での記録共有により、転居等に伴う継続的な支援が可能となっています。
記録が受給者に及ぼす影響と対応方法
ケースワーカーとの相談内容が記録として残ることは、受給者にとって様々な影響をもたらします。正確な記録により、継続的で一貫した支援を受けることができる一方で、過去の発言や状況が長期間にわたって保存されることへの心理的負担もあります。
記録の内容によっては、生活保護費の減額や支給停止、自立指導の強化などの措置につながる可能性もあり、受給者にとって記録の内容は重要な意味を持っています。このため、相談時には正確で誠実な報告を行うことが重要である一方、ケースワーカー側にも受給者の立場に配慮した記録作成が求められています。
面談記録は、生活保護費の支給額の決定、支給の継続・停止の判断、自立支援プログラムの策定などに直接影響を与えます。また、不正受給の疑いがある場合には、過去の面談記録が調査の重要な資料として使用されることもあります。
受給者にとっては、面談での発言が長期間にわたって記録として残り、将来の支援内容に影響を与える可能性があるため、正確で誠実な報告を行うことが重要となります。虚偽の申告や意図的な情報の隠蔽は、後に発覚した際に大きな問題となり、生活保護の廃止や返還請求の対象となる可能性があります。
記録管理における秘密保護と信頼確保
生活保護決定に関しては、個人の秘密にわたる事項まで調査することがあるため、これらの事項についてその秘密を厳守することは、住民の福祉事務所に対する信頼を確保する上から欠くことができないものとされています。
生活保護業務の個人情報保護については、各地方公共団体の個人情報保護条例に基づき実施され、個人情報の適正な取扱いを確保することが求められています。これにより、記録の作成、保存、利用、開示のすべての段階において、適切な個人情報保護措置が講じられることになっています。
記録の質を向上させるためには、ケースワーカーの専門性向上が不可欠です。適切な面接技法、記録作成スキル、個人情報保護に関する知識などの習得により、受給者の尊厳を保ちながら必要な情報を適切に記録することが可能になります。
また、記録作成の標準化や、AI技術を活用した記録支援システムの開発なども、記録の質の向上と業務効率化の両立を図る上で重要な取り組みとなっています。
2025年の最新統計と動向
2024年5月の生活保護被保護者調査の結果では、全国の生活保護を受けている人の数は約201万人で、生活保護の申請件数は約23,952件となり、前年同月と比較すると約1,272件増加し、5.6%の増加率を示しました。
この増加傾向に対応するため、ケースワーカーの業務負荷軽減と記録管理の効率化が急務となっており、IT技術を活用した業務改善が積極的に推進されています。現在、生活保護業務のデジタル化は進展しているものの、統一的なデータベースシステムの構築や自治体間の情報共有については、まだ課題が残されている状況です。
厚生労働省は「生活保護手帳や別冊問答集、厚生労働省通知、各自治体の生活保護運用事例集・問答集、生活保護に係る判例、都道府県知事裁決、他の社会保障制度等の資料」についてデータベース化し、全国のケースワーカーがそれを閲覧できるようにすれば、生活保護制度の運用上の誤りは少なくなると考えられていますが、役所の業務はIT化が遅れ、相変わらず旧態依然としたやり方を続けている部分もあります。
記録保存の長期化とデータ管理の課題
ケース記録の長期保存については、従来の紙媒体による保存から電子媒体による保存への移行が進んでいます。これにより、保存スペースの削減、検索性の向上、劣化防止などのメリットが得られています。
しかし、電子化に伴う新たな課題として、データの長期保存技術、システムの互換性確保、災害時のデータ保護などが挙げられており、これらの課題に対する対策の強化が求められています。また、保存期間満了時のデータ消去についても、確実で安全な消去方法の確立が重要な課題となっており、個人情報の完全な削除を保証するシステムの構築が進められています。
生活保護に関するケース記録は、受給者の生活に長期間にわたって影響を与える重要な文書です。これらの記録は法定保存期間に従って適切に管理され、受給者の権利保護と制度の適正運営の両立が図られています。
特に、不正受給に関する記録については、将来の申請時や他の社会保障制度利用時にも参照される可能性があり、受給者にとって長期的な影響を持つ重要な情報となっています。このため、ケースワーカーには正確で公正な記録作成が求められており、継続的な研修と専門性の向上が重要な課題となっています。
今後の展望と受給者が知っておくべきこと
生活保護制度における記録管理については、デジタル化の進展、個人情報保護法制の強化、社会保障制度の変化などを踏まえた継続的な見直しが必要となっています。特に、受給者のプライバシー保護と適切な制度運営のバランス、記録の効率的な管理と活用、ケースワーカーの業務負荷軽減などの課題に対応していく必要があります。
また、AI技術の活用による記録作成の効率化や、データ分析による支援の質の向上なども今後の検討課題となっており、技術革新を活用した制度改善が期待されています。2025年現在、生活保護制度における記録管理はデジタル化が進み、より効率的な情報管理が実現される一方で、個人情報保護やプライバシーへの配慮も一層求められています。
受給者にとっては、相談内容が詳細に記録され長期間保存されることを理解し、正確で誠実な情報提供を心がけることが重要です。同時に、不適切な対応を受けた場合には、適切な機関に相談し、自身の権利を守ることも大切です。開示請求制度を活用することで、自分に関する記録の内容を確認することもできます。
今後も、技術革新を活用した制度改善と、受給者の尊厳を守る支援のあり方について、継続的な検討と改善が求められています。生活保護制度におけるケースワーカーとの相談内容と記録の残存は、受給者の生活支援と制度の適正運営の両面で重要な役割を果たしており、その適切な管理と活用が今後も重要な課題となっていくでしょう。

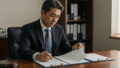

コメント