相続が発生した際、必ずしもすべての財産を引き継ぐ必要はありません。被相続人に借金や債務がある場合、相続人は相続放棄の手続きを通じて、すべての権利義務を承継しないという選択が可能です。相続放棄は家庭裁判所への申立てによって行われる法的手続きであり、一度受理されると原則として撤回できないため、慎重な判断が求められます。本記事では、相続放棄の手続きの流れを、家庭裁判所への申立てから受理証明書の取得まで、実務的な視点から詳しく解説します。2025年現在の最新の制度変更点や、申述書の正確な書き方、照会書への適切な回答方法、さらには受理証明書の活用方法まで、相続放棄に関する包括的な情報をお届けします。債務超過の相続や相続トラブルを避けたい方、相続放棄を検討している方にとって、この記事が確実な手続き完了への道しるべとなるでしょう。
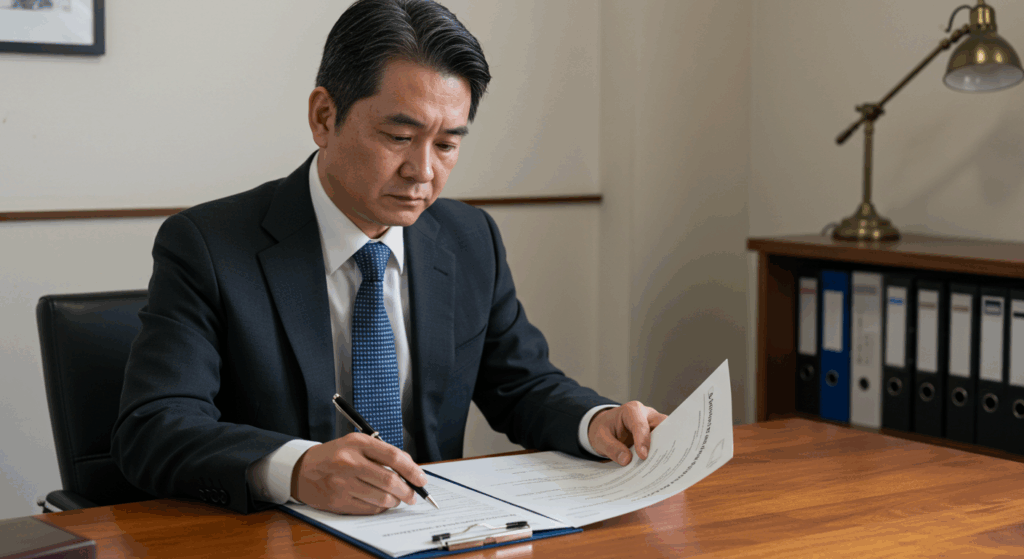
相続放棄とは何か
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切承継しないことを家庭裁判所に申述する法的手続きです。この手続きが完了すると、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、一切の権利義務を引き継がないという強力な効果を持ちます。
相続放棄が選択されるケースは多様ですが、最も一般的なのは被相続人に借金や債務が多く、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合です。このほか、相続争いに巻き込まれたくない場合や、他の相続人に財産を集中させたい場合、あるいは被相続人との関係が疎遠で相続に関わりたくない場合なども、相続放棄が検討されます。
相続放棄の重要な特徴として、相続放棄をした相続人の次の順位の者が新たに相続人となるという点があります。例えば、子が全員相続放棄をすると、被相続人の父母や祖父母が相続人となり、それらの者も相続放棄をすれば、兄弟姉妹が相続人となります。したがって、相続放棄を決断する際には、次順位の相続人への影響も十分に考慮する必要があります。
申立て先となる家庭裁判所
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。これは非常に重要なポイントで、相続放棄をする人の住所地を管轄する裁判所ではありません。被相続人が転居を繰り返していた場合は、死亡時の住民票に記載された住所で管轄裁判所を判断します。
管轄裁判所の確認方法としては、裁判所のウェブサイトで管轄区域を確認する方法や、直接電話で問い合わせる方法があります。遠方の家庭裁判所が管轄である場合でも、申述書の郵送による提出が可能ですので、必ずしも裁判所に直接出向く必要はありません。
なお、通常の相続放棄手続きでは家庭裁判所への出廷は必要ありません。書面による手続きで完結するため、仕事や家庭の事情で裁判所に足を運ぶことが難しい方でも、確実に手続きを進めることができます。
申述期限の重要性
相続放棄の申述には期限が定められており、原則として相続人が相続開始の原因たる事実、つまり被相続人が亡くなったことを知り、さらに自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。この期限を「熟慮期間」と呼びます。
ただし、期限には例外もあります。相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。これは判例によって認められた例外的な取り扱いです。
また、3か月の期間内に相続財産の調査が完了しない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申立てることができます。この申立ては「相続放棄の期間伸長の申立て」として、3か月の期限内に行う必要があります。通常は3か月程度の延長が認められますが、事案の複雑さによってはさらに延長されることもあります。期間延長の申立てには、相続人一人につき800円の収入印紙が必要です。
期限を過ぎてしまった場合でも、特別な事情を証明することで受理される可能性はありますが、確実ではありません。そのため、相続放棄を検討している場合は、できる限り早めに手続きを開始することが重要です。
必要書類の準備
相続放棄の申述には、複数の書類が必要です。書類の種類は、申述人と被相続人の関係によって異なります。
基本的な必要書類
すべてのケースで共通して必要となる書類は以下の通りです。
- 相続放棄の申述書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 申述人の戸籍謄本
申述人と被相続人の関係による追加書類
配偶者が申述する場合は、基本的な必要書類のみで手続きが可能です。
子または孫が申述する場合は、代襲相続のケースでは被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。
父母または祖父母が申述する場合は、より多くの書類が求められます。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子で死亡している人がいる場合はその人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合はその人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹または甥姪が申述する場合は、さらに詳細な書類が必要となります。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子で死亡している人がいる場合はその人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、代襲相続の場合は被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本が求められます。
2025年の重要な制度変更
2025年1月1日以降、資料等の提出方法に変更がありました。従前は原本と写しを提出した後に原本を返還してもらう形でしたが、現在は原本または写し(コピー)での提出が可能となっています。写しのみの提出も認められるようになったため、書類準備の負担が軽減されました。ただし、正確な写しを提出することが条件です。
必要書類の有効期限
相続放棄の申立てに使用する戸籍謄本等には有効期限があります。家庭裁判所では、申述人の戸籍謄本について発行後3か月以内のルールを設けています。古い戸籍謄本では申立てを受理されない可能性があるため、戸籍謄本等は申立て直前に取得することで、有効期限内での手続きを確実に行うことができます。
費用について
相続放棄の申述にかかる費用は、自分で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。
自分で手続きを行う場合
- 申述手数料:収入印紙800円(申述人1人につき)
- 郵便料金:連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なるため、事前に確認が必要)
- 戸籍謄本等の取得費用:1000円から2000円程度
- 合計:2000円から3000円程度
専門家に依頼する場合
- 司法書士に依頼する場合:3万円から5万円程度(実費別)
- 弁護士に依頼する場合:5万円から10万円程度(実費別)
手続きの複雑さや期限の切迫度、確実性を求める場合は、専門家への依頼を検討することが重要です。特に、期限が迫っている場合や、相続財産の内容が複雑な場合、他の相続人との関係が複雑な場合、法的判断が困難な場合などは、弁護士や司法書士への相談を強く推奨します。
申述書の詳細な書き方
相続放棄の申述書は、家庭裁判所が定める書式を使用します。2025年現在、成人用と未成年者用の書式が用意されており、A4サイズの2枚の書面となっています。
申述書の入手方法
申述書は以下の方法で入手できます。
- 家庭裁判所の窓口で直接取得
- 裁判所のウェブサイトからダウンロード
- 郵送での請求(切手を同封)
申述書表面の記載事項
収入印紙の貼付は、800円分の収入印紙を申述書表面の「相続放棄申述書」の題字下部に貼付します。収入印紙には割印をしません。
申述先の記載では、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を記載します。管轄裁判所は事前に確認が必要です。
申述人情報の記載では、氏名は必ず自筆で署名します。本籍は戸籍謄本の記載通りに正確に記入し、住所は住民票の記載通りに記入します。生年月日は和暦で記入し、職業は具体的に記載します。電話番号は日中連絡の取れる番号を記入してください。
被相続人情報の記載では、氏名は死亡時の戸籍に記載された通りに記入します。最後の住所は死亡時の住民票の住所、本籍は死亡時の戸籍の本籍を記載し、死亡年月日は死亡届や除籍謄本で確認して記入します。
申述書裏面の記載事項
相続の開始を知った日を記載し、該当する項目に丸印をつけます。選択肢には、死亡の当日に死亡の事実を知った、死亡の通知を受けた日、先順位者の相続放棄を知った日、その他(具体的に記載)があります。
申述の理由では、該当する理由に丸印をつけます。選択肢には、被相続人から生前に贈与を受けている、生活が安定している、遺産が少ない、遺産を分散させたくない、債務超過のため、その他(具体的に記載)があります。
相続財産の概略では、把握している相続財産について記載します。不動産の有無と概算価額、預貯金の有無と金額、有価証券の有無、債務の有無と金額、その他の財産を記入します。
申述書記載時の注意点
使用する筆記用具は、黒のボールペンまたは万年筆を使用します。鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは使用できません。
代筆については、申述人に相続放棄をする意思があれば、申述書は代筆でも問題ありません。代筆する場合は、申述書に代筆者の氏名を明記し、申述人本人の署名と押印が必要で、代筆理由を記載します。
訂正方法は、記載を間違えた場合、誤りのある箇所を二重線で削除し、訂正印を押印します。正しい内容を近くに記載してください。修正液や修正テープは使用できません。
印鑑については、相続放棄申述書には実印は不要で、認印で構いません。ただし、シャチハタなどのスタンプ印は避けることが推奨されます。
日付の記載は、申述書の提出日または作成日を記載します。和暦での記載が一般的です。
添付書類との整合性は非常に重要です。申述書の記載内容は、添付する戸籍謄本等の内容と一致させる必要があります。特に、氏名の漢字、本籍地の表記、生年月日、被相続人との続柄には注意が必要です。
申述書作成時のよくある間違い
氏名の誤記では、戸籍上の正式な漢字と異なる字体で記載してしまうケースがあります。必ず戸籍謄本を確認して記載してください。
住所の省略では、住所を省略して記載すると受理されない場合があります。住民票記載の通りに正確に記載してください。
続柄の誤記では、被相続人との続柄を間違えて記載するケースがあります。戸籍謄本で正確な続柄を確認してください。
相続開始を知った日の誤記は、実際に知った日と異なる日付を記載すると、後の照会で問題となる可能性があります。正確な日付を記載することが重要です。
申述書の提出方法
申述書の提出には、窓口提出と郵送提出の2つの方法があります。
窓口提出は、家庭裁判所の窓口に直接持参して提出します。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
郵送提出は、書留郵便での郵送が推奨されます。郵送の場合は、書留郵便で送付し、返信用封筒と切手を同封します。配達証明をつけることも推奨されます。
提出書類の確認として、提出前に以下を確認してください。申述書の記載漏れがないか、収入印紙が貼付されているか、必要書類がすべて揃っているか、署名と押印があるかをチェックしましょう。
照会書への回答
申述書を提出すると、通常2週間から1か月程度で家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送付されます。照会書には、相続開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の処分の有無、他の相続人の存在、被相続人との関係、申述の意思確認などの質問が記載されています。
照会書・回答書の目的
照会書は、申立人の名義で相続放棄の申立があったことを確認し、本人の真意による申立であることを確認するための書類です。回答書は、自分の意思で相続放棄することを家庭裁判所に伝えるための重要な書面です。
回答書記載時の重要な注意点
代筆の制限として、原則として回答書の代筆は認められません。ただし、腕の怪我など、やむを得ない事情がある場合は例外があります。その場合、代筆者は相続人および配偶者以外の利害関係のない人で、申述人本人の署名と押印が必要です。申述書と同一の印鑑を使用してください。
期限の厳守は極めて重要です。回答書には明確な返送期限が記載されており、一般的には1週間から10日程度です。期限は家庭裁判所により異なりますが、期限内に返送しないと相続放棄が受理されない可能性があります。また、記載内容に不備があると再提出が必要となります。
一般的な質問項目と回答のポイント
基本情報の確認では、申述人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄、被相続人の死亡を知った日、相続放棄の申述日を確認します。
意思確認に関する質問では、相続放棄は本人の意思によるものか、強制や脅迫によるものではないか、相続放棄の内容を理解しているか、申述書の記載内容に間違いはないかが問われます。
相続財産に関する質問では、相続財産の処分行為の有無、相続財産の隠匿行為の有無、遺産分割協議への参加の有無、債務の支払いの有無が確認されます。
相続放棄の理由に関する質問では、具体的な相続放棄の理由、債務超過の場合はその詳細、他の相続人との関係、生前贈与の有無が尋ねられます。
回答書の正しい記載方法
申述書との整合性は非常に重要です。回答書の記載内容は、提出済みの相続放棄申述書と矛盾しないよう注意が必要です。申述書のコピーを手元に置いて確認し、日付や理由に相違がないかチェックしましょう。新たな事実が判明した場合は正直に記載してください。
具体的で明確な回答を心がけます。質問に対しては具体的で明確な回答をしてください。「はい」「いいえ」で答えられる質問は明確に回答し、理由を問う質問には具体的な事情を記載します。曖昧な表現は避けましょう。
正確な日付の記載も重要です。日付に関する質問では正確な情報を記載してください。被相続人の死亡を知った正確な日、相続財産の存在を知った日、債務の存在を知った日を記入します。
回答書でよくある間違い
申述書との矛盾が発生すると、追加の説明が求められます。相続開始を知った日の相違、相続放棄の理由の相違、相続財産の処分に関する記載の相違には特に注意が必要です。
不正確な日付の記載も問題となります。記憶が曖昧な場合でも、推測で日付を記載するのは危険です。正確に覚えていない場合はその旨を記載し、概ね何月頃などの表現を使用してください。後で訂正が必要になる可能性を避けることが重要です。
不完全な回答は再照会の原因となります。質問に対して不完全な回答をすると、再照会される可能性があります。すべての質問に回答し、空欄を残さず、不明な点は「不明」と正直に記載してください。
専門家の関与について
弁護士の関与では、弁護士は申述人を代理して回答書を記入することができます。完全な代理が可能ですが、申述人の署名押印は必要です。内容の責任は弁護士が負います。
司法書士の関与では、司法書士は代理権がないため、回答書の文案作成や記載方法の指導にとどまります。申述人本人による自書が必要です。
回答書提出後の流れ
照会書への回答に問題がなければ、回答書提出後、通常1週間から10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書の受領をもって、相続放棄の手続きが完了します。
審査期間は、回答書提出後、家庭裁判所で審査が行われます。通常1週間から10日程度で、内容に問題がなければ受理されます。問題がある場合は追加照会があります。
受理通知書の送付では、審査に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送付されます。これにより相続放棄の効力が発生し、法的に相続人ではなくなります。この通知書は債権者に対する証明書類としても使用されます。
受理証明書について
相続放棄が受理された後、場合によっては相続放棄申述受理証明書が必要となります。
受理証明書とは何か
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄をしたことを第三者に証明するための公的書類です。相続放棄申述受理通知書と混同されがちですが、通知書は申立人への通知目的であり、証明書は第三者への証明目的という違いがあります。
通知書と証明書の違いは以下の通りです。
- 相続放棄申述受理通知書:申立人への通知(再発行不可)
- 相続放棄申述受理証明書:第三者への証明(何度でも発行可能)
受理証明書の申請方法
申請先は、相続放棄申述を行った家庭裁判所に申請します。被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所が申請先となります。
必要書類と費用は以下の通りです。
- 申請書(家庭裁判所備付けの専用用紙)
- 収入印紙150円分(1通につき)
- 郵送の場合は返信用切手
- 申請者の身分証明書
- 事件番号(受理通知書に記載)
申請者の資格として、以下の者が申請可能です。
- 相続放棄をした本人
- 他の相続人
- 相続債権者
- その他の利害関係者
申請書の記載事項には、申請者の氏名、住所、被相続人との関係、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、死亡年月日、相続放棄申述受理の年月日、事件番号、証明書の使用目的があります。
受理証明書が必要となる主な場面
銀行・金融機関での証明では、金融機関で相続手続きを行う際、相続放棄をした相続人がいる場合は証明書の提出が求められます。預金口座の解約手続き、定期預金の相続手続き、投資信託等の相続手続き、生命保険金の請求手続きなどで使用されます。
不動産の相続登記では、不動産の相続登記(名義変更)において、相続放棄をした相続人がいる場合は必須書類となります。相続による所有権移転登記、持分移転登記、抵当権等の担保権の整理に使用します。
債権者への証明として、被相続人の債権者から督促や請求があった場合の証明に使用します。借金の債権者への証明、クレジットカード会社への証明、住宅ローン等の金融機関への証明、税務署への証明などが含まれます。
その他の利用場面として、遺産分割協議での証明、家庭裁判所での他の手続きにおける証明、税務申告における証明、保険会社への証明などがあります。
受理証明書取得時の注意点
発行までの期間は、窓口申請で数日から1週間程度、郵送申請で1週間から10日程度です。即日発行は不可で、裁判官の許可が必要です。
事件番号の確認として、申請には事件番号が必要です。受理通知書に記載されており、通知書を紛失した場合は裁判所に問い合わせます。申述日と申立人名で照会が可能です。
郵送での申請方法は、遠方の場合は郵送での申請が可能です。申請書と必要書類を同封し、収入印紙を貼付します。返信用封筒と切手を同封し、書留郵便での送付を推奨します。
申請書の入手方法は、家庭裁判所の窓口で取得、裁判所ウェブサイトからダウンロード、電話での請求(郵送で送付)があります。
費用と発行数の制限
費用は、1通につき150円(収入印紙)と郵送料(実費)で、その他の手数料は不要です。
発行数の制限として、発行回数に制限はなく、必要に応じて何度でも申請可能です。同一目的での複数申請も可能です。
有効期限は、証明書に有効期限の記載はありません。ただし、提出先が独自に期限を設定する場合があり、一般的には発行から3か月以内の提出が求められることが多いです。
申請時のよくあるトラブル
事件番号不明の場合、受理通知書を紛失した場合は、申述日と申立人名で裁判所に照会します。戸籍謄本等での本人確認が必要です。
申請者の資格では、利害関係の証明が求められる場合があります。債権者は債権の存在証明が必要で、相続人は戸籍謄本等での関係証明が必要です。
記載内容の誤りとして、被相続人の情報の間違い、申述日の記載誤り、事件番号の記載誤りなどがあります。
重要な注意事項
相続放棄を行う際には、いくつかの重要な注意事項があります。
単純承認事由の回避
以下の行為を行うと、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 相続財産の全部または一部の処分
- 相続財産の隠匿、消費、悪意での財産目録不記載
- 熟慮期間経過後の相続放棄
具体的に避けるべき行為として、預金の解約や引き出し、不動産の売却や名義変更、債務の支払い、遺産分割協議への参加、相続財産の処分があります。これらの行為は相続を承認したとみなされるため、絶対に避ける必要があります。
撤回の不可
一度家庭裁判所によって相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。そのため、慎重な判断が必要です。相続放棄をした後に新たな財産が見つかっても相続することはできず、相続放棄の効力は既に確定しています。
生前の相続放棄の禁止
被相続人の生前に相続放棄の手続きを行うことはできません。相続放棄は相続開始後にのみ可能な手続きです。
次順位相続人への影響
相続放棄をすると、次の順位の相続人が相続人となります。そのため、次順位の相続人にも債務が承継される可能性があることを考慮する必要があります。自分が相続放棄をすることで、次の順位の相続人が新たに相続人となるため、これらの人にも債務が承継される可能性があります。事前に連絡を取ることが望ましいです。
相続放棄後の手続き
相続放棄が受理された後にも、いくつかの手続きが必要になる場合があります。
債権者への通知
相続放棄をしても、債権者に自動的に通知されるわけではありません。債権者から請求があった場合は、受理証明書を提示して相続放棄の事実を証明する必要があります。
次順位相続人への配慮
自分が相続放棄をすることで、次の順位の相続人が新たに相続人となります。これらの人にも債務が承継される可能性があるため、事前に連絡を取ることが望ましいです。
不動産の管理責任
相続放棄をしても、次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理する義務があります。これは民法で定められた義務であり、放置することはできません。
相続財産管理人の選任
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が管理することになります。
相続放棄の代替手段
相続放棄以外にも、相続に関する選択肢があります。
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する制度です。プラスの財産の範囲内でのみ債務を承継するため、債務超過かどうか不明な場合に有効な手段です。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも相続放棄より複雑です。
遺産分割による調整
相続人間での協議により、特定の相続人が債務を引き受ける方法もあります。ただし、債権者に対してはこの約束は対抗できません。債権者は法定相続分に応じて各相続人に請求することができます。
債務整理
相続した債務が支払い困難な場合は、債務整理を検討することも可能です。任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
相続放棄と税務
相続放棄をした場合の税務上の取り扱いについて理解しておくことも重要です。
相続税
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、相続税の課税対象となりません。ただし、生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産については別途検討が必要です。
贈与税
相続放棄により他の相続人の相続分が増加しても、贈与税の課税対象にはなりません。これは相続放棄が法律上の効果として当然に発生するものだからです。
生命保険金の取り扱い
被相続人が保険料を負担し、相続人が受益者となっている生命保険金は、相続財産ではなく固有の権利として受け取ることができます。相続放棄をしても生命保険金は受け取れますが、税務上はみなし相続財産として相続税の課税対象となる場合があります。
2025年の制度変更と動向
2025年現在の相続放棄に関する法的環境について説明します。
デジタル化の進展
家庭裁判所手続きのデジタル化が進んでおり、一部の手続きではオンライン申請が可能になっています。今後、相続放棄の申述についてもオンライン化が進むことが予想されます。
受理証明書についても、一部の裁判所では申請手続きのデジタル化が進んでいます。オンライン申請の試行、電子的な証明書発行の検討、デジタル署名への対応が行われています。
書式の標準化
全国の家庭裁判所で使用される申述書の書式がより標準化され、手続きの統一化が図られています。申請書の記載項目の見直し、必要書類の簡略化、処理期間の短縮が進められています。
情報提供の充実
裁判所のウェブサイトでの情報提供が充実し、手続きに関する詳細な説明が容易に入手できるようになっています。ウェブサイトでの詳細説明、申請書記載例の提供、よくある質問の公開が行われています。
よくあるトラブルと対策
相続放棄手続きでよく発生するトラブルとその対策について説明します。
期限切れトラブル
3か月の期限を過ぎてから相続放棄を知ったケースでは、特別な事情を証明することで受理される可能性があります。ただし、確実ではないため、早めの相談が重要です。
単純承認トラブル
相続財産を処分してしまった後に相続放棄を希望するケースでは、既に単純承認したものとみなされ、相続放棄ができない場合があります。
書類不備トラブル
必要書類が不足していたり、記載内容に誤りがあったりすると、手続きが遅延する可能性があります。事前のチェックが重要です。
他の相続人とのトラブル
相続放棄により他の相続人の相続分が増加するため、トラブルが発生する場合があります。事前の話し合いが重要です。
よくある質問
相続放棄後に新たな財産が見つかった場合はどうなりますか?
相続放棄が受理された後は、新たな財産が見つかっても相続することはできません。相続放棄の効力は既に確定しているためです。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
被相続人が保険料を負担し、相続人が受益者となっている生命保険金は、相続財産ではなく固有の権利として受け取ることができます。
家庭裁判所への出廷は必要ですか?
通常の相続放棄手続きでは、家庭裁判所への出廷は必要ありません。書面による手続きで完結します。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法は?
期限を過ぎた場合でも、特別な事情があれば受理される可能性があります。弁護士などの専門家に相談することを推奨します。
専門家への相談
相続放棄は法的効果が大きい手続きであるため、以下の場合は専門家への相談を強く推奨します。
専門家相談が推奨される場合
- 相続財産の内容が複雑な場合
- 期限が迫っている場合
- 他の相続人との関係が複雑な場合
- 法的判断が困難な場合
相談できる専門家
- 弁護士(法的アドバイス全般、代理権あり)
- 司法書士(書類作成支援、代理権なし)
- 税理士(税務面のアドバイス)
相続放棄は一度受理されると撤回できない重要な手続きです。慎重に判断し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、確実な手続き完了を目指しましょう。

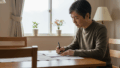

コメント