近年、ファッション業界における環境問題への関心が高まる中で、サステナブルファッションとファストファッションの比較が消費者にとって重要なテーマとなっています。私たちが日常的に着用する衣服が、地球環境や労働者の生活に大きな影響を与えていることをご存知でしょうか。国連環境計画の報告によれば、ファッション産業は世界の温室効果ガス排出量の約10パーセントを占めており、これは国際航空便と海運業を合わせた排出量よりも多い数値です。一方で、2025年を迎えた現在、日本国内外のアパレルブランドは持続可能性への取り組みを加速させており、消費者の意識も大きく変化しています。本記事では、サステナブルファッションとファストファッションの根本的な違いから、具体的なブランドの取り組み、素材の特性、そして私たち消費者が実践できる選択肢まで、網羅的に解説していきます。環境に配慮したファッション選びを始めたい方にとって、この情報が持続可能な未来への第一歩となることを願っています。

- サステナブルファッションの本質と定義
- ファストファッションの実態と深刻な環境問題
- ファストファッションブランドの労働問題と人権課題
- 2025年のサステナブルファッション動向と市場変化
- サステナブルブランドの具体例と先進的な取り組み
- サステナブル素材の種類とメリット
- 古着と中古市場の成長とリユースの重要性
- 循環型ファッションとアップサイクルの取り組み
- 日本のサステナブルブランドと独自技術
- 実践的な取り組み方法と消費者の選択
- ファッションレンタル・サブスクサービスの台頭
- ファストファッションブランドの環境対策の動き
- 政府の取り組みとサステナブルファッション推進
- 繊維リサイクルの最新技術と服から服への取り組み
- 消費者意識の変化とこれからの選択
- ファッション業界の今後の展望と私たちにできること
サステナブルファッションの本質と定義
環境省の定義によれば、サステナブルファッションとは、衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人、社会に配慮した取り組みを指します。これをより分かりやすく表現するならば、人や環境、地域社会に配慮したファッションであり、衣服づくりの過程で地球環境や動物福祉が考えられており、労働者への適正な賃金などもしっかりと保障するものです。使い捨てするようなものではなく、長く、大切に着ていく前提のファッションと言えます。
サステナブルファッションと並んで語られる言葉にエシカルファッションがあります。エシカルファッションとは、人や社会、地球環境、地域に配慮された商品やサービスを選ぶエシカル消費に基づいて製造、流通、販売されるファッションです。サステナブルファッションとエシカルファッションは、ほぼ同義で使われることが多く、どちらも人や環境への配慮を重視する点で共通しています。この二つの概念は、現代のファッション業界における新しい価値観として、企業と消費者の双方に浸透しつつあります。
サステナブルファッションが重視する要素は多岐にわたります。まず、環境面では、水資源の保護、化学物質の削減、温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全などが挙げられます。社会面では、労働者の権利保護、適正な賃金の支払い、安全な労働環境の確保、児童労働の撤廃などが重要です。経済面では、長期的な視点でのビジネスモデル、適正な在庫管理、循環型経済への移行などが求められています。これらの要素が統合されることで、真の意味でのサステナブルファッションが実現します。
ファストファッションの実態と深刻な環境問題
ファストファッション業界の最大の特徴は、トレンドを取り入れた安価な衣類を短いサイクルで大量生産し、消費者に提供するビジネスモデルにあります。しかし、この仕組みには深刻な環境問題が潜んでいます。国連貿易開発会議が2019年に発表した資料によると、アパレル業界は石油に次いで世界で第二位の汚染産業と言われています。この衝撃的な事実は、私たちの日常的なファッション消費が地球環境に与えている影響の大きさを物語っています。
具体的な数字で見ると、ファッション業界の年間のCO2排出量は約90,000キロトン、水消費量は83億立方メートルにも及びます。服1着あたりで見ると、CO2排出量は約25.5キログラム、水消費量は約2,300リットルです。これは、服1着を作る際にはペットボトル約255本を製造するのと同じだけのCO2が排出され、浴槽約11杯分もの水が使われている計算になります。たった1枚のTシャツをつくるのに消費される水の量は、平均にして約2,700リットルで、これは平均的な人が3年かけて飲む水の量に相当します。
廃棄の問題も深刻です。購入された服のうちリサイクルやリユースに回されるのは全体の34パーセントほどで、残りの66パーセントが焼却処分や埋め立て処分がされています。1日あたりに焼却、埋め立てされる衣服の重さは1,300トンで、大型トラック130台分に相当します。ファストファッション業界で生産される衣類の半分以上が、1年も経たないうちにごみに変わってしまっており、リサイクルされているものは世界的に見ると1パーセント以下です。日本においては、年間に1人当たり20着もの量を捨てているというデータもあります。
そして、この問題は悪化の一途をたどっており、2030年までにファッション業界のCO2排出量は6割以上増加することが見込まれています。過剰生産の仕組みがあるために、アパレル業界、ファッション業界には余剰在庫、在庫過多問題が根深く存在しています。これらの余剰在庫は焼却処分されることが多く、焼却時に二酸化炭素を大量に排出することになり、地球温暖化が進む原因となっています。日本では年間約15億着もの売れ残りが発生していると言われており、この問題への対処が急務となっています。
ファストファッションブランドの労働問題と人権課題
ファストファッションには、環境問題だけでなく、深刻な労働問題と人権課題も存在します。業界で働く労働者の多くは、低賃金で働いており、一部の国では最低賃金すら支払われていないことや、残業代が支払われないこともあります。約7500万人いるファストファッションに関連する工場労働者のうち、最低賃金を得ているのは2パーセントに過ぎないという報告もあり、綿花栽培や縫製などの児童労働も深刻な問題です。
2013年4月24日にバングラデシュの首都ダッカで8階建ての商業ビル、ラナプラザの倒壊事故が発生しました。この事故では1,130名以上の死者と2,500名以上の負傷者を出しました。この悲劇的な事故の結果、バングラデシュで洋服を生産しているH&M、ZARA、ユニクロなどが建物の安全性に関わる協定に署名することになりました。この事故は、ファストファッションの裏側にある労働環境の問題を世界に知らしめる契機となり、業界全体に大きな影響を与えました。
労働問題の背景には、価格競争の激化があります。消費者により安い商品を提供するために、生産コストを極限まで削減する必要があり、その結果として労働者の賃金が抑えられ、労働環境が悪化しています。特に発展途上国では、労働法の整備が不十分であったり、法律があっても適切に執行されていなかったりするケースが多く、労働者の権利が守られにくい状況にあります。これらの問題は、単に企業の倫理的責任だけでなく、消費者である私たちの選択とも密接に関連しています。
2025年のサステナブルファッション動向と市場変化
2025年は、日本のサステナブルファッションにおいて、大手企業による持続可能性への取り組みが加速する年となっています。アダストリアは全ファッションブランドで100パーセントサステナブルコットンへの切り替えを目指すなど、具体的な目標を掲げています。サステナランウェイ2025では、オンワード樫山が参加するなど、ファッションを通じてサステナビリティを体現するイベントが開催されています。これらの動きは、業界全体がサステナビリティを単なる付加価値ではなく、ビジネスの中核に据えつつあることを示しています。
2025年の市場調査では、サステナブル商品への需要が前年比20パーセント増加しており、Global Fashion Agendaの調査では、消費者の40パーセントが購入時に環境影響を考慮すると回答しています。これは、消費者の意識が大きく変化していることを示しています。特に若い世代を中心に、価格やデザインだけでなく、製品がどのように作られているか、環境にどのような影響を与えているかを重視する傾向が強まっています。
法規制の面でも大きな動きがあります。欧州委員会のエコデザイン規則からニューヨークファッション法、グリーンウォッシング法、デジタル製品パスポートまで、ファッション分野の法律は整備されつつあり、2025年には大きな進展が見られると予想されています。これらの法規制は、企業に対してより透明性の高い情報開示を求めるものであり、消費者が適切な判断を行うための基盤となります。グリーンウォッシング、つまり実際には環境に配慮していないにもかかわらず、そのように見せかける行為を規制することで、真に持続可能な取り組みを行っている企業が評価される環境が整いつつあります。
サステナブルブランドの具体例と先進的な取り組み
パタゴニアは、長年にわたりリサイクル素材を使用し、社会的責任を果たしてきたパイオニア的存在として知られています。品質の高さと環境配慮の両立を実現しており、修理プログラムの提供により、製品寿命を延ばす取り組みも評価されています。2025年までにバージン石油由来素材をすべて排除し、再生原料や自然繊維へ全面移行するロードマップを公表しています。同社の創業者が会社の株式を環境保護団体に譲渡するという決断は、利益追求だけでなく地球環境の保護を最優先する姿勢を明確に示しました。
ステラ・マッカートニーは、動物由来の素材を使用せず、リサイクル素材やヴィーガンレザーでラグジュアリーなファッションを提供する先駆的存在です。高級ファッションブランドでありながら、徹底した動物福祉と環境配慮の姿勢を貫いています。同ブランドは、革や毛皮を使用しないという明確な方針を持ちながらも、デザイン性や品質を妥協することなく、ラグジュアリーファッションとサステナビリティが両立できることを証明しています。
ECOALFはスペイン発のサスティナブルブランドで、2020年に日本に上陸しました。海洋プラスチックをファッションアイテムに変換する技術で注目を集めており、廃棄物を資源として活用する循環型モデルを実現しています。同ブランドは、海から回収されたプラスチックボトルを原料として、高品質な衣類を製造しており、環境問題の解決とファッション性の両立を目指しています。
H&Mは、ファストファッションブランドでありながら、サステナビリティへの転換を図っています。2030年までに100パーセントサステナブル素材使用を目標とし、2025年時点でリサイクルポリエステルの使用率が50パーセントに到達しています。店頭での衣類回収プログラムも積極的に展開しており、消費者が不要になった衣類を持ち込むことで、リサイクルやリユースに貢献できる仕組みを構築しています。
グッチは、2025年までには環境負荷を40パーセント削減し、原材料の調達状況を追跡できるトレーサビリティを100パーセント実現することを目指していました。実際、2015年から2020年末までに環境負荷を44パーセント、温室効果ガス排出量を47パーセント削減し、これらの目標を予定よりも4年早く達成しました。ラグジュアリーブランドとしての地位を維持しながら、環境への配慮を経営の中核に据える姿勢は、業界全体に大きな影響を与えています。
サステナブル素材の種類とメリット
オーガニックコットンは、サステナブルファッションの代表的な素材です。化学物質を使用しないため、土壌や水源への汚染を防ぎ、栽培に必要な水の量も削減できます。有機農法は有害な化学物質の使用を避け、資源の使用量削減を目標とした、環境に対するサステナビリティに配慮した方法です。化学物質を使用していないため農地寿命が長く、綿花を栽培し商品を生み出し続けることができます。
人体、健康面でのメリットも大きく、化学物質を使用していないため、肌に優しく、特に肌が敏感な赤ちゃんのベビー服や子供服、アレルギー体質の方におすすめです。オーガニックコットンは通気性が良く、汗を吸収しやすいので、季節を問わず快適に着用できます。農薬の使用量が少なければ土壌劣化も少なく、畑の寿命が伸びることにもつながります。さらに、農家で働く方々の健康被害も劇的に改善されます。従来のコットン栽培では、大量の農薬が使用されることで、農家の人々が健康被害を受けるケースが多く報告されていましたが、オーガニックコットンへの転換により、こうした問題が大幅に軽減されています。
リサイクル素材も重要な役割を果たしています。廃棄ペットボトルを再利用したリサイクルポリエステル素材は、アウトドアブランドから高級ファッションまで幅広く採用されています。この素材は耐久性に優れ、従来のポリエステルと比較して二酸化炭素排出量を大幅に削減できることが確認されています。リサイクルポリエステルの製造過程では、バージンポリエステルと比較してエネルギー消費量を約50パーセント削減でき、温室効果ガス排出量も大幅に減少します。
主な原料としては、土壌の二酸化炭素吸収を高めるオーガニックコットン、土地への負担が大幅に小さいリヨセル、ペットボトルをリサイクルし紡績したポリエステル糸とポリエステル中わたが使用されています。使用済みの素材や製品を再利用して作られるため、資源の節約に寄与するという大きなメリットがあります。リヨセルは、ユーカリなどの木材パルプから作られる繊維で、製造過程で使用される溶剤の99パーセント以上が回収され再利用されるため、環境負荷が非常に低い素材として注目されています。
木に実るダウンと呼ばれる新素材カポックを使用するKAPOK KNOTなど、独自の技術や素材を開発するブランドも増えています。オーガニックコットン、リサイクルポリエステル、温湿度調節テクノロジーを持つ素材などが2025年の市場を牽引しています。カポックは、熱帯地域に生育するカポックの木の実から採取される天然繊維で、軽量かつ保温性に優れており、動物性ダウンの代替として期待されています。水に浮くほど軽く、保温性はダウンに匹敵しながらも、動物を犠牲にすることなく調達できる点で、倫理的な素材として評価されています。
古着と中古市場の成長とリユースの重要性
サステナブルファッションの実践方法として、古着や中古品の活用も重要です。アメリカ発のリセールECであるスレッドアップは、世界の中古市場が2022年の1,770億ドル、約27兆4,300億円を基準として、2027年には約3,500億ドル、約54兆4,300億円までほぼ倍増すると予想しています。この成長は、新品を購入する代わりに中古品を選ぶことで、資源の節約と廃棄物の削減に貢献できるという消費者の意識の高まりを反映しています。
ブランド品を除く衣類、服飾品のリユース市場規模は2018年から2021年で20.9パーセント増加しており、1,212億円となっています。この成長は、消費者の意識変化と、環境への配慮を重視する価値観の広がりを示しています。特に若い世代を中心に、新品を購入することよりも、既存の資源を有効活用することに価値を見出す傾向が強まっています。
中古市場の拡大を支えているのは、オンラインプラットフォームの発展です。メルカリなどのフリマアプリの普及により、個人間での衣類の売買が容易になり、不要になった服を簡単にリユースに回すことができるようになりました。また、ヴィンテージ品やデザイナーズブランドの古着を専門に扱うセレクトショップも増加しており、古着に対するイメージが大きく変化しています。かつては古着というと安価な代替品というイメージがありましたが、現在では個性的でサステナブルな選択肢として、ポジティブに捉えられるようになっています。
循環型ファッションとアップサイクルの取り組み
循環型ファッションとは、適量生産、適量購入、循環利用により、衣服や素材を循環させ、廃棄される衣服を少なくする循環型の取り組みです。この考え方は、サステナブルファッションの実現において重要な役割を果たしています。具体例として以下が挙げられます。今持っている服を長く大切に着ること、長期間着られることを前提とした商品企画やリペアなどです。リユースすること、シェアリングサービスの導入、フリマアプリなどリユース市場の拡大などです。先のことを考えて生産販売すること、適正な在庫管理、短サイクル化の見直しです。作られ方をしっかり見ること、サステナブルな素材の使用の有無を伝えるといったトレーサビリティの確保、アップサイクルへの挑戦です。服を資源として再活用すること、店頭回収の推進、服から服を作る取り組みなどです。
アップサイクルとは、使わなくなったものや不要なものに手を加え、元の素材よりも価値の高いものに生まれ変わらせることです。リサイクルが資源を一度原材料に戻して再生するのに対し、アップサイクルは元の形や特徴を活かしながら新たな価値を創造します。例えば、古いジーンズをバッグにリメイクしたり、使用済みの帆布をトートバッグに加工したりする取り組みがあります。
カラーループでは、素材分別が難しい廃棄繊維を色で分けてアップサイクルする独自の方法、カラーリサイクルシステムを採用しています。この取り組みは、従来は廃棄されていた混合繊維に新たな価値を与える画期的な方法です。混合繊維は、異なる素材が組み合わされているため、従来のリサイクル方法では分離が困難でしたが、色別に分類してアップサイクルすることで、新たな製品として生まれ変わることができます。
三陽商会やTSIのマーガレット・ハウエル、ユニクロなどは回収した衣類をリセール、再販する取り組みも始めています。これらの取り組みは、衣類の寿命を延ばし、廃棄を減らすことに貢献しています。無印良品では、回収した衣類を染め直した服、つながる服、服と服とリメイクしたものとして再生し、一部の店舗限定で販売を行っています。この取り組みは、既存の衣類に新たな命を吹き込む循環型モデルの好例です。
日本のサステナブルブランドと独自技術
日本国内にも、多くのサステナブルファッションブランドが存在します。Enter the Eは、オーガニックコットンコレクションを展開し、人や環境に配慮した服が当たり前の社会をつくることを目指しています。アパレルの大量廃棄を減らすための取り組みを積極的に行っています。
ピープルツリーは、オーガニックコットン、エシカルファッションのフェアトレード専門ブランドとして、長年にわたり活動しています。公正な取引を通じて、生産者の生活向上と環境保護を両立させる取り組みを続けています。発展途上国の生産者と直接取引を行い、適正な価格で製品を購入することで、生産者の自立を支援しています。
イッセイミヤケは、A-POC、A Piece of Clothの計画で、1本の糸から衣服を作り、生産中の生地の無駄を最小限に抑える取り組みを行っています。この技術は、素材の無駄を極限まで減らし、サステナブルなものづくりを実現しています。従来の服づくりでは、パターンに合わせて生地を裁断する際に、どうしても端材が出てしまいますが、A-POC技術では、一本の糸から立体的に服を編み上げることで、廃棄物をほぼゼロにすることができます。
島精機製作所は、無縫製ニット ホールガーメント横編機や、バーチャルサンプルを作成できる3Dデザインシステムを開発、製造、販売している機械メーカーで、2017年から自社製品を通じたサステナビリティの提唱を行っています。この技術により、サンプル作成の段階での廃棄物を大幅に削減することができます。ホールガーメント技術は、縫い目のないニット製品を一着まるごと編み上げる革新的な技術で、縫製工程が不要になることで、労働時間の削減や製造コストの低減にもつながります。
KAPOK KNOTは、木に実るダウンと呼ばれる新素材カポックを使用し、消費者、生産者、地球環境の3つの視点に寄り添ったモノづくりを目指すブランドです。カポックは軽量で保温性に優れ、動物性ダウンの代替として注目されています。同ブランドは、カポックの調達から製品化まで、一貫してサステナビリティを重視しており、生産地の労働環境改善にも取り組んでいます。
実践的な取り組み方法と消費者の選択
消費者として、サステナブルファッションを実践する方法はいくつかあります。新しい洋服を買うときは、オーガニックコットン素材や、リサイクルプラスチック素材を使用した商品を選ぶように意識してみることが第一歩です。これは、エシカルファッションブランドだけでなく、ユニクロやイオンなどの店舗でも比較的安く購入できるため、誰でも取り組みやすくなっています。
既に持っている服を長く着続けることも重要です。修理やリメイクを活用し、服の寿命を延ばすことで、新たな資源の消費を抑えることができます。パタゴニアのような修理プログラムを提供するブランドを選ぶことも、持続可能な消費行動の一つです。自分で簡単な修理ができるように、基本的な裁縫技術を身につけることも有効です。ボタンの付け直しや、ほつれの修繕など、ちょっとした手入れで服の寿命は大きく延ばすことができます。
購入する際には、そのブランドがどのような取り組みをしているかを確認することも大切です。トレーサビリティが確保されているか、労働環境は適切か、使用されている素材は何かなど、情報を調べることで、より責任ある選択ができます。多くのサステナブルブランドは、自社のウェブサイトで詳細な情報を公開しており、製品がどこで、どのように作られているかを知ることができます。
スローファッションという選択肢も重要です。スローファッションは、ファストファッションとは対極の概念で、トレンドに左右されず、長く愛用できる質の高い衣服を選ぶという考え方です。大量生産、大量消費のサイクルから脱却し、本当に必要なもの、本当に気に入ったものを大切に着るという価値観を重視します。品質の高い、長持ちする衣服を選ぶこと、流行に左右されないベーシックなデザインを選ぶこと、修理やお直しを活用して、服の寿命を延ばすこと、自分のスタイルを確立し、衝動買いを避けること、服の製造背景や素材について学び、理解を深めることが、スローファッションの実践方法です。
ファッションレンタル・サブスクサービスの台頭
ファストファッションの代替として注目されているのが、ファッションレンタルやサブスクリプションサービスです。気になるブランドやスタイルを手軽に、低コストで試せると注目が高まる洋服のレンタル、サブスクサービスは、1つの服を人と共有することで、服の着用回数が増えたり、長く着ることができれば、環境にも嬉しい選択肢となっています。
環境省のデータによると、1人が1年間に購入する服の枚数は平均18着です。サブスクレンタルサービスを利用すると、店頭価格30,000円の洋服を1か月間、3着で1万円で着られるという経済的なメリットもあります。忙しくて服を買いに行く時間がない、毎回似たようなコーディネートになりがちという方におすすめなのが、幅広いブランドの服や小物の中から自分好みのアイテムをレンタルできる洋服レンタルサービスです。
洋服レンタル、洋服サブスクは、利用者一人ひとりに合わせたコーディネートをスタイリストが選んでくれるタイプと、自分でアイテムを選ぶタイプの2種類があります。2025年最新のファッションレンタルサービスとして、エアークローゼット、メチャカリ、ブリスタなどが人気を集めています。これらのサービスは、ファストファッションの代替として、環境負荷を減らしながらファッションを楽しむ選択肢として注目されています。
シェアリングエコノミーの概念は、ファッション業界にも広がっています。所有から共有へという価値観の転換は、特に若い世代を中心に支持を集めています。服をシェアすることのメリットは、経済的な負担の軽減、クローゼットのスペース削減、様々なスタイルを試せる楽しさ、環境負荷の削減など、多岐にわたります。ファッションシェアリングの形態には、レンタルサービス、サブスクリプションサービス、友人間でのシェアリング、コミュニティベースの衣服交換会などがあります。これらの取り組みは、新品を購入することなくファッションを楽しむ新しい形として、サステナブルファッションの実現に寄与しています。
ファストファッションブランドの環境対策の動き
一方で、ファストファッションブランドも環境対策に取り組み始めています。ユニクロをはじめ、H&Mなどのファストファッションブランドが、2020年に向けて有害化学物質の全廃に取り組むことを宣言しました。2021年の調査では多くのブランドが自社施設の9割から有害化学物質を排除できていることがわかりました。この取り組みは、製造過程での環境負荷を減らすだけでなく、労働者の健康被害を防ぐことにもつながっています。
ZARAは、オーガニックコットンや再生ポリエステルなどのサステナブル素材を使用する取り組みを行い、水と化学物質の使用を大幅に削減することに成功しました。同ブランドは、Join Lifeというコレクションを展開しており、環境に配慮した素材や製造方法を採用した製品を明確に表示しています。
ユニクロは2020年までに店頭での使い捨てプラスチック包装を85パーセント削減すると発表しており、リサイクルダウンと、リサイクルポリエステルを活用した商品を2020年から発売するとしています。実際に服から服へのリサイクルに挑戦し、リサイクルダウンジャケットなども開発しています。顧客から回収した古着を原料として、新たな製品を作り出す取り組みは、循環型ファッションの実現に向けた重要な一歩です。
政府の取り組みとサステナブルファッション推進
2021年8月に消費者庁、経済産業省、環境省の連携のもと、サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議が発足しました。この会議により、政府レベルでのサステナブルファッションの推進体制が整備されています。環境省は、サステナブルファッション特設サイトを開設し、消費者への情報提供や啓発活動を行っています。また、消費者庁はエシカル消費特設サイトでサステナブルファッション習慣のすすめを掲載し、個人が取り組める具体的な行動を紹介しています。
政府の取り組みは、企業への支援だけでなく、消費者への啓発活動にも力を入れています。サステナブルファッションの意義を広く社会に伝え、個人の行動変容を促すことで、業界全体の変革を後押ししています。また、企業に対しては、環境配慮型の製品開発や循環型ビジネスモデルの構築を支援する施策を展開しており、サステナブルファッションへの転換を促進しています。
繊維リサイクルの最新技術と服から服への取り組み
繊維リサイクルの技術も進化しています。従来は衣類を構成する複数の素材を分離することが難しく、リサイクルが困難でした。しかし、最新の技術では、混合繊維から各素材を分離する技術や、化学的な手法で繊維を分解し、再び原料として利用できる状態にする技術が開発されています。これらの技術革新により、従来は廃棄するしかなかった衣類を、新たな資源として活用できるようになりつつあります。
服から服を作る取り組みは、繊維産業の循環型モデルの象徴です。回収した古着を原料レベルまで分解し、新たな糸や生地として再生することで、バージンポリエステルやバージンコットンの使用を削減できます。この技術は、資源の有効活用だけでなく、製造過程でのエネルギー消費や温室効果ガス排出の削減にも貢献しています。
サーキュラーファッションは、循環型経済の考え方をファッション業界に適用したものです。製品のライフサイクル全体を通じて、資源の価値を最大限に保ち、廃棄物を最小限に抑えることを目指します。具体的には、デザイン段階から製品の長寿命化や修理可能性を考慮し、使用後は回収してリサイクルやアップサイクルするという循環を作り出します。この考え方は、従来のリニアエコノミー、作って使って捨てる経済から、サーキュラーエコノミー、循環型経済への転換を促します。
消費者意識の変化とこれからの選択
消費者庁が令和3年7月に実施したサステナブルファッションに関する消費者意識調査によると、衣服を選ぶ際のサステナブルファッションへの配慮について、半数以上の消費者が特になしと回答しています。これは、サステナブルファッションへの関心はあるものの、実際の購買行動にはまだ結びついていない現状を示しています。一方で、人気の処分方法としては、フリマアプリやリサイクルショップで売る、店舗の回収サービスを利用するといった選択肢が挙げられており、リユースへの意識は高まっていることがわかります。
財務省の2024年の報告によると、ファッション業界は環境負荷の高い産業とされており、SDGsやESG投資の影響から、サステナブルファッションへの関心が高まっています。消費者の衣服選択に関する調査では、ブランド名や流行を重視する傾向は比較的低く、実用性や品質を重視する傾向が見られます。新型コロナウイルスの影響により、アパレル業界の消費者ニーズは変化し、高級志向と低価格志向に二極化する傾向が見られます。この変化は、ファッション消費のあり方を見直すきっかけともなっています。
ファッション業界の今後の展望と私たちにできること
2025年以降、ファッション業界はさらなる変革を迫られるでしょう。消費者の環境意識の高まり、法規制の強化、技術革新の進展により、サステナブルファッションは主流となることが予想されます。企業には、透明性の高い情報開示、トレーサビリティの確保、労働環境の改善、環境負荷の削減など、多角的な取り組みが求められます。一方、消費者には、購入前に本当に必要かを考える、長く着られるものを選ぶ、不要になったものは適切に処分するなど、責任ある消費行動が期待されます。
ファッションレンタル、シェアリング、スローファッションといった新しい消費スタイルの普及により、ファストファッション一辺倒だった市場は多様化し、より持続可能な方向へと進化しています。私たち一人ひとりが、日々の選択を通じて、より持続可能な未来を築いていくことが求められています。サステナブルファッションは一過性のブームではなく、ファッション業界の新たなスタンダードとして定着しつつあります。政府、企業、消費者が一体となって取り組むことで、人と環境に優しいファッション産業の実現が可能となります。
私たちが毎日身につける服は、単なるファッションアイテムではなく、地球環境や世界中の労働者とつながっています。サステナブルファッションとファストファッションの比較を通じて、それぞれの特徴と影響を理解することで、より賢明な選択ができるようになります。完璧なサステナブルファッションの実践は難しくても、できることから少しずつ始めることが大切です。オーガニックコットンの製品を選ぶ、古着を活用する、レンタルサービスを利用する、長く着られる質の良い服を選ぶなど、一人ひとりの小さな行動が、やがて大きな変化につながっていきます。持続可能な未来のために、今日から始められるサステナブルファッションの選択を、ぜひ実践してみてください。

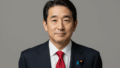

コメント