2025年は税制改正により、多くの働く人々にとって大きな転換点となる年です。給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられ、さらに基礎控除も48万円から95万円へと大幅に増額されます。この二つの控除の引き上げにより、所得税が発生しない年収の上限が従来の103万円から160万円へと拡大することになりました。いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」へと移行するこの改正は、パートタイマーやアルバイトで働く方々、扶養範囲内で働く配偶者、学生アルバイト、そして年金と給与の両方を受け取る高齢者など、幅広い層に影響を及ぼします。年末調整の実務においても、企業の給与担当者は新しい制度に対応した計算や従業員への説明が求められます。この記事では、給与所得控除65万円への引き上げと年末調整における最低保障の仕組みについて、実務に役立つ具体的な情報を詳しく解説していきます。
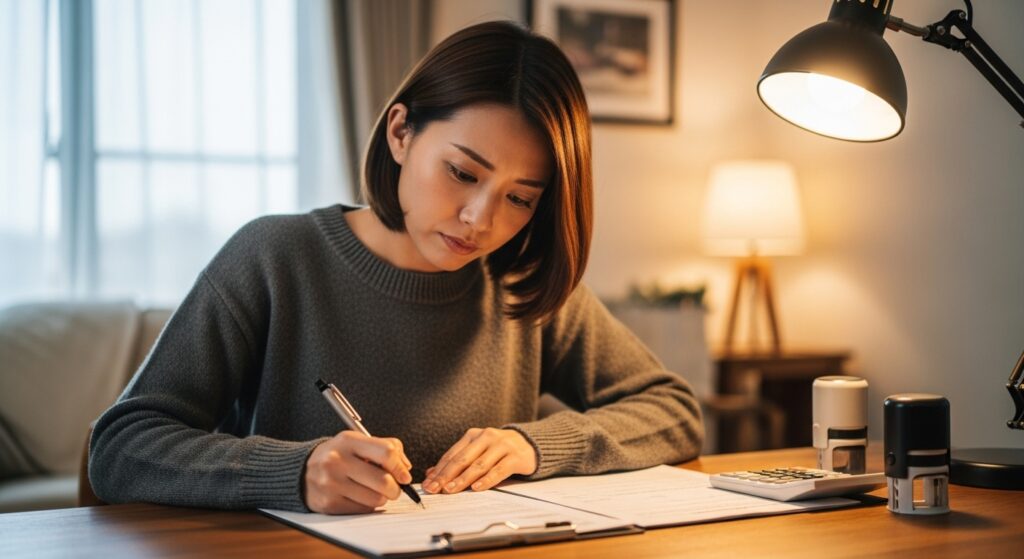
- 給与所得控除の最低保障額が65万円になる背景と意義
- 給与所得控除とは何か:基礎知識の整理
- 最低保障額65万円の具体的な意味と計算方法
- 基礎控除の引き上げと103万円の壁から160万円の壁への移行
- 年末調整における具体的な手続きと注意点
- パートタイマー・アルバイトで働く方への影響
- 学生アルバイトへの影響と勤労学生控除
- 年金受給者が給与所得も得ている場合の取り扱い
- 扶養控除の所得要件緩和と配偶者控除への影響
- 特定親族特別控除の新設:大学生世代への配慮
- 所得税と住民税の違いと住民税への影響
- 企業が準備すべきこと:システム更新と従業員への周知
- よくある質問:実務で疑問に思われるポイント
- 源泉徴収税額表の改正と2026年以降の変化
- 確定申告への影響と注意点
- 今後の税制改正の動向と長期的な視点
- まとめ:2025年の改正を活用して手取り収入を最大化する
給与所得控除の最低保障額が65万円になる背景と意義
令和7年度税制改正大綱において決定された給与所得控除の改正は、2025年12月1日から施行されます。この改正により、年収190万円以下の給与所得者は、収入金額にかかわらず一律で65万円の給与所得控除を受けられるようになります。従来の制度では、年収162.5万円以下で一律55万円の控除でしたから、適用範囲が拡大されただけでなく、控除額そのものも10万円増加したことになります。
この改正の背景には、物価上昇に対する家計支援という明確な政策目的があります。近年のインフレーションにより、食料品や日用品、光熱費などが値上がりし、特に低所得者層の生活が圧迫されている現状があります。給与所得控除と基礎控除を引き上げることで、実質的な減税効果を生み出し、家計の負担を軽減することが意図されているのです。
また、労働供給の増加という経済政策上の狙いもあります。従来は「103万円の壁」を意識して労働時間を抑制していた方々が、160万円まで所得税が発生しないことで、より長く働けるようになります。これにより、深刻化する人手不足の解消や経済の活性化が期待されています。
さらに、税制の簡素化という側面も見逃せません。給与所得控除の最低保障額の適用範囲が162.5万円以下から190万円以下に拡大されることで、より多くの給与所得者が一律の控除額を適用でき、計算がシンプルになるというメリットがあります。複雑な計算式を使わずに済むため、年末調整の実務負担も軽減される効果が期待できます。
給与所得控除とは何か:基礎知識の整理
給与所得控除とは、給与所得者に認められている所得控除の一つで、給与収入から一定額を差し引くことができる仕組みです。個人事業主が事業を行う際に必要経費を計上できるように、サラリーマンやパート、アルバイトなど給与を受け取る人々にも、仕事をするために必要な経費があると考えられています。
具体的には、通勤用のスーツや靴、カバン、名刺入れ、仕事関連の書籍や資料、自己啓発のための研修費用など、実際には様々な経費が発生しています。しかし、これらを個別に領収書を保管して申告するのは非常に煩雑です。そこで、給与収入に応じて自動的に一定額を控除するという簡便な方法が採用されているのが給与所得控除です。
この控除は、確定申告や年末調整で特別な手続きをしなくても自動的に適用されます。給与明細に記載されている総支給額(いわゆる額面給与)から給与所得控除を差し引いた金額が「給与所得」となり、この給与所得を基に所得税が計算される仕組みです。
給与所得控除の金額は、給与収入の額に応じて段階的に設定されています。年収が高くなるほど控除率は下がりますが、控除額の絶対値は増えていく仕組みになっています。ただし、上限も設けられており、年収850万円を超える場合は一律195万円が上限となります。
最低保障額65万円の具体的な意味と計算方法
2025年の改正により、年収190万円以下の場合は、収入金額にかかわらず一律65万円の給与所得控除が適用されます。この「最低保障額」という概念は、どんなに年収が少なくても最低限この金額は控除できるという意味です。
例えば、年収が80万円の場合を考えてみましょう。従来の制度では55万円の給与所得控除が適用され、給与所得は80万円-55万円=25万円でした。新制度では65万円の控除が適用されるため、80万円-65万円=15万円が給与所得となります。給与所得が10万円減少するため、所得税の負担も軽減されます。
年収が150万円の場合はどうでしょうか。従来は150万円-55万円=95万円が給与所得でしたが、新制度では150万円-65万円=85万円となります。ここでも10万円の差が生まれ、その分だけ課税所得が減少します。
このように、年収190万円以下の範囲であれば、どのような金額であっても必ず65万円の控除が保障されるのが「最低保障額」の仕組みです。これにより、低所得者層の税負担が確実に軽減されることになります。
一方、年収が190万円を超える場合には、収入金額に応じた計算式が適用されます。年収190万円超360万円以下の場合は「収入金額×30%+17万円」、年収360万円超660万円以下の場合は「収入金額×20%+53万円」という具合に、段階的に計算式が変わります。例えば年収300万円の場合、300万円×30%+17万円=107万円が給与所得控除額となります。
基礎控除の引き上げと103万円の壁から160万円の壁への移行
給与所得控除の改正と並んで重要なのが、基礎控除の引き上げです。基礎控除とは、すべての納税者に認められる基本的な控除で、所得の種類にかかわらず差し引くことができます。従来は一律48万円でしたが、2025年からは合計所得金額が2485万円以下の場合、95万円に引き上げられます。
この二つの控除を合計すると、給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円となります。つまり、年収160万円までであれば、給与所得控除と基礎控除だけで課税所得がゼロになり、所得税が発生しないということです。
従来は給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円が、所得税が発生しない年収の上限でした。いわゆる「103万円の壁」と呼ばれ、多くのパートタイマーやアルバイトの方々がこの金額を超えないように労働時間を調整していました。配偶者の扶養に入っている方や、学生で親の扶養に入っている方にとって、103万円は重要な基準だったのです。
2025年からは、この壁が160万円に移行します。従来よりも57万円も余裕ができるため、より多くの時間働いても所得税が発生しなくなります。これは、働きたいけれど税金を気にして時間を制限していた方々にとって、大きな朗報と言えるでしょう。
ただし、注意すべき点もあります。所得税の「103万円の壁」が「160万円の壁」になっても、社会保険の扶養要件は変わりません。社会保険の被扶養者となるためには、従来どおり年収130万円未満(一部の条件下では106万円以上で社会保険加入義務)という基準があります。また、企業が独自に設定している配偶者手当や家族手当の支給基準も、自動的に変更されるわけではありません。
年末調整における具体的な手続きと注意点
2025年の年末調整では、この改正後の給与所得控除と基礎控除を適用して税額を精算します。年末調整とは、1年間の給与から源泉徴収された所得税について、年末に正確な税額を計算し直し、過不足を調整する手続きです。
重要なポイントは、今回の改正の施行日が2025年12月1日であることです。つまり、2025年1月から11月までの給与については、従来の制度(給与所得控除55万円、基礎控除48万円)に基づく源泉徴収税額表を使用して源泉徴収が行われます。そして、12月に実施する年末調整の際に、改正後の制度に基づいて1年間の税額を計算し直し、差額を精算する仕組みになっています。
この方法により、多くの給与所得者では、12月の給与支払い時に還付金が発生することが予想されます。特に、年収が103万円超160万円以下の範囲にある方については、1月から11月までは源泉徴収されていた所得税が、年末調整で全額還付される可能性があります。
企業の給与担当者は、給与計算システムや年末調整ソフトウェアが最新の税制に対応しているか確認することが重要です。多くの給与計算ソフトでは、税制改正に対応したアップデートが提供されますので、必ず適用しておく必要があります。また、年末調整申告書の様式も変更される可能性がありますので、国税庁から最新の様式を入手し、従業員に配布する準備が必要です。
従業員側も、扶養控除等申告書や基礎控除申告書などの書類を正確に記入することが求められます。特に、扶養親族の所得要件が変更されているため(後述)、配偶者や子どもの年収を正確に把握して申告する必要があります。記入漏れや誤りがあると、正しく控除が受けられず、本来よりも多くの税金を支払うことになりかねません。
パートタイマー・アルバイトで働く方への影響
パートタイマーやアルバイトで働く方々にとって、今回の改正は非常に大きな影響があります。従来、年収103万円を超えないように労働時間や勤務日数を調整していた方が多くいました。月収に換算すると約8.5万円程度で、週に2〜3日程度の勤務が一般的でした。
2025年からは、年収160万円まで所得税が発生しないため、月収に換算すると約13.3万円まで働けるようになります。週4〜5日のフルタイムに近い働き方も可能になり、より多くの収入を得ることができます。従来よりも月4〜5万円程度多く稼げる計算になり、年間では60万円近い収入増が見込めます。
ただし、いくつかの注意点があります。まず、社会保険の扶養要件は年収130万円未満のままです。年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入する必要が出てきます。社会保険料の負担は決して小さくないため、年収130万円を超えて働く場合は、手取り額がどのくらいになるかを事前に計算しておく必要があります。
また、勤務先が従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上などの条件を満たすと、年収が106万円程度でも社会保険への加入が義務付けられます。いわゆる「106万円の壁」と呼ばれるものです。
さらに、企業が支給している配偶者手当や家族手当の基準も確認が必要です。多くの企業では「配偶者の年収が103万円以下」という条件で手当を支給していますが、この基準が自動的に160万円に変更されるわけではありません。勤務先の就業規則や給与規程を確認し、手当の支給条件を把握しておくことが重要です。配偶者の年収が103万円を超えて手当が打ち切られると、世帯全体の収入が減少する可能性もあります。
学生アルバイトへの影響と勤労学生控除
大学生や専門学校生がアルバイトをする場合にも、今回の改正は大きな影響を及ぼします。学生の場合、勤労学生控除という特別な控除を受けることができます。勤労学生控除は27万円で、一定の条件を満たす学生に適用されます。
基礎控除95万円、給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円を合計すると187万円となります。つまり、勤労学生控除を適用できる学生の場合、年収187万円まで所得税が発生しないことになります。従来は103万円+27万円=130万円が上限でしたから、大幅に余裕ができたことになります。
月収に換算すると約15.5万円まで働けることになり、学費や生活費の足しにするために、より多くの時間をアルバイトに充てることが可能になります。特に、学費が高額になりがちな私立大学や専門学校に通う学生にとっては、家計の負担を軽減する大きな助けとなるでしょう。
ただし、親の扶養から外れるかどうかの判定には注意が必要です。扶養控除の対象となるかどうかは、学生本人の合計所得金額が一定額以下かどうかで判定されます。2025年からは、合計所得金額が58万円以下であれば扶養控除の対象となります。給与収入に換算すると、給与所得控除65万円+58万円=123万円以下です。
したがって、学生が年収123万円を超えて働くと、親の扶養控除の対象から外れ、親の所得税が増加する可能性があります。扶養控除の金額は、一般の扶養親族(16歳以上)で38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の大学生世代)で63万円です。親の所得税率が10%の場合、63万円×10%=6.3万円の税負担増となります。
学生本人は年収187万円まで所得税がかからなくても、年収123万円を超えると親の税負担が増えるため、家計全体で考える必要があります。ただし、後述する「特定親族特別控除」という新しい制度により、年収123万円を超えても一定の控除が受けられる場合があります。
年金受給者が給与所得も得ている場合の取り扱い
年金を受給しながら、パートなどで給与収入も得ている高齢者の方々にとっても、今回の改正は重要です。定年退職後も健康のため、社会とのつながりを保つため、あるいは年金だけでは生活が厳しいため、働き続ける方が増えています。
公的年金には公的年金等控除という控除があり、給与には給与所得控除があります。両方の収入がある場合、それぞれの控除を適用できるため、二重に控除を受けることができます。
65歳未満の場合、公的年金等控除の最低額は60万円です。給与所得控除が65万円になったことで、両方を合わせると125万円の控除を受けられます。さらに基礎控除95万円を加えると、合計220万円の控除となります。
65歳以上の場合、公的年金等控除の最低額は110万円です。給与所得控除65万円と合わせて175万円、基礎控除95万円を加えると合計270万円の控除を受けられます。
例えば、65歳以上の方が年金を年額150万円、給与を年額100万円受け取っている場合を考えてみましょう。年金収入150万円から公的年金等控除110万円を差し引くと、雑所得(年金)は40万円です。給与収入100万円から給与所得控除65万円を差し引くと、給与所得は35万円です。合計所得金額は40万円+35万円=75万円となり、ここから基礎控除95万円を差し引くと、課税所得はゼロとなり、所得税は発生しません。
このように、年金と給与の両方がある場合でも、それぞれの控除と基礎控除を組み合わせることで、かなりの金額まで所得税が発生しない仕組みになっています。高齢者の方々が働きやすい環境が整えられていると言えるでしょう。
扶養控除の所得要件緩和と配偶者控除への影響
扶養親族に関する所得要件も緩和されました。従来、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件は「合計所得金額48万円以下」でしたが、2025年からは「合計所得金額58万円以下」に引き上げられました。
給与収入に換算すると、給与所得控除65万円+合計所得金額58万円=123万円以下となります。従来は103万円以下でしたから、20万円分の余裕ができたことになります。
これにより、扶養親族がパートやアルバイトで働いている場合、従来よりも多くの収入を得ても扶養控除の対象となる可能性があります。例えば、配偶者が年収110万円のパートで働いている場合、従来は103万円を超えているため扶養控除の対象外でしたが、新制度では123万円以下なので対象となります。
扶養控除の金額は、一般の扶養親族(16歳以上)で38万円です。所得税率が10%の場合、38万円×10%=3.8万円の節税効果があります。年収が7万円増えても扶養控除が受けられるのは、家計にとって大きなメリットです。
配偶者控除についても同様の変更があります。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に適用される控除です。2025年からは、配偶者の合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除の対象となります。給与収入に換算すると123万円以下です。従来は103万円以下でしたから、こちらも20万円の余裕ができました。
配偶者控除の金額は、納税者本人の所得金額によって異なりますが、一般的には38万円です。配偶者が年収123万円まで働いても配偶者控除が受けられるため、世帯全体の税負担を抑えながら、より多くの収入を得ることが可能になります。
配偶者特別控除についても見ておきましょう。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内である場合に適用される控除で、所得金額に応じて段階的に控除額が設定されています。2025年からは、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に適用されます。給与収入に換算すると、123万円超201.6万円未満となります。
例えば、配偶者の給与収入が150万円の場合、給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は85万円です。この場合、配偶者特別控除の対象となり、納税者本人の所得金額に応じて一定額の控除を受けることができます。控除額は段階的に減少していきますが、完全にゼロになるまでには相当の余裕があるため、配偶者がかなり働いても世帯全体の税負担が急激に増えることは避けられます。
特定親族特別控除の新設:大学生世代への配慮
2025年度税制改正では、新たに特定親族特別控除という制度が創設されました。これは、扶養控除の所得要件を超えて働く大学生世代などを対象とした新しい控除で、いわゆる「扶養の壁」による労働抑制を緩和する目的があります。
特定親族とは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。給与収入に換算すると、年収123万円超188万円以下の大学生などが該当することになります。
従来の扶養控除の所得要件(合計所得金額58万円以下、給与収入123万円以下)を超えてしまった場合でも、この特定親族特別控除により、一定の控除を受けられるようになります。これは、大学生の子どもがアルバイトで多く稼いだ場合でも、親が一定の控除を受けられるため、家計全体での税負担の急激な増加を緩和できる制度です。
控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。具体的には、合計所得金額が58万円超73万円以下の場合は63万円、73万円超88万円以下の場合は53万円、88万円超103万円以下の場合は43万円、103万円超118万円以下の場合は33万円、118万円超123万円以下の場合は28万円となります。
給与収入で考えると、年収123万円超138万円以下で控除額63万円、138万円超153万円以下で控除額53万円という具合です。特定扶養親族の控除額が63万円であることを考えると、年収が少し増えても同額の控除が受けられるため、税負担の急増を防ぐことができます。
例えば、大学生の子どもがアルバイトで年収130万円を稼いだ場合、給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は65万円です。従来であれば扶養控除の対象外となり、親は控除を一切受けられませんでしたが、新制度では特定親族特別控除として63万円の控除を受けることができます。特定扶養親族の控除額と同額なので、親の税負担は変わりません。
この制度により、大学生は「103万円の壁」や「123万円の壁」を意識せずに、より自由に働くことができるようになります。学費や生活費を自分で稼ぎたいという学生にとって、労働意欲を阻害しない制度設計となっています。
所得税と住民税の違いと住民税への影響
ここまで主に所得税について説明してきましたが、住民税についても理解しておく必要があります。住民税は、都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、前年の所得に基づいて課税される地方税です。
住民税の給与所得控除は、所得税と同じ計算方法を使用します。したがって、2025年分からは住民税の計算においても、給与所得控除の最低保障額が65万円となります。これにより、2026年度の住民税(2025年分の所得に対する住民税)から、新しい控除額が適用されることになります。
ただし、住民税の基礎控除は所得税と異なります。所得税の基礎控除が95万円であるのに対し、住民税の基礎控除は90万円です。所得税と住民税では、基礎控除の金額に5万円の差があることに注意が必要です。
したがって、給与所得控除65万円と基礎控除90万円を合わせた155万円が、住民税が発生しない年収の目安となります。所得税は年収160万円まで非課税ですが、住民税は年収155万円を超えると課税される可能性があります。
また、住民税には均等割と所得割があります。所得割は所得金額に応じて税額が計算されますが、均等割は所得金額にかかわらず一定額(多くの自治体で年間5,000円程度)が課税されます。ただし、均等割にも非課税の基準があり、一定の所得以下の場合は非課税となります。この非課税基準は自治体によって異なりますが、一般的には年収100万円前後となっています。
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、税負担の軽減効果を実感するのは1年遅れとなります。2025年に働いて得た所得に対する住民税は、2026年6月から2027年5月にかけて支払うことになります。この時期になって初めて、給与所得控除と基礎控除の引き上げによる減税効果が住民税にも反映されます。
企業の給与担当者は、住民税の特別徴収(給与天引き)を行う際に、2026年5月頃に市区町村から送付される「特別徴収税額決定通知書」を確認し、従業員ごとの住民税額を給与システムに設定する必要があります。改正による影響で、前年と比べて住民税額が減少する従業員が多くなると予想されます。
企業が準備すべきこと:システム更新と従業員への周知
企業の給与担当者や経理担当者は、2025年の年末調整に向けて、いくつかの重要な準備をする必要があります。適切な準備を怠ると、年末調整で誤った計算をしてしまい、後で修正申告が必要になるなどのトラブルが発生する可能性があります。
まず最も重要なのが、給与計算システムや年末調整ソフトウェアの更新です。多くの給与計算ソフトやクラウドサービスでは、税制改正に対応したアップデートが提供されます。システムベンダーから案内があったら、必ず適用しておく必要があります。特に、給与所得控除の計算ロジック、基礎控除の判定ロジック、特定親族特別控除の計算ロジックなどが変更されるため、システムのアップデートは必須です。
アップデートを適用したら、必ずテスト計算を行うことをお勧めします。サンプルデータを使って、年末調整の計算結果が正しいかどうかを確認しておくと安心です。特に、年収103万円超160万円以下の従業員、扶養親族がいる従業員、大学生世代の子どもがいる従業員など、今回の改正で影響を受けやすいケースについて、重点的に確認しておくと良いでしょう。
次に重要なのが、従業員への周知です。税制改正の内容は複雑であり、多くの従業員にとって理解しづらいものです。説明会の開催、社内通知の発行、Q&A資料の作成などを通じて、改正内容を従業員にわかりやすく伝えることが大切です。
特に説明すべき内容としては、給与所得控除が65万円に引き上げられること、基礎控除が95万円に引き上げられること、年収160万円まで所得税が発生しなくなること、扶養親族の所得要件が58万円以下(給与収入123万円以下)に変更されること、特定親族特別控除という新しい制度が創設されたことなどが挙げられます。
また、年末調整の申告書類の準備も必要です。国税庁から新しい様式の申告書が公表されますので、それを従業員に配布し、期限内に提出してもらう必要があります。申告書の様式や記入方法が変更される可能性があるため、記入例とともに提供すると親切です。
電子申告を導入している企業では、システムの設定変更も必要になるかもしれません。国税庁の「年調ソフト」や民間の給与計算ソフト、クラウドサービスを利用している場合、改正に対応した最新バージョンにアップデートする必要があります。また、従業員向けのマニュアルやヘルプ画面も更新が必要です。
さらに、顧問税理士や社会保険労務士との連携も重要です。複雑な事例や判断に迷うケースについては、専門家に相談しながら適切に処理することが求められます。特に、外国人従業員がいる場合や、役員報酬がある場合、複数の事業所から給与を支払っている場合など、特殊なケースについては、事前に専門家の意見を聞いておくと安心です。
年末調整のスケジュールも確認しておきましょう。2025年は施行日が12月1日となるため、年末調整の時期と重なります。通常よりも業務が集中する可能性があるため、早めの準備と余裕を持ったスケジュール設定が重要です。従業員への申告書配布は11月初旬、提出期限は11月末、年末調整の計算は12月上旬から中旬、源泉徴収票の発行は12月末から1月というスケジュールが一般的です。
よくある質問:実務で疑問に思われるポイント
年末調整の実務において、従業員や企業の担当者から寄せられることが多い質問をいくつか取り上げて、回答していきます。
Q1:2025年1月から11月の給与にも新しい給与所得控除が適用されますか?
A1:制度としては2025年1月1日から適用されますが、施行日が12月1日となっているため、1月から11月までの給与については従来の源泉徴収税額表を使用して源泉徴収が行われます。新しい給与所得控除と基礎控除は、12月に実施する年末調整で反映され、差額が精算されます。
Q2:2024年分の年末調整には新しい控除額は適用されませんか?
A2:いいえ、2024年分の年末調整には旧制度(給与所得控除の最低保障額55万円、基礎控除48万円)が適用されます。新制度が適用されるのは2025年分からです。2024年12月に実施する年末調整では、まだ新しい控除額は使用しません。
Q3:給与所得控除の引き上げで還付金は増えますか?
A3:多くの場合、還付金が増える、または納付額が減ることになります。特に、年収が低めの方や、扶養親族が多い方は、還付金が増える可能性が高いです。ただし、個々の状況(他の所得の有無、各種控除の適用状況など)によって異なりますので、一概には言えません。
Q4:アルバイトやパートでも給与所得控除は適用されますか?
A4:はい、雇用形態にかかわらず、給与所得者であれば全員に給与所得控除が適用されます。アルバイト、パート、契約社員、正社員など、どのような働き方であっても、給与として支払われる収入には給与所得控除が適用されます。
Q5:複数の会社から給与を受け取っている場合はどうなりますか?
A5:複数の会社から給与を受け取っている場合、それぞれの会社では別々に源泉徴収されますが、年末調整または確定申告で合算して計算します。給与収入の合計額に対して給与所得控除を適用します。ただし、年末調整は通常、主たる給与の支払者(扶養控除等申告書を提出した会社)でのみ行われるため、複数の会社から給与を受け取っている場合は、確定申告が必要になることが多いです。
Q6:扶養親族の年収はいつの時点で判定しますか?
A6:扶養親族の年収は、その年の1月1日から12月31日までの収入で判定します。2025年分の年末調整であれば、2025年1月1日から12月31日までの扶養親族の年収が123万円以下(合計所得金額58万円以下)であるかどうかで判定します。12月の時点で見込みの年収を申告し、後で確定した金額と異なる場合は修正が必要になることもあります。
Q7:配偶者手当が103万円基準のままの場合、どうすれば良いですか?
A7:企業の配偶者手当の支給基準は、税制とは独立して定められていますので、勤務先の就業規則や給与規程を確認することが重要です。税制上は年収123万円まで配偶者控除が受けられても、配偶者手当は年収103万円以下という基準のままである可能性があります。配偶者が年収103万円を超えて働く場合、配偶者手当が支給されなくなることで、世帯収入が減少する可能性も考慮に入れる必要があります。
Q8:社会保険の扶養要件も変わりますか?
A8:いいえ、社会保険の扶養要件は変わりません。健康保険の被扶養者となるためには、従来どおり年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)という基準があります。また、勤務先の従業員数や労働時間などの条件によっては、年収106万円程度で社会保険への加入が義務付けられる場合もあります(いわゆる「106万円の壁」)。税制上の扶養と社会保険上の扶養は別の制度ですので、両方を考慮する必要があります。
源泉徴収税額表の改正と2026年以降の変化
年末調整だけでなく、毎月の給与から源泉徴収する際に使用する源泉徴収税額表も改正されます。源泉徴収税額表とは、月々の給与額と扶養親族の数に応じて、どれだけの所得税を天引きするかを定めた表です。
2025年分については、前述のとおり施行日が12月1日となるため、実際に新しい源泉徴収税額表が使用されるのは年末調整の計算時のみとなります。1月から11月までの毎月の源泉徴収は、従来の税額表を使用して行われます。
2026年1月以降に支払われる給与からは、改正後の源泉徴収税額表を使用して、毎月の源泉徴収が行われることになります。新しい税額表では、給与所得控除と基礎控除の引き上げが反映されており、同じ給与額でも源泉徴収される税額が少なくなります。
これにより、2026年以降は、毎月の手取り額が増加することになります。従業員にとっては、毎月の給料日に実感できる減税効果となります。ただし、年末調整で精算される金額(還付金または納付額)が減少するため、年間の税額としては同じですが、月々のキャッシュフローが改善されることになります。
企業の給与担当者は、2026年1月の給与計算から新しい源泉徴収税額表を使用する必要があります。給与計算システムのアップデートを忘れずに行い、正確な源泉徴収を実施することが重要です。
確定申告への影響と注意点
年末調整で完結せずに確定申告が必要な方もいます。例えば、複数の会社から給与を受け取っている方、給与以外に不動産所得や事業所得がある方、年収が2000万円を超える方、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受けたい方などです。
これらの方が2025年分の確定申告を行う際(2026年2月16日から3月15日まで)にも、改正後の給与所得控除と基礎控除が適用されます。確定申告書の様式や記入方法も変更される可能性がありますので、注意が必要です。
特に、給与所得と他の所得(不動産所得、事業所得、雑所得など)がある方の場合、給与所得控除後の給与所得金額の計算方法が変わることで、総所得金額が変わり、各種控除の適用可否や控除額に影響する可能性があります。例えば、配偶者特別控除や扶養控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額以下である場合に適用されるため、給与所得が減少することで控除が受けられるようになるケースもあります。
また、確定申告をする際に使用する源泉徴収票の様式も変更される可能性があります。企業は、2025年分の源泉徴収票を発行する際(2026年1月末まで)に、最新の様式を使用する必要があります。源泉徴収票には、給与所得控除後の給与等の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額などが記載されますが、これらの金額が新しい制度に基づいて計算されているかを確認することが重要です。
年末調整で控除しきれなかった医療費控除や寄附金控除などがある場合、確定申告により還付を受けることができます。2025年分の確定申告では、給与所得控除と基礎控除の引き上げにより課税所得が減少しているため、還付額が従来よりも多くなる可能性があります。
今後の税制改正の動向と長期的な視点
今回の給与所得控除と基礎控除の引き上げは、物価上昇への対応と労働供給の増加を目的とした改正です。しかし、今後も経済情勢や財政状況に応じて、さらなる税制改正が行われる可能性があります。
特に、少子高齢化が進む中で、社会保障費の財源確保が大きな課題となっています。年金、医療、介護などの社会保障給付費は年々増加しており、その財源をどのように確保するかが政策課題となっています。将来的には、消費税の税率引き上げや、所得税・住民税の増税、控除の見直しなどが議論される可能性もあります。
一方で、働き方の多様化に対応した税制の見直しも進められています。フリーランスや副業を持つ人が増える中で、給与所得控除だけでなく、他の所得控除や経費の取り扱いについても見直しが行われる可能性があります。例えば、副業で得た雑所得や事業所得について、必要経費の範囲をどのように定めるか、青色申告の適用範囲をどうするかなどが議論されています。
また、デジタル化の推進も税制に影響を与えています。マイナンバーカードの普及により、確定申告や年末調整の電子化が進められています。将来的には、給与所得控除や基礎控除などの控除が自動的に適用され、納税者が特別な手続きをしなくても正確な税額が計算される仕組みが構築される可能性もあります。
環境税制の導入も議論されています。地球温暖化対策として、炭素税やガソリン税の引き上げなどが検討されています。これらは直接的には所得税とは関係ありませんが、家計全体の税負担に影響を与えるため、給与所得控除などの所得税の控除と合わせて考える必要があります。
従業員も企業も、税制改正の動向を常に注視し、最新の情報をキャッチアップしていくことが重要です。国税庁のウェブサイト、税理士会、商工会議所などが提供する情報を定期的に確認することをお勧めします。また、信頼できる税理士や社会保険労務士と継続的な関係を築き、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
まとめ:2025年の改正を活用して手取り収入を最大化する
2025年の給与所得控除と基礎控除の改正は、多くの給与所得者にとって実質的な減税となる重要な改正です。給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ、基礎控除が48万円から95万円へと引き上げられることで、年収160万円まで所得税が発生しなくなります。
この改正により、低所得者層の税負担が軽減され、より柔軟な働き方が可能になります。特に、パートタイマーやアルバイト、年金と給与の両方がある方、大学生のアルバイトなどにとっては、有利な改正となります。従来の「103万円の壁」が「160万円の壁」に移行することで、税金を気にせずに働ける範囲が大幅に拡大します。
扶養控除の所得要件も緩和され、扶養親族の年収が123万円以下であれば扶養控除の対象となります。さらに、特定親族特別控除という新しい制度の創設により、大学生世代の子どもがアルバイトで多く稼いだ場合でも、親が一定の控除を受けられるようになります。これにより、家計全体での税負担の急激な増加を緩和することができます。
一方で、企業の給与担当者は、給与計算システムの更新や従業員への周知など、適切な準備をする必要があります。施行日が2025年12月1日となっているため、年末調整の時期と重なり、通常よりも業務が集中する可能性があります。早めの準備と余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
従業員個人としても、自分の年収と適用される控除額を確認し、扶養家族の収入を正確に把握することが大切です。年末調整の申告書を正確に記入し、社会保険の扶養要件や企業の手当の支給基準も考慮に入れて、総合的に判断する必要があります。
ただし、注意すべき点もあります。社会保険の扶養要件は年収130万円未満のままであり、企業独自の配偶者手当や家族手当の支給基準も自動的に変更されるわけではありません。税制上は年収160万円まで所得税が発生しなくても、社会保険料の負担が発生したり、企業の手当が打ち切られたりする可能性があります。働き方を決める際には、これらの要素を総合的に考慮することが重要です。
住民税については、基礎控除が90万円であるため、年収155万円を超えると課税される可能性があります。また、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、税負担の軽減効果を実感するのは1年遅れとなります。
源泉徴収票を受け取ったら内容を確認し、疑問点があれば給与担当者に質問することをお勧めします。年末調整で控除しきれなかった場合や、年末調整後に控除の漏れに気づいた場合は、翌年の確定申告で修正することができます。
2025年の税制改正は、働く人にとって有利な改正となっています。この機会を積極的に活用し、適切な税務処理を行うことで、手取り収入を最大化し、家計の改善につなげることができます。税制は複雑で理解しづらい面もありますが、基本的な仕組みを理解し、自分の状況に当てはめて考えることで、最適な働き方を選択することが可能になります。
企業と従業員が協力し、正確な年末調整を実施することで、2025年の税制改正の恩恵を最大限に享受することができるでしょう。今後も税制改正の動向を注視し、最新の情報を常にキャッチアップしていくことが、賢い税務戦略の基本となります。
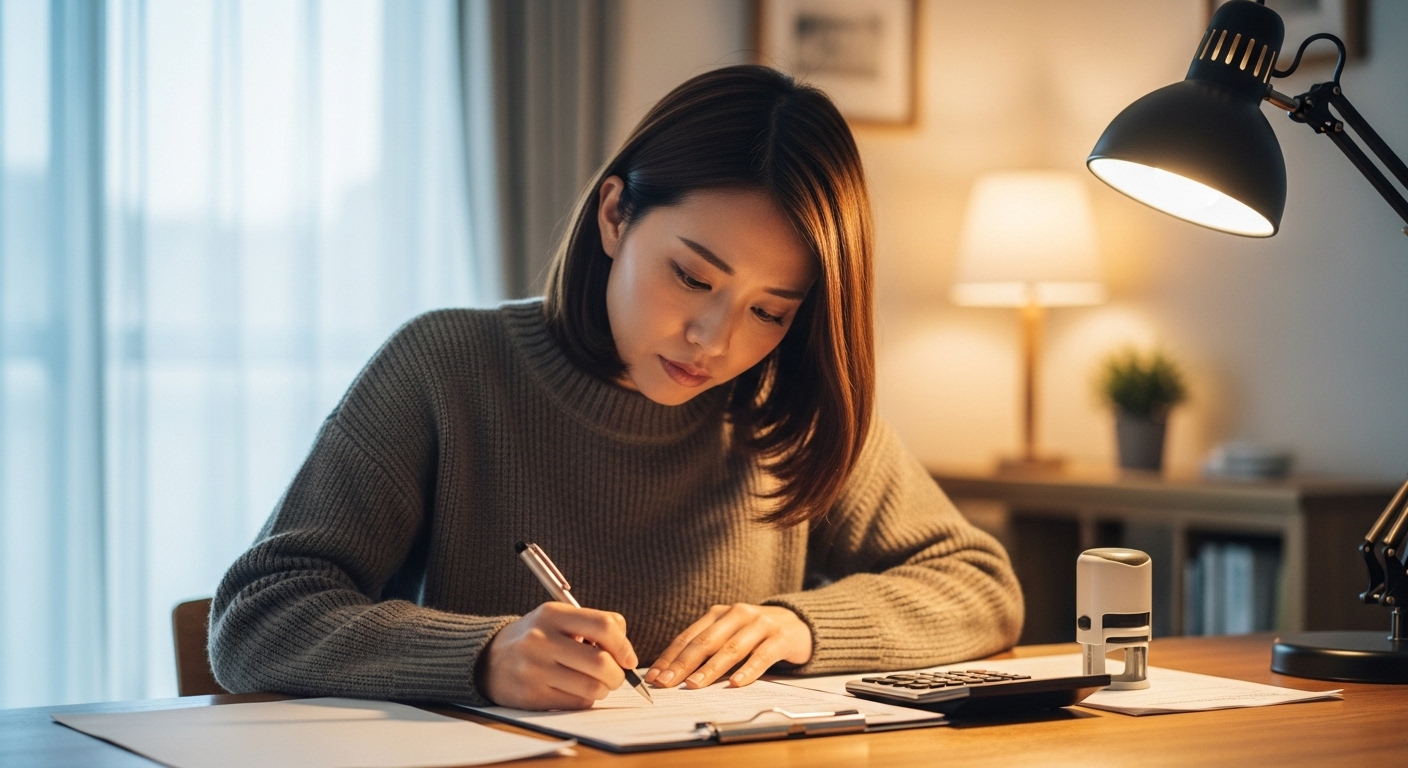
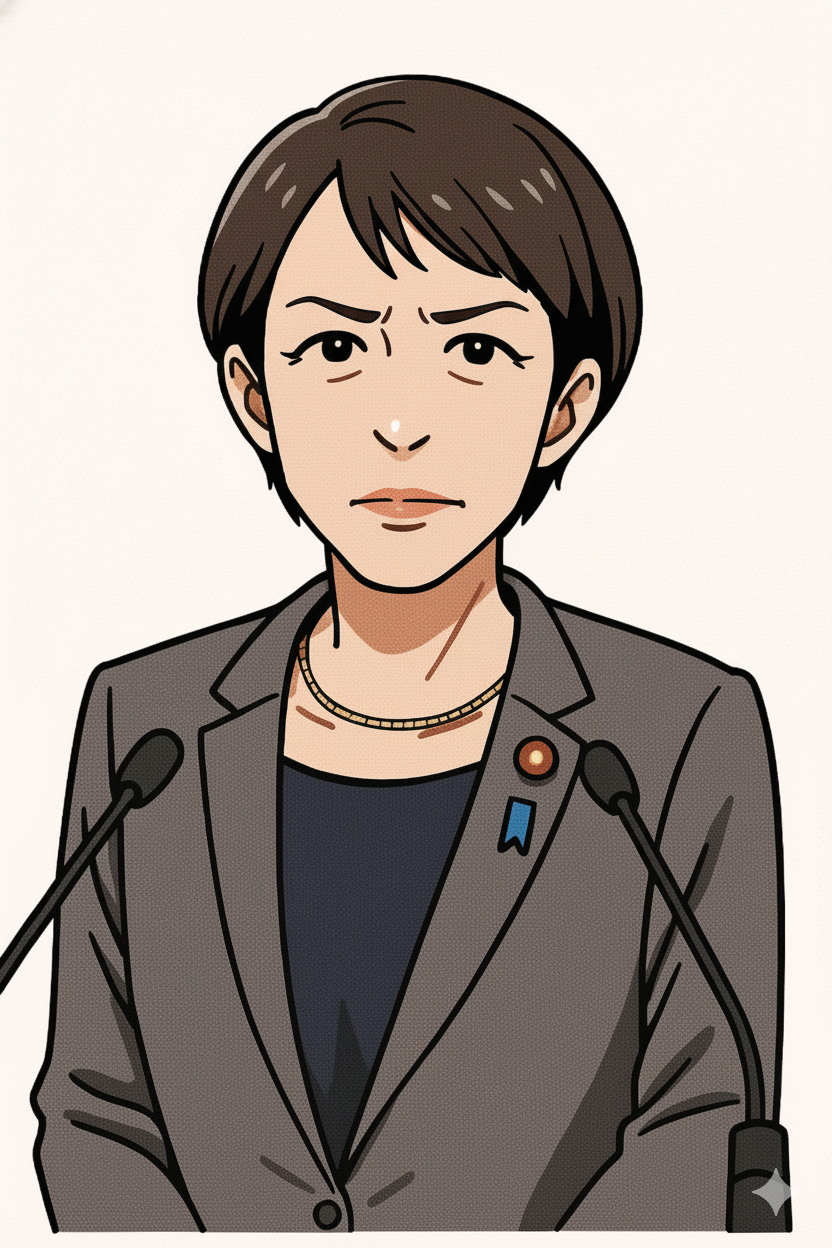

コメント