インターネットやSNSの普及により、誰もが自由に情報を発信できる時代となりました。しかし、その一方で、名誉毀損による逮捕事例も増加しています。もし自分や家族が名誉毀損の容疑で逮捕された場合、身柄拘束期間はどのくらい続くのか、いつまで留置されるのか、いつ釈放されるのか、という疑問は切実な問題です。名誉毀損での逮捕から釈放までの流れを理解することは、適切な対応を取るために極めて重要です。本記事では、名誉毀損で逮捕された場合の身柄拘束期間、釈放のタイミング、早期釈放のための対策について、刑事手続きの流れに沿って詳しく解説します。また、2025年6月からの刑法改正の影響や、実際の逮捕事例も紹介しながら、名誉毀損事件における身柄拘束の実態を明らかにします。SNS時代において、誰もが加害者にも被害者にもなり得る現代社会で、正しい知識を持つことが自分自身と家族を守ることにつながります。
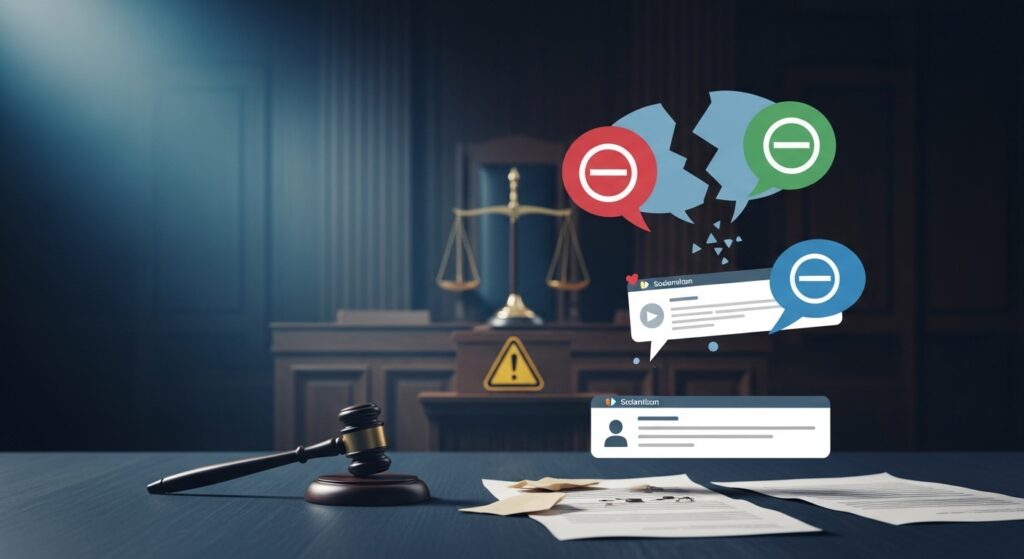
名誉毀損罪の基本と逮捕の可能性
名誉毀損罪は、刑法第230条に規定される犯罪であり、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっており、決して軽微な犯罪ではありません。インターネットやSNSが日常生活に浸透した現代では、ちょっとした書き込みが名誉毀損罪に該当してしまうケースが後を絶ちません。
名誉毀損事件において、実際に逮捕される確率は約10パーセント程度とされています。多くの事件は在宅捜査で進められますが、これは名誉毀損が比較的軽微な犯罪と見なされることや、証拠隠滅や逃亡の恐れが低いと判断されることが理由です。しかし、組織的に誹謗中傷を繰り返している場合、被害者が多数に及ぶ場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合、過去に同様の犯罪歴がある場合などでは、逮捕される可能性が高まります。
特に近年では、SNS上での誹謗中傷に対する社会的な関心が高まっており、警察や検察も厳しい姿勢で臨むようになっています。2024年から2025年にかけても、教諭への誹謗中傷で中学生が逮捕されたケースや、プロ野球選手やオリンピック選手への誹謗中傷で法的措置が取られたケースなど、さまざまな事例が報告されています。
逮捕から勾留までの身柄拘束期間
名誉毀損で逮捕された場合、身柄拘束は段階的に進行します。最初の段階は逮捕直後から48時間以内の期間です。警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。この48時間は警察での留置期間と呼ばれ、警察は取り調べを行い、証拠を収集します。もし48時間以内に送検されない場合は、そのまま釈放されます。
次の段階は送検後から24時間以内です。検察官は、警察から事件を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行うかどうかを決定します。つまり、逮捕から数えて72時間以内に勾留請求の有無が決まることになります。検察官が勾留請求を行わない場合、または裁判官が勾留請求を却下した場合は、この時点で釈放されます。
この72時間は、被疑者にとって非常に重要な期間です。なぜなら、この間に弁護士による適切な弁護活動が行われれば、勾留を回避して早期釈放される可能性があるからです。弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張したりすることができます。
勾留期間の詳細といつまで続くのか
勾留が認められた場合、最初の勾留期間は10日間です。この10日間の勾留期間中、検察官や警察は引き続き取り調べを行い、事件の全容解明に努めます。被疑者は、警察署の留置場または拘置所に収容され、外部との連絡が制限されます。
さらに、検察官の請求により、勾留期間は最大10日間延長される可能性があります。延長が認められるのは、事件が複雑で捜査に時間を要する場合や、共犯者がいる場合などです。つまり、勾留期間は初回10日間プラス延長10日間で合計最大20日間となります。
逮捕時の警察での身柄拘束期間である最大72時間を含めると、起訴されるまでの最大身柄拘束期間は23日間です。この23日間という期間は、被疑者とその家族にとって非常に長く感じられるものです。仕事や学校に行けなくなり、社会生活に大きな支障をきたすことになります。
勾留満期とは、勾留期間が終了する日のことを指します。検察官は、勾留満期までに起訴するか不起訴にするかを決定しなければなりません。この決定が、被疑者の運命を大きく左右することになります。
釈放されるタイミングと可能性
名誉毀損で逮捕された場合、釈放されるタイミングはいくつかのパターンがあります。最も早い釈放は逮捕後48時間以内です。警察が検察官に送致しない場合、48時間以内に釈放されます。これは、証拠が不十分であったり、逮捕の必要性がないと判断されたりした場合に起こります。
次に可能性があるのは逮捕後72時間以内の釈放です。検察官が勾留請求をしない場合、または裁判官が勾留請求を却下した場合、72時間以内に釈放されます。弁護士による適切な弁護活動が功を奏すれば、この段階での釈放が実現する可能性があります。
勾留が決定した後でも、釈放の可能性はあります。勾留中の釈放は、弁護士が裁判所に勾留取消請求や準抗告を行い、それが認められた場合に実現します。また、検察官が処分保留で釈放することもあります。処分保留釈放とは、起訴するかどうかの判断を保留したまま、一旦釈放する措置です。
勾留満期での釈放は、検察官が不起訴処分とした場合に起こります。不起訴処分には、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしの三種類があります。起訴猶予は、犯罪の嫌疑は十分だが諸般の事情を考慮して起訴を見合わせる処分です。名誉毀損事件では、被害者との示談が成立すれば起訴猶予処分となる可能性が高まります。
起訴された場合でも、保釈が認められれば釈放されます。保釈とは、起訴後の被告人が保釈金を納付することを条件に、裁判が確定するまでの間、一時的に身柄拘束を解かれる制度です。名誉毀損罪の場合、比較的保釈が認められやすい傾向にあります。
保釈制度と保釈金の実態
起訴後の釈放を実現するためには、保釈制度を理解することが重要です。保釈が認められる要件は、罪証隠滅の恐れがないこと、逃亡の恐れがないこと、被害者等への危害の恐れがないことです。名誉毀損罪は比較的軽微な犯罪であるため、これらの要件を満たしやすく、保釈が認められる可能性が高いといえます。
保釈金の相場は、一般的に150万円から300万円程度とされています。ただし、実際の金額は被告人の資産状況、犯罪の性質や重大性、社会的影響の大きさ、逃亡や証拠隠滅の恐れの程度などによって大きく変動します。名誉毀損事件でも、被害が甚大であったり、被告人が著名人であったり、高額な収入がある場合は、保釈金が高額になることがあります。
実際の事例として、YouTuberの東谷義和氏の名誉毀損事件では、保釈金が3000万円に設定されました。これは、高額な収入と潤沢な資産があったこと、著名人の名誉を著しく毀損したことなどが考慮された結果です。このように、個別の事情によって保釈金の額は大きく異なります。
保釈金は、裁判所の出納課で現金で納付します。弁護士を通じて納付するのが一般的です。早期釈放を実現するため、保釈許可決定の当日に支払うことが推奨されます。もし保釈金が準備できない場合は、日本保釈支援協会という機関を利用する方法があります。この協会は、手数料の支払いと引き換えに保釈金の立て替えを行っています。手数料は保釈金額の10パーセント程度が相場です。
保釈金は、刑事裁判が終了し判決が確定した後、原則として全額返還されます。ただし、保釈中に逃亡した場合、正当な理由なく公判に出頭しなかった場合、証拠隠滅を図った場合、被害者や証人に接触した場合、住居制限などの保釈条件に違反した場合は、保釈金が没収されることがあります。保釈条件をしっかり守れば、有罪判決を受けた場合でも保釈金は返還されます。
早期釈放を実現するための具体的対策
名誉毀損で逮捕された場合、早期釈放を実現するためには、適切な対応が不可欠です。最も重要なのは、逮捕直後から弁護士を選任することです。国選弁護人を待つのではなく、早期に私選弁護人を選任することで、より迅速な対応が可能になります。弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会でき、適切なアドバイスを提供します。
弁護士による勾留阻止活動も重要です。弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張したりします。具体的には、被疑者に逃亡の恐れがないこと、証拠隠滅の恐れがないこと、定まった住居があること、家族の監督が期待できることなどを主張します。
もし勾留が決定した場合でも、弁護士は勾留取消請求や準抗告を行い、勾留決定を取り消すよう求めることができます。勾留取消請求は、勾留の理由や必要性が失われた場合に行う手続きです。準抗告は、勾留決定自体に不服がある場合に、上級の裁判所に対して行う不服申立てです。
名誉毀損事件では、被害者との示談が早期釈放や不起訴処分につながる最も有効な手段です。弁護士を通じて被害者に謝罪し、適切な賠償を行うことで、被害者の処罰感情が和らぎます。示談が成立すれば、検察官は起訴猶予処分とする可能性が高くなります。また、示談成立は勾留の必要性を低下させる事情としても考慮されるため、早期釈放につながります。
示談金の相場は、名誉毀損事件の内容や被害の程度によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度とされています。被害者が有名人や企業の場合は、より高額になることがあります。示談交渉は専門的な知識が必要であり、加害者本人が直接被害者に接触すると、かえって事態を悪化させる可能性があるため、必ず弁護士を通じて行うべきです。
身柄拘束中の面会と差し入れについて
家族が逮捕された場合、面会できるかどうかは身柄拘束の段階によって異なります。逮捕直後から最大72時間は、家族であっても原則として面会することができません。この期間は捜査の初期段階であり、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐため、外部との接触が厳しく制限されています。
ただし、弁護士だけは例外で、逮捕直後からいつでも面会できます。これは憲法で保障された弁護人依頼権に基づく重要な権利です。弁護士は24時間いつでも接見可能であり、立ち会いなしで秘密が守られ、回数や時間の制限もなく、事件について自由に話し合えます。このため、逮捕直後に弁護士を選任することが非常に重要なのです。
勾留が決定した後は、家族や友人も面会できるようになります。ただし、面会時間は平日の日中に限られることが多く、土日祝日は面会できないことが多いです。1回の面会時間は15分から30分程度で、面会は警察官または刑務官の立ち会いのもとで行われ、会話内容は監視されます。また、事件に関する話題は禁止されます。
勾留後であっても、裁判所が接見禁止の決定を下した場合は、弁護士以外の人との面会が一切禁止されます。接見禁止は、被疑者が容疑を否認している場合、共犯者がいる事件で口裏合わせの恐れがある場合、被害者や証人への働きかけの恐れがある場合、組織的な犯罪の場合などに付されることがあります。名誉毀損事件では通常は接見禁止がつくことは少ないですが、組織的に誹謗中傷を行っていた場合や複数の被疑者がいる場合には接見禁止となる可能性があります。
逮捕・勾留中の家族に対して、日用品や現金を差し入れることができます。差し入れ可能な物品は、衣類、タオルや洗面用具、現金、書籍や雑誌、筆記用具や便箋などです。一方、差し入れができない物品は、食べ物や飲み物、刃物類、電子機器、事件に関する資料などです。差し入れの方法は、警察署や拘置所の受付窓口で手続きを行います。施設によってルールが異なるため、事前に問い合わせることをお勧めします。
2025年6月からの刑法改正の影響
2022年に成立した改正刑法により、2025年6月1日から、従来の懲役と禁錮が統合され、新たに拘禁刑という刑罰が導入されました。これにより、名誉毀損罪の法定刑も3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。
この改正の目的は、受刑者の改善更生と円滑な社会復帰をより効果的に促すことです。従来の懲役と禁錮の区別は、実務上ほとんど意味がなくなっており、また、受刑者一人ひとりの特性に応じた処遇を柔軟に行うことが困難でした。拘禁刑の導入により、すべての受刑者に対して、刑務作業だけでなく、教育や職業訓練など、さまざまなプログラムを組み合わせた処遇が可能になります。
名誉毀損で有罪判決を受けた場合、初犯であれば罰金刑や執行猶予付き判決となることが多いですが、実刑判決を受けた場合は、この新しい拘禁刑が科されることになります。拘禁刑の導入により、受刑者の社会復帰がより円滑に進むことが期待されています。
在宅捜査で進む場合の流れ
名誉毀損事件の約90パーセントは、逮捕されずに在宅捜査で進められます。在宅捜査とは、被疑者を逮捕せずに、自宅から警察署等に呼び出して取り調べを行う捜査方法です。在宅捜査の場合、日常生活を送りながら捜査に協力することができます。
在宅捜査であっても、警察や検察からの呼び出しには応じる必要があります。正当な理由なく出頭を拒否すると、逮捕される可能性もあります。在宅捜査であることは、事件が軽微であるとか、有罪にならないという意味ではありません。在宅のまま起訴されて裁判になることもあります。
在宅捜査の場合でも、弁護士に相談することが重要です。取り調べでどのように対応すべきか、被害者との示談をどう進めるか、不起訴処分を獲得するにはどうすればよいかなど、専門的なアドバイスを受けることができます。早期に適切な対応を取ることで、不起訴処分を獲得したり、罰金刑で済んだりする可能性が高まります。
SNSでの名誉毀損が成立する条件と注意点
SNS上での書き込みが名誉毀損罪に該当するかどうかは、公然性、事実の摘示、名誉の毀損という三つの要件を満たすかどうかで判断されます。SNSは不特定または多数の人が閲覧可能な媒体であるため、投稿することで公然性の要件を満たします。たとえフォロワーが少数であっても、拡散される可能性があれば公然性が認められます。
事実の摘示とは、具体的な事実を示して名誉を毀損した場合を指します。特定の人物が不倫をしているとか、横領をしたなど、具体的な事実を示す表現が該当します。一方、単なる意見や感想、たとえばその人が嫌いだとか、仕事ができないと思うといった主観的な評価は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に該当する可能性があります。
名誉の毀損とは、社会的評価を低下させる内容である必要があります。人の社会的評価を害する内容であれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損で逮捕されないためには、情報を発信する前にその内容が真実かどうかを十分に確認すること、個人を特定できる情報とともに誹謗中傷を行わないこと、感情的な投稿を避けることが重要です。
一度投稿した内容は、削除しても証拠として残る可能性があります。スクリーンショットやアーカイブなどによって、削除後も証拠が保全されることがあるためです。また、政治家や公人に対する批判であっても、公共の利害に関する場合には表現の自由が認められることがありますが、その場合でも事実に基づいた批判である必要があります。
名誉毀損と侮辱罪の違いと厳罰化
名誉毀損罪と類似した犯罪として、侮辱罪があります。両者の最大の違いは、事実の摘示があるかどうかです。名誉毀損罪は、具体的な事実を摘示して名誉を毀損する犯罪であり、刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。一方、侮辱罪は、事実を摘示せずに人を侮辱する犯罪であり、刑罰は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
具体例を挙げると、ある人が過去に窃盗で逮捕されたことがあると投稿することは、具体的な事実を摘示しているため名誉毀損罪に該当します。一方、その人はバカだとか無能だといった投稿は、事実の摘示がないため侮辱罪に該当します。
2022年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑も厳罰化されました。従来の侮辱罪の法定刑は拘留または科料でしたが、改正後は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となりました。これにより、SNSでの誹謗中傷に対する法的規制が強化されています。
実際の逮捕事例から学ぶ
近年の名誉毀損での逮捕事例を見ると、SNS上での誹謗中傷がいかに深刻な問題となっているかがわかります。2024年11月には、高知市内の公立中学校において、15歳の中学3年生の男子生徒が名誉毀損の疑いで逮捕されました。この生徒は20代の女性教諭を中傷する内容の動画を撮影し、SNSに投稿しました。未成年であっても、SNS上での誹謗中傷行為は刑事責任を問われることを示す事例です。
2024年10月には、プロ野球選手が自身とチームメイトに対するSNS上の誹謗中傷に対して法的措置を講じた事例が報告されています。スポーツ選手を標的とした誹謗中傷は、本人だけでなくチーム全体の名誉も傷つける行為として、厳しく対処されています。また、2024年9月には、殺人犯と噂され長年にわたり誹謗中傷を受け続けた芸能人が法的措置を取った事例があります。インターネット上のデマや根拠のない噂の拡散が、いかに深刻な被害をもたらすかを示す事例です。
2024年8月には、オリンピック選手に対する誹謗中傷の事例が報告されています。国際的な舞台で活躍する選手への中傷は、個人の名誉を傷つけるだけでなく、国家のイメージにも影響を与える可能性があります。これらの事例から、誰もが加害者になり得ることを認識し、SNSでの発信には十分な注意が必要であることがわかります。
略式起訴と略式命令の手続き
名誉毀損事件では、罰金刑で処理される場合、略式起訴という簡易な手続きで進められることがあります。略式起訴とは、検察官が正式な裁判を開かずに、書面による簡易な手続きで罰金刑を求める起訴方法です。100万円以下の罰金または科料に相当する事件で、被疑者が同意した場合に限り、略式起訴が可能です。
略式命令とは、略式起訴を受けた裁判所が、被告人を裁判所に呼び出すことなく、書面審査だけで罰金刑を言い渡す決定のことです。略式命令は、検察官による略式起訴から14日以内に出されます。略式手続きのメリットは、早期に事件が終結すること、身柄拘束が短期間で済むこと、正式裁判のような公開法廷で裁かれることがないこと、プライバシーが保たれやすいことです。
一方、略式手続きのデメリットもあります。罰金刑でも前科がつくこと、執行猶予は付かないこと、争う機会が限られることです。略式命令に不服がある場合、通知を受けた日の翌日から14日以内に、正式裁判を請求することができます。正式裁判を請求すると、通常の刑事裁判が開かれることになります。
前科と前歴の違いと影響
名誉毀損事件で処分を受けた場合、前科や前歴がつく可能性があります。前科とは、有罪判決を受けた経歴のことを指します。罰金刑であっても前科となります。前科がつくと、就職や資格取得などに影響が出る可能性があります。特に、公務員や教員、弁護士や医師などの一部の職業では、前科があると就職や資格取得が困難になることがあります。
前歴とは、逮捕や起訴された経歴のことを指します。不起訴処分となった場合は、前科はつきませんが、前歴は残ります。前歴は前科ほどの影響はありませんが、将来的に別の事件を起こした場合、前歴があることが情状として不利に働く可能性があります。
前科を避ける唯一の方法は、不起訴処分を獲得することです。そのためには、早期に弁護士を選任し、示談交渉を進めることが重要です。示談が成立すれば、起訴猶予処分となる可能性が高まり、前科を避けることができます。
名誉毀損の被害に遭った場合の対処法
自分が名誉毀損の被害に遭った場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。まず、証拠の保全が最優先です。誹謗中傷の投稿やメッセージをスクリーンショットで保存するなど、証拠を確保することが重要です。削除される前に、URLや投稿日時も記録しておきましょう。
次に、SNSやウェブサイトの運営者に対して、投稿の削除を依頼することができます。多くのプラットフォームには、誹謗中傷に対する報告機能が設けられています。悪質な誹謗中傷の場合は、警察に相談することができます。被害届を提出することで、捜査が開始される可能性があります。
法的措置を検討する場合は、弁護士に相談することが推奨されます。弁護士は、発信者情報開示請求や損害賠償請求などの手続きをサポートしてくれます。匿名での誹謗中傷の場合、発信者を特定するために発信者情報開示請求という手続きが必要です。
発信者情報開示請求の流れは、まずコンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を請求し、IPアドレスからアクセスプロバイダを特定し、アクセスプロバイダに対して契約者情報の開示を請求し、発信者を特定後に損害賠償請求や刑事告訴を検討します。2022年に施行されたプロバイダ責任制限法の改正により、開示請求の手続きが簡素化され、発信者の特定がより容易になりました。
まとめと今後の対策
名誉毀損で逮捕された場合の身柄拘束期間は、最大23日間です。内訳は、警察での留置が最大48時間、検察での留置が最大24時間で逮捕から72時間まで、勾留期間が最大20日間で初回10日プラス延長10日となります。ただし、必ずしも最大期間身柄を拘束されるわけではなく、弁護士による適切な弁護活動や被害者との示談により、早期釈放される可能性もあります。
釈放のタイミングは、逮捕後48時間以内、逮捕後72時間以内、勾留中、勾留満期、起訴後の保釈など、複数のパターンがあります。いつまで身柄拘束が続くかは、事件の内容や弁護活動の成果によって異なりますが、早期に適切な対応を取ることで、拘束期間を短縮できる可能性があります。
名誉毀損事件の約90パーセントは在宅捜査で進められており、逮捕されるケースは比較的少数です。しかし、逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。2025年6月からは刑法改正により、懲役と禁錮が統合されて拘禁刑となることも押さえておくべきポイントです。
SNSやインターネットが普及した現代社会では、誰もが加害者にも被害者にもなり得ます。発信する情報には十分注意し、他者の名誉や権利を尊重することが求められます。万が一、名誉毀損の疑いで逮捕された場合や被害に遭った場合は、速やかに専門家に相談することが重要です。適切な法的対応により、身柄拘束期間を短縮し、早期釈放を実現することが可能です。

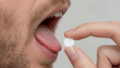

コメント