2025年(令和7年)は、公的年金を受給する多くの方々にとって、税制面で大きな転換点となる年です。特に65歳以上で年金収入が205万円未満の方々は、基礎控除の見直しによって、これまでとは異なる税負担の仕組みに直面することになります。源泉徴収という制度は、毎月の年金から自動的に税金が天引きされる仕組みですが、2025年の税制改正により、その計算方法や負担額が変化する可能性があります。この変化は単なる数字の変更にとどまらず、日々の生活に直結する手取り額に影響を与えるため、正しい知識を持つことが重要です。本記事では、公的年金の源泉徴収制度の基本から、2025年に予定されている基礎控除の見直し、そして65歳以上で年金収入205万円未満の方々が知っておくべきポイントについて、詳しく解説していきます。

公的年金の源泉徴収制度とは何か
公的年金から源泉徴収される税金は、所得税と復興特別所得税の合計です。毎月の年金支給額から自動的に天引きされるこの制度は、年金受給者が自ら税金を納付する手間を省くために設けられています。しかし、この源泉徴収額がどのように計算されているのかを理解している方は意外と少ないのが現状です。
源泉徴収の計算では、まず年金の支給額から社会保険料(介護保険料や国民健康保険料など)を差し引きます。その残額に対して、一定の計算式を適用して控除額を算出し、さらにその控除額を差し引いた金額に税率を掛けることで、最終的な源泉徴収税額が決定されます。この一連の計算プロセスは複雑に見えますが、その根底にあるのは「年金生活者の最低限の生活を保障する」という社会政策的な配慮です。
特に65歳以上の年金受給者には、65歳未満の方と比べて有利な控除額が設定されています。これは、高齢期における生活保障を税制面から支えるための仕組みであり、長年にわたって維持されてきた制度です。
65歳という年齢が持つ税制上の意味
日本の税制において、65歳という年齢は極めて重要な境界線として機能しています。公的年金等控除額は、65歳未満の受給者の場合は最低保証額が60万円に設定されていますが、65歳以上になると一気に110万円へと跳ね上がります。この50万円の差は決して小さくありません。
なぜこのような年齢による差が設けられているのでしょうか。それは、65歳以上の方々が現役世代のように他の収入源を得ることが難しく、年金が主要な生活資金となるケースが多いためです。この110万円という控除額は、年金収入から自動的に差し引かれる「非課税枠」として機能し、実質的な税負担を軽減する役割を果たしています。
例えば、年金収入が年間180万円の方の場合、公的年金等控除110万円を差し引くと、残りは70万円となります。この70万円が雑所得として計算され、さらにここから基礎控除などの各種控除が差し引かれることになります。現行制度では基礎控除が48万円ですので、70万円から48万円を引いた22万円が課税対象の所得となり、ここに税率が適用されるという仕組みです。
205万円未満という境界線の重要性
年金収入が205万円未満という数字は、税制と社会保障の両面において重要な意味を持っています。この金額帯の受給者は、日本の年金受給者の中で最も多くの割合を占める層であり、いわば年金制度のボリュームゾーンといえます。
源泉徴収の実務において、月額の年金支給額が一定額以下の場合、源泉徴収税額が発生しない、あるいは極めて少額にとどまる仕組みになっています。具体的には、65歳以上の方の場合、月の年金支給額から社会保険料を控除した後の金額が約165,000円以下であれば、源泉徴収税額はゼロと計算されます。これを年額に換算すると、おおむね200万円前後となり、205万円未満という数字の意味が見えてきます。
この層の方々は、源泉徴収による税負担が比較的軽い、あるいはゼロであることが多い一方で、わずかな収入増や制度変更によって課税ラインを超えてしまうリスクも抱えています。そのため、税制改正の影響を最も敏感に受ける層でもあるのです。
2025年の基礎控除見直しがもたらす影響
2025年に向けて議論されている最も重要な税制改正が、基礎控除の引き上げです。基礎控除は、すべての納税者が一律に所得から差し引くことができる控除であり、現行では48万円に設定されています。しかし、近年の急激な物価上昇やエネルギー価格の高騰により、この48万円という水準では最低限度の生活を維持するための経費として不十分だという認識が広がっています。
政府・与党内では、基礎控除を58万円程度に引き上げる案が検討されているとされています。もしこの改正が実現すれば、年金受給者にとっては大きな恩恵となります。なぜなら、基礎控除が10万円増えることで、課税対象となる所得が10万円分減少し、その結果として所得税の負担が軽くなるか、あるいは非課税になる可能性があるからです。
具体的に計算してみましょう。現行制度では、65歳以上の方が所得税非課税となる年金収入のラインは、公的年金等控除110万円と基礎控除48万円を合計した158万円です。しかし、基礎控除が58万円に引き上げられれば、このラインは168万円へと上昇します。つまり、年金収入が158万円から168万円の間にある方々は、改正後に所得税が非課税になるという大きなメリットを享受できることになります。
さらに、一部の野党からは基礎控除をより大幅に引き上げるべきだという提案も出されています。もし基礎控除が75万円程度まで引き上げられた場合、非課税ラインは185万円まで上昇し、205万円未満の層のかなりの部分が所得税の負担から完全に解放される可能性もあります。
源泉徴収税額の計算メカニズム
源泉徴収税額がどのように計算されるのかを理解することは、自分の手取り額を正確に把握するために重要です。65歳以上の年金受給者の場合、源泉徴収税額は次のようなプロセスで算出されます。
まず、その月の年金支給額から社会保険料等を差し引きます。次に、その残額に対して「年金支給額の25%プラス10万円」という計算式を適用して控除額を算出します。ただし、この計算結果が165,000円未満となる場合は、一律で165,000円が控除額として適用されます。
この仕組みにより、月額の年金支給額が165,000円以下の方は、課税対象となる所得がゼロと計算されるため、源泉徴収税額も発生しません。しかし、年金支給額がこのラインをわずかに超えると、突然税金が天引きされるようになるため、手取り額の逆転現象を感じる方もいらっしゃいます。
さらに、源泉徴収される税金には、所得税本則の5%に加えて、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が上乗せされています。そのため、実際の税率は5.105%となります。この0.105%という端数は一見わずかですが、計算を複雑にしており、特に205万円未満の層では、わずかな収入の増減が課税・非課税の境界をまたぐ原因となっています。
扶養親族等申告書の重要性
年金を受給している方の多くは、毎年秋頃に日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という緑色の封筒が届くことをご存じでしょう。この申告書は、源泉徴収税額を正しく計算するために必要不可欠な書類です。
2025年の基礎控除見直しに伴い、この申告書の記載内容も変更されます。特に重要なのが、配偶者や扶養親族として認められるための所得要件の緩和です。現行では、配偶者や扶養親族の合計所得金額が48万円以下である必要がありますが、基礎控除の引き上げに連動して、この要件が58万円以下に緩和される見込みです。
この変更は実務上、非常に大きな意味を持ちます。例えば、配偶者がパート勤務をしており、年収が110万円の場合を考えてみましょう。給与所得控除55万円を差し引くと、所得は55万円となります。現行制度では、この55万円は48万円を超えているため、配偶者控除の対象とはなりませんでした。しかし、改正後は所得要件が58万円に緩和されるため、年収110万円の配偶者も配偶者控除の対象として申告できるようになります。
さらに、給与所得控除自体も55万円から65万円に引き上げられる可能性があります。もしこれが実現すれば、年収が123万円以下の配偶者まで扶養親族として認められることになり、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」へと後退することになります。これは、年金受給者世帯において配偶者がパート勤務をしているケースにおいて、世帯全体の手取り額を大きく押し上げる効果をもたらします。
ただし、制度が有利に変更されても、受給者自身がそれを認識し、正しく申告しなければ恩恵を受けることはできません。特に高齢者世帯では、「配偶者の収入が少し増えたから、もう扶養には入れないだろう」という過去の思い込みや、古い知識に基づいた自己判断が横行しています。2025年の改正においては、新しい基準値を確認し、該当する場合は必ず申告書に記載することが重要です。
住民税非課税世帯という重要な概念
年金受給者にとって、所得税以上に生活に直結するのが住民税の課税・非課税判定です。住民税が非課税になるかどうかは、国民健康保険料の軽減、介護保険料の段階区分、さらには各種給付金の受給資格に直接関わってくるため、まさに死活問題といえます。
単身の65歳以上年金受給者が住民税非課税となるボーダーラインは、一般的に155万円とされています(1級地の場合)。この金額は、公的年金等控除110万円と住民税の非課税限度額(基礎控除相当)45万円を合計した数字です。ここで注意が必要なのは、所得税の基礎控除48万円と、住民税の非課税判定に使われる数字45万円は異なるという点です。
2025年の改正で所得税の基礎控除が引き上げられた場合、住民税の非課税ラインも連動して上昇する可能性が高いと考えられます。通常、税制改正においては国税(所得税)と地方税(住民税)の整合性が図られるためです。もし住民税の基準も10万円引き上げられれば、155万円の壁は165万円へとシフトします。
これにより、これまで年金収入160万円程度で住民税を負担していた方々が、一気に完全非課税の領域に移行することになり、社会保障負担の劇的な軽減を享受できる可能性があります。住民税が非課税になると、国民健康保険料の軽減措置が受けられるほか、介護保険料も大幅に安くなるため、年間で数万円から十数万円の負担減となることも珍しくありません。
夫婦世帯における211万円の壁
夫婦で年金を受給している世帯においては、「211万円の壁」という概念が重要になります。これは、世帯主の年金収入が211万円以下であり、かつ配偶者が非課税である場合、世帯全員が住民税非課税となるラインを指します。
この数字は、住民税の非課税基準額の算定式に基づいています。具体的には「35万円×(本人プラス被扶養者数)プラス31万円」という計算式が用いられます(級地により異なる場合があります)。夫婦2人世帯の場合、この基準額が高くなるため、世帯主の年金収入が211万円までなら非課税の枠内に収まるのです。
今回のキーワードである「205万円未満」という層は、まさにこの211万円の壁の内側に位置しています。つまり、この層に属する年金受給者は、適切な申告(扶養親族等申告書での配偶者記載など)を行うことで、住民税非課税世帯のメリットを最大限に活用できる黄金のゾーンにいるといえます。
ここで見落としてはならないのが、遺族年金や障害年金は非課税所得であるという点です。例えば、老齢年金が180万円で遺族年金が50万円を受給している場合、合計収入は230万円ですが、税務上の判定対象は老齢年金の180万円のみとなります。この非課税年金の存在を考慮せずに「自分は収入が多いから非課税にはならない」と諦めている方も多いのですが、実際には205万円未満の枠内で非課税判定を受けられるケースが多々あります。
介護保険料への影響と80万9千円への改定
年金からの天引きにおいて、税金以上に重い負担感を伴うのが介護保険料です。2025年4月からの制度改正により、介護保険料の所得段階を決定する基準額の一部が、80万円から80万9千円に変更されることが決定されています。
なぜ9千円という中途半端な数字なのかと疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。これは、近年の年金支給額の改定(プラス改定)に対応するための微調整です。年金支給額は物価や賃金の上昇に合わせてスライド改定されますが、介護保険料の段階区分が固定されていると、年金が数千円増えただけで基準額を超えてしまい、介護保険料のランクが上がってしまうという問題が生じます。
その結果、「年金は増えたが、保険料天引きが増えて手取りが減った」という逆進的な現象が発生してしまいます。80万9千円への変更は、このようなインフレ調整措置であり、年金の名目増が実質的な負担増につながらないようにするための防波堤なのです。
介護保険料は所得に応じて細かく段階分けされており、標準で9段階、自治体によっては15段階以上に分かれています。年金収入205万円前後の層は、通常「第5段階(基準額)」や「第6段階」といった、平均的な保険料を負担する層に該当します。
しかし、基礎控除の見直しによって住民税が「課税」から「非課税」に変わると、介護保険料の計算ロジックが根本から変わります。住民税非課税世帯は介護保険料の第1段階から第3段階に区分されることが多く、保険料は基準額の0.3倍から0.7倍程度に激減します。つまり、年金収入が同じ205万円であっても、税制改正によって住民税が非課税になれば、介護保険料だけで年間3万円から5万円の手取り増となる可能性があるのです。
在職老齢年金と社会保険の適用拡大
年金を受け取りながら働く「在職老齢年金」受給者にとって、2025年以降の社会保険適用拡大も重要な論点です。これまで、従業員数51人以上の企業で働くパートタイマーに適用されていた社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が、さらに小規模な企業へと拡大される議論が進んでいます。
週20時間以上働き、月額賃金が88,000円(年収約106万円)を超える場合、社会保険への加入が義務付けられます。これにより、給与から厚生年金保険料と健康保険料が天引きされるため、手取り収入は減少します。一方で、将来受け取る年金額が増えるというメリットもありますが、65歳以上の高齢者にとっては「将来の増額」よりも「現在のキャッシュフロー」の方が切実な場合が多いのが実情です。
205万円未満の年金に加えてパート収入を得ている層は、この「106万円の壁」と「税金の壁」の狭間で、極めて難しい就労調整を迫られることになります。特に、給与所得控除の引き上げによって「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わる可能性がある中で、社会保険の適用ライン(106万円)がどこに設定されるかは、働く高齢者にとって重大な関心事となっています。
確定申告不要制度の正しい理解
公的年金等の収入が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。この「確定申告不要制度」は、年金受給者の手間を軽減するための制度ですが、誤解されやすいポイントでもあります。
確定申告が不要であるからといって、「扶養親族等申告書も出さなくていい」と拡大解釈している受給者が後を絶ちません。しかし、この申告書を提出しなかった場合、源泉徴収税率は各種控除が適用されない、事実上の高い税率で計算されてしまうリスクがあります。
具体的には、扶養親族等の数が0人として扱われ、配偶者控除等の適用が漏れてしまいます。また、データが市町村に正しく連携されず、住民税が高額に算定されるという「データ連携の事故」を招く原因ともなります。確定申告が不要であっても、扶養親族等申告書は必ず提出することが、正しい税額で源泉徴収を受けるための鉄則です。
級地制度による地域格差
住民税の非課税ラインは、居住する自治体の「級地」によって異なります。東京23区や大阪市などの大都市(1級地)では155万円が基準ですが、地方の町村(3級地)ではこの基準が下がり、148万円程度で課税されてしまうことがあります。
この地域格差は、同じ年金額を受給していても、住んでいる場所によって税負担が異なるという不公平感を生んでいます。2025年の改正で基礎控除が一律に引き上げられれば、この地域格差による不公平感も一定程度緩和される可能性がありますが、依然として「どこに住むか」が手取り額を左右する状況は続くと考えられます。
自分の住む自治体がどの級地に該当し、非課税ラインがいくらなのかを確認することは、税制改正の恩恵を正しく受けるために不可欠です。多くの自治体では、ホームページ上で住民税の非課税基準を公開していますので、一度確認してみることをお勧めします。
実務における混乱と対応策
2025年のこれら一連の税制改正は、実務を担う自治体や年金事務所に甚大な事務負担を強いることになります。特に、基礎控除の引き上げ幅が年末ギリギリまで確定しない場合、システム改修が間に合わず、年度初めの源泉徴収や住民税決定通知に混乱が生じるリスクがあります。
過去には、定額減税の実施時に通知書の記載ミスや計算誤りが散見されました。2025年も同様に、6月に届く「年金振込通知書」や「住民税決定通知書」の内容に誤りが含まれている可能性を排除できません。通知書が届いたら、記載内容を鵜呑みにせず、計算根拠を自分なりに確認する姿勢が重要です。
また、マイナンバー制度の普及により行政機関同士の情報連携は進んでいますが、扶養親族の状況に関しては依然として受給者本人からの申告がベースとなっています。「配偶者の収入が減った」という事実は、自動的には年金事務所に伝わりません。特に205万円未満の層においては、配偶者もまた低年金であったり、パート就労をしていたりと、所得状況が変動しやすいため、アナログな紙の申告書を正しく書くことが、デジタル社会においても最強の自衛手段であり続けます。
2025年を賢く乗り切るための3つの行動
2025年は、日本の年金税制における基礎控除という岩盤が動く歴史的な年となります。65歳以上で年金収入205万円未満という、日本社会の最大のボリュームゾーンを形成する年金受給者にとって、この改正は一見すると複雑怪奇なパズルのように見えるかもしれません。しかし、その本質を突き詰めれば、非課税枠の拡大という明確なメッセージが浮かび上がります。
基礎控除の引き上げは、インフレによる生活費増大に対する政府の「せめてもの回答」です。この回答を正しく受け取り、自らの生活防衛につなげるためには、以下の3つのアクションが不可欠となります。
第一に、自らの年金収入と所得を再計算することです。年金収入から公的年金等控除110万円を差し引いた額が雑所得となり、そこからさらに基礎控除を差し引いた額が課税対象となります。新しい基礎控除額(仮に58万円)を用いて、自分が課税されるのか、非課税になるのかを把握しましょう。
第二に、配偶者のパート収入や年金収入を精査することです。基礎控除の引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除の所得要件も緩和されます。これまで「収入が多いから控除は受けられない」と思い込んでいた方も、改めて確認してみる価値があります。103万円の壁が123万円へと後退する可能性があることを念頭に、配偶者の働き方についても再検討してみましょう。
第三に、役所から届く通知書を鵜呑みにせず、計算根拠を疑うリテラシーを持つことです。過去の経験から、制度改正の初年度には計算ミスや通知の誤りが発生しやすいことが分かっています。自分で計算できる部分は確認し、不明な点があれば年金事務所や市区町村の税務課に問い合わせる姿勢が重要です。
インフレ時代の年金生活を守るために
2025年の税制改正は、インフレ経済下における高齢者の「生存権保障ライン」の再定義という側面を持っています。物価高騰が続く中で、固定的な控除額では最低限度の生活すら維持できないという現実に対応するための措置です。
しかし、制度がどれだけ有利に変更されても、それを知らなければ、あるいは正しく申告しなければ、恩恵を受けることはできません。源泉徴収という自動的な徴収システムに身を任せるだけでなく、自らの手で申告書というコントロールレバーを正しく操作することで、手取り額を最大化し、インフレの波を乗り切ることができます。
65歳以上で年金収入205万円未満という層は、税制改正の恩恵を最も受けやすい位置にいます。同時に、わずかな申告漏れや制度の理解不足によって、本来受けられるはずの軽減措置を逃してしまうリスクも抱えています。この記事で解説した知識を活用し、2025年の税制改正を味方につけて、安心できる年金生活を実現していただければ幸いです。

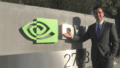

コメント