生活保護制度に対する「若者には条件が厳しい」という認識が広く存在していますが、これは大きな誤解です。2025年7月現在、生活保護の受給条件は年齢に関係なく、若者も高齢者も同じ基準で判断されます。実際には、制度そのものよりも運用面での不適切な対応や、制度への理解不足が「厳しい」という印象を生んでいるのが現状です。
近年、精神疾患やひきこもり、家族からの支援が得られないなどの理由で生活保護を必要とする若者が増加しています。しかし、受給資格がある世帯のうち約80%が生活保護を利用していないというデータも存在し、これは制度の周知不足や心理的障壁、行政窓口での不適切な対応が原因と考えられています。
本記事では、生活保護制度の実態と若者が直面する課題、そして2025年に実施された制度改正による支援強化について詳しく解説します。正しい知識を持つことで、本当に困っている若者が適切な支援を受けられる社会の実現を目指しましょう。
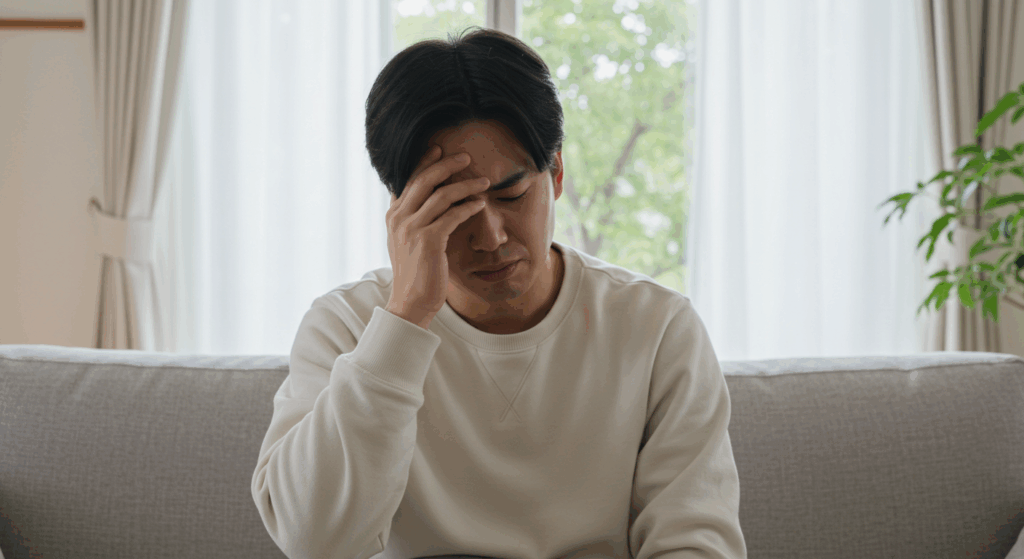
Q1: 生活保護は若者にとって本当に条件が厳しいのか?制度の実態とは
生活保護の基本原則は年齢に関係なく同じです。厚生労働省が定める基準によって算定される「最低生活費」と比較して、世帯の収入が低い場合、その差額が生活保護費として支給されます。収入が全くない場合は、最低生活費と同額が支給される仕組みです。
主な受給条件は以下の通りです:
世帯収入が最低生活費を下回っていることが最も重要な条件です。最低生活費は地域ごとの物価や世帯構成、年齢、障害の有無などによって異なります。例えば、東京23区で一人暮らしをする45歳の最低生活費は13万5,140円、愛知県名古屋市で一人暮らしをする20代では11万6,230円となっています。
預貯金や高価な資産がないことも条件の一つですが、すべての資産を手放す必要はありません。1〜10万円程度の預金や、住宅ローンを完済した自宅、エアコン、冷蔵庫、スマートフォンなどの生活必需品は所持が認められます。自動車やバイクも、交通の便が悪い地域で他に移動手段がない場合は所持可能です。
病気や怪我、障害などが原因で働けない状況については、診断書や障害者手帳があると申請がスムーズに進みます。外見からは分かりにくい精神疾患を患っている若者も、この条件に該当します。
他の制度を利用しても生活費が足りないことも重要な要件です。年金や失業保険などの公的制度を優先的に活用し、それでも最低生活費に満たない場合に生活保護が適用されます。
「厳しい条件」という誤解の背景には、行政窓口での不適切な対応があります。群馬県桐生市では実際には扶養からの仕送りがないにもかかわらず収入認定を行い申請を却下する事案が多数確認されました。また、奈良県生駒市では認知症の母親に扶養の意思があることを根拠に申請を却下しましたが、後に地方裁判所で却下処分が違法と判断される事例もありました。
これらの事例は、制度そのものが厳しいのではなく、運用において不適切な障壁が設けられている現状を示しています。本来の制度は、憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための最後のセーフティネットとして機能すべきものなのです。
Q2: 若者が生活保護を受給する際の具体的な条件と申請プロセスは?
若者が生活保護を必要とする背景には、多様で複雑な事情があります。精神疾患を患って働けないケースが近年特に増加しており、外見からは分かりにくいため「怠けている」と誤解されやすいのが現状です。ひきこもり状態にある若者も少なくなく、2023年の調査では15歳から39歳までのひきこもりの割合は増加傾向にあります。
また、周囲に頼れる人がいない状況も深刻です。親族との関係が悪く虐待やDVを受けていた場合や、親族自身も経済的に困窮していて援助が期待できない場合など、家族に頼れない若者は制度の隙間に落ちてしまうことがあります。
申請プロセスは以下の手順で進みます:
まず、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で相談します。住む場所が定まっていない場合でも、現在滞在している地域の福祉事務所で申請可能です。窓口で生活保護を希望する旨を伝えると、経済状況や就労の有無などが聞き取られ、必要と判断されれば申請書が渡されます。
次に、収入や資産、家族構成などの情報を提出します。申請書に記入し提出すると、家庭訪問、資産調査、扶養照会などが行われます。必要書類があれば提出を求められますが、書類が揃わないからといって申請を諦める必要はありません。
審査は基本的に14日以内(最長30日以内)に完了し、決定が通知されます。保護が開始されれば、申請日に遡って生活保護費が支給されます。
万が一、申請窓口で受け付けてもらえなかったり却下されたりした場合でも、生活保護法第7条の「申請保護の原則」により、何度でも繰り返し申請することができます。却下通知書に記載された理由を改善し、再度申請することが重要です。また、却下理由に不服がある場合は、60日以内に審査請求を行うことも可能です。
申請時に重要なのは、正直に現状を伝えることです。収入や資産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、後に不正受給として処罰される可能性があります。一方で、必要以上に遠慮したり、「まだ大丈夫」と無理をしたりせず、本当に困っている状況であれば素直に相談することが大切です。
Q3: 扶養照会とは何か?親族への連絡を避ける方法はある?
扶養照会は生活保護の要件ではありません。これは非常に重要なポイントです。法律では「扶養は保護に優先する」とされていますが、これは「実際に仕送りがあったらその分だけ保護費を減らす」という意味に過ぎず、援助を強制されることはありません。
扶養照会とは、役所が生活保護を申請した人の親や兄弟などの親族に対し、「援助できますか?」と問い合わせを行うことです。親族は援助できる範囲であればすればよく、援助する気持ちや余裕がない場合には断ることができます。親族が援助を断ったとしても、生活保護の利用は可能です。
しかし、現実的には扶養照会への恐れから生活保護の申請を躊躇する若者が多いのも事実です。特に家族との関係が悪化している場合や、親族に経済的負担をかけたくない場合、居場所を知られたくない場合などは深刻な問題となります。
扶養照会を避ける方法も法的に認められています:
虐待やDVなどの事情で親族に居場所を知られると危険な場合は、扶養照会を差し控えてもらうことが可能です。DVの加害者である親族への照会を嫌がる申請者に対して「証拠を持ってこい」という不適切な対応をされるケースもありますが、これは間違った運用です。
長年音信不通の場合や、未成年者、主婦、概ね70歳以上など明らかに仕送りが期待できない場合も扶養照会を差し控える対象となります。
2025年現在でも、扶養照会に関する不適切な運用が全国で報告されています。群馬県桐生市では実際には扶養からの仕送りがないにもかかわらず収入認定(カラ認定)を行い申請を却下する事案が多数確認されました。このような運用は明らかに違法です。
弁護士や有識者らでつくる団体は、厚生労働省の通知にある「要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養およびその他の支援を求めるよう要保護者を指導すること」という部分の改正を求めています。法律上、扶養を求めるかどうかは申請者の自由であり、役所が扶養請求権の行使を義務付ける運用自体が不適切対応の根本原因であると指摘されています。
扶養照会への不安がある場合は、申請時にその旨を正直に相談員に伝えることが重要です。適切な理由があれば照会を避けることができ、安心して生活保護を利用することが可能になります。
Q4: 生活保護を受けている若者が大学進学する際の問題と対策は?
生活保護世帯の子どもたちが直面する最大の課題の一つが、大学進学の壁です。2025年7月現在、日本では大学や専門学校などへの進学率が8割を超える一方で、生活保護世帯の進学率は39.9%と半分以下にとどまっています。
この格差の主な要因は「世帯分離」の必要性にあります。生活保護は世帯ごとに支給され、18歳以上は原則として「就労能力がある」とみなされるため、大学に進学すると「就労能力を活用していない」として生活保護受給の対象外となってしまいます。
そのため、大学に進学するためには住民票を分けて「別世帯」とみなされる「世帯分離」の手続きが必要になります。しかし、この制度には深刻な問題があります。
世帯分離による経済的困窮が最も深刻な問題です。世帯分離をすると、親の生活保護費から自身の分の支給がなくなるため、世帯全体の支給額が減少します。大学の授業料減免や給付型奨学金を受けても、生活費や教材費、予期せぬ出費は自分で賄わなければなりません。
この結果、深夜まで複数のアルバイトを掛け持ちして過労状態になる学生が後を絶ちません。「親ガチャ」や「この世のバグ」といった言葉で表現されるように、環境的要因で教育を享受できなくなる社会構造への疑問が若者たちから投げかけられています。
厚生労働省の部会では「一般世帯にも奨学金やアルバイトなどで学費・生活費を賄っている学生もいる中、一般世帯との均衡を考慮する必要がある」として、生活保護を受けながら大学に通うことは依然として認められていません。
しかし、制度改善の動きも見られます。2024年4月24日に公布され、2024年1月1日に遡って適用されている生活保護法の改正により、高等学校等を卒業後に就職する生活保護受給世帯の子どもに対して、新生活の立ち上げ費用として一時金が支給されるようになりました。自宅外の場合は30万円、自宅の場合は10万円が支給されます。
対策としては以下の方法があります:
まず、奨学金制度の活用が重要です。日本学生支援機構の給付型奨学金や各大学の独自奨学金制度を最大限活用しましょう。また、地域の支援団体への相談も有効です。生活保護世帯の大学進学を支援するNPO法人なども存在します。
進学前の準備も大切です。高校在学中から奨学金の申請準備を進め、アルバイト先の確保や生活費の計画を立てておくことで、世帯分離後の生活を安定させることができます。
最も重要なのは、一人で抱え込まず相談することです。学校のスクールソーシャルワーカーや地域の相談窓口に早めに相談し、利用可能な支援制度を把握しておくことが成功への第一歩となります。
Q5: 2025年最新の生活保護制度改正で若者への支援はどう変わった?
2025年7月現在、生活保護法を含む関連法案の改正が順次施行されており、生活困窮者への自立支援の強化が図られています。特に若者の自立を促進するための取り組みが大幅に強化されています。
最も重要な改正点は、生活困窮者向けの事業への一体的実施の仕組みの創設(2025年4月1日施行)です。これまで生活保護受給者は生活困窮者向けの就労準備支援事業などを利用できませんでしたが、この改正により、将来的に保護脱却が見込まれる「特定被保護者」も、生活困窮者向けの就労準備支援事業、家計改善支援事業、地域居住支援事業を利用できるようになりました。
これにより、制度間の切れ目のない継続的な支援が可能となり、特に若者の場合は、生活保護受給中から就労に向けた準備を段階的に進められるようになりました。従来は生活保護を脱却してから就労支援を受ける必要がありましたが、受給中から準備できることで、よりスムーズな自立が期待できます。
就労自立給付金の算定方法の見直し(2024年10月1日施行)も重要な変更点です。生活保護を脱却し安定した職業に就いた者に対して支給される給付金について、早期に保護が廃止された場合の最低給付額を引き上げるなど、就労期間に応じたメリハリが付けられました。単身世帯では最低給付額が2万円、複数世帯では3万円となり、若者の就労インセンティブがより効果的になっています。
住まいの確保に関する支援強化も見逃せない改正点です。居住サポート住宅における住宅扶助の代理納付の原則化により、家賃等の支払いに係る賃貸人の不安が軽減され、生活保護受給者の安心な住まいの確保が促進されています。若者にとって安定した住まいは自立の基盤となるため、この改正は非常に意義深いものです。
高校卒業後の支援強化として、前述の新生活立ち上げ費用の支給(自宅外30万円、自宅10万円)が新設されました。これまで大学等に進学する際にのみ給付金が支給されていましたが、高校卒業後の就職者も対象にすることで、進路に関わらず生活基盤の確立に向けた自立支援が強化されています。
関係機関との連携強化も進んでいます。支援調整等を行う会議体の設置規定の創設により、福祉、就労、教育、税務、住宅などの関係部局が連携して生活困窮者を把握し、自立相談支援事業の利用を勧奨する体制が整備されました。これにより、若者が一つの窓口で包括的な支援を受けられる環境が整いつつあります。
これらの改正は、生活保護制度が単なる困窮者への支給に留まらず、より包括的かつ早期的な自立支援を目指していることを明確に示しています。特に若年層の将来性を重視し、一時的な支援に終わらない持続可能な自立を促進する仕組みが構築されているのです。
重要なのは、これらの新しい支援制度を積極的に活用することです。福祉事務所や地域の相談窓口で最新の支援制度について情報収集し、自分に適用可能な制度を把握しておくことが、効果的な自立への道筋となります。
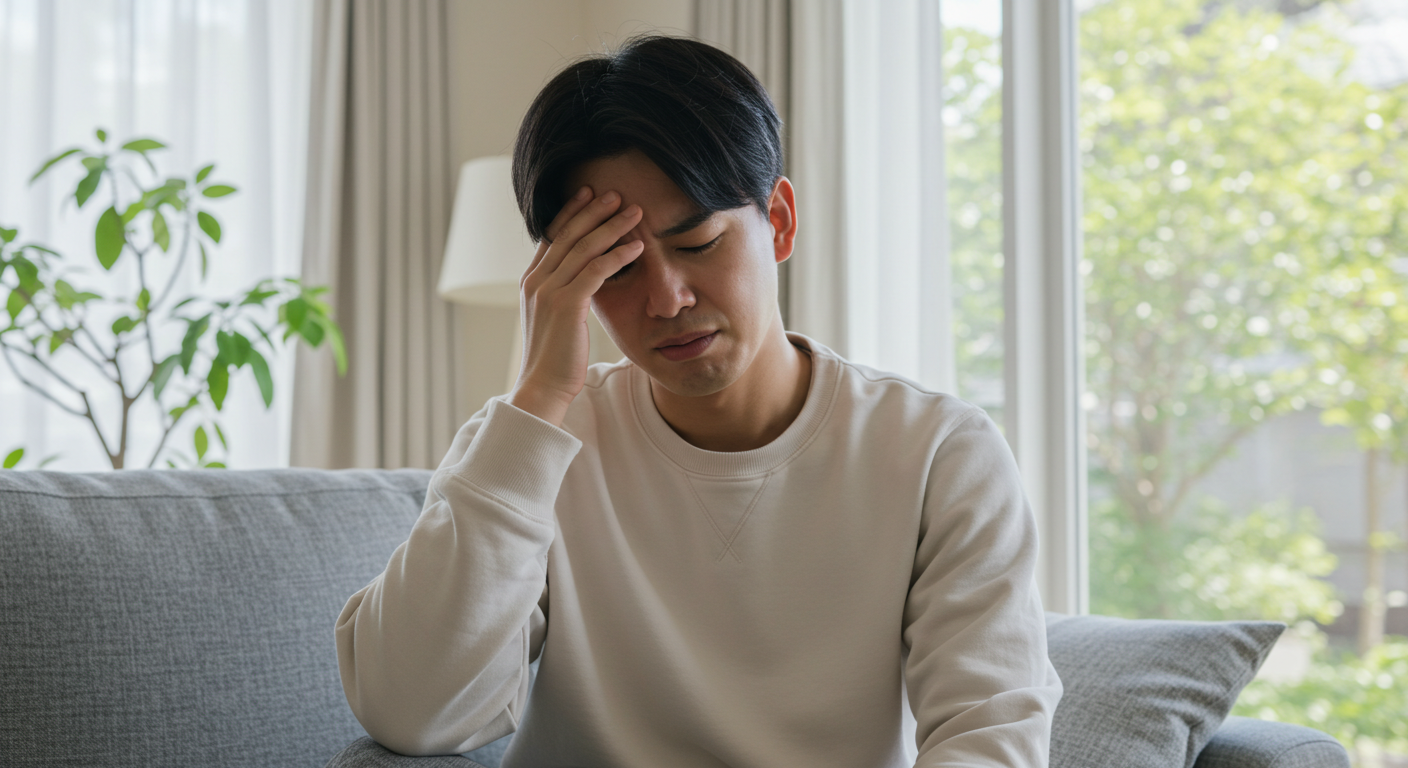

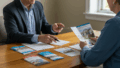
コメント