65歳を迎えると、介護保険制度における立場が大きく変わります。40歳から64歳までの第2号被保険者の時期は、加入している医療保険を通じて保険料を支払っていましたが、65歳以降は第1号被保険者となり、居住する市区町村が直接保険料を管理するようになります。
この変化により、保険料の計算方法や支払い方法が根本的に変更され、個人の所得状況や居住地域によって負担額に大きな差が生じるようになります。特に年金からの天引きという新しい徴収方法が導入されることで、多くの方が戸惑いを感じることも少なくありません。
2025年現在、全国の市区町村の基準額平均は月額約6,225円となっていますが、実際の負担額は最低で月額3,374円から最高で月額9,249円まで、地域によって2.7倍もの格差が存在しています。また、同じ地域内でも所得に応じて9段階から19段階までの細かい区分が設けられており、個人の経済状況に応じた負担となるよう配慮されています。
今後の高齢化の進展に伴い、2040年には現在の1.5倍程度まで保険料が上昇する可能性も指摘されており、制度の理解と適切な準備が重要になっています。
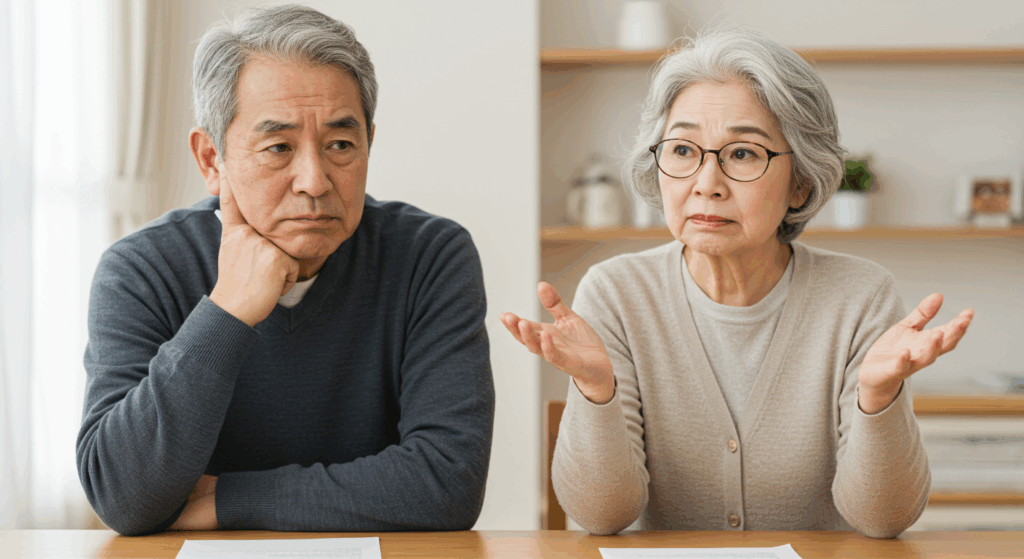
65歳になると介護保険料の計算方法はどう変わるの?
65歳になると、介護保険料の計算方法は劇的に変化します。最も大きな変化は、全額自己負担になることと、市区町村ごとに異なる基準額が適用されることです。
40歳から64歳までの第2号被保険者時代は、医療保険料と合わせて全国一律の料率(2025年度は1.82%)で計算されていました。会社員の場合は労使折半で実質0.91%の負担となり、給与が30万円であれば月額2,730円程度の負担でした。
しかし65歳以降は、居住する自治体が設定する「基準額」を基準として、個人の所得に応じて段階的に保険料が決定されます。この基準額は、各自治体における介護給付の見込額を、その地域の65歳以上人口で割って算出されるため、地域によって大きく異なります。
具体的な計算方法は、まず合計所得金額を算出することから始まります。ここでいう合計所得金額とは、年金・給与・事業等の所得の合計で、扶養控除や基礎控除などの各種所得控除を差し引く前の金額です。この金額に基づいて、各自治体が設定した所得段階に当てはめられます。
例えば、全国平均の基準額6,225円の自治体では以下のような計算になります。第1段階(生活保護受給者等)では基準額×0.3で月額1,868円、第5段階(基準額適用)では月額6,225円、高所得の第13段階以上では基準額×2.3以上で月額14,318円以上となります。
2025年度からの変更点として、基礎年金の支払額増加に伴い、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の所得基準額が80万円から80万9千円に変更されました。これにより、より細かな所得区分による公平な負担が図られています。
また、公費による軽減措置も重要なポイントです。第1段階から第3段階までの低所得者については、国・都道府県・市町村の公費により保険料が軽減されており、本来の保険料額よりも低い設定となっています。この軽減により、最も所得の低い第1段階では本来の5割程度の負担で済むようになっています。
保険料は3年ごとに見直されるため、現在の2024年度から2026年度の期間が終了すると、2027年度から新しい基準額が適用されます。高齢化の進展に伴い、基準額は上昇傾向にあり、長期的な家計設計においてこの負担増を考慮することが重要です。
介護保険料が年金から天引きされる条件と仕組みとは?
65歳以降の介護保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)により徴収されますが、すべての方が対象になるわけではありません。天引きには明確な条件があり、その仕組みを理解することで納付方法の変更に備えることができます。
特別徴収の対象条件は以下の通りです。まず、年額18万円以上の年金を受給していることが必要です。この18万円は複数の年金の合計額ではなく、単一の年金制度からの受給額です。次に、介護保険料と国民健康保険料等の合計が年金額の2分の1を超えないことが条件となります。さらに、日本年金機構などの年金保険者からの年金を受給していることも必要です。
天引きは年6回、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給時に実施されます。興味深いのは「仮徴収」と「本徴収」という2つの仕組みです。4月・6月・8月の仮徴収期間は、前年度2月と同額を暫定的に天引きします。これは新年度の保険料がまだ確定していないためです。
10月・12月・2月の本徴収期間では、6月に決定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残額を3回に分けて天引きします。そのため、本徴収時期には金額が変わる場合があり、「なぜ急に天引き額が変わったのか」という疑問の原因となることがあります。
複数年金を受給している場合の天引き順位は法律で決められています。優先順位は①老齢基礎年金、②老齢厚生年金、③退職共済年金、④障害基礎年金、⑤遺族基礎年金の順となり、最も優先度の高い年金から天引きされます。
普通徴収となる場合もあります。年金額が年額18万円未満の方、年度途中で65歳になった方、他市町村から転入した方、介護保険料と国民健康保険料等の合計が年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替による普通徴収となります。
特に注意が必要なのは、天引き開始までの準備期間です。65歳になったばかりの方や転入者は、年金機構との事務手続きに半年から1年程度かかるため、その間は普通徴収での納付が必要です。この期間は第1期から第10期まで、6月から翌年3月まで設定されており、各期の納期限までに忘れずに納付しなければなりません。
重要なポイントとして、後期高齢者医療保険料とは異なり、介護保険料の年金天引きを個人の希望で停止することはできません。これは介護保険法の規定によるもので、制度の安定的な運営のために必要な措置とされています。
年金から天引きされた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。年金の源泉徴収票に記載されるため、確定申告や年末調整の際には忘れずに控除を受けることができます。
住んでいる地域によって介護保険料にどれくらい差があるの?
65歳以上の介護保険料は、居住地によって大きな格差が存在します。2024年度の実態を見ると、全国で最も高い自治体と最も安い自治体では2.7倍以上もの差があり、同じ国の制度でありながら地域による負担格差は深刻な状況となっています。
最高額の自治体は大阪府大阪市で月額9,249円、最低額の自治体は東京都小笠原村で月額3,374円となっており、月額で5,875円、年額では70,500円もの差が生じています。この差額は軽自動車税の年額に匹敵する金額であり、居住地選択が家計に与える影響の大きさを物語っています。
高額ランキング上位を見ると、大阪府の自治体が多く占めています。大阪市に続き、守口市(8,970円)、門真市(8,749円)、松原市(7,900円)など、都市部での負担が特に重くなっています。一方で、地方部でも岩手県西和賀町(8,100円)や青森県の複数自治体が高額ランキングに入っており、単純に都市部だけが高いわけではないことがわかります。
低額ランキングでは、離島や人口の少ない地域が多く見られます。小笠原村に続き、北海道音威子府村(3,600円)、群馬県草津町(3,600円)などが低額となっており、地理的条件や人口構成が保険料設定に大きく影響していることが理解できます。
都道府県レベルでの比較では、最も高い大阪府(7,486円)と最も低い山口県(5,568円)で1.34倍の格差があります。これは都道府県という広域単位でも、高齢化の進展度や介護インフラの整備状況に違いがあることを示しています。
格差が生じる主な理由は複数あります。まず、高齢化率の違いが挙げられます。高齢化が進んだ地域ほど介護サービスの需要が高く、給付費が増加するため保険料も高くなります。次に、介護サービス基盤の違いも重要な要因です。介護施設や訪問サービス事業所の整備状況により、サービス提供体制やコストに差が生じます。
人件費の地域差も見逃せません。都市部では介護従事者の人件費が高く、これが直接保険料に反映されます。また、地理的条件による影響もあり、離島や山間部では効率的なサービス提供が困難になる場合があります。人口密度も関係しており、人口が少ない地域では固定費を分担する人数が少ないため、一人当たりの負担が重くなる傾向があります。
具体的な負担例を見てみましょう。基準額適用の第5段階の方の場合、大阪市では年額110,988円、小笠原村では年額40,488円となり、同じ所得段階でも年額7万円以上の差が生じます。高所得の第13段階の方では、この差がさらに拡大し、年額16万円以上の負担差になることもあります。
この格差問題に対して、国レベルでの調整も検討されています。財政力の弱い自治体への支援強化や、広域連合による保険料格差の縮小などが議論されていますが、抜本的な解決には時間がかかると予想されます。
将来の住まい選択において、介護保険料の水準も考慮要因の一つとなりつつあります。ただし、保険料だけでなく、実際に必要となった際のサービス提供体制や質も重要な判断材料であることを忘れてはなりません。
介護保険料を滞納するとどんなペナルティがあるの?
介護保険料を滞納すると、段階的に厳しいペナルティが科されます。これらの措置は制度の公平性を保つために設けられており、滞納期間に応じて徐々に重くなる仕組みとなっています。
初期段階のペナルティとして、納付期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状の発行には1通につき70円から100円の手数料がかかり、さらに延滞金も加算されます。延滞金は納付期限から実際の納付日までの日数に応じて計算され、長期間放置するほど負担が重くなります。
1年以上滞納すると、介護サービス利用時の支払い方法が大きく変わります。通常であれば利用料の1割から3割を支払うだけでサービスを受けられますが、滞納者はサービス費用を全額自己負担しなければならなくなります。後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることはできますが、一時的な負担が非常に重くなり、実質的にサービス利用が困難になる場合があります。
1年6か月以上滞納した場合、さらに厳しい措置が取られます。保険給付の全部または一部が一時差し止められ、差し止められた分は滞納している保険料に充てられます。つまり、本来受け取れるはずの保険給付が、滞納保険料の回収に使われてしまうのです。差し止め額から滞納保険料を差し引いた残額がある場合のみ払い戻されるため、実質的な強制徴収となります。
2年以上滞納すると、最も重いペナルティが科されます。介護保険料は2年で時効となり支払いができなくなりますが、その代わりに利用者負担が引き上げられます。本来1割または2割で済むサービス利用料が3割に引き上げられ(既に3割の方は4割)、さらに高額介護サービス費などの負担軽減制度からも除外されてしまいます。
差押え処分のリスクも見逃せません。長期滞納者に対する差押え件数は年々増加傾向にあり、2019年度には19,000人以上が対象となりました。差押えでは、預金・年金・給与・不動産などの財産が強制的に処分され、滞納金の回収に充てられます。
特に深刻なのは相続への影響です。介護保険料の滞納は債務として相続人に承継されるため、家族にも負担が及ぶ可能性があります。これにより、本人だけでなく家族関係にも影響を与える恐れがあります。
実際の事例を見ると、滞納によるペナルティの影響は深刻です。要介護度が高い方が1年以上滞納した場合、月額20万円のサービスを利用していれば、通常2万円の自己負担で済むところが、全額20万円を一旦支払わなければならなくなります。高齢者にとってこの負担は現実的ではなく、結果的にサービス利用を諦めざるを得ない状況に陥ります。
一方で、減免制度も用意されています。失業や収入の大幅減少、災害による被害など、やむを得ない理由により保険料の支払いが困難な場合は、自治体に相談することで減免や分割納付が認められる場合があります。2024年のデータでは、滞納者数は減少傾向にあり、これは早期の相談対応や減免制度の活用が広がったことが要因とされています。
対策として重要なのは、支払いが困難になった時点で速やかに自治体の介護保険担当窓口に相談することです。放置すればするほどペナルティは重くなるため、早期の相談と適切な対応が必要不可欠です。分割納付や減免制度を活用することで、ペナルティを回避しながら制度を利用することが可能です。
将来の介護保険料負担はどこまで上がる予想なの?
介護保険料の将来負担は、急速な高齢化に伴い大幅な上昇が避けられない状況にあります。政府の長期見通しによると、2040年には月額9,000円程度まで上昇すると予測されており、現在の基準額6,225円と比較すると約1.5倍の負担増となります。
2040年問題が最大の要因となっています。この時期には団塊の世代の子どもたちである「団塊ジュニア世代」が65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎えます。65歳以上の人口が全人口の35%まで増加し、要介護認定者数も大幅に増加する見込みです。これに伴い、介護サービスにかかる費用は2023年度予算の2倍にあたる約26兆円まで膨らむと予測されています。
人口構造の変化も深刻な影響を与えます。2050年には「肩車型」と呼ばれる人口構造となり、65歳以上1人に対し現役世代1.2人という極めて厳しい状況になります。現在の「騎馬戦型」(現役世代2.1人で高齢者1人を支える)から大きく変化し、実質的に現役世代1人が高齢者1人を支えることになります。
保険料率の歴史的推移を見ると、制度開始時の2000年は0.60%でしたが、2025年現在は1.82%まで上昇しており、23年間で約3倍となっています。この上昇トレンドは今後も続くと予想され、2040年には現役世代の負担がさらに重くなることは確実です。
具体的な将来負担をシミュレーションすると、標準報酬月額30万円の会社員の場合、現在の月額保険料2,730円が2040年には4,000円を超える可能性があります。年額では現在の32,760円から48,000円以上へと1.5倍以上の増加が予想されます。
65歳以上の第1号被保険者についても同様に、2040年の月額9,000円という予測は各所得段階に影響します。基準額適用の第5段階では年額108,000円、高所得の第13段階では年額200,000円を超える負担となる可能性があります。
社会保障費全体への影響も深刻です。内閣府の試算によると、社会保障費は2040年度に190兆円に達すると予測されており、このうち介護関連費用が特に大きな割合を占めることになります。これは現在の社会保障費の約1.5倍に相当し、現役世代の負担増は避けられない状況です。
制度改革の議論も活発化しています。負担年齢の拡大については、現在40歳からとなっている保険料負担を20歳まで引き下げることで負担を分散させる案が検討されています。また、給付と負担のバランス見直しにより、サービス内容の効率化や利用者負担の適正化も議論されています。
税財源の活用も重要な論点です。保険料だけでなく、税による公費負担の割合を現在の50%からさらに引き上げることで、現役世代の保険料負担を軽減する方向性も検討されています。
個人レベルでの対策も重要になります。健康寿命の延伸により要介護状態になるリスクを減らす取り組み、家計設計の見直しによる将来負担への備え、地域選択の検討による保険料水準の考慮などが必要です。
予防重視への転換も制度の持続可能性を高める鍵となります。介護予防事業の充実により、将来的な給付費の伸びを抑制し、保険料上昇を緩和する取り組みが強化されています。
2027年度の制度改正では、これらの課題に対する具体的な対応策が示される予定です。制度の持続可能性確保のため、負担と給付の両面からの見直しが避けられない状況となっており、国民一人ひとりの理解と協力が求められています。



コメント