2025年は、マイナンバーカードを初期に取得した多くの方が更新時期を迎える記念すべき年です。電子証明書では約1580万人、カード本体では約1200万人という史上最大規模の更新ピークが到来します。この大量更新により、各自治体の窓口混雑が予想されるため、早めの準備と正確な手続き方法の理解が重要になります。マイナンバーカードは今後、運転免許証との一体化やパスポートオンライン申請での活用など、ますます重要な役割を果たすことが期待されています。更新手続きは無料で行えますが、必要書類や申請方法を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを完了できます。本記事では、マイナンバーカード更新に関するよくある疑問を5つのQ&A形式で詳しく解説し、あなたの更新手続きをサポートします。
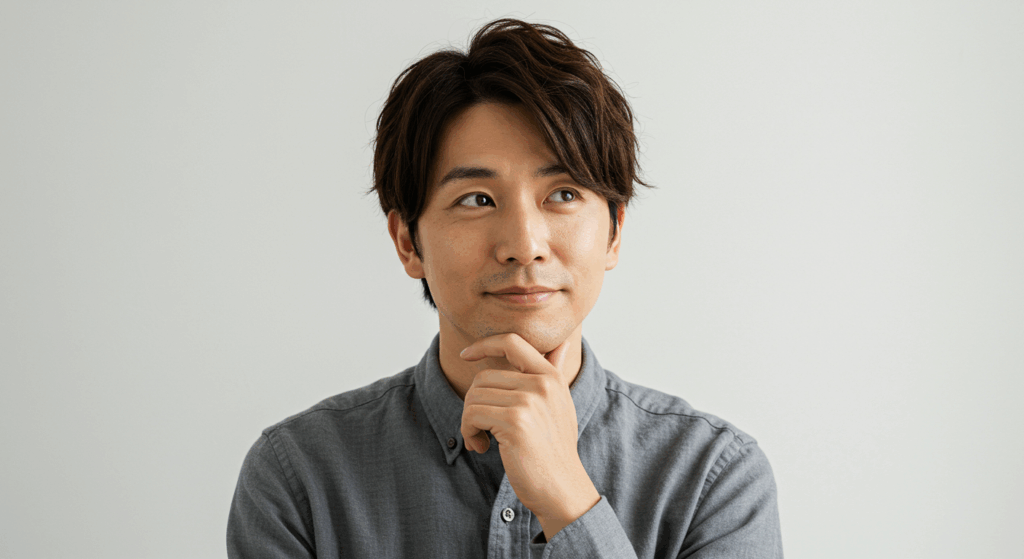
Q1: マイナンバーカードの更新はいつから手続きできる?有効期限の確認方法は?
マイナンバーカードの更新手続きは、有効期間の満了する日までの期間が3か月未満になった日から可能となります。例えば、2025年10月1日が有効期限の場合、2025年7月2日から更新手続きを開始できます。
カード本体と電子証明書で有効期限が異なることを理解しておくことが重要です。カード本体の有効期間は、18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までです。一方、電子証明書は年齢に関係なく、すべての方が発行日から5回目の誕生日までとなっています。
有効期限の確認方法は複数あります。最も簡単なのは、カード表面を直接確認する方法です。カード本体の有効期限は表面下部に「有効期限」として記載され、電子証明書の有効期限は表面右下に小さく記載されています。また、マイナポータルにログインすることで、電子証明書の有効期限をオンラインで確認することも可能です。
有効期限の2~3か月前になると、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が登録住所に郵送されます。この通知書には、更新手続きに必要な申請書IDやQRコード、更新方法の詳しい説明が記載されているため、届いたら大切に保管してください。
早めの更新手続きを推奨する理由は、手続きには時間がかかる場合があることと、有効期限が切れてしまうと電子証明書を使用するサービス(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付、健康保険証利用など)が利用できなくなるためです。ただし、有効期限が過ぎても更新は可能で、費用も無料のままです。
Q2: マイナンバーカード更新に必要な書類は何?電子証明書とカード本体で違いはある?
マイナンバーカードの更新に必要な書類は、電子証明書のみの更新かカード本体の更新かによって大きく異なります。
電子証明書のみの更新の場合、必要な書類は比較的少なくて済みます。有効期限内のマイナンバーカード(必須)、有効期限通知書(なくても手続き可能)、そして4桁の暗証番号の記憶が必要です。暗証番号を忘れた場合でも、窓口で再設定が可能ですが、その際は本人確認書類の追加提示を求められる場合があります。
カード本体の更新には、新しい顔写真が必要となります。具体的には、有効期限通知書に記載の申請書IDまたはQRコード、新しい顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影、無帽、無背景)、そして受取時に現在のマイナンバーカードが必要です。オンライン申請の場合は、デジタル写真(480~6000ピクセル×480~6000ピクセル)も使用可能で、スマートフォンで撮影した写真でも規格を満たしていれば申請できます。
代理人による電子証明書更新の場合は、本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書(本人が記入・封印したもの)、代理人の本人確認書類(顔写真付き)が必要です。15歳未満の子供や成年被後見人の場合は、本人のマイナンバーカード、法定代理人の本人確認書類、法定代理権を証明する書類(戸籍謄本など)が必要ですが、同一世帯で親子関係が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
顔写真の規格では特に注意が必要です。正面向きで無表情または自然な表情、帽子・サングラス・マスクは不可、背景は無地(白、グレー、青など)、影がないこと、ピンぼけしていないことが重要なポイントです。これらの規格を満たしていない場合、申請が受理されない可能性があります。
更新費用は基本的に無料ですが、カードを紛失して再発行する場合は1,000円(カード再発行800円+電子証明書200円)、外国人住民の方で在留期限による更新(特別永住者・永住者を除く)の場合は有料となります。
Q3: マイナンバーカード更新の申請方法は?オンライン・窓口・郵送のメリット・デメリット
マイナンバーカードの更新申請方法は、主にオンライン申請、窓口手続き、郵送申請、証明写真機での申請の4つがあります。それぞれに特徴があるため、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。
オンライン申請(カード本体更新)は最も便利な方法です。有効期限通知書に記載のQRコードをスマートフォンで読み取るか、申請用URLにアクセスし、メールアドレスを登録、送られてきたメールから申請者専用サイトにアクセス、顔写真をアップロードまたは撮影、必要事項を入力して送信という流れです。24時間いつでも申請可能で、待ち時間もなく、申請完了後約1か月で交付通知書(はがき)が届きます。デメリットとしては、スマートフォンやパソコンの操作に慣れていない方には難しい場合があることです。
証明写真機での申請も便利な選択肢です。Ki-Re-iなど対応している証明写真機で、申請書IDを入力またはQRコードを読み取り、顔写真を撮影、画面の指示に従って申請します。写真撮影と申請が同時にできるため、写真の準備が不要で、外出のついでに手続きできる点がメリットです。
郵送申請は、更新申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付(裏面に氏名と生年月日を記入)、申請書を専用封筒で郵送する方法です。白紙の手書き用申請書も使用可能ですが、その場合は12桁のマイナンバーの記入が必要です。自宅で手続きできる点がメリットですが、郵送による時間のロスと、写真の規格チェックが厳しい点がデメリットです。
窓口での手続き(電子証明書更新)は、必要書類を持参して市区町村窓口で行います。本人確認後、暗証番号を入力し、新しい電子証明書の書き込みを行います。手続きは通常15~30分程度で完了し、その場で手続きが完了する点が最大のメリットです。ただし、2025年は窓口の混雑が予想されるため、予約システムの活用や混雑時間を避けることが重要です。
申請方法を選ぶ際は、自分のITスキル、時間的制約、手続きの確実性を総合的に考慮することが大切です。急ぎの場合は窓口手続き、時間に余裕がある場合はオンライン申請がおすすめです。
Q4: 子供や代理人によるマイナンバーカード更新手続きの注意点は?
子供のマイナンバーカード更新には、大人とは異なる特別な注意点があります。最も重要なのは、18歳未満の子供のカードは有効期間が5年間と短く設定されていることです。これは成長による顔の変化を考慮したもので、小学生や中学生の時期に作成したカードは比較的早く更新時期を迎えます。
15歳未満の子供の更新手続きは、法定代理人(親権者など)が行う必要があります。必要書類は、子供のマイナンバーカード、新しい顔写真、法定代理人の本人確認書類、法定代理権を証明する書類(同一世帯の場合は不要)です。特に注意すべきは、子供の成長が著しいため、できるだけ新しい顔写真を用意することです。
学校に通う子供の場合、更新手続きには平日の来庁が必要な場合が多いため、学校行事や部活動との調整が必要です。長期休暇中の手続きがおすすめですが、その時期は窓口が混雑する傾向があるため、予約システムを活用することが重要です。
代理人による電子証明書更新の場合、通常の代理人手続きでは、本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書(本人が記入・封印)、代理人の本人確認書類(顔写真付き)が必要です。照会書兼回答書は本人が必ず記入し、封印する必要があり、これができない場合は代理人手続きは利用できません。
任意代理人と法定代理人の違いも理解しておく必要があります。任意代理人の場合は本人の意思確認が厳格に行われるため、照会書兼回答書の記入・封印が必須です。一方、法定代理人(親権者など)の場合は、法定代理権を証明する書類で代理権が確認されるため、手続きがより簡単です。
代理人手続きでは複数回の来庁が必要になる場合があります。特に書類に不備があった場合や、本人確認に時間がかかる場合は、再度来庁を求められることがあります。事前に市区町村窓口に電話で確認し、必要書類を正確に準備することが大切です。
また、暗証番号の取り扱いにも注意が必要です。代理人が手続きを行う場合でも、暗証番号は本人が設定する必要があります。子供の場合は保護者と相談して覚えやすい番号を設定し、忘れないように管理することが重要です。
Q5: マイナンバーカード更新で混雑を避けるコツは?2025年の大量更新に備える方法
2025年は史上最大規模の更新ピークを迎えるため、混雑を避ける戦略的なアプローチが重要です。まず、混雑する時期と時間帯を把握しておきましょう。
特に混雑する時期は、3月~5月(引っ越しシーズン)、年度末・年度初め、月末の日曜日(臨時窓口開設日)です。混雑する時間帯は、平日11時~14時、土曜日の午前中、臨時窓口開設日の開庁直後です。これらの時期・時間帯を避けることで、待ち時間を大幅に短縮できます。
予約システムの活用は混雑回避の最も有効な方法です。多くの自治体で予約システムが導入されており、最大30日前から予約可能(朝8時30分から)、オンラインで空き状況確認、希望日時を選択して予約、予約確認メールの送信という流れで利用できます。予約なしでも手続き可能な自治体もありますが、2025年は待ち時間が大幅に長くなる可能性が高いため、必ず予約を取ってから来庁することをおすすめします。
土日・夜間窓口の活用も有効な選択肢です。働いている方や学生向けに、多くの自治体で特別窓口を開設しています。横浜市では平日夜間、土日祝日対応(特設センター)、福岡市では水木金12時~20時、土日9時30分~17時30分、札幌市では土曜日、日曜日、平日夜間対応を実施しています。事前に自治体のウェブサイトで開庁日時を確認し、これらの時間帯を積極的に活用しましょう。
オンライン申請の優先活用は、2025年の大量更新に対する最も効果的な対策です。カード本体の更新はオンライン申請が可能で、24時間いつでも申請でき、窓口に行く必要がありません。電子証明書の更新は窓口手続きが必要ですが、事前にオンラインで予約を取ることで、スムーズに手続きを完了できます。
早めの手続き開始も重要なポイントです。更新可能時期(有効期限の3か月前)になったらすぐに手続きを開始することで、混雑ピークを避けることができます。特に2025年3月以降は混雑が予想されるため、2025年1月~2月に更新時期を迎える方は、できるだけ早く手続きを完了させることをおすすめします。
引っ越し予定がある場合は、引っ越し前に更新手続きを完了させることが重要です。引っ越し後は住所変更手続きも必要になり、さらに窓口が混雑する原因となります。引っ越しと更新時期が重なる場合は、必ず引っ越し前に手続きを完了させてください。
最後に、必要書類の事前準備を徹底することで、窓口での手続き時間を短縮できます。顔写真の規格確認、暗証番号の確認、必要書類のチェックリスト作成など、事前準備を完璧にして臨むことで、スムーズな手続きが可能になります。

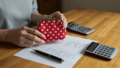
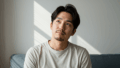
コメント