2025年10月1日から、健康保険における被扶養者認定の基準が大きく変更されることになりました。この改正は、19歳以上23歳未満の若年層を対象としており、年収要件が従来の130万円未満から150万円未満へと拡大されます。この変更は、税制改正と連動して実施されるもので、大学生や専門学校生など学生世代のアルバイト収入における「年収の壁」問題を緩和する重要な政策となっています。労働力不足が深刻化する中で、若年層がより柔軟に働くことができる環境を整備し、学業と就労の両立を支援することが目的です。この制度改正により、多くの学生やその家族にとって、経済的な選択肢が広がることになります。健康保険の被扶養者として認定されることで、国民健康保険や国民年金への加入が不要となり、家計全体の負担軽減につながるため、制度の詳細をしっかりと理解しておくことが重要です。

制度改正の全体像と施行時期
2025年10月1日を境に、健康保険における被扶養者認定の仕組みが変わります。この改正は、厚生労働省からの通達により正式に公表されており、全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽや各企業が運営する健康保険組合において一斉に適用されることになっています。対象となるのは、19歳以上23歳未満の方で、被保険者の配偶者を除く親族となります。この年齢層に該当する方は、年収要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられることで、より多くの収入を得ても親や保護者の健康保険の被扶養者として認定され続けることが可能になります。
この改正は、単なる年収基準の引き上げだけでなく、税制改正とも密接に連携しています。所得税や住民税における扶養控除の基準も同時に見直されることで、健康保険と税制の両面から若年層の就労環境が改善される仕組みとなっています。従来は、130万円という壁があったために、学生がアルバイトの時間を調整せざるを得ない状況がありましたが、新しい制度では150万円まで余裕を持って働くことができるようになります。
対象者の詳細な条件
この制度改正の対象となるのは、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、年齢が19歳以上23歳未満であることが第一の条件です。この年齢判定については、被扶養者認定を受ける年の12月31日時点での年齢で判断されることになっています。例えば、2025年の12月31日時点で19歳であれば、その年度においては新しい150万円基準が適用されます。また、2025年中に19歳になる方についても、19歳に達した時点から新基準が適用されることになります。
次に重要な条件として、被保険者の配偶者でないことが挙げられます。配偶者には内縁関係にある方も含まれますが、配偶者に該当する場合は、年齢に関わらず従来通りの130万円未満という基準が適用されます。この点は、若年層の中でも既婚者と未婚者で扱いが異なることを意味しており、政策の対象が学生を中心とした若年層の就労促進にあることを示しています。
さらに、2025年10月1日以降に被扶養者認定を受ける方だけでなく、既に被扶養者として認定されている方にも新基準が適用されます。つまり、現在すでに親の健康保険の被扶養者となっている19歳以上23歳未満の方は、10月1日以降は自動的に150万円基準が適用されることになるため、特別な手続きを行う必要はありません。ただし、収入状況に変更があった場合には、適切に報告することが求められます。
年収150万円未満の具体的な判定方法
年収150万円未満という基準は、将来に向かって恒常的な収入の年間見込み額が150万円未満であることを意味しています。この収入の判定方法は、過去の収入実績、現時点での収入状況、さらには今後の収入見込みを総合的に勘案して判断されます。健康保険組合や協会けんぽでは、直近3ヶ月程度の給与明細や雇用契約書の内容などを基に、今後1年間でどれくらいの収入が見込まれるかを評価します。
給与収入の場合、基本給だけでなく、通勤手当などの非課税所得も含めて計算される点に注意が必要です。税制上は一定額までの通勤手当は非課税となりますが、健康保険の被扶養者認定における収入判定では、すべての手当を含めた総額で判断されます。例えば、月額給与が12万円で通勤手当が5,000円の場合、社会保険上の月収は12万5,000円として扱われます。
また、給与以外の収入についても考慮されます。アルバイトやパートの給与だけでなく、事業収入、年金収入、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金なども収入として算定されます。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての収入を合算して判断されるため、注意が必要です。
月額に換算すると、150万円を12ヶ月で割って月額12万5,000円未満が基準となります。日額では、150万円を360日で割って日額4,166円未満という計算になります。収入が月によって変動する場合は、平均的な月収や契約内容から年間の見込み額を算出することになります。
従来基準との比較と改正の意義
従来の被扶養者認定基準では、年齢に関わらず一律で年収130万円未満という要件が設けられていました。この130万円の壁は、多くのパートタイマーやアルバイトで働く方にとって、就労調整を行う大きな要因となっていました。特に、大学生などの若年層にとっては、学費や生活費を稼ぎたいと思っても、130万円を超えると親の扶養から外れてしまい、国民健康保険や国民年金への加入が必要となるため、年間で約30万円程度の追加負担が発生する可能性がありました。
ただし、従来の制度においても、60歳以上の方や障害年金受給者については、年収180万円未満という特例が認められていました。今回の改正により、19歳以上23歳未満の方については、これらの中間的な基準として年収150万円未満という新たな区分が設けられることになります。この変更により、該当する年齢層の方は、従来よりも20万円多く収入を得ることができるようになり、より柔軟な働き方が可能となります。
この20万円の差は、学生にとって大きな意味を持ちます。例えば、時給1,200円で働く学生の場合、20万円は約167時間分の労働に相当します。月に換算すると約14時間、週に換算すると約3時間の追加勤務が可能になる計算です。これにより、学費や生活費の負担を軽減したり、より充実した学生生活を送るための資金を確保したりすることが可能になります。
学生である必要はない重要なポイント
この制度改正において、特に重要なポイントは、学生であるかどうかは要件とされていないことです。あくまでも年齢のみで判断されるため、大学生や専門学校生だけでなく、高校卒業後に就職した方、フリーターとして働いている方、資格試験の勉強をしながら働いている方など、様々な立場の19歳以上23歳未満の方が対象となります。
従来から、社会保険の被扶養者認定における106万円の壁については、学生は適用除外とされていました。しかし、今回の150万円の新基準については、学生であるかどうかは問われません。これは、若年層全体の就労を促進するという政策目的が、学生に限定されないことを示しています。高校卒業後に進学せずに働いている方や、一度就職した後に離職して親元に戻っている方なども、年齢条件を満たせば新基準の対象となります。
ただし、社会保険の適用要件である106万円の壁については、依然として学生は原則として対象外とされています。週20時間以上働き、月額賃金が88,000円以上などの条件を満たす場合でも、学生であれば勤務先の社会保険への加入義務は発生しません。一方で、学生でない19歳以上23歳未満の方については、これらの条件を満たすと勤務先の社会保険に加入することになり、その場合は親の被扶養者からは外れることになります。
収入要件以外の認定条件
被扶養者として認定されるためには、収入要件だけでなく、他の条件も満たす必要があります。これらの条件は、今回の改正によっても変更されておらず、従来通りの基準が適用されます。
まず、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。これは、親や保護者の経済的支援を主として生活していることを意味します。被扶養者が自身で生活できるほどの収入を得ている場合は、収入基準を満たしていても、この生計維持要件を満たさないと判断されることがあります。
被保険者と同居している場合は、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であることが求められます。例えば、親の年収が500万円の場合、被扶養者となる子どもの年収は250万円未満である必要があります。ただし、150万円未満という収入基準がありますので、実質的にはこの条件が問題になることは少ないでしょう。
被保険者と別居している場合は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満であることが必要です。例えば、親が月に10万円の仕送りをしている場合、子どもの月収が10万円未満でなければなりません。別居の場合は、仕送りの事実を証明するため、振込明細書や通帳の写しなどの提出が求められることが一般的です。
また、日本国内に住所を有することも原則として求められます。ただし、海外留学中の学生については、一定の条件を満たせば被扶養者として認定されることがあります。留学の場合は、留学を証明する書類、ビザの写し、在学証明書などの提出が必要となります。
税制改正との連動と相互関係
健康保険の被扶養者認定基準の変更は、2025年度の税制改正と密接に連動しています。税制においても、大幅な改正が予定されており、基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円にそれぞれ引き上げられます。これにより、本人に所得税がかからない給与収入の上限は、従来の103万円から123万円に引き上げられることになります。
さらに、19歳から22歳までの特定扶養親族については、特別な措置が設けられます。年収123万円までであれば、従来通りの特定扶養控除63万円が適用されます。年収が123万円を超えて150万円までの場合は、新設される特定親族特別控除63万円が適用されることになります。ただし、この特別控除を受けるためには、親の所得が1,000万円以下である必要があります。
この税制改正により、健康保険と税制の両面で、大学生世代の就労環境が整備されることになります。年収150万円まで働いても、親の扶養控除が適用され続けることで、家族全体での税負担が増加することなく、若年層がより多くの収入を得ることができるようになります。
ただし、税制と健康保険では、収入の計算方法や対象範囲が異なる部分もあります。税制上の収入は給与所得控除後の金額で判定されますが、健康保険の収入判定では総収入で判定されます。また、通勤手当の扱いも異なるため、両方の制度を正しく理解することが重要です。
年収の壁問題の背景と今回の改正の位置づけ
「年収の壁」とは、パートやアルバイトで働く方が、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減少したり増加が鈍化したりする現象を指します。日本には複数の年収の壁が存在しており、働く人々の就労行動に大きな影響を与えてきました。
最もよく知られているのが103万円の壁です。年収が103万円を超えると、本人に所得税が課税されます。また、扶養する側の配偶者控除や扶養控除の対象から外れる可能性があります。2025年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の特定扶養親族については、この基準が150万円に引き上げられる予定です。
次に、106万円の壁があります。これは社会保険の壁の一つで、一定の条件を満たす場合に適用されます。勤務先の従業員数が51人以上、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、雇用期間が2ヶ月を超える見込み、そして学生でないことという条件をすべて満たす場合、年収が106万円以上になると勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
そして、今回の改正の対象となる130万円の壁があります。これは、勤務先の規模や労働時間に関わらず、すべての人に適用される社会保険の壁です。年収が130万円以上になると、親や配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要が生じます。この負担は年間で約30万円程度となることが多く、手取り収入に大きな影響を与えます。
2025年10月からは、19歳以上23歳未満の方について、この130万円の壁が150万円の壁に引き上げられます。これにより、大学生世代のアルバイト収入における制約が緩和され、より多くの時間働くことができるようになります。ただし、この150万円の壁は配偶者には適用されず、配偶者については従来通り130万円の壁が残ります。
実務上の手続きと必要書類
被扶養者として認定を受けるためには、被保険者が勤務先を通じて、健康保険組合または協会けんぽに対して被扶養者届を提出する必要があります。この手続きは、被保険者自身が認定条件を満たしていることを書類等で証明する必要があります。
基本的な必要書類としては、まず被扶養者届があります。これは健康保険組合または協会けんぽが指定する様式の届出書で、被保険者の勤務先を通じて入手できます。次に、続柄を証明する書類として、住民票または戸籍謄本が必要です。住民票の場合は、被保険者との続柄が記載されたもので、マイナンバーの記載がないものを準備します。
収入を証明する書類も重要です。学生でアルバイトをしている場合は、給与明細書の直近3ヶ月分、雇用契約書、または源泉徴収票を提出します。無収入または低収入の場合は、無職であることの申立書や退職証明書が必要となります。事業収入がある場合は確定申告書の写しと収支内訳書、年金収入がある場合は年金額改定通知書や年金振込通知書を提出します。
生計維持関係を証明する書類も求められます。別居の場合は、被保険者から被扶養者への仕送りを証明する書類、具体的には振込明細書や通帳の写しなどが必要です。仕送り額が被扶養者の収入を上回っている必要があります。同居の場合は、通常は住民票で同一世帯であることが確認できれば、生計維持関係があるものとみなされます。
その他、該当する場合のみ必要となる書類もあります。学生の場合は在学証明書または学生証の写しを提出します。海外留学中の場合は、留学を証明する書類、ビザの写し、在学証明書が必要です。障害がある場合は障害者手帳の写しを提出します。
手続きのタイミングとしては、被扶養者認定の届出は事実発生日から5日以内に行うことが原則とされています。実務上は事実発生日から速やかに行うことが求められます。19歳以上23歳未満の方で、2025年10月1日時点で既に被扶養者として認定されている方については、自動的に新しい基準が適用されるため、特別な手続きは不要です。
手続きの流れとしては、被保険者が必要書類を準備し、勤務先の人事担当部署に提出します。勤務先が健康保険組合または協会けんぽに届出を行い、審査が実施されます。認定されると、被扶養者の健康保険証が発行されます。審査には通常1から2週間程度かかります。
収入が基準を超えた場合の対応方法
年収が150万円以上となった場合、被扶養者の資格を喪失することになります。収入が恒常的に基準を超える見込みとなった場合は、速やかに被保険者の勤務先に連絡し、被扶養者削除の手続きを行う必要があります。届出が遅れた場合、さかのぼって被扶養者資格が取り消され、その期間に受けた医療サービスに対する医療費の返還を求められることがあります。
資格を喪失した後は、自身で国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険に加入する必要があります。国民健康保険の保険料は、自治体や所得によって異なりますが、年収150万円程度の場合、年間で10万円から15万円程度となることが一般的です。また、20歳以上の場合は国民年金への加入も必要となり、2024年度の保険料は月額16,980円、年間で約20万4,000円の負担となります。
このように、150万円を超えると、社会保険料の負担が発生し、手取り収入に大きな影響が出る可能性があります。例えば、年収155万円で働いた場合、社会保険料と税金を差し引くと、手取り収入は130万円程度とあまり変わらない可能性があります。そのため、150万円のラインを意識して働くか、もっと多く働いて手取りを増やすかの判断が重要になります。
具体的なケーススタディで理解を深める
実際の事例を通じて、2025年10月以降の制度改正の影響をより具体的に見ていきましょう。
ある大学2年生で20歳の方が、週3から4日程度アルバイトをしており、年収が140万円である場合を考えます。2025年10月以降は、年収150万円未満であるため、親の健康保険の被扶養者として認定されます。健康保険料の自己負担はありません。税制面では、年収123万円を超えているため本人に所得税と住民税が課税されますが、親は特定親族特別控除63万円を受けることができます。所得税と住民税の負担はありますが、社会保険料の負担がないため、手取り収入は約135万円程度となり、効率的に収入を得ることができます。
一方、大学4年生で22歳の方が、就職活動が終わり、卒業までの間に週4から5日程度アルバイトをして年収が155万円になる見込みの場合はどうでしょうか。年収150万円以上となるため、被扶養者の資格を喪失します。国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、年間で約30万円程度の保険料負担が発生します。税制面でも、年収150万円を超えているため親の扶養控除の対象外となり、親の税負担が増加します。所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料を差し引くと、手取り収入は約120万円程度となります。155万円稼いでも、手取りは130万円程度稼いだ場合とあまり変わらない可能性があるため、収入を150万円未満に抑えるか、もっと多く働いて手取りを増やすかの判断が重要です。
専門学校1年生で19歳の方が、週3日程度アルバイトをしており、年収が120万円の場合はどうでしょうか。年収150万円未満であるため、親の健康保険の被扶養者として認定されます。年収123万円以下であるため本人に所得税は課税されず、親は特定扶養控除63万円を受けることができます。税金も社会保険料もほとんど負担がなく、効率的に収入を得ることができます。
24歳のフリーターで、年収が140万円の場合はどうでしょうか。24歳であるため、新基準である150万円未満は適用されません。年収130万円以上であるため、被扶養者の資格を喪失しており、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。年間で約30万円程度の保険料負担が発生します。税制面でも、一般扶養控除の収入基準も超えているため親の扶養控除の対象外です。所得税、住民税、社会保険料を差し引くと、手取り収入は約105万円程度となります。年齢が23歳を超えると新基準は適用されないため、年収を130万円未満に抑えるか、もっと多く働いて収入を増やす必要があります。
よくある質問とその回答
制度改正について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
2025年9月まで働いていて、年収が既に130万円を超えている場合はどうなるかという質問があります。被扶養者認定における年収は、将来に向かっての年間見込み額で判断されます。2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の方については、今後1年間の収入見込みが150万円未満であれば被扶養者として認定されます。過去に130万円を超えていたとしても、それだけで直ちに資格を喪失するわけではありません。
扶養認定日が2025年9月で、10月時点で19歳以上23歳未満の場合、150万円の基準が適用されるかという質問もあります。この場合、適用されません。2025年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日がそれより前の期間である場合は、従来の130万円未満の基準で判定されます。あくまでも2025年10月1日以降に認定を受ける場合に新基準が適用されます。
アルバイトの通勤手当が年収に含まれるかという質問もよくあります。税制上、通勤手当は一定額まで非課税となりますが、社会保険の被扶養者認定における年収の計算では、通勤手当も含めて計算されます。例えば、月額給与が12万円、通勤手当が5,000円の場合、社会保険上の月収は12万5,000円となります。
親の会社から支給される家族手当についての質問もあります。会社から支給される家族手当や扶養手当の支給基準は会社ごとに異なります。多くの会社では税制上の扶養控除の基準を採用していることがあります。健康保険の被扶養者認定基準が150万円に引き上げられても、会社の家族手当の基準が自動的に変わるわけではないため、親の勤務先の規定を確認することが重要です。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合の収入計算についても質問があります。この場合、すべての収入を合算して計算します。例えば、アルバイトAで月7万円、アルバイトBで月5万円稼いでいる場合、合計で月12万円、年収144万円となり、150万円未満であるため被扶養者として認定されます。
月によって収入にばらつきがある場合の判断方法についても質問があります。被扶養者認定における年収は、将来に向かっての年間見込み額で判断されます。過去3ヶ月の平均収入や雇用契約書の内容などを基に、今後1年間の収入を見積もります。
年度の途中で収入が増えて150万円を超えそうになった場合は、年収が150万円を超える見込みとなった時点で速やかに被保険者の勤務先に連絡し、被扶養者削除の手続きを行う必要があります。
大学を卒業して就職した場合は、就職して勤務先の健康保険に加入した時点で被扶養者の資格を喪失します。就職日から5日以内に被保険者の勤務先に連絡し、被扶養者削除の手続きを行う必要があります。
配偶者と子どもの扱いの違い
今回の制度改正において重要なポイントは、配偶者と子どもの扱いが異なることです。配偶者には内縁関係を含みますが、配偶者の場合、年収要件は従来通り130万円未満のままです。150万円の新基準は適用されません。配偶者の場合、年収が130万円以上になると被扶養者の資格を喪失します。
一方、19歳以上23歳未満の子どもや親族の場合は、年収要件が150万円未満に拡大されます。これにより、大学生などの若年層は、より多くのアルバイト収入を得ても被扶養者の資格を維持できます。この違いは、若年層の就労を促進し、労働力不足を緩和するという政策目的に基づいています。配偶者については、別途「年収の壁・支援強化パッケージ」などの対策が講じられています。
2023年10月からは、年収の壁・支援強化パッケージが開始されました。これは、一時的に収入が130万円を超えた場合でも、事業主の証明により引き続き被扶養者として認定される仕組みです。ただし、この特例は連続して2回まで、最長2年間の適用となります。また、社会保険に加入した従業員の保険料負担を軽減するための助成金制度なども設けられており、企業側の負担を軽減することで、従業員が安心して社会保険に加入できる環境を整備しています。
企業の人事担当者が注意すべき点
企業の人事担当者や健康保険組合の担当者は、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者の収入確認において、新しい基準である150万円未満を適用する必要があります。既に被扶養者として認定されている方についても、収入の確認を行う際には年齢に応じた基準を適用する必要があります。
特に、年齢が19歳になる方や24歳になる方については、基準が変わるタイミングを正確に把握することが重要です。19歳になる年の1月1日から12月31日までの期間は、その年度全体で150万円基準が適用されます。逆に、24歳になる年は、その年の1月1日から12月31日までの期間において130万円基準が適用されることになります。
また、被扶養者の収入状況の確認を定期的に行う際には、年齢と収入基準の組み合わせを正しく適用することが求められます。システムの設定変更や、従業員への周知も必要となるため、早めの準備が重要です。
まとめと今後の展望
2025年10月1日からの被扶養者認定基準の変更は、19歳以上23歳未満の方にとってより柔軟な働き方を可能にする重要な改正です。年収の壁が130万円から150万円に引き上げられることで、大学生などの若年層は、学業と両立しながらより多くの収入を得ることができるようになります。従来は130万円という壁があったために就労調整を行わざるを得なかった学生が、20万円分多く働けることは、学費や生活費の負担を軽減する上で大きな意味を持ちます。
ただし、収入要件以外の認定要件は従来と変わらないこと、また税制上の扶養控除とは別の制度であることに注意が必要です。生計維持関係の要件や、同居・別居の条件、日本国内に住所を有することなど、従来からの要件はすべて引き続き適用されます。また、税制改正とは連動していますが、収入の計算方法や対象範囲が異なる部分もあるため、両方の制度を正しく理解することが重要です。
配偶者には150万円の新基準は適用されず、従来通り130万円の基準が適用される点にも注意が必要です。さらに、会社から支給される家族手当や扶養手当の基準は、健康保険の基準とは異なる場合があるため、親の勤務先の規定を確認することも重要です。多くの企業では、税制上の103万円や123万円を基準としていることがあり、健康保険の基準が変わっても手当の支給基準は変わらない可能性があります。
この制度改正を理解し、計画的に働くことで、学生や若年層の経済的な自立を支援し、家計全体の負担を軽減することができます。150万円という新しい基準をうまく活用しながら、学業や将来のキャリアとのバランスを取ることが重要です。また、収入が基準を超えそうな場合には、早めに対応することで、後から医療費の返還を求められるなどのトラブルを避けることができます。
今後も、労働力不足の解消や働き方改革の一環として、様々な制度改正が予定されています。社会保険の適用拡大や、最低賃金の引き上げなど、働く環境は大きく変化していく見込みです。これらの変化に対応しながら、自身や家族にとって最適な働き方を選択していくことが求められます。制度の詳細については、加入している健康保険組合や協会けんぽ、また親の勤務先の人事担当部署に確認することをお勧めします。

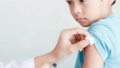

コメント