2025年11月、日本の外食産業界に衝撃的なニュースが駆け巡りました。世界的な投資銀行であるゴールドマン・サックスが、バーガーキングの日本事業を約700億円で買収する独占交渉権を獲得したと、日本経済新聞をはじめとする複数の主要メディアが報じたのです。この取引は、単なる企業買収の枠を超えて、日本のハンバーガー市場の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めています。現在、香港を拠点とするアフィニティ・エクイティ・パートナーズが運営するバーガーキング日本事業は、わずか数年で店舗数を倍増させ、企業価値を飛躍的に高めてきました。ゴールドマン・サックスという巨大な資本力を持つ新たなオーナーの登場は、マクドナルドが絶対的な優位を占める日本市場において、バーガーキングが真の競合として台頭する転換点となる可能性があります。この700億円規模の取引の背景には、グローバルな資本戦略と日本市場特有の競争環境が複雑に絡み合っており、今後の展開から目が離せません。

バーガーキング日本事業売却の全貌
バーガーキング日本事業の売却は、2025年11月に大きな注目を集めました。この取引の核心は、BKジャパンホールディングスの株式が、香港を拠点とするアフィニティ・エクイティ・パートナーズからゴールドマン・サックスへと移行するという点にあります。報道によると、この取引の評価額は約700億円、米ドル換算で約4億5,200万ドルに達する見込みです。
M&Aの世界において、独占交渉権の付与は取引成立に向けた重要なマイルストーンとなります。これは通常、数ヶ月にわたる競争入札プロセスの末、ゴールドマン・サックスが他の買い手候補を抑えて最も有力な買収者として選定されたことを意味します。この段階では、売却主であるアフィニティ・エクイティ・パートナーズは他の候補との交渉を一時停止し、ゴールドマン・サックスとの間でのみ、資産査定や最終的な契約条件の交渉という、取引成立に向けた最終段階に入ることになります。
この700億円という取引規模は、日本のファストフード業界におけるM&Aとしては極めて大規模なものです。これは単なる運営権の売買ではなく、香港の有力プライベート・エクイティファンドが約7年かけて企業価値を最大化した資産を、米国の巨大投資銀行がそのグローバルな知見と莫大な資本力を背景に買い受けるという、国際的な資本戦略が交錯するクロスボーダーM&Aなのです。
アフィニティ・エクイティ・パートナーズの戦略的投資回収
今回の取引の重要な側面として、売却者であるアフィニティ・エクイティ・パートナーズの投資戦略を理解する必要があります。アフィニティ・エクイティ・パートナーズは、アジア太平洋地域に特化した経験豊富なプライベート・エクイティファンドとして知られています。彼らの外食産業への投資は計画的かつ戦略的でした。
2016年には、まずバーガーキングの韓国事業を約1億7,000万ドルで買収しました。その翌年の2017年には日本事業も買収し、地理的に近い日韓事業を一体的に運営管理する戦略を展開してきました。しかし、この投資の道のりは必ずしも平坦ではありませんでした。
実は、アフィニティ・エクイティ・パートナーズは2022年1月にも、日韓事業の同時売却を試みていました。ロイター通信の報道によれば、当時は日韓事業の売却額として10億ドルを超える可能性があるという強気な価格設定で買い手を探していたのです。
当時の事業状況を見ると、韓国事業と日本事業の間には大きな差がありました。韓国事業は2021年の調整後EBITDAが800億ウォン、約77億円と非常に好調で、店舗数も440店に達し、韓国市場においてはマクドナルドを上回る規模を誇っていました。一方、日本事業の調整後EBITDAはわずか7億円程度に過ぎず、店舗数も2022年1月時点で149店と、韓国事業の3分の1程度の規模に留まっていました。
この数字が示すのは、2022年当時の売却パッケージが、EBITDAの大半を稼ぎ出す韓国の優良資産と、まだ成長途上にある日本資産の抱き合わせであったということです。多くの買い手候補は韓国事業だけを欲しがったと考えられ、結果として2022年の日韓同時売却計画は成立しませんでした。
V字回復を実現した成長戦略
2022年の売却失敗を受けて、アフィニティ・エクイティ・パートナーズは驚異的な戦略転換を実行しました。それは、日本事業を単体で高額売却できるレベルまで徹底的に成長させるという、プライベート・エクイティファンドの王道であるバイ・アンド・ビルド戦略の加速でした。
アフィニティ・エクイティ・パートナーズは、2022年の売却不調後、日本事業の価値を最大化するために積極的な店舗拡大策に舵を切りました。BKジャパンホールディングスの店舗数の推移は、その戦略の実行速度を如実に物語っています。アフィニティ・エクイティ・パートナーズによる買収後の2019年時点では、店舗数はわずか77店舗でした。これが2022年1月の売却計画時点では149店舗となり、そして2025年11月の今回の売却報道時点では約310店舗へと、わずか3年弱で倍増するという爆発的な成長を遂げています。
この店舗数の急拡大は、単に数を増やしただけではありません。2022年時点のEBITDAが7億円程度であったことを考えると、700億円という売却価格を正当化するためには、EBITDAが劇的に改善している必要があります。仮にEBITDAが70億円規模に達していたとすれば、700億円の買収価格はマルチプル10倍となり、近年の外食産業M&Aのバリュエーションとして極めて妥当な範囲に収まります。
アフィニティ・エクイティ・パートナーズは、2022年の抱き合わせ売却の失敗からわずか3年で、日本事業を単体で700億円の価値がある優良資産へと変貌させました。これは、プライベート・エクイティファンドが企業価値を最大化する王道のプレイブックを完璧に実行し、最も価値が高まったタイミングで投資回収するという、見事な成功事例といえます。
バーガーキング日本事業の歴史的背景
アフィニティ・エクイティ・パートナーズが2017年に買収し、700億円の価値にまで成長させたバーガーキング日本事業には、実は苦難に満ちた歴史的背景があります。この歴史を理解することで、なぜこれほどまでの成長余地が残されていたのかが明らかになります。
バーガーキングの日本市場での挑戦は、今回が初めてではありません。1990年代に一度、日本市場に参入したものの、当時は絶対王者であったマクドナルドとの激しい競争に敗れ、2001年には業績不振を理由に日本市場からの完全撤退を余儀なくされています。この失敗の10年は、マクドナルドが日本市場で絶対的な地位を確立し、全国に店舗網を張り巡らせる期間と重なります。
市場からの撤退という過去を背負ったバーガーキングは、2007年に日本市場へ再上陸を果たしました。しかし、その形態はグローバル本社が本腰を入れた直営展開ではなく、韓国のロッテグループと日本の経営コンサルティング会社であるリヴァンプによるフランチャイズパートナーシップという、限定的なものでした。
さらに2010年には、バーガーキング日本事業の運営がロッテの子会社であり、ハンバーガーチェーンとして直接的な競合他社であるロッテリアの傘下へと移管されます。これは、バーガーキングにとって成長の足かせとなりました。
自社のブランドの成長戦略を、競合ブランドを運営する親会社に委ねるという構図は、明らかに矛盾をはらんでいました。ロッテリアの経営陣にとって、自社ブランドと顧客を奪い合う可能性のあるバーガーキングの積極的な店舗展開や、大規模なマーケティング投資に経営資源を優先的に投下するインセンティブが働きにくかったと考えられます。
実際、ロッテリアの傘下にあった2017年にアフィニティ・エクイティ・パートナーズが買収するまでの間、バーガーキング日本事業の成長は極めて緩慢でした。アフィニティ・エクイティ・パートナーズによる買収から2年後の2019年時点でも、全国の店舗数はわずか77店舗という、マクドナルドの約3,000店舗とは比較にならない小規模なチェーンに過ぎませんでした。
2017年のアフィニティ・エクイティ・パートナーズによる買収は、バーガーキングがロッテグループという競合の親の束縛から解放された転換点でした。バーガーキングの成長だけにコミットする独立した資本パートナーを得て初めて、独自のブランド戦略と積極的な出店攻勢を開始することが可能になったのです。
ゴールドマン・サックスの投資戦略
買収者であるゴールドマン・サックスは、この700億円の資産を今後どのように成長させようとしているのでしょうか。ゴールドマン・サックスは単なるM&Aの仲介者ではなく、自らも世界最大級のプリンシパル投資部門を持つ、経験豊富な投資家です。今回の買収は、ゴールドマン・サックスが持つグローバルな外食産業における豊富な知見と莫大な資本力を活用し、バーガーキング日本事業を次の成長フェーズへと導くことを明確に目的としています。
ゴールドマン・サックスがアフィニティ・エクイティ・パートナーズから引き継ごうとしているバーガーキング日本事業の経営計画は、極めて野心的です。現在の約310店舗という体制から、わずか3年後の2028年末までに最大600店舗へと、再び店舗数を倍増させる計画を持っています。
アフィニティ・エクイティ・パートナーズが達成した77店から310店への成長がフェーズ1のV字回復だとすれば、ゴールドマン・サックスがこれから仕掛ける310店から600店への成長は、日本市場での本格的な覇権争いに参加するためのフェーズ2の本格拡大といえます。
このフェーズ2は、フェーズ1とは比較にならないほどの困難を伴います。300店舗を超える規模からの倍増は、アフィニティ・エクイティ・パートナーズ時代よりもはるかに巨額の資本投下を、より短期間で実行しなくてはならないからです。一等地への不動産取得、最新の内装設備、オペレーションシステムの構築など、すべてに莫大な投資が必要となります。
ここに、アフィニティ・エクイティ・パートナーズが売却し、ゴールドマン・サックスが買収する理由の一つが隠されています。アフィニティ・エクイティ・パートナーズのような典型的なプライベート・エクイティファンドは、通常5年から7年の投資期間で投資回収を目指すため、この種の超長期的かつ巨額の設備投資フェーズを担うには限界があります。一方で、ゴールドマン・サックスのような潤沢な資金力を持つグローバルな投資プレイヤーこそが、このフェーズ2の重厚な成長を担うのに最も適しているのです。
レストラン・ブランズ・インターナショナルのグローバル戦略
ゴールドマン・サックスがこの困難なフェーズ2に自信を見せる背景には、バーガーキングの親会社であるレストラン・ブランズ・インターナショナルのグローバル戦略に対する高い評価があります。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、バーガーキングの親会社であるレストラン・ブランズ・インターナショナルの企業分析を行っており、その戦略を高く評価しています。ゴールドマン・サックスがレストラン・ブランズ・インターナショナルの戦略分析で特に重視している点は、新経営陣による事業転換、フランチャイジーの収益性向上への集中的な取り組み、そして米国での大手フランチャイジー買収による店舗の近代化加速です。
ゴールドマン・サックスは特に、米国でレストラン・ブランズ・インターナショナルが大手フランチャイジーであるキャロル・レストラン・グループを買収し、店舗の近代化を加速させている動きを、米国事業の広範なターンアラウンドに不可欠な施策として高く評価しています。
ゴールドマン・サックスが日本で実行しようとしている戦略は極めて明確です。それは、レストラン・ブランズ・インターナショナル本社が米国でReclaim the Flame(炎を取り戻せ)というスローガンの下で実行し、成功を収めつつある店舗の近代化、フランチャイジー収益性の改善、それによる平均販売台数の向上という勝ち筋のプレイブックを、ゴールドマン・サックスが日本の強力な資本パートナーとして、バーガーキング日本事業に徹底的に導入し、実行することです。
600店舗体制を実現するには、既存の直営店モデルだけでは限界があり、優秀なフランチャイジーの獲得が不可欠です。ゴールドマン・サックスは日本で、まず既存の店舗の収益性をこのプレイブックによって劇的に高め、その成功モデルを提示することで、新たな優良フランチャイジーを惹きつける戦略をとると考えられます。
ゴールドマン・サックスの情報優位性
ゴールドマン・サックスがこの取引に踏み切るもう一つの重要な理由として、彼らが持つ究極の情報優位性があります。アフィニティ・エクイティ・パートナーズは2022年にも日韓事業の売却を試みましたが、その際に売却側のアドバイザーとして起用したのが、他ならぬゴールドマン・サックスだったのです。
これは、ゴールドマン・サックスが2022年時点で、バーガーキング日本事業の財務状況、店舗ごとの収益性、アフィニティ・エクイティ・パートナーズが抱えていた経営課題、そしてそのポテンシャルを内部から徹底的に調査・分析していたことを意味します。
ゴールドマン・サックスは、アフィニティ・エクイティ・パートナーズが2022年の売却延期後に実行した149店から310店への店舗拡大プロセスと、それに伴うEBITDAの改善の軌跡を、他の誰よりも詳細に把握していた可能性が極めて高いのです。今回のゴールドマン・サックスによる買収は、未知の資産への飛び込みのディールではなく、3年越しで成熟を待っていた果実を、完璧な情報優位性を持って獲得する、計算ずくの戦略的投資といえます。
レストラン・ブランズ・インターナショナルのアジア事業再編
今回の日本事業の売却交渉は、日本市場だけの孤立した事象ではありません。これは、バーガーキングの親会社であるレストラン・ブランズ・インターナショナルがグローバルで推し進める、より広範なアジア事業の再編の重要な一部分なのです。
この再編の動きを象徴するのが、中国事業の売却です。日本でのゴールドマン・サックスとの独占交渉が報じられるほんの数日前、2025年11月10日に、レストラン・ブランズ・インターナショナルは中国事業に関する重大な発表を行いました。レストラン・ブランズ・インターナショナルは、バーガーキング中国の株式の83%を、中国の有力プライベート・エクイティファンドであるCPEに3億5,000万ドルで売却することに合意したのです。
この中国でのディールは、レストラン・ブランズ・インターナショナルの新たなアジア戦略を明確に示しています。レストラン・ブランズ・インターナショナルは中国事業の株式17%と取締役会の議席は維持します。ブランドやグローバル基準はレストラン・ブランズ・インターナショナルが管理するものの、店舗展開の資本、不動産開発、そして現地でのオペレーションは、その市場を最もよく知る最強の地元パートナーに任せるというモデルです。
この新しいジョイントベンチャーの目的は、中国での成長を加速させることです。パートナーであるCPEは、5年以内に店舗数を倍増させ、2035年までには4,000店舗以上に拡大するという野心的な計画を掲げています。
なぜレストラン・ブランズ・インターナショナルが経営の主導権を手放したのかという疑問には、明確な理由があります。中国市場はレストラン・ブランズ・インターナショナルにとって店舗数ベースで最大のグローバル市場で、1,474店舗を展開していましたが、深刻な問題を抱えていました。1店舗あたりの平均売上が約40万ドルと、例えばフランス市場の380万ドルなどと比較して、極端に低迷していたのです。
レストラン・ブランズ・インターナショナルは、自力での中国市場の経営改善は困難と判断しました。そこで彼らは、アジアの主要市場において、自社でリスクを負って直営展開や煩雑なマスターフランチャイズ管理を行う重い戦略を放棄したのです。
このレストラン・ブランズ・インターナショナルのアジア・ピボットの文脈で日本の取引を見ると、全てが繋がります。レストラン・ブランズ・インターナショナルにとって、日本市場も中国市場と同様、自社で直接コントロールするには複雑で、コストがかかり、そしてマクドナルドという絶対王者が存在する難しい市場です。レストラン・ブランズ・インターナショナルの新しいグローバル戦略は、ブランドはレストラン・ブランズ・インターナショナルが握るものの、店舗展開の資本とオペレーションは、その市場で最強の地元パートナーに任せるというものです。
中国市場において、その最強パートナーとしてCPEが選ばれました。そして日本市場において、その最強パートナーとして、世界的な外食産業の知見と700億円の資本を用意できるゴールドマン・サックスが選ばれたのです。今回のゴールドマン・サックスによる買収は、レストラン・ブランズ・インターナショナル本社が進めるこのアジア戦略の転換と完璧に連動した動きといえます。
日本のハンバーガー市場の競争環境
アフィニティ・エクイティ・パートナーズによるV字回復、ゴールドマン・サックスの資本力、レストラン・ブランズ・インターナショナルのグローバル戦略という好材料が揃っていても、ゴールドマン・サックスが700億円を投じて参入する日本市場は、決して容易な市場ではありません。そこは、複数の強力なプレイヤーが激しく競い合う、過酷な戦場なのです。
絶対王者マクドナルドの圧倒的な強さ
日本のファストフード市場の絶対王者である日本マクドナルドホールディングスは、もはやハンバーガーチェーンではなく、外食インフラと呼ぶべき存在です。その強さは業績に端的に表れており、日本マクドナルドは2015年第4四半期から2025年第3四半期に至るまで、実に40四半期連続で既存店売上高が増加するという、前人未到の記録を更新中です。2025年12月期の通期業績予想も増収増益を見込んでおり、その勢いに陰りはありません。
この鉄壁の強さを支えるのが、メニュー・バリュー、店舗ポートフォリオ・デジタル、サステナビリティ・ピープルの3本柱戦略です。特に、ゴールドマン・サックス率いるバーガーキング日本事業の前に立ちはだかるのが、店舗ポートフォリオ・デジタル戦略です。
マクドナルドは、店舗の大型化、ドライブスルーの拡充、そして顧客体験の向上を目的とした店舗リモデルに巨額の投資を続けており、2025年度だけで約200店舗のリモデルを計画しています。さらに、他社を圧倒するモバイルオーダーやマックデリバリー、そして2025年からは米国でデジタルマーケティング基金を設立するなど、デジタルと利便性において他社の追随を許さないインフラを構築しています。バーガーキングがこれから600店舗を目指す中で、マクドナルドは既存の約3,000店舗の質をさらに高め、利便性の砦を築いているのです。
ゼンショー・ロッテリア連合の台頭
バーガーキングの旧運営会社であるロッテリアも、日本市場における重大な脅威へと変貌を遂げました。2023年、国内の外食最大手であり、すき家やはま寿司を運営するゼンショーホールディングスが、ロッテホールディングスからロッテリアの全株式を取得したのです。
この買収の狙いは明確で、シナジー効果の追求です。ゼンショーが持つ日本最大級の食材調達網、全国を網羅する物流ネットワーク、そして数千店舗を運営する高度な店舗運営ノウハウが、ロッテリアに注入されることになります。
これにより、ロッテリアは他のバーガーチェーンが決して真似のできないレベルのコスト競争力とバリューを手に入れることになります。マクドナルドが利便性で市場を支配するならば、ゼンショー・ロッテリア連合は、その巨大な物流・調達インフラを武器に、価格とバリューの市場を支配しに来ると考えられます。
モスバーガーの独自ポジション
この強力な競合に対して、独自のポジションを確立しているのがモスフードサービスです。モスバーガーは、おいしさ、安全、健康という創業以来の理念をモスの心として2025年に再整理し、価格や利便性とは異なる価値を求める、強固なブランド・ロイヤルティを持つ顧客層を維持しています。
2025年から2027年の中期経営計画では、ブランドをMOS BURGERからMOSへと拡張し、既存のハンバーガーの枠にとらわれない成長を目指しています。モスバーガーは品質、健康、日本的という独自のプレミアム・ニッチ市場を固めているのです。
バーガーキング日本事業の成功への道筋
この厳しい競争環境の中で、ゴールドマン・サックスとバーガーキングが600店舗を達成し、生き残るための活路はどこにあるのでしょうか。それは価格でも利便性でも健康志向でもありません。それは、バーガーキングの代名詞であるワッパーという絶対的な主力商品、独自の直火焼きという調理法、そして競合他社には真似のできないエッジの効いたブランド・マーケティングという、バーガーキングにしか提供できない強烈なブランド体験の一点突破です。
ゴールドマン・サックスが投じる700億円の資本は、この強烈なブランド体験を、日本中の消費者の手の届く場所、すなわち600店舗という規模に配置するためだけに使われることになるでしょう。
マクドナルドが提供する圧倒的な利便性、ゼンショー・ロッテリアが提供する驚異的な価格、モスバーガーが提供する安心の品質、そしてバーガーキングが提供する直火焼きのワッパー体験という、明確に差別化された選択肢が日本の消費者に提供されることになります。
今後の展望と市場への影響
ゴールドマン・サックスによる700億円規模のバーガーキング日本事業の買収は、単なるプライベート・エクイティファンド間の資産の移転ではありません。これは、日本のファストフード市場の勢力図を塗り替える可能性を秘めた、壮大な戦略的投資なのです。
この700億円の投資は、アフィニティ・エクイティ・パートナーズがV字回復させたバーガーキング日本事業という資産に、レストラン・ブランズ・インターナショナルのグローバルなフランチャイジー収益性改善のプレイブックを注入し、日本市場で絶対王者のマクドナルドと、国内の巨人ゼンショー・ロッテリア連合に伍する第三の柱を確立できるかという挑戦です。
アフィニティ・エクイティ・パートナーズのフェーズは、競合の束縛からブランドを解放し、店舗数を増やしてEBITDAを改善するという、比較的シンプルな資本のゲームでした。しかし、ゴールドマン・サックスがこれから挑むフェーズ2は、マクドナルドのデジタル網とゼンショーの物流網という巨大なインフラと正面から戦いながら、店舗ごとの収益性を高めるという、はるかに複雑な運営のゲームとなります。
日本のハンバーガー市場は、二つの異なるM&Aモデルが激突する戦場となりました。ゼンショーによるロッテリア買収が国内産業の水平統合の象徴だとすれば、今回のゴールドマン・サックスによるバーガーキング日本事業買収は、グローバル資本による垂直的成長の象徴です。
このバーガー戦国時代の激化は、日本の消費者にとっては朗報といえます。複数の強力なプレイヤーが競い合うことで、サービスの質、商品の多様性、そして価格競争力が高まり、消費者が享受できる選択肢の質と量が劇的に向上することが期待されます。
ゴールドマン・サックスによる700億円の巨額投資の成否は、バーガーキングというブランドが、マクドナルドとゼンショーという二つのインフラの狭間で、独自のブランド体験という名の第三の柱を日本市場に打ち立てることができるかどうかにかかっています。2028年末までの600店舗達成という野心的な目標に向けた取り組みが、今後の日本のファストフード業界の動向を大きく左右することは間違いありません。


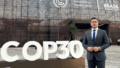
コメント