2025年11月10日から21日まで、ブラジルのベレンで開催されるCOP30(国連気候変動枠組条約第30回締約国会議)は、地球温暖化対策の新たな転換点として世界中から注目を集めています。地球の肺とも称されるアマゾン熱帯雨林地域に位置するベレンでの開催は、気候危機の深刻さを象徴するとともに、自然と調和した持続可能な未来への道筋を示す重要な意味を持ちます。パリ協定採択から10年という節目の年に開催されるこの会議では、各国の新たな削減目標の提出と評価が行われ、1.5度目標達成に向けた具体的な行動計画が求められています。日本政府は、緩和策の重視、技術力を活かした国際貢献、気候資金の拠出、持続可能燃料の拡大など、多面的なアプローチでCOP30に臨む方針を示しており、2050年カーボンニュートラル実現に向けた強い決意を国際社会に発信しようとしています。

COP30ベレン会議の重要性と開催背景
2025年11月10日から21日までの12日間にわたって開催されるCOP30は、気候変動対策における極めて重要な国際会議です。開催地のベレンは、アマゾン熱帯雨林地域の中心都市であり、この選定には深い象徴的意義があります。アマゾンは世界最大の熱帯雨林として地球の気候システムにおいて不可欠な役割を果たしていますが、同時に森林減少や気候変動の影響を強く受けている地域でもあります。
2025年はパリ協定が採択されてから10年の節目の年であり、協定の実効性が試される重要な時期を迎えています。パリ協定では、産業革命前と比較して地球の平均気温上昇を2度より十分下方に抑え、1.5度に抑える努力を継続することが合意されました。しかし2024年には地球の平均気温が初めて年間を通じて1.5度を突破し、目標達成が危ぶまれる危険水域に達しています。
COP30は気候変動対策の「再スタート」となる世界会議と位置づけられており、各国政府関係者、国際機関、NGO、企業、研究者など多様なステークホルダーが集結します。この会議では、各国が提出する2035年の削減目標を含む新たなNDC(国別削減目標)の評価が行われ、1.5度目標達成に向けた道筋が議論される予定です。
なぜベレンが選ばれたのか──「ネイチャーCOP」の意義
COP30が「ネイチャーCOP」として特に注目されている理由は、開催地であるベレンが世界最大の熱帯雨林アマゾンの中心都市であることに起因します。アマゾン熱帯雨林は地球全体の酸素供給源として機能するとともに、膨大な量の二酸化炭素を吸収する重要な役割を担っています。しかし近年、違法伐採や農地開発によって森林減少が深刻化しており、気候変動をさらに加速させる要因となっています。
従来、気候変動対策と生物多様性保全は別々の課題として扱われることが多かったのですが、科学的研究の進展により、これらが密接に関連した一つの危機であることが明らかになってきました。森林や海洋などの自然生態系は、大量の二酸化炭素を吸収し貯蔵する機能を持っており、これらの生態系が破壊されることは気候変動を加速させる直接的な原因となります。
議長国ブラジルが推進するバイオエコノミーは、自然保護と経済開発を対立するものとして捉えるのではなく、自然資本を健全に維持し活用することで持続可能な経済成長を実現しようとする革新的な経済モデルです。COP30では、森林再生プロジェクト、先住民族の権利保護と伝統的知識の活用、生物多様性に基づく持続的な経済活動などが重要なテーマとして議論される見込みです。
パリ協定と1.5度目標の現状
パリ協定は2015年12月に採択され、気候変動対策における国際的な枠組みとして機能してきました。この協定では、温室効果ガス排出削減の長期目標として、産業革命前と比較した地球の平均気温上昇を2度より十分下方に抑えるとともに、1.5度に抑える努力を継続することが明記されています。
しかし2024年の観測データによれば、地球の平均気温が初めて年間を通じて1.5度を突破し、パリ協定の目標達成が極めて困難な状況に直面しています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の科学的評価によれば、1.5度目標を達成するためには、2025年までに世界全体の温室効果ガス排出量をピークアウトさせ、2030年までに2019年比で43パーセント、2035年までに60パーセントの大幅な削減が必要とされています。
本来であれば2025年2月が2035年の削減目標を含む新たなNDCの提出期限でしたが、2025年9月初旬時点で正式に提出した国は限られており、世界の国・地域の8割以上が未提出の状況でした。COP30開催の2ヶ月前という段階でも多くの国が目標を提出していないことは、グローバルな気候変動対策の機運が十分に高まっていないことを示しています。
国際社会は今、気候変動という人類共通の危機に対して、より強力で実効性のある対策を講じる必要性に迫られています。COP30は、各国が野心的な削減目標を掲げ、具体的な行動計画を示す重要な機会となります。
日本政府がCOP30で重視する基本方針
日本政府はCOP30に向けて、明確な基本方針を策定しています。その中核となるのが、緩和策(温室効果ガス削減)の推進です。日本は、気候変動問題に対処する上で最も重要なことは、温室効果ガスの排出そのものを削減する緩和策を進めることであると強調しています。
緩和策とは、温室効果ガスの排出量を減らすための取り組み全般を指し、再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギー技術の開発と普及、化石燃料依存からの段階的な脱却、産業プロセスの効率化などが含まれます。日本は技術立国として、これらの分野において世界をリードする革新的な技術を開発し、国際社会に貢献できる立場にあると認識しています。
日本政府はまた、NDCの未提出国に対して早期提出を促す立場を明確にしています。各国が可能な限り野心度の高い削減目標を設定し、それを確実に実行に移すことが、地球規模での気候変動対策の成功には不可欠です。COP30において、新たなNDCを踏まえた1.5度目標からの現在地の評価や、目標達成への具体的な道筋、現行のNDCの世界全体での実施状況について議論することの重要性を訴えています。
日本は、主要排出国を含むあらゆる国が脱炭素化に真剣に取り組むべきであるという立場を一貫して示しており、国際的な協調と公平な負担分担を重視しています。先進国だけでなく、新興国や途上国も含めた全ての国が、それぞれの能力と状況に応じて最大限の努力を行うことが求められています。
日本の温室効果ガス削減目標の詳細
日本は2020年10月に、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)を実現するという野心的な長期目標を宣言しました。この目標は、2050年度までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指すものであり、日本の経済社会システム全体の抜本的な変革を伴う挑戦です。
2021年10月22日には、日本のNDCを国連気候変動枠組条約事務局に正式に提出しました。このNDCでは、2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で46パーセント削減し、さらに50パーセントの高みに向けて挑戦を続けることが明記されています。この目標は、従来の目標から大幅に引き上げられたものであり、国際社会に対して日本の強い決意を示すものとなりました。
2025年2月18日には、環境省が新たな中期目標を発表しました。2035年度までに63パーセント削減、2040年度までに70パーセント削減(いずれも2013年度比)という段階的な目標を設定し、2050年度のカーボンニュートラル達成に向けた道筋をより明確化しました。これらの目標は既に国連に提出されており、日本は国際公約として確実な実施を求められています。
これらの削減目標の達成には、エネルギー政策の抜本的な転換、産業構造の変革、技術革新の加速、国民一人ひとりのライフスタイルの見直しなど、社会全体での大規模な取り組みが必要となります。政府は、規制的手法と経済的インセンティブを組み合わせた政策パッケージを通じて、官民一体となった削減努力を推進しています。
ジャパン・パビリオンによる国際技術発信
環境省は、COP30において「ソリューションを世界の隅々へ」をテーマに掲げた「ジャパン・パビリオン」を設置し、日本の優れた環境技術や先進的な取り組みを国際社会に発信します。このパビリオンは、日本が長年培ってきた技術力とノウハウを世界と共有し、グローバルな脱炭素化に貢献する重要なプラットフォームとなります。
ジャパン・パビリオンでは、日本の気候変動対策の長期目標である2050年ネット・ゼロの実現と、世界の脱炭素化や気候変動への適応を支える様々な技術、製品、サービスが展示されます。具体的には、世界最高水準の省エネルギー技術、太陽光や風力などの再生可能エネルギー技術、水素・アンモニアを活用した次世代エネルギー技術、二酸化炭素を有効活用するカーボンリサイクル技術、気候変動の影響に対する適応技術などが紹介される予定です。
特に注目されるのは、日本が世界に先駆けて開発を進めている水素社会関連技術です。水素は燃焼時に二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源であり、発電、運輸、産業プロセスなど幅広い分野での活用が期待されています。日本は水素の製造、貯蔵、輸送、利用に関する一貫した技術開発を進めており、これらの成果を国際社会と共有することで、世界の水素経済への移行を後押しします。
また、日本国内だけでなく世界中の国々から参加できるオンラインセミナーやバーチャル展示も実施されます。地理的な制約を超えて、より多くの人々が日本の取り組みについて学び、技術導入や協力の可能性を探る機会が提供されます。このデジタル技術を活用したアプローチは、知識の民主化と国際協力の促進に大きく貢献すると期待されています。
持続可能燃料の拡大に向けた国際宣言
COP30では、議長国のブラジルが日本やイタリアなどとともに、2035年までに持続可能燃料の使用を4倍以上に増やすことを目指す国際宣言を表明する予定です。この宣言は「ベレン・グリーン産業化宣言」として知られており、現時点で12カ国が署名を表明しています。
持続可能燃料とは、バイオ燃料、合成燃料、グリーン水素などを指し、化石燃料に代わるクリーンなエネルギー源として注目されています。これらの燃料は、原料の生産から利用までのライフサイクル全体で見たときに、温室効果ガス排出量を大幅に削減できる特徴があります。特に航空業界や海運業界など、電化が技術的・経済的に困難な分野において、持続可能燃料は脱炭素化の重要な選択肢となります。
バイオ燃料は、植物や廃棄物などのバイオマスを原料として製造される燃料であり、植物の成長過程で大気中の二酸化炭素を吸収するため、燃焼時の排出と合わせるとカーボンニュートラルまたは低炭素となります。合成燃料は、再生可能エネルギー由来の電力を使って水素と二酸化炭素から合成される燃料であり、既存のインフラを活用できる利点があります。
日本は、これらの持続可能燃料の技術開発と実用化において先進的な取り組みを進めています。特にグリーン水素の製造技術や、水素をより効率的に貯蔵・輸送するためのアンモニア活用技術などで世界をリードしています。「10年で4倍」という具体的な数値目標を国際的に共有することで、各国の政策支援や民間投資を促進し、持続可能燃料市場の拡大を加速させる狙いがあります。
気候資金と途上国支援の枠組み
COP29(2024年11月開催)では、温暖化対策で先進国から発展途上国向けに拠出する気候資金について重要な合意が成立しました。この合意では、2035年までに少なくとも年3000億ドル(約46兆4000億円)に資金を増やすことが決定されました。これは公的資金と民間資金を合わせた資金の流れを指しており、国際的な目標として各国が取り組むべき水準を示しています。
さらに、2035年までに世界全体で官民合わせて途上国への支援額を少なくとも年1兆3000億ドルに増やすという、より野心的な目標も採択されました。この金額は現行の資金拠出額の約3倍に相当する規模であり、気候変動対策における国際協力の大幅な強化を意味しています。
ただし、途上国側からは「不十分である」との強い不満が表明されています。途上国グループは最低でも年5000億ドル、可能であれば1兆ドル以上の公的資金による支援を求めており、先進国と途上国の間には依然として大きな認識の隔たりが存在します。気候変動の影響を最も強く受けるのは脆弱な途上国であり、適応策の実施や損失・損害への対応には膨大な資金が必要となります。
COP29では、新しい資金源の検討を行うための「1.3兆ドルに向けたバクーからベレンへのロードマップ」が設立され、COP30において進捗報告が行われることになっています。このロードマップでは、革新的な資金調達メカニズム、民間資金の動員手法、炭素市場の活用などが検討される予定です。
日本はこれまでも、アジア、アフリカ、中南米、中東など世界各地の気候変動対策プロジェクトに協力し、技術支援と資金拠出を行ってきました。再生可能エネルギーの導入支援、省エネルギー技術の移転、気候変動適応策の実施、人材育成など、多岐にわたる分野で途上国を支援しています。日本の経験と技術を活かした支援は、途上国の持続可能な発展に大きく貢献しています。
適応策の重要性と日本の取り組み
パリ協定では温室効果ガス排出削減という緩和策が主要な柱となっていますが、同時に適応策の重要性も強調されています。たとえ1.5度目標を達成したとしても、気候変動による影響は完全には避けられないため、その影響に適切に対処する適応策が極めて重要となります。
適応策とは、既に起きている、あるいは今後予想される気候変動の影響に対して、自然や社会のあり方を調整することで被害を最小限に抑える取り組みのことです。具体的には、洪水や高潮に対する防災インフラの整備、渇水や干ばつに強い農作物品種の開発、熱中症対策としての都市緑化や冷却施設の整備、気候変動に伴う感染症リスクへの対応などが含まれます。
日本は、国内での適応策の実施において先進的な取り組みを進めています。2018年12月には気候変動適応法が施行され、国、地方自治体、事業者、国民が連携して適応策を推進する法的枠組みが整備されました。各分野における気候変動影響の評価と適応計画の策定が進められており、科学的知見に基づいた体系的なアプローチが実践されています。
国際的には、日本は途上国における適応策の支援に力を入れています。特にアジア太平洋地域の島嶼国や沿岸国は、海面上昇、台風の強大化、サンゴ礁の白化などの気候変動影響を強く受けており、日本の技術や経験を活かした支援が強く求められています。防災技術、水資源管理、農業技術、気象観測システムなど、日本が長年培ってきた知見を途上国と共有し、現地の能力向上を支援することが重要な国際貢献となっています。
自然資本とTNFDの動向
近年、企業経営において自然資本や生物多様性への配慮がますます重要になっています。この流れを象徴するのが、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の設立と普及です。TNFDは、企業や金融機関が自然資本や生物多様性に関するリスクと機会を評価し、情報開示するための国際的な枠組みです。
TNFDは、気候変動の情報開示枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)と並行して重要性が高まっています。企業は、自社の事業活動が森林、水資源、海洋、土壌などの自然環境にどのような影響を与えているか、また自然環境の変化が自社の事業にどのようなリスクやチャンスをもたらすかを評価し、開示することが求められるようになっています。
日本企業においても、TNFDへの対応が急速に進んでいます。特に国際的なサプライチェーンを持つ企業は、森林破壊や生態系の破壊に関与していないことを証明する必要性が高まっており、調達方針の見直し、サプライヤーへの監査強化、トレーサビリティの確保などの取り組みを進めています。
例えば、パーム油、大豆、木材、紙などの原材料は、熱帯雨林の破壊と関連していることが指摘されており、これらを使用する食品メーカーや製紙会社は、持続可能な調達を証明できる認証制度の活用や、サプライチェーンの透明性向上に取り組んでいます。金融機関も、融資や投資の判断において自然資本への影響を考慮するようになっており、企業の環境パフォーマンスが資金調達コストに影響を与える時代となっています。
日本のエネルギー戦略
日本政府は、2050年カーボンニュートラルを達成するための重要な柱として、再生可能エネルギーの拡大と水素・アンモニア技術の開発に力を入れています。2030年度の電源構成における目標として、再生可能エネルギーを36パーセントから38パーセント、原子力を20パーセントから22パーセント、水素・アンモニア火力を1パーセントと設定しています。
この目標は、現状からの大幅な転換を意味しています。再生可能エネルギーの導入拡大には、送電網の整備、蓄電池の大量導入、デマンドレスポンス(需要側の柔軟な調整)の促進など、多面的な取り組みが必要です。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは天候によって発電量が変動するため、電力の安定供給を確保するための技術革新とインフラ投資が不可欠となります。
日本政府は、今後10年間でマスタープランに基づき系統整備を加速する方針を示しています。全国規模での送電網の強化により、再生可能エネルギーが豊富な地域で発電された電力を需要地に効率的に送ることが可能になります。また、蓄電設備の拡充により、発電量の変動を吸収し、電力需給のバランスを保つことができます。
水素技術においては、製造方法によって環境負荷が大きく異なります。風力や太陽光などの再生可能エネルギーを使って水を電気分解して製造するグリーン水素は、製造時にも全く二酸化炭素を排出しない最も環境に優しい水素です。一方、天然ガスなどの化石燃料から水素を製造する際に、発生する二酸化炭素を回収・貯留する技術(CCS)と組み合わせたブルー水素も、移行期における現実的な選択肢として位置づけられています。
日本は、グリーン水素の製造・利用技術の開発に注力しており、将来的には水素社会の実現を目指しています。水素は発電だけでなく、運輸部門(燃料電池自動車、船舶、航空機)、産業部門(製鉄、化学)など幅広い分野での脱炭素化に貢献することが期待されています。
GX(グリーントランスフォーメーション)推進
日本政府は、気候変動対策を単なる環境規制としてではなく、経済成長の機会として捉える「GX(グリーントランスフォーメーション)」を強力に推進しています。GXとは、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを通じて、経済社会システムを変革し、持続可能な成長を実現することを意味します。
経済産業省は、GXを「2050年カーボンニュートラルおよび2030年の温室効果ガス削減目標の実現を、経済成長の機会と捉える取り組み」と定義しています。従来、環境対策は経済成長の制約要因と捉えられることが多かったのですが、GXの考え方では、脱炭素化への取り組みが新たな産業を生み出し、技術革新を促進し、国際競争力を高める機会となると位置づけられています。
日本政府は、今後10年間で官民合わせて150兆円のGX投資を実現することを目標としています。この巨大な投資は、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー技術の開発、水素・アンモニア技術の実用化、カーボンリサイクル技術の開発、次世代自動車の普及、グリーン建築の推進など、極めて幅広い分野に向けられます。
政府は、GX経済移行債を発行し、今後10年間で約20兆円を調達する計画を進めています。この資金は、民間投資を呼び込むための呼び水として活用され、官民一体となった大規模な投資の実現を目指しています。技術開発への補助金、脱炭素設備導入への支援、グリーンプロジェクトへの融資保証などを通じて、企業のGX投資を後押しします。
GX推進の重要な政策ツールとして、成長志向型カーボンプライシングの導入が計画されています。これは、企業の二酸化炭素排出に価格をつけることで、排出削減を促すとともに、脱炭素技術への投資を加速させる仕組みです。具体的には、2028年度から化石燃料賦課金を開始し、2033年度からは発電事業者に対する有償排出枠取引を導入する予定です。
企業にとって、GXへの取り組みは単なるコスト負担ではなく、企業価値向上の機会となっています。ESG投資の拡大により、気候変動対策に積極的な企業は投資家から高く評価され、資金調達が有利になる傾向があります。また、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められるようになっており、大企業が取引先である中小企業に対しても温室効果ガス排出削減の取り組みを求めるケースが増加しています。
森林保全とカーボンクレジット
COP30が「ネイチャーCOP」と呼ばれることから明らかなように、森林保全は極めて重要な議題となります。日本も国内外で森林保全に積極的に取り組んでおり、カーボンクレジット制度を活用した革新的な仕組みを推進しています。
REDD+(レッドプラス)は、「途上国における森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減」を意味する国際的な枠組みです。先進国が資金を拠出し、途上国が森林保全に取り組むことで、地球規模での温室効果ガス削減を進める仕組みとして機能しています。森林は膨大な量の二酸化炭素を吸収・貯蔵しており、森林破壊が進むと蓄えられていた二酸化炭素が大気中に放出されます。REDD+は、森林を保全することでこの排出を防ぐとともに、森林の二酸化炭素吸収機能を維持することを目指しています。
自主的カーボン市場における森林・土地セクター由来のカーボンクレジットは、市場全体の45.8パーセントを占めており、極めて重要な位置を占めています。しかし近年、プロジェクトレベルのREDD+カーボンクレジットについて、ベースライン設定(プロジェクトを実施しなかった場合の排出量推定)やリーケージ(森林保全地域外での森林破壊の発生)の問題に関する批判があり、民間企業が森林クレジットへの投資を躊躇する状況も生まれています。
日本には、国内独自の森林カーボンクレジット制度として森林J-クレジットがあります。これは、政府が排出削減量や吸収量を認証する信頼性の高い制度であり、適切な森林管理によって生み出される二酸化炭素吸収量を、確立されたルールに従ってクレジットとして認証します。日本政府は、森林J-クレジットの創出を拡大する方針を示しており、2030年までに500万トンの森林J-クレジットを創出することを目指しています。
COP30では、2030年までに森林破壊ゼロを達成するという国際的な目標に向けた進捗状況が評価される見込みです。日本は、REDD+への資金拠出、技術協力、森林保全プロジェクトの支援などを通じて、国際的な森林保全に貢献しています。また、企業の再生材利用率を開示する国際枠組みを日本主導で提案する方針が報道されており、資源循環と森林保全を結びつけた新たな取り組みが期待されています。
日本の国際的役割と今後の課題
日本は、技術力と資金力を活かして国際的な気候変動対策に大きく貢献できる立場にあります。省エネルギー技術、再生可能エネルギー技術、水素技術、カーボンリサイクル技術などの分野で世界をリードしており、これらの技術を途上国に移転することで、世界全体の脱炭素化に貢献できます。
しかし、日本にはいくつかの重要な課題も存在します。まず、石炭火力発電への依存度が依然として高く、国際的には「石炭依存国」としての批判を受けることがあります。日本政府は石炭火力発電の段階的廃止に向けた明確な計画とスケジュールを示すことが国際社会から求められています。
また、高市首相がCOP30への出席を見送る方針を示していることは、国際的な懸念を招いています。トップリーダーの会議欠席は、日本の気候変動対策への本気度が疑問視され、国際交渉における存在感や影響力の低下につながる可能性があります。気候資金目標や国際協調をどのように前進させていくのか、首相が不在の中で日本がどのようにリーダーシップを発揮するかが問われています。
さらに、日本の削減目標は国際的に見て十分に野心的であるとは言えないとする指摘もあります。一部の専門家や環境団体は、日本は2030年の削減目標を60パーセント以上に引き上げるべきだと主張しており、より積極的な目標設定が求められています。科学的知見に基づけば、1.5度目標達成には2030年までに43パーセント削減が必要とされており、日本の46パーセントという目標は最低限のラインに近いと見られています。
COP30において日本は、ジャパン・パビリオンでの技術発信、気候資金の拠出、途上国への技術移転と人材育成、持続可能燃料の拡大、アジア太平洋地域でのリーダーシップ発揮など、多面的な貢献を通じて国際社会における存在感を示すことが期待されています。同時に、国内における脱炭素化の取り組みを加速し、石炭火力依存からの脱却を進め、より野心的な目標を掲げることで、言葉だけでなく行動で示すことが求められています。
気候変動は、もはや将来の問題ではなく、現在進行形の危機です。2024年には地球の平均気温が初めて年間を通じて1.5度を突破し、極端な気象現象が世界各地で頻発しています。日本各地でも、記録的な豪雨、猛暑、台風の大型化などが観測されており、気候変動の影響は日常生活にも及んでいます。
COP30が、地球規模での気候変動対策を加速させる真の転換点となることが強く望まれています。日本が技術力、資金力、そして国際協調への強い意志を示すことで、世界の脱炭素化をリードし、次世代に持続可能な地球環境を引き継ぐことができるでしょう。2025年11月にベレンで開催されるCOP30は、日本がその決意を世界に示す極めて重要な機会となります。

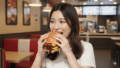

コメント