私たちの社会には、静かに、しかし確実に広がり続けている深刻な現実があります。こども家庭庁が発表した令和5年度の統計によれば、全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、約22万6,000件に達しました。この数字は過去最多を更新し続けており、想像を超える規模で、子どもたちが危機に瀕していることを示しています。胸につけられたオレンジ色のリボンには、こうした子どもたちを守るための深い願いが込められています。児童虐待防止のシンボルとして知られるこのオレンジリボンは、単なるキャンペーンマークではなく、ある痛ましい事件をきっかけに市民の手によって生み出された運動の証なのです。そして、虐待かもしれないと感じた時に誰でもすぐに通報できる全国共通の電話番号「189(いちはやく)」は、命を救うための最も強力な手段となっています。11月の児童虐待防止推進月間を前に、私たち一人ひとりが知っておくべき知識と、今すぐにでもできる行動について、詳しくお伝えします。

深刻化する児童虐待の実態と見えにくい心の傷
全国で22万6,000件という膨大な数の児童虐待相談が対応されている中で、特に注目すべき傾向が浮かび上がっています。対応件数のうち、最も多いのは心理的虐待であり、全体の約6割にあたる59.8%を占めているのです。これは、殴る、蹴るといった身体的虐待の22.9%や、育児を放棄するネグレクトの16.2%を遥かに上回る割合となっています。つまり、現代の児童虐待の主流は、外からは見えにくい心の傷なのです。
児童相談所への通告経路を見ると、最も多いのは警察等からの通報であり、全体の半数以上にあたる51.7%を占めています。近隣や知人からの通報は9.8%、学校からは7.4%に過ぎません。この数字が示すのは、本来であれば早期に発見すべき地域コミュニティや学校のセーフティネットが、目に見えない心理的虐待のサインを見過ごしてしまい、事態が深刻化して警察が介入するレベルになって初めて発覚しているケースが多いという現実です。
心理的虐待の定義には、言葉による脅しや脅迫、子どもを無視したり拒否的な態度を示すこと、子どもの心を傷つけることを繰り返し言うこと、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをすることなどが含まれます。そして特に重要なのは、子どもの目の前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるうこと、すなわち面前DVも、明確に心理的虐待に含まれると定義されていることです。
警察からの通報が最も多く、同時に心理的虐待が最も多い理由の多くは、この面前DVにあります。警察が介入する事案の多くは、家庭内での暴力や激しい口論です。大人がDVを目撃させることは、たとえ子どもに直接手を上げていなくても、それ自体が子どもに対する心理的虐待として明確にカウントされるのです。夫婦喧嘩は家庭内の問題という古い価値観は、もはや通用しません。子どもが目撃した時点で、それは児童虐待であり、即座に通報の対象となるべき社会的な問題であると、私たちは認識をアップデートする必要があります。
オレンジリボンに込められた悲しみと希望の起源
毎年11月になると、多くの人が胸につけるオレンジリボンは、子ども虐待防止のシンボルマークとして広く知られています。しかし、このリボンが行政のキャンペーンマークではなく、ある痛ましい事件をきっかけに市民の手によって生み出された運動の証であることは、あまり知られていません。
この運動の起源は、2004年9月、栃木県小山市で起きた幼い兄弟の虐待死事件に遡ります。当時、3歳と4歳の兄弟が、凄惨な虐待の末に命を落としました。この悲劇に直面した小山市の市民団体「カンガルーOYAMA」が、二度とこのような事件が起こらないようにという強い願いを込めて、翌2005年にこの運動をオレンジリボン運動として開始しました。行政主導ではなく、悲劇を目の当たりにした市民が自ら立ち上がったという事実こそ、この運動の本質です。
なぜオレンジ色だったのでしょうか。それは、子どもたちの未来が、おひさま(太陽)のように明るく輝き、あたたかく穏やかであるようにという願いが込められているからです。オレンジリボンは、子育てを温かく見守り、子育てを手伝う意志があることを示す意思表示のマークなのです。
この小山市から始まった市民の小さなうねりは、やがてNPO法人児童虐待防止全国ネットワークに引き継がれ、全国的な市民運動へと拡大しました。そして、その想いの強さが国を動かし、政府も公式にこのオレンジリボンをシンボルとして採用し、11月を児童虐待防止推進月間と定めています。私たちがオレンジリボンを身につけることは、単なるキャンペーンへの同調ではありません。それは、小山市の市民たちが抱いた二度と繰り返させないという悲しみと決意のバトンを受け継ぎ、虐待のない社会を築くというネットワークに自ら参加するという、主体的な行動の証なのです。
虐待が起きる背景にある世代間連鎖という負のループ
虐待のニュースに触れると、私たちはしばしば加害者である親を一方的に非難しがちです。しかし、問題を根本的に解決するためには、その背景にあるメカニズムを深く理解しなくてはなりません。虐待の発生要因は一つではありませんが、最も深刻な要因の一つとして指摘されているのが虐待の世代間連鎖です。これは、親自身が子ども時代に実の親から不適切な養育を受けてきた経験が、自分の子育てにおいて連鎖してしまう現象を指します。虐待をしてしまう親の30%から50%に、この世代間連鎖が認められたという報告もあります。
この負のループは、主に3つのメカニズムによって引き起こされます。第一に、愛着形成の不全です。幼少期に親から十分な愛情を受け、安心できる愛着を経験していない親は、自分が親になった時、子どもの愛し方や愛着の築き方がわからず、無関心になったり、逆に過干渉になったりしてしまいます。第二に、トラウマと負の感情の伝達です。虐待を受けた経験がトラウマとなり、自分はダメな親だという低い自己評価や、大人は信頼できないという他者イメージを持ってしまいます。そして第三に、最も重要な要因が孤立です。人を信用できない、頼り方を知らないため、子育てで困難に直面しても誰にも相談できず、一人で問題を抱え込み、社会的に孤立してしまうのです。
この世代間連鎖の核心には、被害的認知と呼ばれる特有の心理メカニズムが存在します。これは、親が子どもの泣き声やぐずりといった、乳幼児の当然の反応に直面した際、それをありのままのサインとして受け取れない状態を指します。自らのトラウマにより、親はそれを自分をわざと困らせようとしている、自分を責めている、自分を否定しているといった、親自身への攻撃や非難として歪んで認知してしまうのです。
その結果、親は、過去に自分が親から否定されたトラウマから自分を守るため、目の前の子どもに対して怒る、無視するといった、かつて自分がされたのと同じ防衛的な行動をとってしまいます。虐待とは、この被害的認知という歪みが生み出す、親自身の未治療のトラウマの症状でもあるのです。したがって、虐待をする親に必要なのは、一方的な非難や罰ではなく、この歪んだ認知とトラウマを修正するための治療であり、孤立から救い出すための支援に他なりません。
妊娠期から始まる切れ目ない支援で連鎖を断ち切る
虐待の根本原因が親の孤立とトラウマにあるならば、社会がすべきことは、その孤立を防ぎ、トラウマを抱えたままでも子育てができるよう支援することです。日本の児童虐待予防策は、問題が発生してからではなく、発生する前、すなわち妊娠期から始まっています。
こども家庭庁は、妊娠期から子育て期まで、公的機関による切れ目のない支援を強力に推進しています。これは、虐待の世代間連鎖を断ち切るための、社会的なセーフティネットです。具体的な支援策として重要なものが3つあります。
一つ目は、特定妊婦への支援です。これは、出産前の支援が特に必要と認められる妊婦、例えば若年での妊娠、経済的困窮、精神的な不安が強い、社会的に孤立しているといったケースを特定妊婦として早期に把握し、保健師などが積極的に家庭訪問を行ったり、相談支援を行う制度です。
二つ目は、産後ケア事業です。出産後、母親はホルモンバランスの急激な変化や睡眠不足により、心身ともに不安定になりがちです。この時期に育児不安や産後うつを抱える母親に対し、助産師や保健師が心身のケアや授乳・育児の指導を行い、孤立を防ぎます。
三つ目は、乳児家庭全戸訪問事業、通称こんにちは赤ちゃん事業です。これは、生後4ヶ月までの乳児がいる全ての家庭を、自治体の担当者や保健師が訪問する事業です。養育環境を把握し、子育てに関する情報提供を行い、何よりもあなたは一人ではないというメッセージを届け、社会とのつながりを作ります。
これらの制度に共通するのは、家庭からの申請を待つ待ちの姿勢ではなく、行政側からアウトリーチし、全ての家庭やハイリスク群に先回りして介入する攻めの姿勢です。虐待リスクの高い親は頼り方を知らない、人を信用できない傾向が強いため、彼ら・彼女らが自ら助けてと声を上げることは期待できません。だからこそ、こんにちは赤ちゃん事業や産後ケアは、単なる子育てサービスではなく、孤立という虐待の最大の要因を防ぎ、社会とのつながりをある意味で強制的に作り出すための、最も重要な虐待予防策なのです。
命を救う189という電話番号の力
予防策が機能していても、なお発生してしまう虐待に対し、私たちが持つ最も強力な介入手段が、児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく)です。これは、虐待かも、と思った時にいちはやく児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
この189には、通報のハードルを可能な限り下げるための、3つの重要な仕組みが備わっています。第一に、通話料無料であることです。令和元年12月より、このダイヤルは通話料が無料化されました。金銭的な負担を一切感じることなく、命を救うための電話をかけることができます。第二に、自動接続であることです。この3桁の番号に電話をかけると、発信地の近くにある児童相談所に自動でつながります。自分が住んでいる地域の管轄の児童相談所がどこなのか、電話番号は何番なのかを、わざわざ調べる必要は一切ありません。第三に、匿名性の担保です。通告・相談は匿名で行うことができ、通報者が誰であるか、どのような内容を話したかに関する秘密は守られることが法律で定められています。
2019年という比較的最近まで、この緊急ダイヤルが有料であったという事実は、通報に対する心理的・経済的な障壁が長らく存在していたことを示しています。この無料化という決定は、単なる利便性の向上ではありません。それは、国が通報は、コストをかけてでも奨励すべき社会的な善であると明確に位置づけた、政策的な転換を意味します。あなたの通報は、国がインフラを整備してでも求めている、社会的に価値のある支援なのです。
通報をためらわないために知っておくべきこと
189の仕組みを理解しても、実際に電話をかけるとなると、多くの人がためらいを感じます。その心理的な障壁を一つひとつ解消することが重要です。
最も大きなためらいは、虐待かどうか確信が持てない、間違いだったらどうしようという不安です。しかし、結論から言えば、虐待かどうかわからない段階でこそ、通報すべきなのです。あなたの役割は虐待かどうかを判断することではありません。それは、専門的な訓練を受けた児童福祉司の仕事です。あなたの役割は、専門家ではないあなたの目から見ても気になる、心配だという事実を、児童相談所に伝えることです。
通報は告発や罰を与える行為ではありません。それは支援の始まりのスイッチです。通報をきっかけに行政が家庭の状況を確認し、もし虐待でなかったとしても、何かしら子育てに困難を抱えている家庭であれば、適切な子育て支援サービスにつなぐ支援のきっかけになります。虐待かもしれないというあなたの迷いこそが、その家庭が何らかの困難を抱えているという、最も重要なサインなのです。
では、具体的にどのようなサインに気づいたらよいのでしょうか。子ども側のサインとしては、いつも子どもの泣き叫ぶ声や養育者の怒鳴り声がすること、不自然な傷や打撲のあとがあること、衣服やからだがいつも汚れていること、表情が乏しく活気がない様子、そして夜遅くまで一人で家の外にいることなどです。
養育者側のサインとしては、地域などと交流が少なく孤立している様子、小さいこどもを家においたまま外出していること、子どもの養育に関して拒否的・無関心である態度、あるいは子どものけがについて不自然な説明をすることなどが挙げられます。これらはほんの一例です。一つでも当てはまれば、それは189に電話をかける十分な理由となります。
通報したら、あの子はどうなるのか、すぐに親から引き離されるのかという不安もあるでしょう。通報後のプロセスがわからないことも、不安の一因です。通報は、決して無責任な引き離しにつながるものではありません。法に基づいた、子どもの命を守るための厳格なプロセスが作動します。
第一に、48時間ルールの作動です。児童相談所は、通告を受けると、原則として48時間以内に子どもを直接目で見て、安全確認を行うことがルール化されています。これは、過去に通報はあったが対応が間に合わず死亡したという悲劇的な事例の反省から生まれた、極めて重要なルールです。
第二に、安全確認後の多様な支援です。安全確認の結果、緊急性が高いと判断されれば、子どもの安全を確保し、客観的に状況を把握するために一時保護が行われることがあります。しかし、必ずしもすぐに保護されるわけではありません。多くのケースでは在宅指導として、家庭訪問や保健師、児童委員などによる見守りや支援が実施されます。
あなたの189への一本の電話は、この48時間以内の安全確認という、法に基づいた迅速なセーフティネットを作動させる最初のスイッチです。あなたの通報がなければ、この命を守るためのカウントダウンは、いつまでも始まらないのです。
11月に日本がオレンジに染まる意味
毎年11月は、児童虐待防止法が施行された月である2000年11月にちなみ、児童虐待防止推進月間と定められています。この期間、全国の自治体や関係機関、そして市民が一体となり、オレンジリボンをシンボルとした集中的な啓発活動を行います。
2025年度の標語は、知らせよう あなたが あの子の声になるです。このスローガンには、極めて重要なメッセージが込められています。過去のスローガンを振り返ると、令和元年度は189(いちはやく)ちいさな命に待ったなし、令和2年度は189(いちはやく)知らせて守るこどもの未来、令和4年度はもしかして?ためらわないで!189、そして令和5年度はあなたしか気づいてないかもそのサインでした。
これまでのスローガンは、主に通報の緊急性や、市民の気づきの重要性を訴えるものでした。市民は傍観者あるいは第一発見者として位置づけられていました。しかし、2025年の標語は、市民の役割をさらに一歩進め、声を出せない子どもの代弁者、すなわち当事者として行動することを促す、極めて能動的なメッセージです。これは、市民を受動的な気づきから能動的な代弁へとシフトさせようとする、こども家庭庁の明確な意志の表れと言えます。
2025年度のキャンペーンは、この声になるというスローガンを社会全体で実現するための、極めて洗練された複合的な戦略として展開されます。まず、シンボリック戦略として、ランドマークのライトアップがあります。2025年11月1日・2日、ニデック京都タワーはオレンジ色にライトアップされます。日常の風景であるタワーが非日常の色に染まることで、道行く人々は否応なくその意味を問い直すことになります。虐待という家庭内の見えにくい問題を、街のシンボルという最も見えやすい形で社会全体に突きつけ、私たちはこの問題を見つめているという力強い意思表示となるのです。
次に、アンビエント戦略として、メッセージを人々の日常の風景に溶け込ませ、刷り込む手法があります。京都府の取り組みでは、郵便局と協働し、集配車両やバイクに啓発ステッカーが掲示されます。また、ヤマト運輸株式会社とも協働し、集配車両にもステッカーが貼られます。これは動く広告塔として、メッセージが特定の場所に留まらず、市民の生活圏の隅々まで能動的に入り込んでいくことを意味します。さらに重要なのは、郵便局員やヤマト運輸の社員が、業務中にオレンジリボンを着用することです。彼ら・彼女らは、地域住民にとって最も身近で信頼できる顔です。その人々がリボンをつけることで、運動への信頼性と受容性が高まり、虐待防止が特別なことではなく社会の日常であるという認識を広げます。
そして、コミュニティ戦略として、特定のターゲット層が集まる場に出向き、対話と教育を行う手法があります。東京都日野市では、児童虐待防止講演会や啓発パネル展示が実施されます。これは、市民が問題の構造を深く学び、具体的な知識を得る学びの場です。一方、京都府では、2025年11月9日に開催される京都サンガF.C.のホームゲームにおいて、入場者への啓発グッズ配布が予定されています。これは、子育て世代の家族や、普段は社会問題に触れにくい層が集まるレジャーの場をあえて選ぶという、高度なターゲティング戦略です。福利厚生や社会福祉といった伝統的な枠組みを超え、スポーツやエンターテイメントの文脈でメッセージを届けることで、より広い層への浸透を図っています。
このように、2025年のキャンペーンは、象徴であるライトアップ、日常に溶け込む郵便バイク、参加を促すサッカー観戦や講演会という3つの層が連携し、社会全体をオレンジ色で包み込むことで、虐待を見逃さない社会の目を重層的に構築しようとしているのです。
私たち一人ひとりができること
ここまで、22万件という児童虐待の現実、その背景にある親の孤立と被害的認知というトラウマ、それを防ぐための妊娠期からの切れ目ない支援、そして私たち市民にできる最大の行動である189への通報と、その通報が起動させる48時間ルールというセーフティネットについて詳しくお伝えしてきました。
知識は、行動に移されて初めて力となります。この記事を読み終えた私たちが、今すぐできることは何でしょうか。
第一に、あなたの携帯電話の連絡先に、今すぐ189を登録してください。いつ、どこでもしかして?という瞬間に立ち会うかわかりません。その時に番号がわからないという理由で行動をためらわないよう、準備をすることが重要です。
第二に、あなたの地域でのあいさつや声かけを見直してください。虐待の最大の要因は孤立です。その孤立を防ぐ最も簡単で、しかし最も効果的な方法は、近隣住民とのゆるやかなつながりを持つことです。
そして、子育て中の家庭への理解を深めてください。公共の場で子どもが泣いている時、私たちは被害的認知のことを思い出すべきです。その親は、周囲の非難の視線によって自分はダメな親だと追い詰められ、被害的認知を強めているかもしれません。その時、非難の目を向けるのではなく、温かく見守る、あるいは何かお手伝いしましょうかと声をかけることが、社会全体で行う虐待予防になります。
さらに一歩進んだ行動として、NPO法人への寄付や、ボランティアとしての参加も可能です。また、自分の住む街の支援窓口を知ることも大切です。各地域には独自のセーフティネットがあり、例えば京都市には、国の189とは別に、市独自の24時間体制の子ども虐待SOS専用電話が存在します。
オレンジリボン運動が目指す最終的なゴールは、通報が飛び交う監視社会ではありません。そもそも通報が必要なくなるほど、子育て中の親が孤立せず、誰もがおひさまのような明るい未来を信じられる社会です。その第一歩は、この運動を生み出した小山市の市民たちのように、私たち一人ひとりがあの人の声になると決意することから始まるのです。
胸につけるオレンジリボンは、単なる装飾品ではありません。それは、虐待のない社会を築くという意志の表明であり、困っている子どもと家庭を見守り、支える準備ができているというメッセージです。11月の児童虐待防止推進月間をきっかけに、私たち一人ひとりが地域の目となり、子どもたちの未来を守る行動を起こしていきましょう。もしかして?と感じたら、ためらわずに189に電話をかけてください。あなたの一本の電話が、小さな命を救う第一歩になるのです。
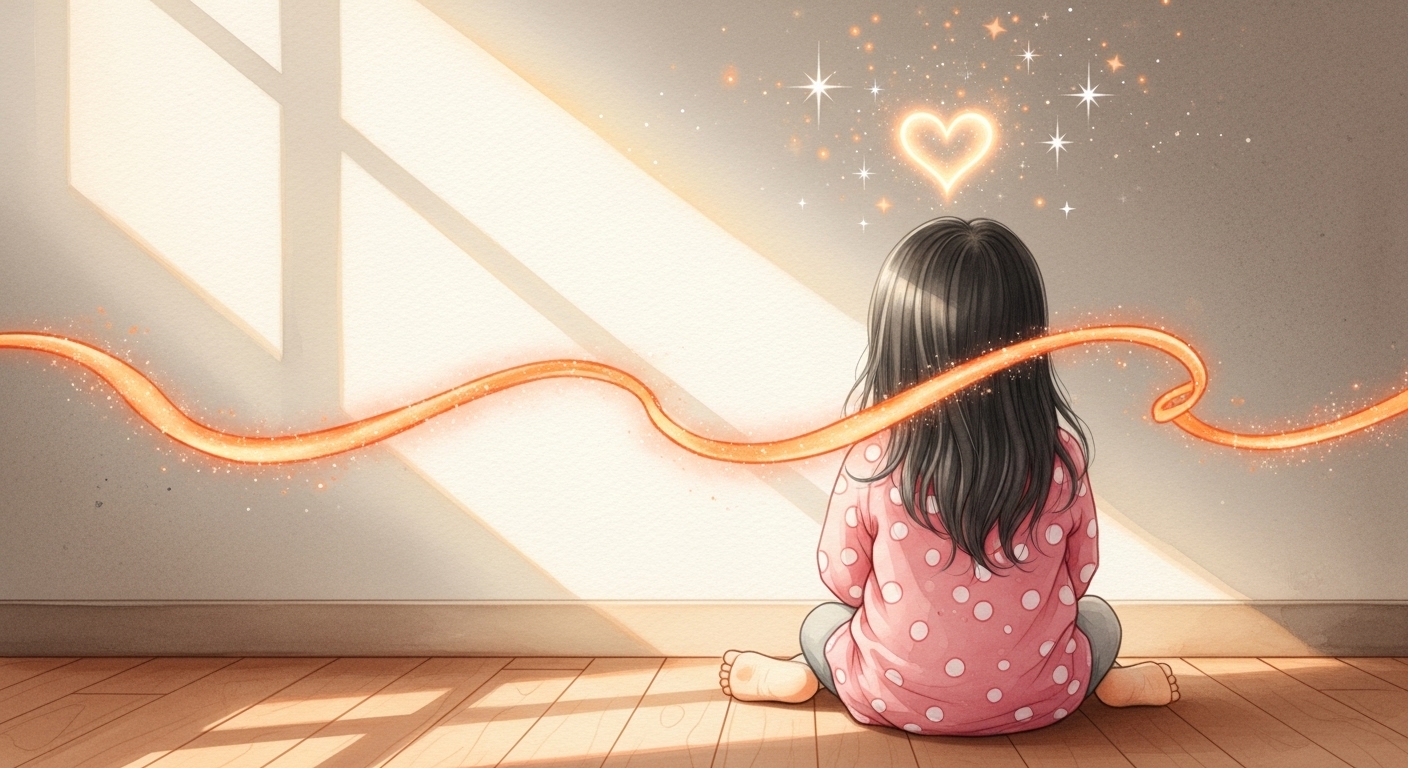


コメント