OTC類似薬の保険適用除外が閣議決定の方針として示され、家計負担への影響が懸念されています。結論から言えば、2025年11月の社会保障審議会で「完全な保険外し」は見送られたものの、「選定療養」という仕組みを通じて患者に追加負担を求める方向で実質的に了承されました。この制度変更により、花粉症薬や湿布薬、保湿剤などを処方される際の窓口負担が大幅に増加する可能性があります。この記事では、OTC類似薬の選定療養化がなぜ決まったのか、具体的にどの薬が対象となるのか、そして私たちの家計にどれほどの影響を与えるのかを詳しく解説します。
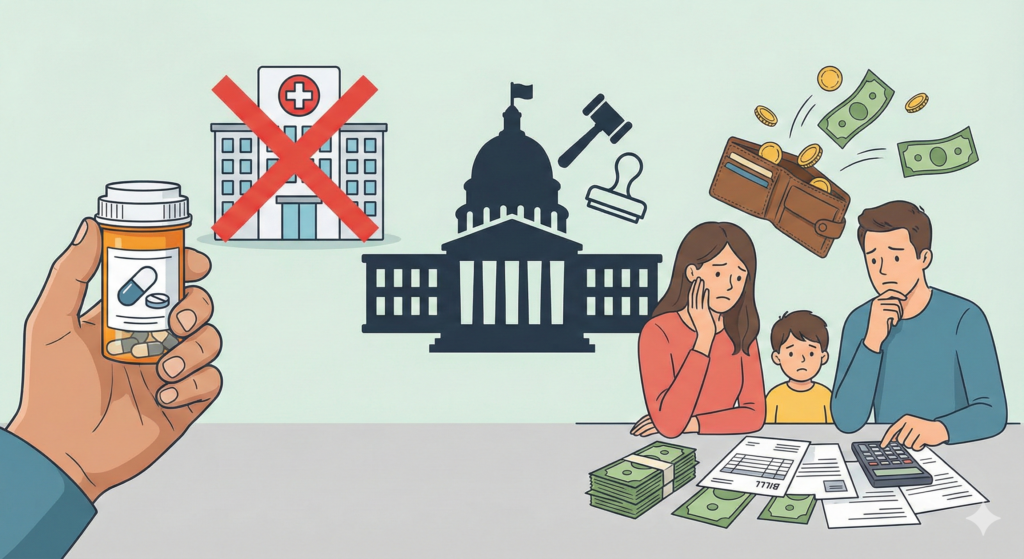
OTC類似薬とは何か?保険適用除外が議論される背景
OTC類似薬とは、医師が処方する医療用医薬品のうち、ドラッグストアなどで購入可能な一般用医薬品(OTC医薬品)と成分や効能が類似している薬剤のことを指します。代表的なものとして、花粉症治療薬の「アレグラ」や「アレジオン」、湿布薬の「ロキソニンテープ」、保湿剤の「ヒルドイド」などが挙げられます。
この問題が議論される背景には、日本の医療財政が直面している深刻な構造的課題があります。2025年、日本は「団塊の世代」が全て75歳以上の後期高齢者となる超高齢社会のピークを迎えつつあります。さらにその先には、高齢者人口がピークに達し、現役世代が急激に減少する「2040年問題」が控えています。この人口構造の変化は、国民皆保険制度の財政基盤を根底から揺るがしており、医療技術の進歩による高額薬剤の登場と相まって、医療費の自然増は避けられない状況となっています。
政府が毎年6月頃に閣議決定する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」において、近年繰り返し焦点となってきたのが「薬剤費の適正化」です。財務省や財政制度等審議会は長年、軽微な不調に対する医療については、公的保険から外してセルフメディケーションに委ねるべきであると主張してきました。一方、医療現場や患者団体からは、経済的理由による受診抑制が国民の健康を損ない、結果として重症化による医療費増大を招くとの反論が強く、議論は長らく膠着状態にありました。
2025年11月の社会保障審議会で何が決まったのか
2025年11月27日に開催された社会保障審議会医療保険部会において、日本の医療保険制度史において重要な転換点となる決定が下されました。厚生労働省は、OTC類似薬について「公的医療保険の適用除外(保険外し)は行わない」とする一方で、「選定療養の枠組みを用いて、患者に別途負担を求める」という案を提示しました。
注目すべきは、この提案に対して、これまで強硬に反対してきた日本医師会や日本薬剤師会を含む委員から、表立った反対意見が出ず、実質的に了承されたことです。これは「完全除外」という最悪のシナリオを回避するために、「一部負担増」という痛み分けを受け入れざるを得ないという、医療側の苦渋の決断があったと考えられます。また、政府・与党内においても、国民の反発が大きい「保険外し」という言葉を避け、「選定療養」という技術的な用語を用いることで、実質的な負担増を実現しようとする政治的な配慮が働いたとみられています。
選定療養とは?制度の仕組みをわかりやすく解説
選定療養とは、日本の公的医療保険制度における例外的な仕組みです。原則として、日本では保険診療と保険外診療(自由診療)を併用すること(混合診療)は禁止されており、もし併用した場合は本来保険が適用される部分も含めて全額自己負担となります。
しかし、選定療養はこの例外として認められた制度です。患者が「追加的な特別のサービス」を自ら選択した場合に限り、その追加費用を患者が全額負担すれば、基礎的な医療部分は保険給付(3割負担など)を受けられます。代表的な例としては、入院時の個室代(差額ベッド代)や予約診療費、大病院に紹介状なしで受診する際の初診料などがあります。
今回、OTC類似薬がこの選定療養の対象に加えられるということは、医学的に必要な薬剤費の一部は保険でカバーしつつ、市販薬との価格差や薬剤の利便性に関わる部分を「患者の個人的な選択に基づく負担」とみなし、そのコストを患者に直接請求する道を開くことを意味します。これは実質的な混合診療の拡大であり、国民皆保険制度の原則を修正する大きな一歩といえます。
導入スケジュールはいつ?閣議決定の意味と今後の流れ
骨太の方針2024および2025に向けた議論において、OTC類似薬の見直しは「早期に実現可能なものは2026年度から実行する」というタイムラインが敷かれています。閣議決定された方針は各省庁にとって絶対的な指針としての性質を持つため、厚生労働省が2025年冬に取りまとめを行う「医療保険制度改革」の最終案に基づき、2026年の通常国会での法改正や省令改正を経て、早ければ2026年10月、遅くとも2027年4月には新制度が稼働すると予測されています。
対象となる主な薬剤の種類と特徴
今回の改革で特にターゲットとされているのは、処方頻度が高く、かつ市販薬市場も成熟している4つのカテゴリーです。
保湿剤(ヘパリン類似物質)の問題
最も象徴的なのが、「ヒルドイド」に代表されるヘパリン類似物質製剤です。数年前、SNSなどを通じて「高級美容クリームより安くて効く」といった情報が拡散し、美容目的で皮膚科を受診してヒルドイドを処方してもらう若年層が急増したことが社会問題化しました。医療用医薬品としてのヒルドイドは、アトピー性皮膚炎や放射線治療後の皮膚障害など、深刻な乾燥を伴う疾患にとって不可欠な薬剤です。しかし、単なる乾燥肌に対して安易に処方されているケースも少なくないとの指摘があり、これが選定療養化の最大の根拠となっています。
解熱鎮痛消炎剤(湿布薬)と日本の「貼る文化」
次にターゲットとなっているのが、整形外科領域で大量に処方される湿布薬です。ロキソプロフェンやケトプロフェンを含む製品が代表的です。日本は世界的に見ても突出した「湿布大国」であり、高齢者が腰痛や膝痛に対して日常的に湿布を使用する文化が根付いています。現状、ロキソニンテープなどは1枚あたりの薬価が非常に安く設定されていますが、一度の受診で70枚といった大量処方が行われることが常態化しており、自宅に使いきれない湿布が山積みになっている「残薬問題」も指摘されています。
抗アレルギー薬(花粉症治療薬)への影響
春先の花粉症シーズンに処方される「アレグラ(フェキソフェナジン)」や「アレジオン(エピナスチン)」などの第2世代抗ヒスタミン薬も主要な対象です。花粉症は生命に関わる疾患ではないという認識から、「軽症なら市販薬で対応すべき」という圧力が最も強い領域の一つとなっています。市販薬のアレグラFXなどは、医療用と全く同じ成分・用量で販売されており、代替可能性が非常に高いとされています。ただし、耳鼻科での受診は吸引やネブライザーなどの処置とセットで行われることが多く、単純な薬の置き換えだけで議論できない側面もあります。
ビタミン剤等その他の薬剤
ビタミンB12製剤(メコバラミン)なども、末梢性神経障害などで処方されますが、ビタミン剤はサプリメントとしても広く流通しているため、保険給付の優先順位が低いとみなされています。これらの薬剤についても、医学的な必要性が厳格に問われることになります。
家計負担はどう変わる?具体的なシミュレーション
OTC類似薬の選定療養化は、国民の家計にどのような具体的変化をもたらすのでしょうか。選定療養の負担額計算式は未定ですが、2024年の長期収載品ルールや「市販薬価格との差額相当」などを想定して分析してみます。
花粉症患者の場合
現在、花粉症で耳鼻科を受診し、アレグラ60mgを28日分(1日2回、計56錠)処方された場合、3割負担の患者の窓口支払額は初診料や処置料を含めて約2,750円程度です。このうち、薬剤料部分の自己負担は数百円に過ぎません。一方、ドラッグストアで同成分の「アレグラFX」を28日分購入しようとすると、実勢価格で約3,000円から4,000円程度の出費となります。
もし選定療養化され、薬剤費部分について「保険給付を縮小し、市販薬価格との差額を徴収する」ような厳しい設計になった場合、窓口支払額は2,750円から跳ね上がり、5,000円から6,000円近くになる可能性があります。こうなると、「病院に行くと市販薬を買うより高くなる」という逆転現象が発生します。これは政策的に意図されたものであり、軽症患者をドラッグストアへ誘導する強力なインセンティブとなりますが、患者にとっては純粋な負担増となります。
アトピー性皮膚炎患者の場合
アトピー性皮膚炎の患者にとって、保湿剤は治療の要であり生命線です。ヒルドイドソフト軟膏0.3%(50g)の薬価は約925円(2024年ベース)であり、3割負担であれば患者は1本あたり約280円で入手できます。月に4本(200g)使用する場合、薬剤費の自己負担は約1,100円程度で済みます。
しかし、これが選定療養化され、市販のヘパリン類似物質クリーム(50gあたり約1,500円から2,000円)と同等の負担を求められるようになった場合、最悪のケースでは1本あたりの負担額が1,000円以上跳ね上がり、月4本の使用で数千円の負担増となります。年間では数万円単位の家計圧迫となり、特に子育て世帯や低所得者層にとっては治療継続を断念せざるを得ない水準になりかねません。
高齢者の慢性疼痛の場合
高齢者が整形外科でロキソニンテープを処方されるケースは非常に多くあります。1割負担の高齢者の場合、1枚あたりの自己負担額はわずか1.7円程度であり、70枚処方されても約120円という驚異的な安さです。一方、市販のロキソニンSテープは1枚あたり約70円から80円であり、約40倍の価格差が存在します。
選定療養化によって、例えば「1枚あたり20円の追加負担」が導入されただけでも、70枚処方されれば1,400円の追加出費となります。年金生活者にとって、毎月数千円の医療費増は死活問題であり、痛みを我慢して生活の質を落とす高齢者が急増するリスクがあります。
2024年「長期収載品の選定療養」から学ぶ教訓
2025年の改革を予見する上で、2024年10月に先行導入された「長期収載品(先発医薬品)の選定療養化」の実態を知ることは極めて重要です。
日本保険薬局協会が実施したアンケート調査によれば、回答した薬局の9割以上が、制度導入に伴う患者への説明や事務処理に「負担を感じている」と回答しています。具体的には、高齢の患者に対して「なぜ今までと同じ薬なのに値段が上がるのか」「選定療養とは何か」を理解してもらうのに多大な時間を要しており、調査では患者一人当たり平均3分近い追加対応が発生し、待ち時間の増加につながっています。また、選定療養費は消費税の課税対象となるため、保険診療分とは別に計算し会計処理を行う必要があり、レジシステムの改修や手計算によるミス誘発のリスクが現場を圧迫しています。さらに、理不尽な負担増に対する怒りは制度を決めた国ではなく目の前の薬剤師に向けられ、疲弊する薬剤師が続出しています。
OTC類似薬の選定療養化は、長期収載品のケース以上に現場を混乱させる可能性があります。長期収載品の場合は「ジェネリックに変更する」という回避策が患者に用意されていましたが、OTC類似薬の場合は代替薬がないため、患者は「追加料金を払う」か「治療を諦める」かの二者択一を迫られることになります。また、医師が「医療上の必要性がある」と判断した場合には選定療養の対象外とする除外規定が設けられる見込みですが、その判断基準を巡って医師と患者の間でトラブルが頻発することも予想されます。
受診抑制と「隠れ重症化」のリスク
日本医師会や患者団体が最も恐れているのが「受診抑制」です。2025年の世論調査でも、経済的理由で受診を控えた経験がある人が3割に上ることが判明しています。OTC類似薬の自己負担増は、この傾向を決定的に強めることになります。
特に懸念されるのは「患者による自己診断」の危険性です。患者が「ただの湿疹だ」「いつもの腰痛だ」と判断して市販薬で済ませようとした症状が、実は内臓悪性腫瘍の皮膚転移であったり、脊椎カリエスや大動脈解離の前兆であったりする可能性があります。医師による診断の機会が失われることで、発見が遅れて取り返しのつかない事態を招く「隠れ重症化」のリスクは、金銭的なコスト削減効果では償えない損失となりえます。
慢性疾患患者における治療継続率の低下も懸念されます。例えば、糖尿病や高血圧で通院している患者が、経済的負担を理由に併用薬を中断することで、生活の質が低下し、運動療法ができなくなったり皮膚感染症を併発したりして、結果として主病のコントロールが悪化するシナリオです。日本難病・疾病団体協議会などの患者団体は、こうした複合的なリスクを指摘し反対声明を出しています。
小児・低所得者への影響と課題
18歳以下の子供の医療費助成を行っている自治体は多くありますが、選定療養費は「保険外」の費用であるため、自治体の助成対象外となる可能性が高いです。つまり、これまで無料で医療を受けられていた子供たちであっても、保湿剤などを処方される際には窓口でお金を払わなければならなくなるかもしれません。これは子育て支援の逆行とも捉えられかねず、制度設計における最大の論点の一つとなっています。審議会でも「18歳以下や低所得者への配慮」が検討事項として挙げられていますが、具体的な線引きは難航が予想されます。
各ステークホルダーの立場と主張
この問題を深く理解するためには、舞台裏で繰り広げられているステークホルダー間の政治的綱引きを知る必要があります。
財務省・健康保険組合連合会の立場
改革の最大の推進者は財務省と、大企業の社員などが加入する健保連です。彼らの論理は「現役世代の負担は限界に達している。軽微なリスクは自助で対応すべきだ」というものです。健保連は「ポスト2025提言」において、OTC類似薬の保険外しを明記し、断固たる姿勢で制度改革を求めています。
日本医師会・日本薬剤師会の立場
対する日本医師会は、国民の生命と健康を守る立場から、安易な自己負担増に反対しています。「医療は市場原理だけで動く商品ではない」というのが彼らの信念です。また、受診抑制による患者数減少はクリニックの経営打撃に直結するため、組織防衛の観点からも反対の立場をとっています。日本薬剤師会も、成分名が同じでも製造工程や添加剤が異なる医薬品の代替可能性について、科学的な見地から慎重な議論を求めています。
患者団体の声
最も弱い立場にあるのが患者です。全国がん患者団体連合会やアレルギー友の会などは、審議会のヒアリングにおいて「数十倍の負担増」「治療の断念」といった悲痛な声を上げています。彼らは「単なる節約」ではなく「生存権」の問題として捉えており、一律の負担増ではなく病状に応じたきめ細やかな配慮を強く求めています。
厚生労働省の苦悩
厚生労働省は、財政規律を求める圧力と医療崩壊を防ぎたい現場の声との板挟みになっています。今回の「選定療養化」という折衷案は、財務省に「患者負担増」という成果を与えつつ、医師会には「保険外し」を回避したという顔を立てる、ギリギリの政治的判断であったといえます。
将来展望と対象薬剤の拡大懸念
一度「OTC類似薬は選定療養」という仕組みが導入されれば、その対象はなし崩し的に拡大していく可能性があります。現在は保湿剤や湿布薬が中心ですが、将来的には胃腸薬、点眼薬、漢方薬などもターゲットになるかもしれません。「市販で売っているものは全て保険外」という考え方が現実味を帯びてくれば、日本の国民皆保険制度が「高額な医療のみをカバーする制度」へと変質していく第一歩となるかもしれません。
政府は、負担増の緩和策として「セルフメディケーション税制」の活用を推奨しています。これは特定のOTC医薬品を購入した際に所得控除を受けられる制度ですが、手続きの煩雑さや、そもそも所得税を払っていない低所得者には恩恵がない点など課題も多くあります。選定療養化とセットで、この税制の拡充や簡素化が議論されるべきでしょう。
私たちはどう対応すべきか
2025年のOTC類似薬を巡る政策決定は、私たちの生活に「医療のコスト意識」を持つことを強制するものです。もはや「とりあえず病院に行けば安く薬がもらえる」時代は終わりを告げようとしています。
第一に、「かかりつけ薬剤師」との関係強化が重要です。 自分の薬が選定療養の対象になるのか、市販薬で代替可能なのか、コストパフォーマンスも含めた相談ができる専門家を味方につけることが家計防衛の鍵となります。
第二に、市販薬の知識武装が求められます。 成分表示を読み解き、自分に合ったOTC医薬品を選べるリテラシーを高めることが大切です。
第三に、声を上げることが不可欠です。 今回の制度変更には「配慮が必要な患者の範囲」など未確定な要素が残されています。パブリックコメントなどを通じて実情に即した制度運用を求めていく姿勢が、患者としての権利を守るために重要です。
OTC類似薬の選定療養化は、単なる値上げではありません。それは日本の社会保障のあり方を「公助」から「自助」へと大きくシフトさせる歴史的な転換点であることを、私たちは深く認識する必要があります。

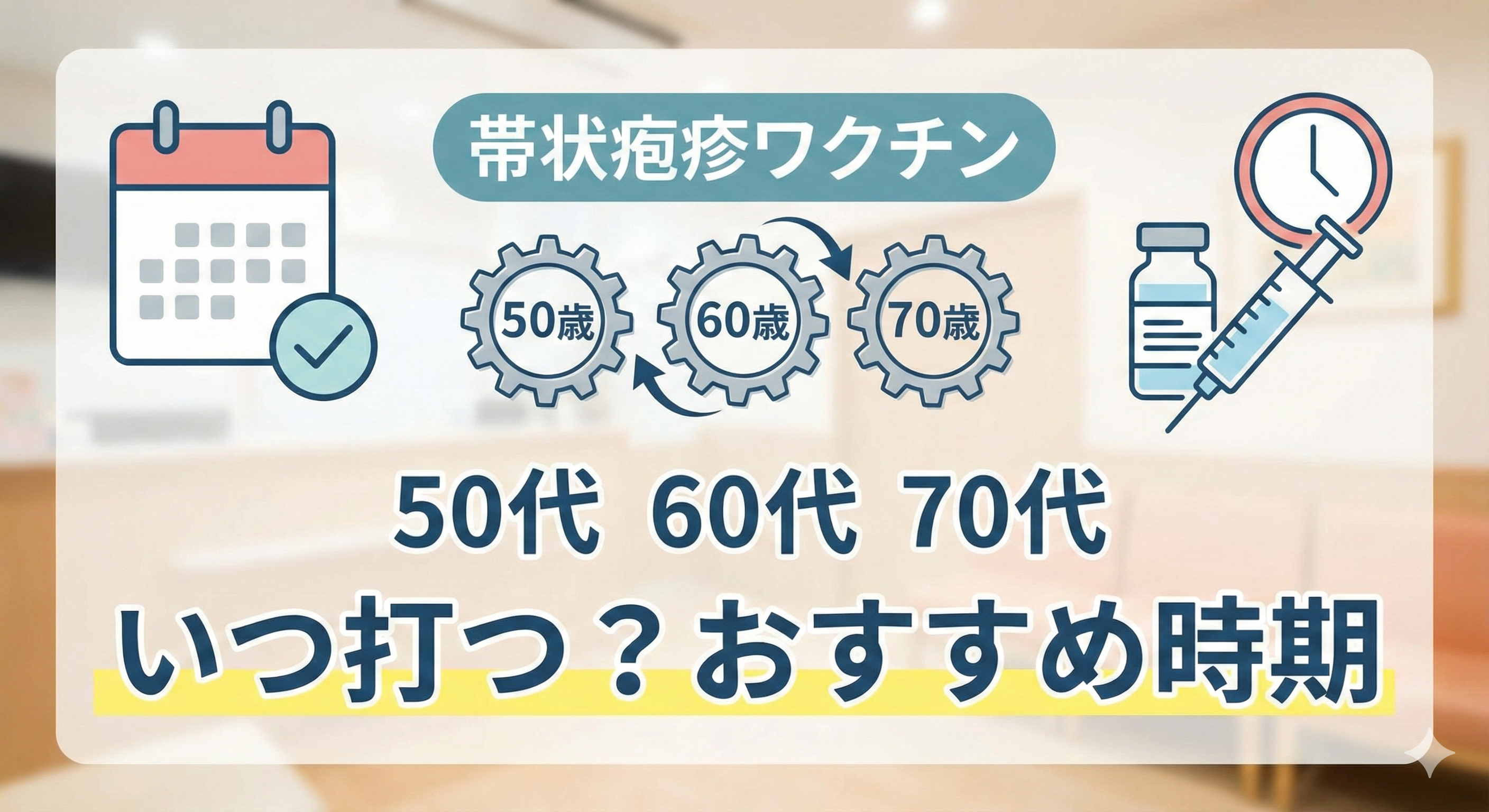

コメント