生活保護制度における医療扶助は、憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する重要な制度です。特に入院が必要となった場合、医療費や食費の負担について多くの受給者が不安を感じることでしょう。2024年6月には入院時の食費基準が改定され、物価高騰を踏まえた新しい制度が導入されています。また、入院期間によって生活保護費の支給額が変更されるルールや、退院後の生活再建支援についても理解しておく必要があります。本記事では、生活保護受給者が入院する際の医療扶助の仕組みから、最新の食費基準、自己負担が発生するケース、そして退院後のサポート体制まで、実際に役立つ情報を詳しく解説していきます。入院に対する不安を解消し、安心して治療に専念できるよう、制度の全体像を把握しましょう。

生活保護受給者が入院した場合、医療費や食費は自己負担なしで受けられるの?
生活保護受給者が入院する際、医療費と食費は基本的に自己負担なしで受けることができます。これは医療扶助という制度によって保障されており、受給者が安心して治療に専念できる仕組みとなっています。
医療扶助は「現物給付」が原則で、受給者が医療機関の窓口で費用を支払う代わりに、福祉事務所が医療機関へ直接費用を支払う形式です。生活保護受給者は国民健康保険に加入していないため、医療費の10割負担分が医療扶助によって賄われます。
入院時の手続きとしては、原則として受診希望日や医療機関名を記載した申請書を事前に福祉事務所へ提出し、医療の必要性が認められれば「医療券」が発行されます。この医療券を保険証の代わりに医療機関の受付に提示することで、入院費が無料となります。
ただし、夜間救急や突然の事故など緊急を要する場合には、医療券がなくても入院が可能です。この際は、受給者であることを病院に伝えることが重要で、後日手続きを行うことができます。
入院中の食事代についても、医療行為の一環とみなされ、医療扶助から支給されます。「入院時食事療養費」という制度により、患者が支払う「食事療養標準負担額」と総額の差額が保険給付として支給され、生活保護受給者はこの自己負担分も医療扶助でカバーされるため、食事代を気にせず栄養を摂って治療に専念できます。
継続して通院する場合は月単位での手続きが必要で、月が変わった後も通院を継続する場合は改めて医療券の申請が必要です。処方箋が発行された場合は、事前に決めた薬局で「調剤券」を利用して薬代も無料で受け取ることができます。
入院が1ヶ月以上続く場合、生活保護費はどのように変わるの?
入院期間によって生活保護の支給金額は大きく変更されます。特に1ヶ月を境に支給基準が大幅に変わるため、事前に理解しておくことが重要です。
入院期間が1ヶ月以内の場合は、生活保護の支給額に変更はありません。通常通り「生活扶助」と「住宅扶助」が毎月支給され、入院費は医療扶助から支給されるため、特別な手続きは不要です。
しかし、入院期間が1ヶ月以上になると、支給基準が「居宅基準」から「入院基準」に変更されます。具体的には、月々支給される生活保護費は「入院患者日用品費」の23,110円(全国一律)のみとなります。この金額は日割り計算ではなく、1ヶ月以上の入院となった翌月の初日から適用されます。
この23,110円という金額は決して多くありません。携帯電話代や自宅の光熱費なども、この限られた費用から支払う必要があるため、入院前に必要な支払いを整理し、不要なサービスは一時停止するなどの準備が推奨されます。
住宅扶助については、6ヶ月以内に退院する見込みがある場合に限り継続して支給されます。これは退院後の生活基盤を維持するための措置です。6ヶ月を超えても入院が継続する見込みの場合、さらに3ヶ月を限度として給付が延長される可能性がありますが、確実に退院が見込まれる場合に限られます。
特に注意が必要なのは、病状が長引き入院期間が9ヶ月以上になった場合です。この時点で住宅扶助の支給は停止され、賃貸の退去を求められることがあります。賃貸契約は家賃の支払いを前提としているため、支払い能力がないと住み続けることが困難になるためです。
家族世帯の場合は、入院した個人の生活扶助は停止されますが、同居している他の家族の支給額は変わりません。ただし、世帯全体の収入が減少するため、生活が厳しくなる可能性があり、困った場合はケースワーカーへの相談が重要です。
2024年に改定された入院時の食費基準について、具体的にどう変わったの?
2024年6月1日より、食材費等の高騰を踏まえて入院時の食費基準が改定されました。この改定は、医療の一環として提供される食事の質を確保する観点から実施されたものです。
一般所得者の場合(1食あたり)の変更は以下の通りです:
- 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関:460円から490円(+30円)
- 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関:420円から450円(+30円)
市区町村民税非課税世帯の場合の変更は:
- 低所得者Ⅱ:210円から230円(+20円)。ただし、過去1年の入院期間が90日を超える場合は160円から180円(+20円)
- 低所得者Ⅰ(70歳以上で住民税非課税かつ年金等収入が80万円以下):130円から140円(+10円)。「医療の必要性の高い方」の場合は100円から110円(+10円)
指定難病・小児慢性特定疾病の患者については:260円から280円(+20円)の変更となりました。
現在の食費総額は、一般所得者の場合で1食あたり670円(入院時生活療養Ⅰを算定する医療機関)です。このうち、患者自己負担が490円、保険給付が180円となっています。住民税非課税世帯の場合は、自己負担230円、保険給付440円という内訳です。
今後の見直しについては、厚生労働省が2025年度の予算編成過程で、継続する食材費等の高騰を踏まえ、さらに1食あたり20円の引き上げを検討しています。これは、給食管理に携わる管理栄養士や栄養士への調査で、物価高騰に対応するために安価な食材の利用や価格変動の少ない食材の使用頻度を増やすなどの工夫が行われており、これが長期化すると食事の質の低下が懸念されているためです。
生活保護受給者にとって重要なのは、これらの食費の自己負担分も医療扶助によってカバーされるため、改定による負担増加の心配がないということです。質の高い食事を通じて栄養を摂取し、治療効果を高めることができる環境が維持されています。
入院中に自己負担が発生するケースはどんな時?個室代やパジャマ代は?
医療扶助でほとんどの入院費用がカバーされますが、一部のケースでは自己負担が発生する場合があります。これらのケースを事前に把握しておくことで、予期しない出費を避けることができます。
個室代については、生活保護では原則として相部屋での入院が基準とされており、個人の希望による個室利用は「贅沢品」と見なされ自己負担となります。しかし、医療上の必要性がある場合や、相部屋が空いていないなどの病院側の都合により個室を利用せざるを得ない場合は、医療扶助の対象となり自己負担が不要となることもあります。トラブルを避けるため、個室の利用については事前に福祉事務所や医療機関に確認することが重要です。
パジャマ代やスリッパ代も自己負担となるケースがあります。病院によっては、感染予防や衛生管理の観点から、持ち込みの病衣やスリッパ、タオルなどを禁止し、リースでのレンタルを義務付けている場合があります。これらのリース費用は医療扶助の対象外となり、入院期間が長引くほど費用負担が大きくなります。持ち込み可能なものがないか病院に相談し、できる限り自己負担を抑える工夫をすることが推奨されます。
おむつ代についても自己負担となることが一般的です。医療上必要な場合でも、日常生活用品として扱われるため、入院患者日用品費から支払う必要があります。
保険診療外の治療は、生活保護の医療扶助が国民健康保険の保険診療の範囲内を対象としているため、美容整形やインプラントなどは給付対象外となり、全額自己負担となります。自己都合での特別な治療やサービスの利用には自己負担が生じる可能性があるため、治療を受ける前に支給対象かどうかを確認することが重要です。
通院移送費については、通院の際の交通費(バス代やタクシー代)は原則として生活費から捻出する必要があります。ただし、病状などにより公共交通機関の利用が困難と認められる場合には、医療一時扶助として通院移送費が支給されることもあります。この場合は低額な運賃の交通機関が原則で、療養に必要な最小限度の日数に限定されます。通院移送費は事後支給の場合が多く、医療機関から通院証明書を取得し、定期的にケースワーカーに提出する必要があります。
これらの自己負担項目は、入院患者日用品費の23,110円という限られた予算から支払う必要があるため、入院前に必要性を十分に検討し、ケースワーカーとも相談しながら適切な判断を行うことが大切です。
長期入院で住居を失った場合、退院後の生活再建はどのようにサポートされるの?
長期入院により住居を失った場合でも、福祉事務所による包括的な生活再建支援が用意されています。退院後の安定した生活を送るためには、早めの準備と適切な支援の活用が重要です。
住居確保に関する支援では、生活保護の開始時や退院・退所時に住まいがない場合、敷金、礼金、仲介手数料といった初期費用は住宅扶助として支給されます(上限額あり)。賃貸契約には通常2週間程度の準備期間が必要なため、退院の見通しが立ったら早めにケースワーカーに連絡し、住居探しを開始することが重要です。
住まいを失っていた人が新たにアパートで生活を始める際に必要な家具や什器については「一時扶助」の「家具什器費」として支給されます。また、退去が必要になった場合の家財の保管や処分にかかる費用も一時扶助として支給されることがあります。単身世帯の場合、1年を上限に家財保管料が支給されることもありますが、他に支援手段がないことが条件となります。
公営住宅や福祉住宅も重要な選択肢です。これらは低所得者向けに提供され、家賃の減免措置がある場合もあります。福祉事務所が住居探しのサポートを行うため、早めに担当のケースワーカーに相談し、必要な申請手続きを進めることが推奨されます。
過去に家賃滞納や自己破産などの履歴がある場合、一般的な賃貸の入居審査に通りにくいことがあります。このような場合は、生活保護専門の不動産会社への依頼が効果的です。「ほごらんど」や「リライフネット」、「ほゴリラ」といった団体が、生活保護申請サポートと並行して住居探しや即日入居可能な物件の紹介、家具・家電付き住居の提供、食事支援など、包括的なサポートを提供しています。
福祉事務所による専門的支援では、ケースワーカーが多職種と連携して支援を行います。保健師や精神保健福祉士といった「健康管理支援員」が退院調整や治療継続支援を、高齢者には「高齢者支援員」が、多重債務者には「多重債務者等支援員」が、年金に関しては「適正受給調査員」が関わります。
社会福祉機関との連携により、地域に根ざした支援も受けることができます。自治体や社会福祉機関では、生活保護の手続きや生活基盤の再建について相談が可能で、退院後の生活に必要な各種サービスの情報提供や手続きサポートも行っています。
退院後の生活再建を成功させるためには、入院中から退院後の計画を立て、必要な支援を早めに申請することが重要です。福祉事務所のケースワーカーとの密な連携により、安心して地域生活に戻ることができる体制が整備されています。

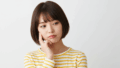
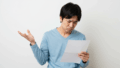
コメント