生活保護は憲法第25条に基づく国民の権利であり、生活に困窮するすべての人が最低限度の生活を営めるよう国が保障する制度です。しかし、申請をしても必ずしも認められるわけではなく、様々な理由で審査に落ちてしまうケースも少なくありません。申請が却下されると「もう打つ手がない」と絶望してしまう方も多いですが、実は却下後にも取れる対策や手続きが数多く存在します。本記事では、生活保護の審査に落ちる具体的な理由から、不服申し立ての方法、専門家のサポートまで、知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。
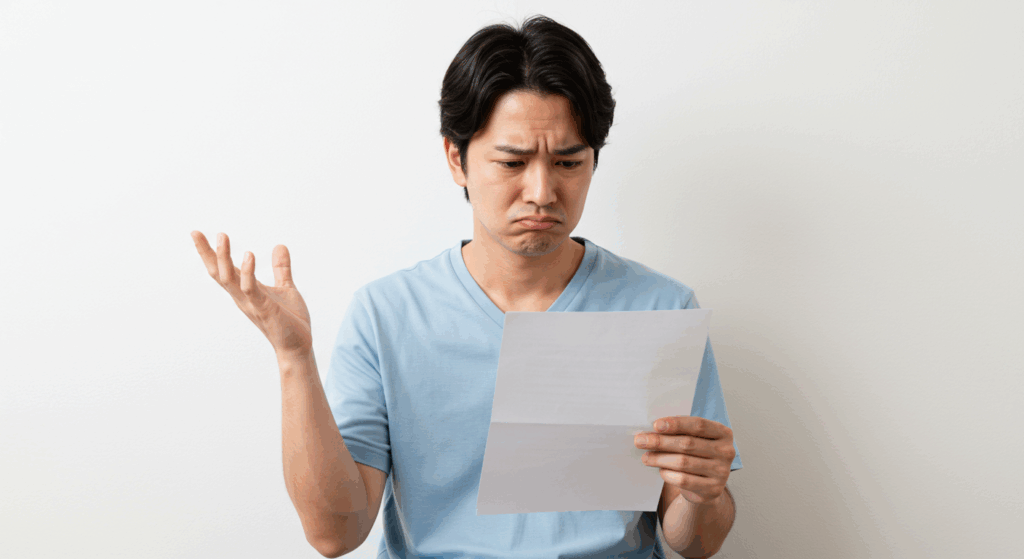
Q1. 生活保護の審査に落ちる主な理由は何ですか?
生活保護の審査に落ちる理由は、主に資産・収入が基準を超えている場合、他の制度の利用可能性がある場合、申請者の協力不足の3つに分類されます。
資産・収入が基準を超えている場合では、まず預貯金が重要なポイントになります。一般的に単身世帯で10万円以下が目安とされており、これを超えると資産があると見なされ却下される可能性があります。ただし、家賃や公共料金の支払いですぐになくなる状況であれば、10万円以上でも認められるケースもあります。厚生労働省の基準では、最低生活費の5割までは収入として認定しない配慮があるとされています。
不動産についても厳しくチェックされます。居住用以外の土地や家屋、売却価格が2,000万円以上の不動産は原則として売却対象となります。現在住んでいる家であっても、処分価値が著しく大きい場合は売却を求められます。住宅ローンが残っている家も、生活保護費でローン返済することは資産形成にあたるため、基本的に売却対象です。
自動車・バイクも原則処分対象ですが、障害者の通勤・通院、公共交通機関の利用が困難な地域での通勤・通院、深夜勤務などの場合は例外的に保有が認められることがあります。生命保険は解約返戻金が出るものは資産として活用を求められますが、解約返戻金が最低生活費の3ヶ月程度以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下なら保有可能です。
月収については、地域の最低生活費基準を上回る場合受給資格がなくなります。例えば東京23区の単身者で約130,010円が基準とされています。年金受給者でも、年金収入が最低生活費を下回れば差額が支給されます。
他の制度の利用可能性では、扶養照会が最大の障壁となっています。三親等以内の親族に経済的援助の可能性を問い合わせる制度ですが、2021年の通知で20年間音信不通だった基準が「10年程度」に緩和されました。DVや虐待の相手方には照会しないとされていますが、依然として不適切な運用事例が報告されています。
失業保険、各種年金、児童扶養手当、生活福祉資金貸付制度などの他の公的支援制度も優先的に活用することが求められ、これらを検討・利用してもなお困窮状態が解消しない場合に生活保護の対象となります。
申請者の協力不足については、収入証明書や預金通帳の提出拒否、家庭訪問の拒否などがあると審査が進まず却下されます。稼働能力があるにも関わらず働かない場合も却下理由となりますが、病気や怪我、精神疾患で働けない場合は対象となります。65歳以上は稼働能力の基準から除外されます。
借金の存在も問題となります。生活保護費での借金返済は認められないため、借金がある場合は申請前に自己破産を選択することが推奨されます。生活保護受給者は法テラスを利用して自己破産費用を立て替えてもらうことができます。
Q2. 「水際作戦」で不当に申請を拒否された場合はどうすればいいですか?
「水際作戦」とは、福祉事務所の窓口で申請書を渡さない、受け付けない、扶養が保護の要件であるかのような説明をするなど、不適切な対応により必要な人が申請できない状況を作り出す行為です。厚生労働省はこれらを「申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為にあたるので、厳に慎むこと」と通知していますが、残念ながら現在も各地で報告されています。
具体的な水際作戦の例として、扶養照会を強要する、無料低額宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請できないと説明する、自動車の保有が一律に認められないと説明する、居所がないと保護を受けられないと説明する、事実上の保護の要否判定を申請前に行うなどがあります。
横浜市神奈川区では20代女性の申請書を受け取らず虚偽の説明をした事例、桐生市では扶養者からの仕送りの事実がないのに収入認定して申請を却下する事案が多数確認されました。奈良県生駒市では精神疾患がある女性の申請を認知症の母親に扶養意思があることを理由に却下し、後に裁判で違法とされた事例もあります。
水際作戦に遭遇した場合の対処法として、まず会話を録音することが重要です。実際に録音データが決め手となり横浜市の水際作戦で区側が謝罪した事例もあります。申請の意思を明確に伝え、申請書の提出を求め続けることも大切です。口頭で拒否されても、文書での回答を求めましょう。
生活困窮者支援団体や弁護士、行政書士などの専門家に相談し、窓口同行をしてもらうことも効果的です。「特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい」のような団体や、「生活保護総合支援ほゴリラ」のようなサービスでは、専門家が申請に同行し高い受給決定率でサポートを行っています。
水際作戦により申請書を受け取ってもらえない、または受け付けてもらえない場合は、却下とみなして不服申し立てを行うことも可能です。申請の意思を明確に示したにも関わらず適切な対応がされない場合は、都道府県知事への審査請求の対象となります。
自治体の対応格差も大きな問題で、扶養照会率は中野区の5.5%から佐賀市の78.0%まで大きな差があります。居住地を変更できる場合は、より適切な運用を行っている自治体での申請も検討できます。
Q3. 生活保護の審査に落ちた後、再申請や不服申し立てはできますか?
生活保護の申請が却下されても、何度でも再申請が可能であり、受給条件も変わりません。また、正式な不服申し立ての手続きも用意されており、諦める必要は全くありません。
再申請については、前回の却下理由を改善した場合に認められる可能性が高まります。状況の変化として、収入や資産が基準を下回るようになった、失業保険などの他制度の受給期間が終了した、病状が悪化して働けなくなったなどがあれば再申請のチャンスです。必要書類の再提出では、収入証明書、預金通帳の写し、医師の診断書など、却下理由を補える書類を準備して提出します。
不服申し立て(審査請求)は、却下に納得できない場合に行える正式な手続きです。都道府県知事に対して「審査請求」を行うことができ、これは生活保護法と行政不服審査法に基づいています。
審査請求の提出先は、却下を決定した福祉事務所を所管する都道府県知事です。提出方法は文書で行い、「審査請求書」の正本と副本の二通を提出し押印が必要です。提出期限は却下通知を受け取ってから60日以内で、処分があった日から1年を経過すると審査請求はできません。
審理期間は原則として3ヶ月以内に判断が出されます。審査庁は請求のあった日から50日以内(第三者機関に諮問する場合は70日以内)に裁決を行う義務があり、この期間内に裁決がない場合は審査請求が棄却されたものとみなして次の手続きに進めます。
審査請求が可能なケースには、保護の申請が却下された場合、申請後30日を経過しても決定がない場合、申請書を渡してもらえない・受け付けてもらえない場合、保護費の額が少ないなど決定内容に不満がある場合、保護の廃止・停止・減額決定に不満がある場合などがあります。
代理人制度も利用でき、弁護士でなくても生活保護法に詳しい人に依頼して代理人になってもらうことができます。特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る審査請求について代理権が与えられており、本人に代わって不服申し立てを行い交渉することが可能です。
都道府県知事の裁決に不服がある場合は、厚生労働大臣に「再審査請求」ができます。再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。
再審査請求の裁決にも不服がある場合は、裁判(訴訟)を起こすことができます。生活保護の却下処分などを争う場合、行政事件訴訟のうち「取消訴訟」や「義務付け訴訟」が一般的です。処分取消訴訟を起こす場合、原則として裁判の前に審査請求の手続きを経ている必要があり、処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に起こさなければなりません。
Q4. 扶養照会が原因で生活保護を諦めざるを得ない場合の対策はありますか?
扶養照会は生活保護申請における「最大の障壁」の一つとされ、「家族に生活保護の申請を知られたくない」「連絡されては困る」という相談が最も多い問題です。しかし、扶養照会を回避する方法や最新の運用変更により、以前より柔軟な対応が可能になっています。
扶養照会の基本的な仕組みとして、民法に定める扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など三親等以内の親族)に扶養能力がある場合、扶養が保護に優先されるとされ、福祉事務所は親族に対し経済的援助の可能性を問い合わせる「扶養照会」を行うのが原則です。
2021年の運用変更では、厚生労働省が2月26日付の通知で、20年間音信不通の場合に照会不要とされていた運用を「10年程度」に緩和するなど、柔軟な運用を促しています。また、DVや虐待の相手方には照会しないとされています。
扶養照会を拒否する具体的な方法として、最も効果的なのは申請書に明記する方法です。申請書そのものに「親族への扶養照会をしないでほしい」という明確な文言と理由を記載して提出することで、申請者の意に反して扶養照会がなされることを防げます。書面で扶養照会をする理由・必要性の説明を求める旨を明記することも重要です。
扶養照会が不要とされるケースには、被保護者、施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者、10年程度の音信不通など交流が断絶している場合、扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害するDV・虐待等の場合があります。これらに該当する場合は、直接の扶養照会を行わないことが差し支えないとされています。
地域格差への対策として、扶養照会に関する運用には大きな地域差があります。中野区の扶養照会率は5.5%と低い一方、佐賀市は78.0%と高いなど、自治体によって大きな格差があります。居住地の変更が可能な場合は、より適切な運用を行っている自治体での申請を検討することも一つの選択肢です。
不適切な扶養照会への対処では、実際には扶養実態がないにも関わらず「収入認定(カラ認定)」され申請が却下された事例や、認知症の母親に扶養意思を確認しただけで却下した事例(後に裁判で違法と判断)も報告されています。このような場合は、専門家への相談や不服申し立てが有効です。
専門家のサポート活用では、行政書士や弁護士、生活困窮者支援団体に相談することで、扶養照会の回避方法について具体的なアドバイスを受けることができます。特に窓口同行をしてもらうことで、福祉事務所との交渉において申請者の権利を守ることができます。
家族関係の複雑な事情がある場合は、DV、虐待、家族からの借金の強要、精神的な支配関係、長期間の絶縁状態など、具体的な事情を詳しく説明し、扶養照会が申請者の安全や自立を阻害する可能性があることを明確に伝えることが重要です。
Q5. 生活保護申請で専門家のサポートを受けるメリットと相談先は?
生活保護の申請は複雑で、一人では対処が困難な場合が多いため、専門家のサポートを受けることで成功率を大幅に向上させることができます。各専門家の役割と具体的な支援内容について詳しく説明します。
行政書士のサポートでは、特に生活保護の申請書類作成や生活状況の整理、窓口同行などで心強い存在となります。特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求など、行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理権が与えられています。これにより、不当な却下処分があった場合に、本人に代わって不服申し立てを行い交渉することが可能です。申請書の作成から不服申し立てまで一貫してサポートを受けられるのが大きなメリットです。
弁護士のサポートでは、生活保護の申請、審査請求、訴訟において、生活保護法や多岐にわたる関係通知の解釈・適用が問題となるため、事実の主張立証・法律の解釈適用の専門家である弁護士の支援が適切です。違法・不当な指導指示に対する撤回交渉、弁明の機会での意見陳述、不当に支給された保護費の返還額の減額交渉なども行います。各地の弁護士会や、日本司法支援センター(法テラス)では収入が少ない人の訴訟費用を立て替える法律扶助制度があります。
生活困窮者支援団体の支援では、「特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい」のような団体が、経済的な困りごとについての相談を受け、公的支援制度の利用をサポートしています。住まいがない人への入居支援や居場所提供、広報・啓発活動も行っています。
専門サービスの活用として、「生活保護総合支援ほゴリラ」のようなサービスでは、生活保護の専門家が申請に同行し、高い受給決定率(99%)でサポートを行っています。また、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者向けに「楽ちん貸」という保証人・保証会社不要のサービスも提供しています。
窓口同行のメリットは非常に大きく、福祉事務所のケースワーカーとの面談において、申請者一人では対処が困難な専門的な質問への回答、不適切な対応への対処、申請書類の適切な記入などをサポートしてもらえます。実際に専門家が同行することで、福祉事務所側も適切な対応を取ることが多くなります。
費用面での配慮として、多くの支援団体では無料相談を実施しており、経済的に困窮している状況を理解した上でサポートを提供しています。法テラスの法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の立て替えも可能です。生活保護受給後は、法テラスの立て替え費用の償還が免除される場合もあります。
継続的なサポートも重要なポイントで、申請から受給決定、その後の生活保護受給中のトラブル対応まで、長期間にわたってサポートを受けることができます。ケースワーカーとの関係で問題が生じた場合や、受給後の各種手続きについても相談できます。
録音・記録の重要性について、福祉事務所のケースワーカーの説明や対応に疑問がある場合は、会話を録音し、専門家に相談することが有効です。実際に録音データが決め手となり、横浜市の水際作戦で区側が謝罪した事例もあります。専門家は録音内容を分析し、不適切な対応があった場合の対処法をアドバイスしてくれます。
相談のタイミングとしては、申請前から相談することが最も効果的ですが、申請中、却下後、受給中のトラブルなど、いつでも相談可能です。早期に専門家のサポートを受けることで、申請の成功率を高め、不要なトラブルを避けることができます。



コメント