子ども・子育て支援金の年収別負担額は、2028年度の満額徴収時において、年収200万円で月額約350円、年収400万円で月額約650円、年収600万円で月額約1,000円、年収800万円で月額約1,350円、年収1,000万円で月額約1,650円が目安となります。計算方法は、加入している医療保険制度によって異なり、被用者保険では標準報酬月額に支援金率(約0.4%)を掛けて労使折半で算出し、国民健康保険では所得割と均等割を組み合わせて計算されます。本記事では、2024年に成立した子ども・子育て支援法改正に基づく支援金制度の詳細な計算ロジックと、あなたの年収に応じた具体的な負担額のシミュレーションを徹底解説します。制度の仕組みを理解することで、家計への影響を正確に把握し、拡充される児童手当などの給付と合わせた収支を見通すことができます。

子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度とは、「異次元の少子化対策」として打ち出された「こども未来戦略」の財源を確保するために創設された新たな負担制度のことです。2024年(令和6年)に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、2026年度から実際の徴収が始まります。
制度が生まれた背景と目的
日本における少子化対策は、1990年の「1.57ショック」を契機に本格化しました。合計特殊出生率が過去最低の1.57を記録したこの出来事以降、「エンゼルプラン」(1994年)、「新エンゼルプラン」(1999年)、「子ども・子育て応援プラン」(2004年)、「子ども・子育てビジョン」(2010年)と、政府は数年おきに新たな計画を策定してきました。しかしながら、これらの施策は出生率の低下傾向を劇的に反転させるには至りませんでした。
その要因として、若年層の所得低迷、雇用不安、晩婚化・非婚化の進行、そして子育てにかかる経済的負担の重さが複合的に絡み合っていることが挙げられます。特に、社会保障給付が高齢者世代に偏重しており、現役世代・子育て世代への再配分が諸外国と比較して不十分であるという構造的な課題が長年議論されてきました。
この状況を打破するため、岸田政権(当時)が掲げたのが「異次元の少子化対策」です。これは従来のような微修正ではなく、政策の規模と質を抜本的に変えることを目指したものです。「こども未来戦略」では、2030年代に入るまでを「少子化傾向を反転できるラストチャンス」と位置づけ、今後3年間で集中的に取り組む「加速化プラン」が提示されました。
財源確保の仕組みと支援金の役割
「加速化プラン」の実行には年間約3.6兆円規模の追加財源が必要です。政府はこの財源を、徹底した歳出改革による公費の節減、既定予算の最大限の活用、そして国民全体で広く負担を分かち合う新たな枠組みという三本柱で賄うとしました。この第三の柱が「子ども・子育て支援金制度」です。
支援金の核心的な理念は「全世代・全経済主体による連帯」にあります。少子化による人口減少は、将来の労働力不足や社会保障制度の持続可能性の低下を招き、子育て世帯のみならず、高齢者や企業、独身者を含む社会全体に甚大な影響を及ぼします。したがって、少子化対策の恩恵は社会全体に還元されるというロジックに基づき、医療保険制度という既存の広範な徴収ルートを活用して、年齢や性別、子どもの有無に関わらず、支払い能力に応じて広く薄く負担を求める仕組みが設計されました。
子ども・子育て支援金の計算方法
支援金の負担額は一律ではなく、加入している医療保険の種類によって計算式が全く異なります。自身の加入制度を把握することが、正確な負担額を知る第一歩となります。
被用者保険(会社員・公務員)の計算方法
会社員や公務員が加入する被用者保険では、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に一定の料率(支援金率)を乗じて計算されます。
標準報酬月額とは、毎年4月から6月の3ヶ月間の給与平均額を基に決定される等級(ランク)のことです。基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、家族手当、住宅手当などの各種手当が含まれます。この等級に基づき、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決定されます。標準賞与額は、税引き前のボーナス総額から千円未満を切り捨てた額です。支援金は、この両方に対してかかり、これを「総報酬割」といいます。
支援金率は、2026年度(令和8年度)から2028年度(令和10年度)にかけて段階的に引き上げられます。2026年度は総額6,000億円、2027年度は8,000億円、2028年度には1兆円を徴収する計画です。これに伴い、被用者保険における支援金率も上昇し、2028年度の満額徴収時において平均的な支援金率は0.4%程度になると見込まれています。
重要なのが労使折半の原則です。厚生年金や健康保険と同様に、被用者保険における支援金も計算された総額の半分を事業主(会社)が負担し、残りの半分を従業員(被保険者)が負担します。したがって、給与から天引きされるのは、(標準報酬月額+標準賞与額)×約0.2%ということになります。この「事業主負担分」は企業の利益を圧迫し、賃上げ原資を減少させる可能性があるため、間接的には従業員への経済的影響となり得ます。
国民健康保険(自営業・フリーランス)の計算方法
会社員以外の層が加入する国民健康保険(国保)では、計算方法がより複雑で、かつ地域差があります。国保の保険料は主に「所得割」と「均等割」で構成されますが、支援金もこの体系に準じます。
所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いた額に、一定の税率(支援金分)を掛けて算出されます。所得が高いほど負担が増える部分です。均等割は、世帯の加入者数に応じて定額で課される部分であり、収入に関わらず加入者一人につきいくらという形で計算されます。
被用者保険と決定的に異なるのは、「事業主負担」が存在しないことです。計算された支援金の全額を被保険者(世帯主)が支払わなければなりません。これはフリーランスや自営業者にとって、会社員と比較して負担感が重くなる要因の一つです。
後期高齢者医療制度の計算方法
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度においても支援金の徴収が行われます。こちらも所得に応じた「所得割」と定額の「均等割」で構成されますが、高齢者の支払い能力に配慮し、制度全体での負担割合は低く抑えられています。しかし、年金生活者にとっては新たな負担増となることに変わりはありません。
年収別の負担額シミュレーション
ここでは、様々な年収における具体的な負担額をシミュレーションします。数値は制度が完成する2028年度(令和10年度)時点の推計値を基準としています。これらはあくまで目安であり、加入する保険組合や居住自治体によって変動する可能性がある点にご留意ください。
年収200万円の負担額
この層は、社会保険加入要件を満たすパートタイマーや新入社員などが該当します。
被用者保険(協会けんぽ等)に加入している場合、年収200万円では標準報酬月額は約17万円程度と想定されます(賞与なしと仮定)。支援金率を0.4%(本人負担0.2%)とすると、月額の負担は約350円、年間では約4,200円の負担増となります。一見少額に見えますが、手取り額が少ないこの層にとって、月350円は日々の食費や消耗品費に直結する金額です。また、これに加えて通常の健康保険料や厚生年金保険料が引かれているため、社会保険料全体の負担率は決して低くありません。
国民健康保険に加入している場合、年収200万円(経費控除後の所得が低い場合)では、国保の「低所得者軽減措置」が適用される可能性があります。所得水準に応じて均等割が7割、5割、2割と軽減される仕組みです。軽減が適用された場合、月額負担は250円程度に抑えられる試算があります。ただし、軽減適用外の所得水準にある場合や、単身世帯か複数世帯かによって負担額は変動します。
年収400万円の負担額
日本の給与所得者の中央値に近い層の負担額を見ていきます。
被用者保険に加入している場合、年収400万円(月給25万円、賞与100万円と仮定)では、本人負担分の月額換算は約650円、年間負担額は約7,800円となります。これは月額の動画配信サブスクリプションサービスの半額から同等程度に相当します。政府が説明する「一人当たり平均月額450円(被保険者以外も含む平均)」よりも高く、実際の給与生活者が感じる負担感は平均値以上であることが分かります。
国民健康保険に加入している場合(単身)、フリーランスで所得(売上から経費を引いた額)が年収400万円相当であれば、月額負担は約550円から600円程度と試算されます。会社員と比較して若干低く見える場合がありますが、これは会社員における「総報酬割(賞与への課金)」の影響がないためです。しかし、全額自己負担であるため、心理的な負担感や、将来の給付(育休等がないこと)とのバランスを考えると、実質的な厳しさは増します。
年収600万円の負担額
中堅社員や係長クラスが該当する年収帯です。
被用者保険に加入している場合、年収600万円(月給35万円、賞与180万円と仮定)では、月額負担は約1,000円の大台に乗ります。年間負担額は約12,000円です。この金額は、一度の昇給分が相殺される、あるいは年間で数回分の外食費に相当する額です。特に子育てを終えた世代や独身者にとっては、直接的な見返りがない中での「純粋な手取り減」となるため、不公平感を抱きやすいラインと言えます。
国民健康保険に加入している場合、自営業者でこの所得帯になると所得割の影響が大きくなります。月額負担は約800円前後と見込まれますが、家族構成(配偶者や子供の有無)によって均等割が加算されるため、世帯全体での負担額はこれより大きくなります。
年収800万円の負担額
管理職や共働き世帯の年収帯における負担額を見ていきます。
被用者保険に加入している場合、年収800万円では月額負担は約1,350円、年間負担額は約16,200円となります。この層は、今回の制度改革で「児童手当の所得制限撤廃」の恩恵を最も受ける層の一つです。これまで所得制限により特例給付(月5,000円)や支給なしとなっていた世帯が、満額(月1万円または1.5万円〜3万円)を受け取れるようになったため、負担増(年1.6万円)を差し引いても差し引きでプラスになる可能性が高い層です。ただし、子どものいない世帯にとっては単なる負担増となります。
年収1,000万円の負担額
高所得層の負担額について解説します。
被用者保険に加入している場合、年収1,000万円では月額負担は約1,650円、年間負担額は約19,800円とほぼ2万円に達します。標準報酬月額には上限があるため、年収がさらに上がっても負担額は青天井には増えませんが、一定の上限(月額2,000円弱程度)で高止まりします。
年収別負担額の比較一覧
以下の表で、年収別の負担額を比較できます。
| 年収 | 月額負担額(被用者保険) | 年間負担額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 約350円 | 約4,200円 |
| 400万円 | 約650円 | 約7,800円 |
| 600万円 | 約1,000円 | 約12,000円 |
| 800万円 | 約1,350円 | 約16,200円 |
| 1,000万円 | 約1,650円 | 約19,800円 |
会社員とフリーランスで異なる負担の仕組み
支援金制度において見過ごされがちなのが、働き方による負担と給付の構造的な格差です。
労使折半と全額自己負担の違い
会社員は「労使折半」により負担の半分を会社が肩代わりしてくれますが、フリーランス(国保加入者)は全額自己負担となります。同じ「年収400万円」でも、会社員の自己負担が月650円であるのに対し、フリーランスも同水準かそれ以上を支払う場合があります。さらに事業主負担分がないため、社会全体としての拠出額で見ると会社員の方が(会社分を含めて)多く負担している構造にはなっていますが、個人の財布からの持ち出し感はフリーランスの方が切実です。
給付における格差の問題
より深刻なのが「給付の格差」です。支援金によって財源が確保される「出生後休業支援給付」や「育児時短就業給付」は、雇用保険制度に基づいた施策です。したがって、雇用保険に加入していないフリーランスや自営業者は、いくら支援金を支払っても、これらの給付を受け取ることができません。
児童手当の拡充などは全世帯共通のメリットですが、育休中の所得補償という極めて重要なセーフティネットにおいて、フリーランスは「払い損」と感じる構造が存在します。これに対し、政府は国民年金保険料の免除措置などを設けていますが、会社員の手厚い休業給付(手取り10割相当)と比較すると、その格差は依然として埋まっていません。
子育て世帯への軽減措置
子育て世帯、特に国民健康保険に加入している自営業世帯にとって重要な軽減措置が設けられています。
こども均等割の10割軽減とは
国保の「均等割」は子育て世帯にとって長年の懸案事項でした。生まれたばかりの0歳児であっても、世帯の一員として数えられ、均等割(一人あたり数万円程度)が加算されるため、子どもが多いほど保険料が高くなる状況がありました。
今回の子ども・子育て支援金制度の導入に合わせて、国保における18歳年度末までの子どもに係る支援金分の均等割額を10割(全額)軽減する措置が導入されます。これは単に「徴収しない」というだけでなく、公費等を投入してその分を補填する仕組みです。これにより、子育て中の自営業世帯においては、子どもの人数によって支援金の負担が増加することはありません。
注意が必要なのは、これが「支援金分」の均等割に関する軽減措置である点です。既存の「医療分」や「介護分」の保険料についても、未就学児の均等割軽減(5割軽減)などの措置は存在しますが、小学生以上18歳までの医療分均等割が完全に無料になるわけではない自治体も多いです。支援金制度によって、少なくとも支援金部分については子どもへの課金が完全に免除されるというのは、これまでの国保制度の課題を一歩前進させる施策と評価できます。
支援金の使い道と子育て世帯が受けられる給付
「取られる額」ばかりに注目が集まりがちですが、「得られる額(サービス)」についても詳細に把握する必要があります。
児童手当の抜本的拡充
2024年10月から実施された児童手当の拡充は、最大の目玉政策です。
まず、所得制限が撤廃されました。従来は主たる稼ぎ手の年収が一定(目安960万円や1200万円)を超えると、児童手当が減額(特例給付5,000円)されたり、支給停止になったりしていました。これが完全に撤廃され、親の年収に関わらず全員が対象となりました。
次に、支給期間が延長されました。「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長されています。これにより、教育費が最もかかる高校生期間に月1万円の支援が得られます。
さらに、第3子以降が増額されました。多子世帯への支援として、第3子以降は月額3万円に倍増されています。「第3子」のカウント方法も見直され、大学生年代(22歳年度末まで)の上の子がいる場合、その子を第1子としてカウントすることで、下の子が第3子扱いになりやすくなりました。
妊産婦・乳幼児への支援
妊婦のための支援給付として、妊娠届出時と出産後の届出時にそれぞれ5万円、計10万円相当の給付が行われます。これは「出産・子育て応援交付金」の恒久化を意味します。
こども誰でも通園制度は、親の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等を利用できる制度です。専業主婦家庭の孤立育児を防ぐ狙いがあります。
共働き・共育て世帯への支援
出生後休業支援給付は、男性育休の取得促進を狙い、産後パパ育休などの期間中、給付率を引き上げ、社会保険料免除と合わせて「手取り10割」を保証するものです。
育児時短就業給付は、2歳未満の子を育てながら時短勤務をする際、賃金の10%を上乗せ支給し、時短による収入減を補います。
これらの施策により、政府は子ども一人当たり、高校卒業までに平均で約146万円の給付増になると試算しています。現行制度と合わせると総額約352万円の給付規模となります。
制度を巡る議論と注意点
支援金制度を巡っては、その導入根拠について様々な議論が交わされています。
「実質負担ゼロ」の意味
政府は「歳出改革と賃上げによって、国民の実質的な負担は生じない」と説明してきました。このロジックは二つの前提に基づいています。
一つ目は歳出改革です。医療や介護の無駄を削減し、社会保険料の自然増を抑制することで、その抑制できた分(浮いた分)の範囲内で支援金を徴収するため、トータルの保険料率は上がらないという考え方です。
二つ目は賃上げです。経済成長により賃金が上がれば、保険料として引かれる額が増えても、手元に残る可処分所得は増えるという想定です。
指摘されている課題
しかし、この説明には多くの疑義が呈されています。社会保険料は本来、病気や失業などのリスクに備えるためのものであり、少子化対策という国の基本政策の財源を保険料に求めるのは実質的な目的税化であるとの指摘があります。また、「実質負担ゼロ」という説明が分かりにくいとの声もあります。
消費税や社会保険料は、所得が低い人ほど収入に対する負担割合が高くなる「逆進性」の性質を持ちます。累進課税である所得税で賄うべき再分配政策を、逆進的な保険料で行うことへの批判もあります。
また、賃上げが全ての層に波及するかは不確実です。大企業では賃上げが進んでいますが、中小企業や年金生活者には波及しきっていないのが実情です。賃上げが物価上昇や保険料アップに追いつかなければ、実質的な生活水準は低下する可能性があります。
2026年からの家計への備え方
2026年度から支援金の徴収が始まります。最初は少額(月数百円)ですが、2028年度には満額(月千円前後〜)となります。家計への影響を最小限にするための対策を解説します。
給与明細の可視化
毎月の天引き額を正確に把握し、固定費の一部として予算に組み込むことが重要です。支援金は健康保険料に上乗せされる形で徴収されるため、給与明細の社会保険料欄を注意深く確認する習慣をつけましょう。
給付制度のフル活用
拡充される児童手当や、新設される給付金を確実に申請することが大切です。特に「妊婦支援給付」や「育児時短就業給付」などは、申請忘れによる逸失利益が大きいため、情報収集が不可欠です。子育て世帯であれば、支援金の負担を上回る給付を受けられる可能性が高いため、各制度の申請漏れがないよう注意してください。
制度への理解を深める
少子化対策は国家の重要課題です。支援金によって確保される1兆円が、真に出生率の反転に寄与する有効な施策に使われるのか、国民一人ひとりが制度の仕組みを正しく理解することが求められています。「負担増」という痛みを伴う改革ですが、それが「未来への投資」として正当化されるかどうかは、これからの施策の効果と、集められた資金の透明性ある運用にかかっています。
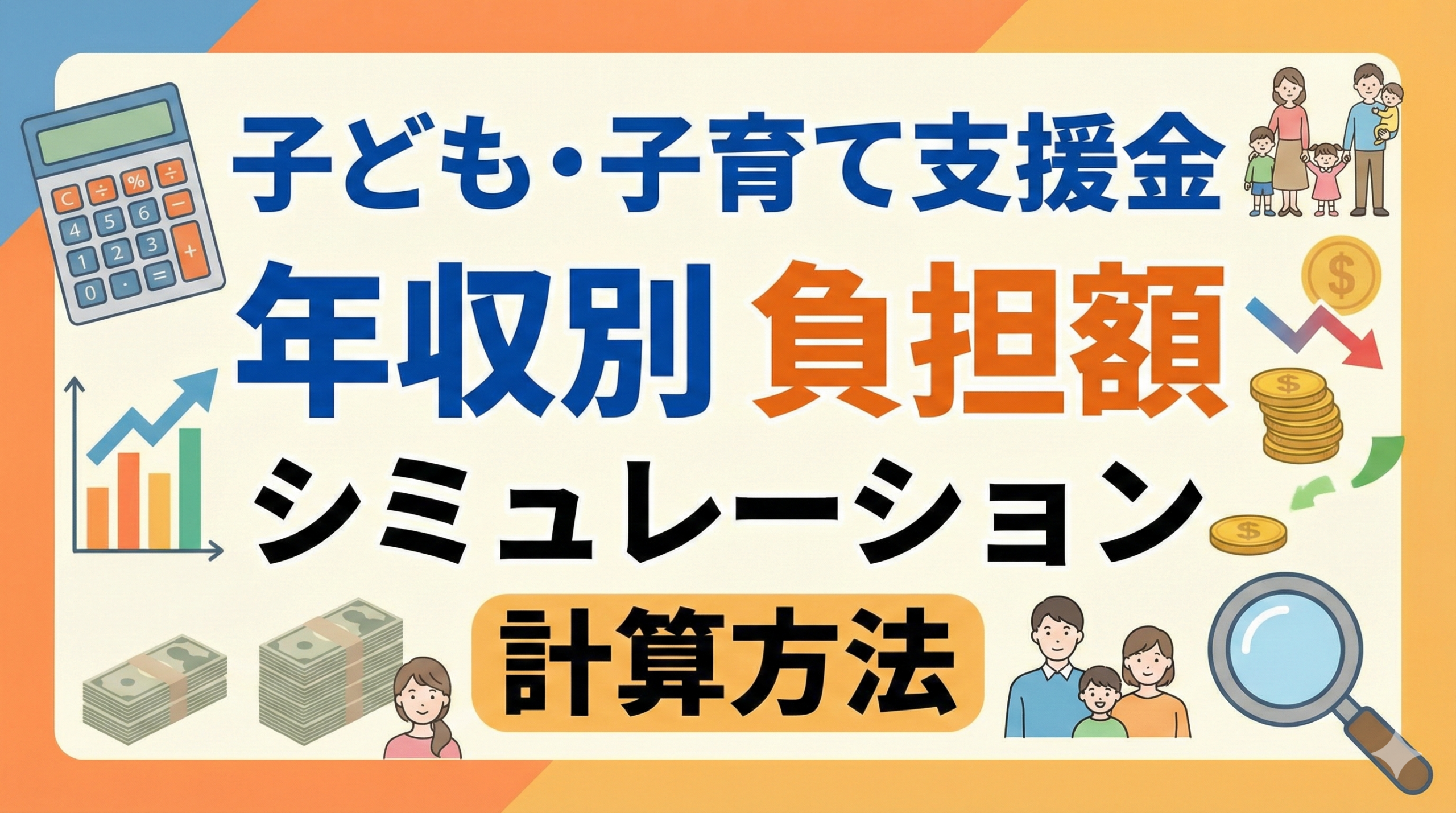


コメント