年金を受給していても生活が困窮している高齢者にとって、生活保護制度は重要なセーフティネットです。2025年現在、年金だけでは最低限の生活を維持することが困難な状況が増えており、年金と生活保護の両方を受給することは法的に認められています。
多くの方が「年金をもらっていると生活保護は受けられない」と誤解していますが、これは事実ではありません。年金額が国の定める最低生活費を下回る場合、不足分を生活保護として受給することができます。この制度により、年金受給者でも安心して生活を送ることが可能になります。
生活保護は憲法第25条に基づく国民の権利であり、長年社会に貢献してきた年金受給者が必要に応じて活用することは当然の権利です。物価高騰が続く2025年においては、特に重要な制度として位置づけられています。適切な知識を持って制度を理解し、必要な場合は躊躇せずに活用することで、健康で文化的な最低限度の生活を確保することができます。

年金をもらいながら生活保護は受けられる?基本的な条件とは
年金を受給していても生活保護を受けることは可能です。この制度の基本的な仕組みは、国が定める最低生活費から年金などの収入を差し引いた額が生活保護費として支給されるというものです。
生活保護の受給には4つの基本要件があります。第一に資産の活用です。不動産、自動車、預貯金、保険の返戻金などの資産がある場合は、まずそれらを生活費に充てることが求められます。ただし、生活に必要最小限の資産は保有が認められており、処分価値が低い自宅や必要最小限の家財道具などは保持できます。
第二に能力の活用です。働ける能力がある場合は、その能力に応じて就労することが求められます。ただし、65歳以上の年金受給者については、健康状態や年齢を考慮して、必ずしも能力の活用を求められないのが一般的です。
第三にあらゆるものの活用です。年金や各種手当など、他の制度で給付を受けられる場合は、それらを優先して活用することが求められます。生活保護は最後のセーフティネットとして位置づけられているため、他の社会保障制度を最大限活用してもなお生活が困窮している場合に適用されます。
第四に扶養義務者からの扶養です。親、子ども、兄弟姉妹からの経済的なサポートが期待できる場合は、まずそちらを頼ることが求められます。ただし、扶養義務者に扶養能力がない場合や、扶養を受けることが困難な事情がある場合は、この要件は免除されることがあります。
年金受給者特有の条件として、年金の受給権がある場合は受給手続きを行うことが必要です。年金を受給せずに生活保護だけを受けることは原則として認められません。また、年金の繰り下げ受給を行っている場合でも、生活保護受給中は繰り下げを継続することが困難になる可能性があります。
2025年度の重要な変更点として、物価高騰を考慮した特例加算が継続されており、1人あたり月額1,500円が一律で加算されています。これにより、年金受給者の生活保護における最低生活費の基準が引き上げられています。
年金と生活保護の両方受給時の支給額はどう計算される?
年金と生活保護の両方を受給する場合の支給額計算は、最低生活費 – 年金受給額 = 生活保護費という明確な公式で算出されます。
具体的な計算例を見てみましょう。東京都在住の65歳単身者の場合、最低生活費が13万円、国民年金受給額が6万円とすると、生活保護費は7万円(13万円-6万円)となり、実際の受取総額は13万円(年金6万円+生活保護費7万円)になります。
地方都市在住の70歳単身者では、最低生活費が10万円、厚生年金受給額が8万円の場合、生活保護費は2万円(10万円-8万円)となり、実際の受取総額は10万円(年金8万円+生活保護費2万円)です。
最低生活費の構成要素は複数あります。生活扶助は食費や光熱費など日常生活に必要な基本的な費用をカバーし、住宅扶助は家賃や共益費などの住居費をカバーします。これらが基本となり、必要に応じて教育扶助、医療扶助、介護扶助などが加算されます。
地域による基準額の違いも重要なポイントです。全国は1級地-1から3級地-2まで6段階に分類されており、東京都23区などの大都市では最も高い基準額が設定され、地方の町村部では最も低い基準額となっています。
年金支給月の調整について理解しておく必要があります。年金は偶数月に2か月分がまとめて支給されるため、生活保護費は年金支給月とそうでない月で調整されます。例えば、毎月の生活保護費が5万円、年金が月額6万円(偶数月に12万円支給)の場合、年金支給月は生活保護費が支給されず、年金非支給月は生活保護費10万円が支給されるといった調整が行われます。
住宅扶助の上限額も地域によって異なります。東京都23区の場合、単身者の住宅扶助上限額は月額53,700円ですが、大阪市では42,500円、地方都市では30,000円程度となることが多いです。現在の家賃が上限額を超える場合、転居を求められることがありますが、高齢者の場合は一定期間の居住継続が認められることもあります。
その他の収入がある場合の取り扱いも重要です。勤労収入がある場合は基礎控除が適用され、働くインセンティブが確保されています。しかし、年金収入については控除制度はなく、受給額全額が収入として認定されます。
年金受給者が生活保護を申請する際の必要書類と手続きの流れは?
年金受給者が生活保護を申請する際には、一般的な書類に加えて年金に関する特有の書類が必要になります。
基本的な必要書類として、生活保護申請書、資産申告書、扶養義務者届、生活歴があります。生活保護申請書には住所、氏名、年齢などの基本的な個人情報を記載し、資産申告書では預貯金、不動産、自動車、保険の返戻金など、所有している資産をすべて記載する必要があります。
年金受給者特有の必要書類が重要です。年金証書、年金支払通知書、年金振込通知書などが該当し、これらにより年金の種類、受給額、支払い方法などが確認されます。障害年金や遺族年金を受給している場合は、それらの証書や通知書も必要です。まだ年金を受給していない場合でも、年金の受給権がある場合は年金事務所での手続きを求められることがあります。
申請手続きの流れは段階的に進行します。まず、居住地を管轄する福祉事務所で申請を行います。申請は本人だけでなく、扶養義務者や同居の親族も行うことができます。申請時には身分証明書を持参し、記載内容に間違いがないよう注意深く記入します。
調査段階では複数の調査が並行して実施されます。家庭訪問調査では、ケースワーカーが実際の居住状況を確認し、住居の状態、家族構成、生活実態などが調査されます。年金受給者の場合、高齢による身体的な制約や生活の困難さについても聞き取りが行われます。
資産調査では、金融機関への照会により預貯金の状況が確認され、不動産登記の確認、生命保険会社への照会なども行われます。扶養義務者への照会も重要な調査項目で、扶養義務者に対して申請者を扶養できるかどうかの照会が行われます。ただし、DV被害者である場合や、長期間音信不通である場合など、照会を行うことが適当でない場合は照会が省略されることもあります。
決定までの期間は、通常申請から14日以内とされていますが、調査に時間がかかる場合は30日以内に延長されることがあります。保護が決定された場合、保護決定通知書が交付され、この通知書には保護の開始日、支給される扶助の種類、支給額などが記載されています。
保護決定後の手続きも重要です。医療扶助により医療費は原則として全額が公費で負担され、医療機関を受診する際は福祉事務所から交付される医療券を持参する必要があります。住宅扶助により家賃や共益費などの住居費も支給されますが、上限額があるため、その範囲内での住居に住むことが求められます。
申請時のポイントとして、必要書類を事前に準備し、申請書の記載は正確に行うことが重要です。わからないことがあれば遠慮なく窓口で質問し、虚偽の申告は絶対に行わないよう注意が必要です。相談段階では申請書の提出は必須ではないため、まずは相談だけでも気軽に福祉事務所を訪れることができます。
生活保護受給中の制限事項と年金受給者特有の注意点とは?
生活保護を受給すると、安定した生活を送ることができる一方で、いくつかの制限事項があることを理解しておく必要があります。
資産保有の制限が最も重要な制約です。生活保護受給中は、原則として資産を持つことができません。未使用の家や土地、自動車やバイクなどの資産は売却して生活費に充てるよう指導される可能性が高くなります。ただし、生活に必要最小限のもの、例えば日常生活で使用する家電製品、衣類、食器などは保有が認められています。
自動車の保有については原則として認められませんが、障害者が通院に必要とする場合や、公共交通機関が利用困難な地域での就労に必要な場合など、特別な事情がある場合は例外的に認められることがあります。年金受給者の多くは高齢者であるため、通院の必要性が認められる可能性もあります。
住居に関する制限も重要なポイントです。住宅扶助は居住地域ごとに基準額が決まっており、受給者はその基準額内の家賃の住居にしか住むことができません。現在の住居の家賃が基準額を超える場合、転居を求められることがありますが、高齢者や障害者の場合、転居が困難と判断されると、一定期間は現在の住居での居住が認められることもあります。
継続的な義務と責任として、収入申告義務があります。年金以外の収入が発生した場合は速やかに福祉事務所に報告する必要があり、アルバイトやパートの収入、臨時収入、保険金の受取りなど、どのような収入でも申告が必要です。申告漏れが発覚した場合、保護費の返還を求められることがあります。
ケースワーカーからの指導には従う義務があります。就労指導、家計管理の指導、医療機関への受診指導など、様々な指導が行われ、正当な理由なく指導に従わない場合は、保護の停止や廃止の対象となることがあります。また、定期的な面談や家庭訪問にも協力する必要があり、年に数回、ケースワーカーとの面談や家庭訪問が実施されます。
年金受給者特有の注意点として、年金の繰り下げ受給を行っている場合、生活保護受給中は繰り下げを継続することが困難になる可能性があります。年金を受給せずに生活保護だけを受けることは原則として認められていないためです。
プライバシーへの影響も考慮すべき点です。生活保護を申請する際、原則として3親等内の親族に扶養照会が行われ、これにより生活保護の申請を親族に知られることになります。これを負担に感じる方も多いですが、DV被害者である場合や、長期間音信不通である場合など、照会を行うことが適当でない場合は照会が省略されることもあります。
介護が必要な状況での制約として、年金受給者の多くは高齢者であり、将来的に介護が必要になる可能性があります。生活保護受給者の場合、介護施設の選択に制限が生じることがありますが、介護扶助により必要な介護サービスは受けることができるため、適切なケアを受けることは可能です。
制約の軽減策として、福祉事務所のケースワーカーとの良好な関係を築くことが重要です。困ったことがあれば相談し、指導には誠実に対応することで、より柔軟な支援を受けられる可能性があります。また、支援団体や社会福祉協議会などの相談機関を活用することで、孤立感を軽減し、より良い生活を送るためのアドバイスを受けることができます。
2025年最新の制度変更と今後の見通しは?
2025年度は生活保護制度において重要な変更が実施され、年金受給者にとって有利な改正が行われています。
最も注目すべき変更は、物価高騰を考慮した特例加算の拡充です。2023年から導入された特例加算は、2025年度からさらに拡充され、1人あたり月額1,500円が一律で加算されることになりました。これは2024年度の1,000円から500円の上乗せとなり、年金受給者の生活保護における最低生活費の基準が実質的に引き上げられています。
年金制度との連携強化も進んでいます。2025年度は年金額の引き上げが決定していますが、物価上昇率を下回るため実質的には目減りとなる見込みです。このような状況下で、年金だけでは生活が困難な高齢者が増加する可能性があり、生活保護制度の重要性がさらに高まっています。
年金生活者支援給付金制度も拡充が図られており、低所得の年金受給者への支援が強化されています。この給付金も生活保護の収入認定に含まれますが、生活の安定に寄与しており、生活保護と併用することで総合的な支援体制が整備されています。
デジタル化の推進により、申請手続きの簡素化も進められています。一部の自治体では、オンラインでの相談受付や書類提出が可能になっており、今後さらなる利便性の向上が期待されます。特に高齢の年金受給者にとって、手続きの負担軽減は重要な改善点です。
今後の制度見通しとして、高齢化の進展に伴い、年金だけでは生活が困難な高齢者が増加する傾向は続くと予想されます。政府は年金制度の充実を図る一方で、生活保護制度も重要なセーフティネットとして機能させていく方針を明確にしています。
物価動向への対応も重要な要素です。生活保護費は物価の動向に応じて調整される仕組みとなっており、今後の経済状況によっては追加的な調整が行われる可能性があります。ただし、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するという制度の趣旨から、大幅な削減は考えにくく、むしろ物価上昇に対応した調整が継続される見込みです。
地域格差の是正に向けた取り組みも進んでいます。住宅扶助の基準額について、地域の実情に応じたより細かな設定が検討されており、年金受給者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう配慮されています。
医療・介護分野での連携強化も図られています。年金受給者の多くは高齢者であり、医療や介護のニーズが高いため、生活保護の医療扶助・介護扶助と他の制度との連携がより密接になっています。地域包括ケアシステムとの連携により、総合的な支援体制の構築が進められています。
社会的理解の促進に向けた取り組みも重要な課題です。生活保護に対する偏見や誤解の解消に向けて、制度の正しい理解を広める啓発活動が強化されています。特に年金受給者については、長年社会に貢献してきた方々であることを踏まえ、必要に応じて制度を活用することの正当性が強調されています。
将来的な制度改革として、生活保護制度そのものの抜本的な見直しも議論されています。給付方式の多様化、申請手続きのさらなる簡素化、他の社会保障制度との統合などが検討課題となっており、年金受給者にとってより利用しやすい制度への改革が期待されています。

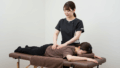
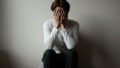
コメント