「固定電話が廃止される」という情報を耳にして、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、固定電話サービスそのものが完全になくなるわけではありません。NTT東日本・西日本が提供する固定電話は、従来の通信網からIP網への移行という大きな転換期を迎えており、2024年末までにすでにその移行が完了しています。この移行に伴い、通話料金の変更やINSネット(ISDN)サービスの段階的終了、さらには2025年5月に成立した改正NTT法による全国一律提供義務の廃止など、さまざまな変化が起きています。本記事では、固定電話のIP網移行がいつから始まり、どのようなスケジュールで進行したのか、そして利用者にどのような影響があるのかを詳しく解説します。NTTのスケジュールを正確に理解することで、今後の通信環境の変化に適切に対応できるようになるでしょう。
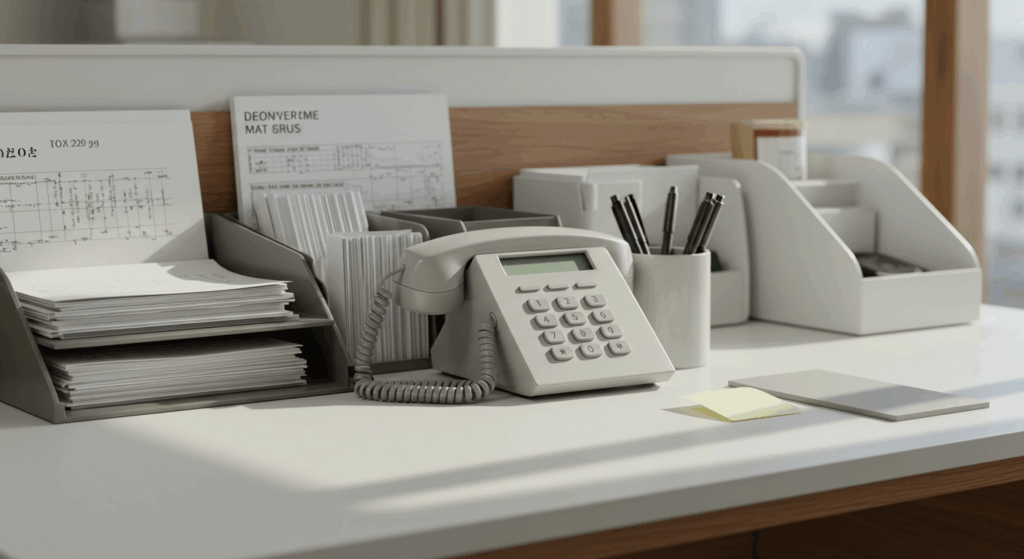
NTT固定電話IP網移行の背景と理由
NTT東日本・西日本は、固定電話の局内設備を従来の公衆交換電話網(PSTN)からIP網へと移行する作業を2024年1月1日以降、地域ごとに段階的に実施し、2024年11月までにすべての移行を完了しました。この大規模な移行の背景には、固定電話を取り巻く環境の大きな変化があります。
ピーク時には約6,000万回線あった固定電話の契約数は、携帯電話やスマートフォンの急速な普及により、現在では約1,000万回線以下にまで大幅に減少しています。契約数が6分の1程度にまで落ち込んだことで、従来のPSTN設備、特に中継交換機や信号交換機といった基幹設備の維持が困難になりつつありました。これらの設備は固定電話の利用が盛んだった時代に構築されたものであり、契約数の減少により設備の維持コストが相対的に増大していたのです。
さらに深刻な問題として、老朽化した設備の更新や保守に必要な部品の調達が困難になりつつあったことが挙げられます。PSTN設備の多くは数十年前の技術で構築されており、製造が終了した部品も少なくありません。このままでは2025年頃に維持限界を迎えることが予測されていたため、NTTは将来にわたって安定的な固定電話サービスを提供し続けるため、IP網への移行を決断しました。
IP網はインターネットと同じ技術基盤を利用した通信網であり、音声通話をデジタルデータに変換して伝送します。従来のPSTNが音声信号を直接伝送する回線交換方式だったのに対し、IP網ではデータをパケットに分割して伝送するパケット交換方式を採用しています。この技術転換により、通信網の効率化、設備の維持コストの削減、そして新しいサービスの提供が可能になります。また、IP網は国際的な標準規格に基づいているため、今後の通信技術の発展にも柔軟に対応できるという利点があります。
IP網移行のスケジュールと完了時期
IP網への移行は、2024年1月1日を起点として全国各地で段階的に実施されました。NTT東日本とNTT西日本は、それぞれのサービスエリアにおいて、地域ごとに異なる日程で局内設備の切り替え作業を進めました。この移行は、利用者側での手続きや工事は一切不要で、NTT側の通信設備における内部的な変更のみで完了しました。
移行作業の第一段階として、2024年1月から地域ごとに順次、局内設備の切り替えが開始されました。電話機はそのまま継続して利用でき、電話番号も変更されることはありませんでした。地域別の詳細なスケジュールについては、NTT東日本は利用者が使用している固定電話の対象地域が一般の行政区域と異なる場合があるため、利用している電話番号の市外局番によって対象地域および切替日時を確認できる仕組みを提供していました。
固定電話から携帯電話宛て、「0120」「0800」から始まる着信課金サービス宛て、「0570」から始まる「ナビダイヤル」宛ての通話などについては、2024年3月から移行作業が進められ、当初は2025年1月までの完了予定でしたが、2024年12月25日にすべての移行が完了したことがNTTから発表されています。この発表により、日本全国の固定電話サービスは2024年末をもって完全にIP網へと移行したことになります。これは、日本の通信インフラの歴史における大きな節目であり、約半世紀にわたって利用されてきたPSTN設備の役割が終わったことを意味します。
切替工事の完了状況については、NTT東日本の専用ホームページで随時お知らせされており、利用者は自分の地域の移行状況を確認することができました。この段階的な移行により、全国の利用者への影響を最小限に抑えながら、スムーズな技術転換が実現されたのです。
IP網移行による料金体系の変更
IP網への移行に伴い、固定電話の料金体系にも重要な変更が生じています。ただし、利用者にとって必ずしも不利な変更ばかりではなく、むしろメリットと感じられる部分も多くあります。
基本料金については現状通りで変更はありません。住宅用・事務用といった契約種別ごとの基本料金は、IP網移行後も従来と同じ金額が適用されます。利用者は今まで通りの月額料金で固定電話サービスを利用できるため、基本料金の面での負担増はありません。
一方、通話料金については大きな変更がありました。従来のPSTN網では、通話料金は距離に応じて段階的に設定されていました。市内通話、隣接区域への通話、県内市外通話、県外通話、長距離通話といった区分があり、距離が遠くなるほど通話料金も高くなる仕組みでした。特に県外への通話や長距離通話は高額になることが多く、遠方に住む家族や取引先との通話では通信費が大きな負担となっていました。
しかし、IP網ではインターネット回線を利用した通話となり、物理的な距離による通信コストの差がなくなりました。このため、2024年1月1日以降は全国どこへかけても一律9.35円/3分(税込み)という料金体系に統一されました。この変更により、従来は長距離通話や県外通話で高額な料金がかかっていた利用者にとっては、大幅な料金削減となる可能性があります。
たとえば、北海道から九州への通話でも、同じ市内への通話でも、料金は同じです。遠方の家族や親戚と頻繁に連絡を取る方、全国に取引先を持つ企業や事業者にとっては、通話料金の削減効果は非常に大きいと言えるでしょう。一方で、市内通話が中心だった利用者にとっては、わずかながら料金が上がるケースもあります。ただし全体としては、料金体系がシンプルになり利用者にとって分かりやすくなったと言えます。
INSネット(ISDN)サービスの段階的終了
IP網への移行に伴い、NTTが提供してきたISDN(統合デジタル通信網)サービスである「INSネット」についても段階的に終了することが決定しています。INSネットは、音声通話とデータ通信を統合して提供するサービスとして、特に企業や事業者に広く利用されてきました。
INSネットには、「通話モード」と「ディジタル通信モード」という2つの利用形態がありました。「通話モード」は一般的な音声通話に使用されるモードで、IP網移行後も引き続き利用可能です。音声通話の利用者は、特別な対応をしなくても従来通りサービスを利用できます。
一方、「ディジタル通信モード」は2024年1月から地域ごとに段階的にサービスを終了しました。「ディジタル通信モード」は、EDI(電子データ交換)やPOS(販売時点情報管理)システムなどの企業向けデータ通信に広く利用されてきたサービスです。多くの企業が受発注業務や在庫管理にこのサービスを利用しており、その終了は業務システムに大きな影響を与える可能性があります。
「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」といったINSネットのサービスは、2024年8月31日をもって新規販売が終了し、2028年12月31日をもってすべてのサービス提供が終了します。つまり、現在INSネットを利用している企業や事業者は、2028年末までに別の通信手段への移行を完了させる必要があるのです。
「ディジタル通信モード」のサービス終了に合わせて、NTTは「切替後のINSネット上のデータ通信(補完策)」を提供しています。これは、既存のINSネット利用者が急激なサービス終了によって業務に支障をきたさないようにするための経過措置です。ただし、この補完策も2028年12月31日にサービス提供を終了します。
補完策を利用する場合、従来の「ディジタル通信モード」より伝送遅延が生じ、処理時間が増大する可能性があります。また、利用する機器によっては通信に影響が発生することもあるため、注意が必要です。企業や事業者は、2028年末までに計画的に別の通信手段への移行を進めることが強く推奨されています。
INSネット終了後の代替サービス
INSネットのサービス終了に伴い、利用者は代替サービスへの移行を検討する必要があります。NTTや他の通信事業者は、さまざまな代替サービスを提供しており、利用目的や業務内容に応じて最適な選択肢を選ぶことができます。
最も一般的な選択肢は、光回線を利用した「ひかり電話」への移行です。ひかり電話は、光ファイバーを利用したIP電話サービスで、従来の固定電話と同じように電話番号を利用でき、音声品質も高いとされています。基本料金も従来の固定電話より安価な場合が多く、通話料金も全国一律で低価格に設定されています。すでに光回線を利用している、またはこれから導入を検討している利用者にとっては、非常に有力な選択肢となります。
また、NTTは「ひかりクラウド電話 ダイレクト for Webex Calling」や「ひかりクラウド電話 for Microsoft Teams」といったサービスも提供しています。これらのサービスを利用すれば、固定電話の番号をWeb会議ツールで利用できるようになり、オフィス外での柔軟な働き方の実現に役立つとされています。テレワークやリモートワークが普及する現代において、こうしたクラウド型の電話サービスは、企業にとって有力な選択肢となっています。
EDIやPOSシステムなど、データ通信用途でINSネットを利用していた企業向けには、「メタルIP電話のデータ通信」という代替サービスがNTTから提供されています。これは、IP網への移行後も既存のメタル回線を継続利用する手法ですが、あくまで経過措置的なサービスと位置づけられています。長期的には、インターネットVPNや専用線サービスなど、より安定した通信手段への移行が推奨されています。
企業や事業者が代替サービスを選択する際には、現在の業務システムとの互換性、通信の安定性、セキュリティ対策、コストなどを総合的に検討することが重要です。システムベンダーや通信事業者と相談しながら、自社の業務に最適な通信手段を選択し、計画的に移行を進めることが求められます。
マイラインサービスの終了
IP網への移行に伴い、「マイライン」サービスも終了しました。マイラインは、固定電話から長距離電話や国際電話をかける際に、あらかじめ利用する電話会社を登録しておくことで、電話番号の前に事業者識別番号をつけずに通話できるサービスでした。
1990年代後半から2000年代にかけて、通信事業の自由化に伴い、NTT以外にも多くの電話会社が長距離通話サービスに参入しました。各社は競争により通話料金を引き下げ、利用者は自分の好みの電話会社を選択できるようになりました。マイラインは、こうした競争環境の中で利用者の利便性を高めるために導入されたサービスでした。
しかし、IP網への移行により、距離による通話料金の差がなくなり、全国一律の料金体系となったため、マイラインの存在意義が失われました。IP網への移行に合わせて、固定電話を利用する地域ごとに段階的にマイラインサービスは終了し、新しい通話サービスへと移行しました。マイラインを利用していた方は、特別な手続きなく自動的に新しい料金体系での利用に切り替わっています。
2025年5月の改正NTT法成立と全国一律提供義務の廃止
2025年5月21日、改正NTT法が参議院本会議で可決・成立しました。この法改正の柱の一つが、NTT東西に課せられていた固定電話サービスの「全国一律提供義務」の廃止です。この改正は、固定電話サービスの将来に関わる非常に重要な変更として注目されています。
「全国一律提供義務」とは、その名の通り、NTT東日本・西日本に対し、日本全国どこであっても公平な条件で固定電話サービスを提供するよう義務付けていた制度です。過疎地や離島など、採算が取れない地域でも例外なく適用されてきました。この義務は、日本全国に通信インフラを行き渡らせるという公共的な使命を果たすために設けられていました。
しかし、固定電話の利用者減少と事業の採算悪化を背景に、この義務の見直しが進められました。ピーク時の約6,000万回線から約1,000万回線以下にまで落ち込んだ固定電話の契約数は、維持コストの増加を招き、NTTの経営を圧迫する要因となっていました。特に、人口が少ない過疎地や離島では、サービス提供のための設備投資や維持費用が収入を大きく上回る状況が続いていました。
改正NTT法では、固定電話サービスに関して、他に事業者がいない地域に限ってNTTに提供を義務づける仕組みに変更されました。他にサービスを提供できる事業者がいない地域については、引き続きNTTが「最終保障提供責務」としてサービスを維持することが法律で定められています。
つまり、競合する通信事業者が存在する都市部などでは、NTTが必ずしも固定電話サービスを提供する義務を負わないことになります。一方で、過疎地や離島など、他に選択肢がない地域では、引き続きNTTがサービスを提供する責任を負います。これにより、NTTの事業の柔軟性が高まる一方で、採算の取れない地域でも最低限の通信サービスは確保される仕組みが維持されます。
ユニバーサルサービス制度の継続
全国一律提供義務が廃止されても、「ユニバーサルサービス制度」は継続されます。ユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠な通信サービスを全国どこでも公平かつ安定的に提供することを目的とした制度です。
現在、ユニバーサルサービスの対象となっているのは、固定電話サービス(加入電話、公衆電話)、携帯電話サービス、インターネット接続サービスなどです。これらのサービスを提供するための費用は、すべての通信事業者が負担する「ユニバーサルサービス料」によって賄われています。
ユニバーサルサービス料は、携帯電話や固定電話の利用者が毎月の通信料金の一部として支払っています。この仕組みにより、都市部と地方の間でサービス提供のコストに差があっても、全国一律のサービス水準が維持されています。改正NTT法による全国一律提供義務の廃止後も、ユニバーサルサービス制度は継続されるため、国民が基本的な通信サービスを利用できる環境は引き続き保たれます。
この制度により、過疎地や離島に住む方々も、都市部と同等の通信サービスを利用できる環境が確保されているのです。災害時の緊急連絡手段としても、固定電話サービスは重要な役割を果たしており、ユニバーサルサービス制度の継続は国民の安心・安全な生活を支える基盤となっています。
双方向番号ポータビリティの開始
2025年1月からは、「双方向番号ポータビリティ」の受付が開始されました。番号ポータビリティとは、電話会社を変更しても同じ電話番号を引き続き使用できる制度です。
従来の番号ポータビリティは、主にNTTから他の電話会社への移行を想定したものでした。しかし、双方向番号ポータビリティの導入により、NTT以外の電話会社で取得した電話番号も、NTTのIP電話サービスへ移行することが可能となりました。
この制度により、利用者は自分のニーズに合わせて、より柔軟に電話会社を選択できるようになります。料金やサービス内容を比較し、最も適した事業者を選ぶことができるため、通信市場の競争が一層促進されることが期待されています。電話番号は企業にとって重要な資産であり、顧客や取引先との信頼関係を築く上で欠かせないものです。双方向番号ポータビリティにより、電話番号を変更することなく、より有利な条件のサービスに移行できるようになったことは、利用者にとって大きなメリットと言えます。
IP網移行に便乗した詐欺的勧誘への注意
IP網への移行に伴い、「固定電話が使えなくなる」「今だと工事料無料」といった便乗の勧誘が増加しています。これらは詐欺的な行為であり、十分な注意が必要です。
実際には、IP網への移行はNTT側の設備切り替えのみで完了するため、利用者側での工事や手続きは一切不要です。電話番号が変わることもなく、固定電話は通常通り使用できます。不審な勧誘を受けた場合は、安易に契約せず、NTTや消費者センターに相談することが重要です。
悪質な業者は、高齢者などを狙って「このままでは電話が使えなくなる」と不安を煽り、不要な工事契約や高額な機器の購入を迫るケースがあります。NTTや正規の代理店が、このような勧誘を行うことはありません。電話での勧誘や訪問販売には十分注意し、少しでも疑問に思ったら、家族や専門機関に相談するようにしましょう。
特に以下のような勧誘には注意が必要です。「IP網への移行に伴い、新しい電話機が必要になる」「工事をしないと電話が使えなくなる」「今だけ特別価格で工事ができる」といった言葉で勧誘してくる業者は、ほぼ間違いなく悪質な業者です。正式な移行作業は、利用者側での対応は一切必要なく、自動的に完了しています。
企業や事業者への影響と対応策
IP網への移行やINSネットの終了は、個人利用者だけでなく、企業や事業者にも大きな影響を及ぼします。特に、以下のような用途で固定電話やINSネットを利用している場合は、早めの対応が必要です。
EDI(電子データ交換)システムを利用している企業は、取引先とのデータのやり取りにINSネットを利用している場合、2028年末までに代替手段への移行が必要です。インターネットVPNやクラウド型EDIサービスへの移行が推奨されています。EDIは受発注業務の根幹を支えるシステムであり、移行には十分な準備期間が必要です。取引先との調整も含めて、早めに移行計画を立てることが重要です。
POSシステムを運用している小売業や飲食業では、店舗とデータセンターの間の通信にINSネットを利用している場合、同様に代替手段への移行が必要です。光回線やモバイル回線を利用したIP通信への切り替えが一般的です。POSシステムは日々の売上管理に直結するため、移行作業中にシステムが停止することのないよう、慎重な計画が求められます。
ビジネスホン・PBXシステムについては、従来のアナログ回線やISDN回線を利用したビジネスホンシステムは、IP網移行後も基本的には利用可能ですが、一部の機能が使えなくなる可能性があります。長期的には、IP-PBXやクラウドPBXへの移行を検討することが望ましいでしょう。最新のクラウドPBXは、テレワーク対応や柔軟な拡張性など、多くのメリットがあります。
セキュリティシステムでは、警備会社との通信にISDN回線を利用している場合、代替手段への移行が必要です。警備会社と相談し、適切な通信手段を選択することが重要です。セキュリティシステムは24時間365日の稼働が求められるため、信頼性の高い通信手段を選択する必要があります。
企業や事業者は、自社がどのような通信サービスを利用しているかを正確に把握し、必要に応じて通信事業者やシステムベンダーと相談しながら、計画的に移行を進めることが求められます。2028年末まではまだ時間がありますが、システムの規模が大きい企業や、複雑な業務システムを運用している企業は、早めに移行準備を開始することが推奨されます。
ひかり電話と従来の固定電話の比較
固定電話からIP網への移行に伴い、多くの利用者が「ひかり電話」への切り替えを検討しています。ひかり電話は、光回線を利用したIP電話サービスで、従来の固定電話とは異なる特徴を持っています。
従来の固定電話は、専用の電話回線(メタル回線)を使用して音声信号を伝送する仕組みでした。一方、ひかり電話は、インターネット回線上のデータ通信を利用するIP電話です。音声をデジタルデータに変換し、インターネットプロトコルを使って伝送します。
ひかり電話の主なメリットとして、まず料金面での優位性が挙げられます。月額使用料は従来の固定電話の基本料金が住宅用で1,760円程度だったのに対し、ひかり電話は月額550円で利用できます。これだけで年間約14,000円以上の節約になります。通話料金についても、ひかり電話は通話先の地域を問わず8.8円/3分と全国一律の料金設定になっています。
また、従来の固定電話を新規に契約する場合、電話加入権(施設設置負担金)として約36,000円が必要でしたが、ひかり電話はインターネット回線上のサービスなので、電話加入権は必要ありません。初期費用を大幅に抑えることができます。
工事についても、既にフレッツ光などの光回線が引かれている場合、追加の大規模な工事は基本的に不要です。光回線の終端装置(ONU)やホームゲートウェイに電話機を接続するだけで、すぐに利用を開始できます。さらに、ナンバーディスプレイ、キャッチホン、着信転送、迷惑電話対策など、さまざまなオプションサービスを簡単に追加できます。
一方で、ひかり電話のデメリットも理解しておく必要があります。最も大きなデメリットは、停電時に使用できないという点です。従来の固定電話は、メタル回線を通じて電話局から電力が供給されるため、停電時でも通話が可能でした。しかし、ひかり電話は光回線の終端装置やホームゲートウェイが電源を必要とするため、停電が発生すると通話ができなくなります。災害発生時の緊急連絡手段として、ひかり電話だけに頼ることは危険です。
また、ひかり電話を利用するには光回線の契約が必須条件です。光回線の月額料金は、戸建て住宅で5,000円前後、集合住宅で4,000円前後が一般的です。インターネットをほとんど使わず、電話だけを利用したい場合は、光回線の基本料金とひかり電話の料金を合わせると、従来の固定電話よりも割高になる可能性があります。
総務省の統計によると、2019年6月末時点で、ひかり電話の契約数が初めて従来の固定電話の契約数を上回りました。料金の安さ、豊富なオプション、高速インターネットとのセット利用など、ひかり電話のメリットが広く認知された結果と言えるでしょう。
スマホ時代における固定電話の必要性
スマートフォンの普及により、固定電話の必要性について疑問を持つ人が増えています。個人でも企業でも、携帯電話だけで十分ではないかという意見は少なくありません。しかし、固定電話には今でも重要な役割があり、特にビジネスシーンでは依然として必要とされています。
総務省の情報通信白書令和3年版によると、固定電話の加入契約者数は2009年の5,787万人から2020年には5,284万人と約500万人減少しています。個人の固定電話保有率も、2010年に85.8%だったのに対し、2020年には68.1%にまで低下しました。一方で、スマートフォンの保有率は2010年の9.7%から2020年には86.8%へと急速に伸びています。
企業にとって固定電話が依然として重要な理由は、まず社会的信用性の確保です。固定電話番号は、市外局番によって発信元の地域を特定できるため、着信時に安心感を与えることができます。初めて取引する企業から連絡があった場合、固定電話番号であれば「この地域に実際にオフィスがある企業だ」と判断でき、信頼感が生まれます。
特に、不動産業、金融業、法律関連など、信用が重要な業種では、固定電話番号を持つことがビジネス上の必須条件とされることが多くあります。また、金融機関に融資の申し込みをする際、法人用の固定電話番号が必要になるケースがあります。銀行や信用金庫などの金融機関は、企業の信用力を評価する際に、固定電話番号の有無を確認しています。
会社を設立する際には、法務局に登記を行いますが、その際に会社の連絡先として電話番号を登録します。登記には固定電話番号を使用するのが一般的です。固定電話番号は、オフィスの所在地と紐づいており、携帯電話番号のように個人の都合で簡単に変更されることがありません。
また、企業には複数の部署や担当者が存在しますが、外部からの連絡窓口として代表番号を設けることが一般的です。固定電話を代表番号とすることで、顧客や取引先は「どこに連絡すればよいか」が明確になります。ビジネスホンシステムやPBXを導入することで、代表番号にかかってきた電話を適切な部署や担当者に転送することができます。
個人の場合、固定電話の必要性は企業ほど高くありません。携帯電話やスマートフォンがあれば、日常生活における連絡手段としては十分です。実際、若い世代を中心に、固定電話を持たない世帯が増えています。ただし、高齢者や家族が多い世帯では、固定電話を維持するメリットもあります。自宅にいる時間が長い場合、固定電話があることで家族や親戚との連絡が取りやすくなります。
クラウドPBXによる固定電話の進化
固定電話の必要性は認識しているものの、オフィスに常駐するスタイルではなくなった企業や、テレワークを導入している企業にとって、従来型の固定電話システムは使いにくい面があります。そこで注目されているのが「クラウドPBX」です。
PBX(Private Branch eXchange)とは、企業内で複数の電話回線を管理し、内線通話や外線の取り次ぎを行う電話交換機のことです。従来は、オフィス内に専用の機器を設置する必要がありましたが、クラウドPBXでは、これらの機能をクラウド上のサーバーで提供します。
クラウドPBXを導入することで、スマートフォンやパソコン、タブレットなどの端末を使って、場所を問わず会社の固定電話番号で発着信ができるようになります。専用のアプリをインストールすることで、外出先や自宅からでも、会社の代表番号で電話をかけたり受けたりできます。
これにより、「会社にいないと電話に出られない」という制約がなくなり、営業担当者が外出中でも顧客からの電話に直接対応できるようになります。また、テレワーク中の社員も、自宅から会社番号で発信できるため、顧客に対して個人の携帯電話番号を教える必要がありません。
従来型のPBX機器は、購入費用や設置工事費用が高額でした。クラウドPBXは、物理的な機器を設置する必要がないため、初期費用を大幅に抑えることができます。月額料金制で利用できるサービスが多く、予算に応じて柔軟にプランを選択できます。また、メンテナンスはサービス事業者が行うため、企業側での保守作業や費用は不要です。
さらに、離れた拠点にいる社員同士の通話が内線扱いとなるため、通話料が無料になります。複数の拠点を持つ企業にとっては、大幅な通話料の削減が期待できます。従来型のPBX機器は、設置工事に時間がかかりましたが、クラウドPBXは、インターネット環境があれば、申し込みから短期間で利用を開始できます。
災害や緊急事態が発生した場合でも、クラウドPBXであれば、社員が自宅や避難先から会社の電話業務を継続できます。オフィスが被災して使用できなくなっても、クラウド上のシステムは影響を受けないため、事業の継続性が確保されます。特に、地震や台風などの自然災害が多い日本において、BCP(事業継続計画)対策は企業にとって重要な課題です。
ただし、クラウドPBXにもいくつかの注意点があります。インターネット回線を利用するサービスであるため、安定したインターネット環境がなければ、音声品質が低下したり、通話が途切れたりする可能性があります。また、一部のクラウドPBXサービスでは、110番や119番などの緊急通報に対応していない場合があります。
IP網移行のメリットと今後の展望
IP網への移行は、単なる設備の更新にとどまらず、通信サービスの質や多様性を向上させる可能性を秘めています。
まず、通信の効率化とコスト削減が挙げられます。IP網は、インターネットと同じ技術基盤を利用するため、音声通話だけでなく、データ通信や映像配信など、さまざまなサービスを統合的に提供できます。これにより、通信事業者は設備投資や運用コストを削減し、より安価で高品質なサービスを提供できるようになります。
また、新しいサービスの開発も容易になります。従来のPSTN網は、音声通話に特化した設計だったため、新しい機能やサービスを追加することが困難でした。一方、IP網はソフトウェアベースで柔軟にカスタマイズできるため、クラウド電話、AI音声アシスタント、高度な通話転送機能など、さまざまな付加価値サービスを提供できます。
さらに、IP網は国際的な標準規格に基づいているため、国内外の通信事業者との連携が容易になります。これにより、国際電話やグローバルなビジネス通信の品質向上やコスト削減が期待できます。今後、5GやIoT(モノのインターネット)の普及に伴い、通信インフラの重要性はますます高まります。IP網への移行は、こうした次世代の通信サービスを支える基盤として、日本の通信インフラの競争力を維持・向上させる重要な取り組みと言えるでしょう。
固定電話は廃止されるのではなく、形を変えながら進化し続けています。IP網への移行、ひかり電話の普及、クラウドPBXの登場など、固定電話サービスは現代のニーズに合わせて柔軟に変化しています。企業にとっては社会的信用性を確保する重要な手段として、個人にとっては必要に応じて選択できる通信手段として、固定電話は今後も日本の通信インフラの重要な一翼を担い続けるでしょう。

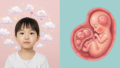
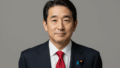
コメント