インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害に悩まされている方にとって、発信者情報開示請求は重要な法的手段です。名誉を傷つけられたり、個人情報を無断で晒されたりした場合、その投稿者を特定して責任を問うためには、まず発信者情報の開示を請求する必要があります。発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法に基づき、サイト管理者やプロバイダに対して、権利侵害投稿を行った発信者の情報開示を求める手続きです。
多くの方は「発信者情報開示請求は弁護士に依頼するもの」と考えがちですが、実は自分自身で行うことも可能です。自分で行えば弁護士費用を節約できる反面、法的知識や手続きの複雑さを自分で乗り越える必要があります。2022年10月にはプロバイダ責任制限法が改正され、従来よりも開示請求がしやすくなりましたが、依然として時間と手間のかかる手続きです。
本記事では、発信者情報開示請求を自分で行う方法、手続きのポイント、書類の書き方、そして自分で行う場合と弁護士に依頼する場合のメリット・デメリットを詳しく解説していきます。ネット上の権利侵害に悩む方が、少しでも解決の糸口を見つける助けになれば幸いです。
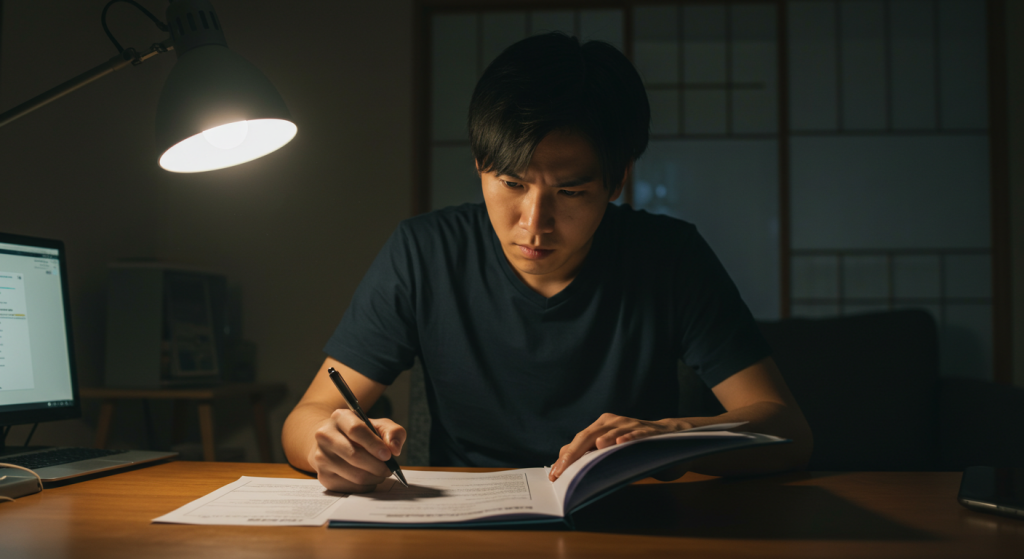
発信者情報開示請求を自分で行う場合の具体的な手順は?
発信者情報開示請求を自分で行う場合、基本的には以下の流れで進めていきます。
まず、発信者情報開示請求の手続きは大きく分けて2段階に分かれています。第1段階として、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)へのIPアドレス等の開示請求、第2段階として、インターネット接続サービス提供者(アクセスプロバイダ)への発信者の個人情報開示請求です。
第1段階:サイト管理者への開示請求
- 証拠の保全:まず権利侵害投稿のスクリーンショットを取り、URLや投稿日時が分かるように保存します。
- 発信者情報開示請求書の作成:テレコムサービス協会が公開している「テレサ書式」と呼ばれる標準的な書式を使用して作成します。請求書には以下の項目を記載します。
- 管理する特定電気通信設備等(該当するURL)
- 掲載された情報(問題の投稿内容)
- 侵害された権利(名誉権、プライバシー権など)
- 権利が明らかに侵害されたとする理由
- 開示を請求する発信者情報(IPアドレスなど)
- 任意開示の請求:作成した請求書をサイト管理者に送付し、任意での開示を求めます。
- 裁判所への仮処分申立て:任意開示に応じてもらえない場合(実際にはほとんどのケースがこれに当たります)、裁判所に仮処分命令の申立てを行います。
仮処分申立てが認められると、サイト管理者は発信者のIPアドレスや投稿日時を開示することになります。この情報をもとに、次の段階へ進みます。
第2段階:プロバイダへの開示請求
- プロバイダの特定:開示されたIPアドレスから、「WHOIS検索」などを使ってプロバイダを特定します。
- プロバイダへの開示請求書送付:このプロバイダに対して発信者情報開示請求書を送付し、発信者の氏名や住所などの個人情報の開示を求めます。
- 任意開示の請求:プロバイダは発信者に連絡を取り、開示に同意するか確認します。発信者が同意すれば情報が開示されますが、拒否されることがほとんどです。
- 訴訟の提起:任意開示に応じてもらえない場合、裁判所に訴訟を提起します。訴状の作成や証拠の準備が必要になります。
2022年10月の法改正以降の方法
2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正され、「発信者情報開示命令」制度が創設されました。これにより、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの開示請求を一つの手続きで行うことが可能になりました。
手続きの流れは以下のようになります:
- 裁判所へ開示命令・提供命令の申立て
- コンテンツプロバイダへの提供命令(アクセス履歴をアクセスプロバイダへ提供するよう命令)
- アクセスプロバイダへの消去禁止命令・開示命令の申立て
- 裁判所による審理
- 発信者情報開示命令の発令
この非訟手続きを利用すれば、従来の方法よりも時間と手間を節約でき、1〜4ヶ月程度で発信者情報の開示まで行き着けるようになりました。
ただし、これらの手続きはいずれも時間的制約があります。プロバイダがログを保存している期間(一般的に3〜6ヶ月)内に手続きを完了させる必要があるため、権利侵害を発見したらできるだけ早く行動を開始することが重要です。
自分で発信者情報開示請求をする際のメリットとデメリットは?
発信者情報開示請求を自分で行うか、弁護士に依頼するかを検討する際には、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
自分で行う場合のメリット
- 費用を節約できる:最大のメリットは弁護士費用が不要になることです。弁護士に依頼すると、任意開示の段階でも10万〜30万円程度、裁判手続きになれば20万〜50万円程度の弁護士費用がかかります。自分で行えば、裁判所に納める手数料(仮処分で数千円、訴訟で1万〜数万円程度)と書類の郵送費用程度で済みます。
- 自分のペースで進められる:自分で行うことで、手続きの全過程を把握し、自分のペースで進めることができます。弁護士に依頼する場合は、弁護士の予定にも左右されます。
- 知識と経験を得られる:自分で行うことで、法的手続きや権利保護についての知識を得ることができます。将来同様の問題が起きた場合にも役立つでしょう。
自分で行う場合のデメリット
- 法的知識の習得が必要:発信者情報開示請求には、プロバイダ責任制限法をはじめとする法的知識が必要です。権利侵害の種類によっては、名誉毀損罪やプライバシー権に関する法律知識も求められます。
- 手続きが複雑で時間がかかる:書類作成や裁判所への提出など、手続きは決して簡単ではありません。特に裁判手続きに移行した場合、法廷での主張立証は専門知識なしに行うのは困難です。
- 成功率が低くなる可能性:弁護士に比べて法的知識や経験が乏しい場合、開示請求が認められない可能性が高まります。特に権利侵害の立証が難しいケースでは、専門家の支援がないと成功しにくいことがあります。
- 時間的制約がある:プロバイダのログ保存期間(3〜6ヶ月程度)内に手続きを完了させる必要があります。自分で行う場合、調査や書類作成に時間がかかり、期限に間に合わないリスクがあります。
弁護士に依頼する場合のメリット
- 専門的知識と経験による高い成功率:弁護士は法的知識と経験を持っており、開示請求が認められる可能性が高まります。
- 時間と労力の節約:複雑な手続きや書類作成を弁護士が代行してくれるため、自分の時間と労力を節約できます。
- 精神的負担の軽減:ネット上の誹謗中傷に悩む方にとって、法的手続きは精神的にも負担が大きいものです。弁護士に依頼することで、その負担を軽減できます。
- 損害賠償請求などの後続手続きへの移行がスムーズ:発信者が特定できた後の損害賠償請求など、次のステップへの移行もスムーズに行えます。
弁護士に依頼する場合のデメリット
- 費用がかかる:前述のとおり、弁護士費用がかかります。ただし、最終的な損害賠償請求訴訟で勝訴した場合、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を「調査費用」として相手方に請求できる可能性があります。
- 弁護士によって対応に差がある:ネット関連の法律に詳しい弁護士ばかりではないため、選び方によっては適切な対応が得られないことがあります。
以上のメリット・デメリットを踏まえると、権利侵害の内容が複雑であったり、時間的余裕がなかったりする場合は弁護士に依頼し、比較的単純な案件で時間と労力をかけられる場合は自分で行うという選択肢があります。また、最初は自分で任意開示請求を行い、裁判手続きに移行する段階で弁護士に依頼するという方法も考えられます。
発信者情報開示請求書はどのように作成すればよいのか?
発信者情報開示請求書は、一般社団法人テレコムサービス協会が設置する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成・公開している標準書式(通称「テレサ書式」)に基づいて作成するのが一般的です。この書式はプロバイダ責任制限法関連情報Webサイトで公開されています。
発信者情報開示請求書の主な記載項目
- 貴社が管理する特定電気通信設備等
- 発信者情報の開示を請求したいURLを記載します。
- トップページのURLではなく、問題の投稿がされた特定のURLを記載しましょう。
- 掲示板の場合はスレッドのURLとレス番号、ブログ記事であれば個別の記事のURLなど、開示を請求する投稿を特定できるURLが必要です。
- 掲載された情報
- 開示請求のきっかけとなった問題の投稿内容を記載します。
- 内容をコピーペーストして記載することも可能です。
- 量が多い場合には別添資料を付けることもできます。
- 侵害された権利
- 投稿によってどんな権利が侵害されたのかを記載します。
- 具体的には、名誉権、プライバシー権などが挙げられます。
- どういった権利侵害と表現すべきか悩む場合は、弁護士に相談することも有効です。
- 権利が明らかに侵害されたとする理由
- 「侵害された権利」と整合性がとれるように、投稿内容が権利侵害をしている理由について記述します。
- 例えば「〇〇は前科があると記載されたが、このような記載は私の社会的評価を低下させるものであり、事実でもないため名誉権の侵害にあたります」などのように、投稿が自分のことを指しており、かつ権利侵害にあたることを明確に記載します。
- プロバイダはネット上の書き込みのすべてを把握しているわけではないため、詳細な記載が必要です。
- 発信者情報の開示を受けるべき正当理由
- 該当する理由をすべて選択します。基本的には「損害賠償請求権の行使のため」を選びます。
- その他、「謝罪広告などの名誉回復措置の要請のため」「差止請求権の行使のため」「発信者に対する削除要求のため」などの選択肢があります。
- 開示を請求する発信者情報
- 開示請求する発信者情報から該当するものをすべて選択します。
- IPアドレスやポート番号、発信日時など技術的情報から、氏名、住所などの個人情報まであります。
- サイト管理者に対する請求とプロバイダに対する請求では、開示可能な情報が異なることに注意しましょう。
- 証拠
- 「添付資料」と記載し、主張を裏付ける証拠を添付します。
- 例えば、問題の投稿ページをURLが含まれるように印刷し、該当箇所にマーカーを引くなどすると効果的です。
- 発信者に示したくない私の情報
- 発信者に示したくない情報があればマークします。
- 「氏名(個人の場合に限る)」「権利が明らかに侵害されたとする理由欄記載事項」「添付した証拠」などが選択肢としてあります。
発信者情報開示請求書作成のポイント
- 具体的で明確な記載:権利侵害の事実や理由は、具体的かつ明確に記載します。漠然とした記載では開示請求が認められにくくなります。
- 証拠の充実:権利侵害の事実を裏付ける証拠は十分に準備します。投稿内容のスクリーンショットだけでなく、URLや投稿日時なども証拠として残しておきましょう。
- 法的根拠の明示:どのような法的根拠に基づいて権利侵害を主張するのか、可能な限り明示します。
- 同定可能性の説明:投稿が自分のことを指していることを証明する「同定可能性」について説明することも重要です。実名で書かれていなくても、状況や内容から自分が特定できる場合は説明します。
発信者情報開示請求書の作成は法的知識を要する作業ですので、自信がない場合は弁護士に相談することをお勧めします。特に権利侵害の主張や法的根拠の明示などは、専門家のアドバイスが役立つでしょう。
自分で発信者情報開示請求をする際の法的要件と注意点は?
発信者情報開示請求を成功させるためには、プロバイダ責任制限法で定められた要件を満たす必要があります。また、手続きを進める上での注意点を把握しておくことも大切です。
発信者情報開示請求の6つの法的要件
- 「特定電気通信による情報の流通」であること
- 「特定電気通信」とは、不特定の者により受信されることを目的とする電気通信のことで、インターネット上のウェブページや掲示板、SNS等が該当します。
- 個別のメールやダイレクトメッセージなど特定の人だけが見るものは該当しません。
- 情報開示の請求者が「自己の権利を侵害されたとする者」自身であること
- 発信者情報開示請求ができるのは、権利侵害を受けた本人(または法定代理人)だけです。
- 「同定可能性」があること、つまり投稿が自分のことを指していることが第三者にも分かる状態であることが必要です。
- 情報開示の請求者が「権利を侵害されたこと」が明らかであること
- 名誉権、プライバシー権、著作権などの権利が侵害されていることが明らかである必要があります。
- また、違法性阻却事由(違法とならない事由)がないことも必要です。例えば、名誉毀損の場合、公共の利害に関する事実で、公益目的であり、かつ内容が真実である場合は、違法性が阻却されます。
- 情報開示を求める「正当な理由」が存在すること
- 損害賠償請求や刑事告訴など、発信者情報を開示してもらう目的が正当であることが必要です。
- 私的制裁や嫌がらせが目的の場合は認められません。
- 開示を求める相手が「発信者情報」を保有していること
- 開示請求の相手方(サイト管理者やプロバイダ)が実際に発信者情報を保有していることが必要です。
- 例えば、ログが既に削除されている場合は開示できません。
- 開示を求める内容が「発信者情報」に該当すること
- プロバイダ責任制限法施行規則で定められた範囲内の情報(発信者の氏名・住所・メールアドレス・IPアドレスなど)であることが必要です。
自分で発信者情報開示請求を行う際の注意点
- 時間的制約を認識する
- プロバイダが保有するアクセスログは一般的に3〜6ヶ月程度で削除されます。この期間内に手続きを完了させる必要があります。
- 特に複数のプロバイダが関係する場合(格安SIMなど)、時間的制約はさらに厳しくなります。
- 任意開示に応じてもらえる可能性は低い
- 発信者情報開示請求書による任意開示は、プロバイダが自主的に判断する必要があるため、実際に応じてもらえるケースは多くありません。
- 多くの場合、裁判所の仮処分命令や訴訟提起が必要になります。
- 裁判手続きの準備をしておく
- 任意開示が拒否された場合に備えて、裁判手続きの準備をしておくとよいでしょう。
- 2022年10月の法改正により、新たな裁判手続き(非訟手続)も選択肢に入りました。
- 証拠の確保と保全を適切に行う
- 権利侵害の証拠はスクリーンショットなどで適切に保存しておきます。
- URLや投稿日時も含めて保存することが重要です。
- 同定可能性を意識する
- 投稿が自分のことを指していることを証明する「同定可能性」を証拠や説明で明確にします。
- 実名でなくても、状況や内容から自分が特定できることを説明できるようにしておきましょう。
- 複数のプロバイダを特定する必要がある場合がある
- 特に格安SIMなどを使用した投稿の場合、複数のプロバイダが関係していることがあります。
- そのような場合、各プロバイダに対して順次開示請求を行う必要があります。
- 法的知識の不足を補う努力をする
- 自分で行う場合でも、基本的な法的知識は必要です。関連法規やガイドラインを調べ、理解するようにしましょう。
- 必要に応じて弁護士に相談することも検討してください。
発信者情報開示請求は決して簡単な手続きではありませんが、準備と知識があれば自分でも行うことは不可能ではありません。ただし、時間的制約や手続きの複雑さを考慮すると、特に急を要する場合や複雑なケースでは弁護士への相談も検討すべきでしょう。
発信者情報開示請求を自分で行う場合と弁護士に依頼する場合の費用比較は?
発信者情報開示請求にかかる費用は、自分で行うか弁護士に依頼するかで大きく異なります。それぞれにかかる費用を比較し、予算に合わせた選択ができるようにしましょう。
自分で発信者情報開示請求を行う場合の費用
- 任意開示請求の段階
- 発信者情報開示請求書の作成・送付にかかる実費(数百円〜数千円程度)
- 印刷代、郵送料など
- 証拠収集にかかる実費(数百円〜数千円程度)
- スクリーンショットの印刷代など
- 発信者情報開示請求書の作成・送付にかかる実費(数百円〜数千円程度)
- 仮処分申立て(IPアドレス開示)の段階
- 裁判所に納める手数料:数千円程度
- 担保金:必要に応じて10万〜30万円程度(申立てが却下された場合に相手方に生じる損害を担保するためのもので、申立てが認められれば返還されます)
- 交通費:裁判所への往復交通費
- 訴訟提起(発信者個人情報開示)の段階
- 裁判所に納める手数料:訴額に応じて1万〜数万円程度
- 実費(証拠の準備、交通費など):数千円〜数万円程度
これらを合計すると、自分で行う場合の費用は、仮処分のみであれば数万円程度、訴訟まで行うと数十万円程度になることが一般的です。ただし、担保金は返還されることがほとんどなので、実質的な負担はもっと少なくなります。
弁護士に依頼する場合の費用
弁護士に依頼する場合は、上記の実費に加えて弁護士費用がかかります。弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
- 任意開示請求の段階
- 着手金:5万〜20万円程度
- 実費(数千円程度)
- 仮処分申立て(IPアドレス開示)の段階
- 着手金:10万〜30万円程度
- 成功報酬:5万〜10万円程度
- 裁判所に納める費用(上記と同様)
- 訴訟提起(発信者個人情報開示)の段階
- 着手金:20万〜40万円程度
- 成功報酬:10万〜20万円程度
- 裁判所に納める費用(上記と同様)
これらを合計すると、弁護士に依頼する場合の費用は、任意開示のみなら10万〜30万円程度、仮処分まで行うと20万〜50万円程度、訴訟まで行うと50万〜100万円程度になることが一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、案件の複雑さや弁護士の経験などによって変動します。
費用比較のポイント
- 時間と労力のトレードオフ
- 自分で行う場合は費用は安くなりますが、調査や書類作成、裁判所への出頭など多くの時間と労力が必要です。
- 弁護士に依頼する場合は費用はかかりますが、手続きのほとんどを代行してもらえるため、時間と労力を節約できます。
- 成功率の違い
- 弁護士に依頼すると、専門的知識と経験により開示請求が認められる可能性が高まります。
- 特に複雑なケースや法的な争点がある場合は、弁護士の専門知識が役立ちます。
- 最終的な訴訟での費用回収
- 発信者が特定できた後、損害賠償請求訴訟で勝訴した場合、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を「調査費用」として相手方に請求できる可能性があります。
- ただし、いくら認められるかは裁判官の判断によります。
- 弁護士費用特約付き保険
- 弁護士費用特約付きの保険に加入している場合、弁護士費用の一部または全部が補償されることがあります。
- 特に誹謗中傷対策に特化した保険もあるので、該当する方は確認してみるとよいでしょう。
- 分割払いや法テラスの利用
- 経済的に困難な場合は、弁護士と分割払いの相談をすることも可能です。
- また、収入が一定基準以下の場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できることもあります。
費用だけで判断するのではなく、時間的余裕、案件の複雑さ、自分の法的知識のレベル、心理的負担の大きさなども含めて総合的に判断することが大切です。特に、精神的なダメージが大きい誹謗中傷被害の場合、弁護士に任せることで精神的負担を軽減できるメリットは大きいかもしれません。
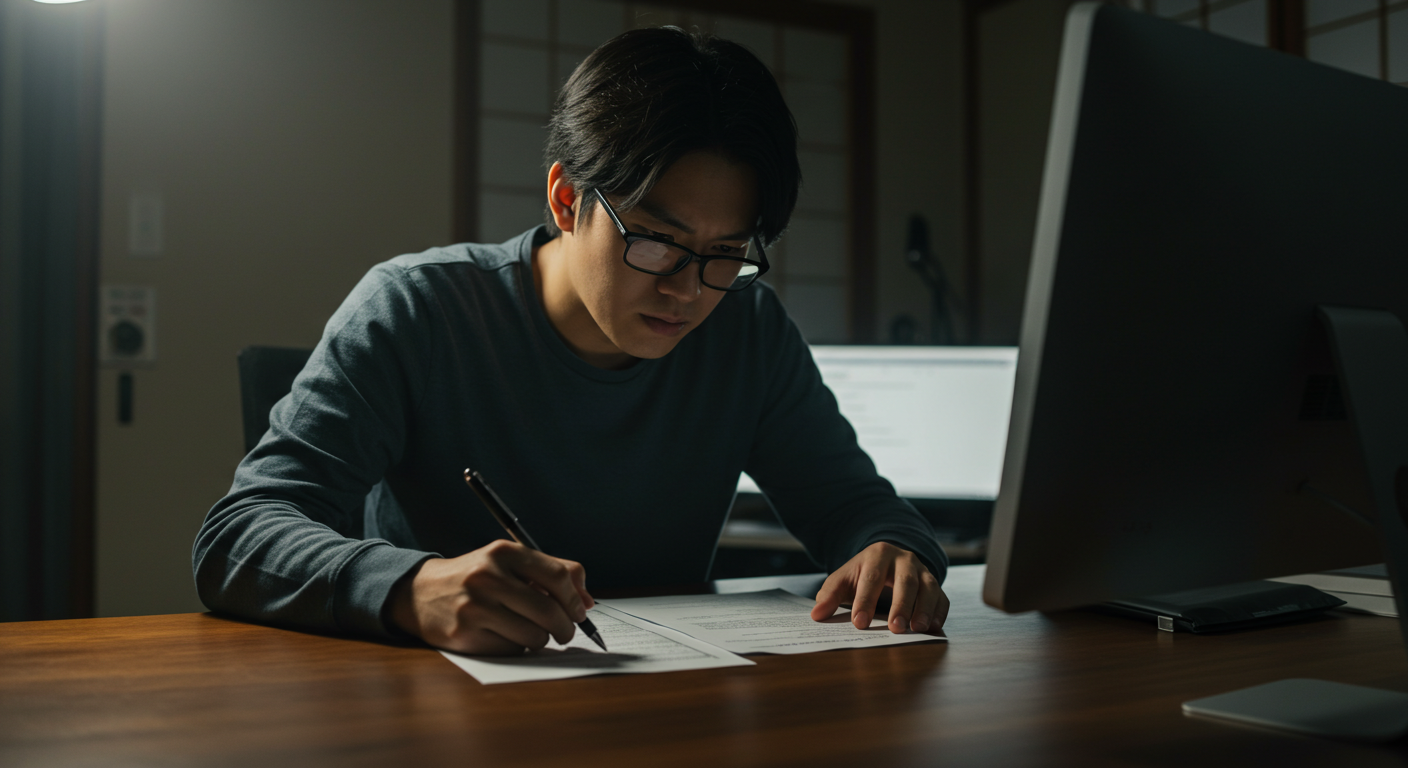


コメント